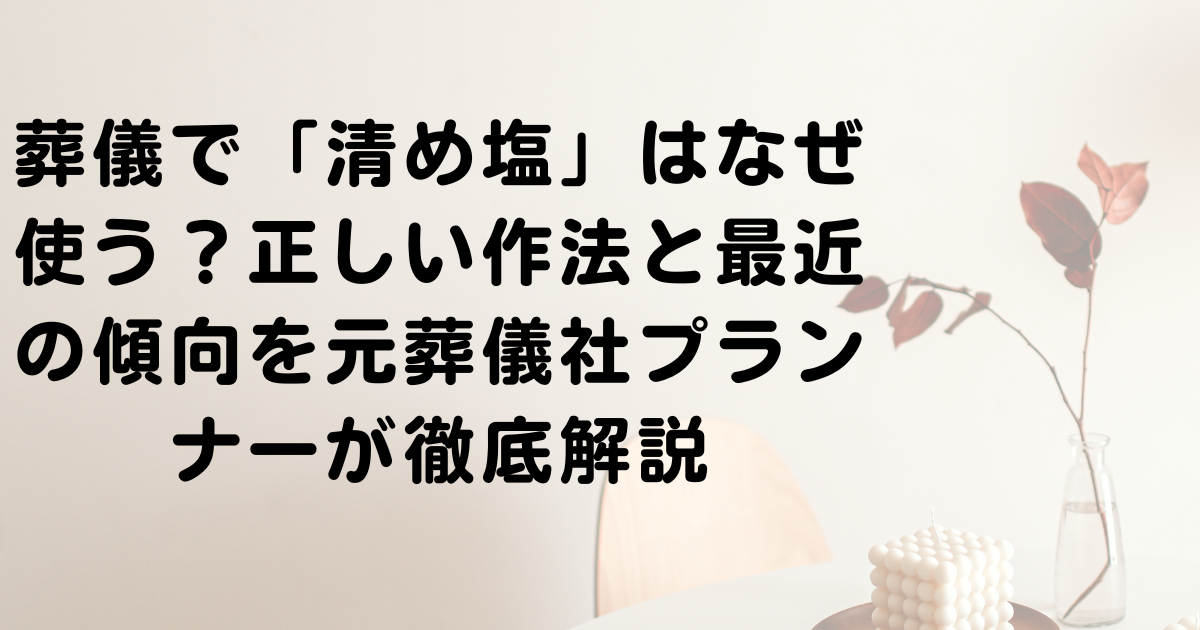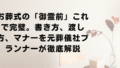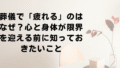こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前、父を突然亡くした経験から、葬儀社プランナーとして12年間働いてきました。これまでに800件を超えるご葬儀に携わる中で、多くのご遺族が「どうすればいいの?」と戸惑う姿を見てきました。特に、昔から伝わる風習やマナーについては、「正しいやり方がわからない」「なぜこれをするのか意味がわからない」という声をよく耳にしました。
今日お話しするのは、その中でも特に多くの人が疑問に思うことの一つ、「葬儀後の清め塩」についてです。玄関に置かれた小さな袋や、持ち帰ったときにどう使えばいいのか、そもそもなぜ塩で清める必要があるのか、そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、元葬儀社プランナーである私の視点から、清め塩の由来や意味、正しい使い方、そして現代における清め塩の考え方まで、詳しく、そして丁寧に解説していきます。
昔から続く「清め塩」の風習――その由来と込められた意味とは
まず、なぜ葬儀の後に塩を使うのか、その理由から見ていきましょう。
「清め塩」という言葉を聞くと、なんとなく「縁起が悪いものを払う」といったイメージをお持ちの方が多いかもしれません。その感覚は間違いではありません。しかし、そこにはもっと深い、昔の人々の考え方や死生観が込められています。
塩が持つ特別な力:古来から信仰されてきた「浄化」のシンボル
昔から、塩はただの調味料ではありませんでした。神道において、塩は「穢(けが)れ」を払い、身を清める力を持つものとして非常に重要視されてきました。
「穢れ」とは、汚れとは少し違います。死や病気、出産など、日常とは異なる「非日常」な出来事によって、人や場所が持つエネルギーが不安定になった状態を指します。この「穢れ」を元の清らかな状態に戻すために、塩の力が借りられてきたのです。
具体的には、お相撲さんが土俵に塩をまくのも、神棚に塩をお供えするのも、すべて同じ理由です。土俵を清め、神聖な空間を保つ。神様が宿る場所を清らかに保つ。そういった願いが込められています。
なぜ「死」が「穢れ」とされたのか?
神道の考え方では、「死」は最も強い「穢れ」の一つとされています。これは、死そのものが悪いもの、不浄なものだというわけではありません。
むしろ、「死」は、それまでの生命活動が終わり、魂が次の世界へと旅立つという、非常に大きな変化を伴う出来事です。この大きな変化が、現世に残された人々や場所に、不安定なエネルギーをもたらすと考えられました。
だからこそ、葬儀に参列し、死という「穢れ」に触れた私たちは、日常生活に戻る前に、塩の力で身を清める必要があったのです。
これは、故人を軽んじているわけではありません。むしろ、故人の魂が安らかに旅立てるよう、そして、残された私たちが健やかな日常を送れるよう、お互いの世界を清らかに保とうとする、古くからの知恵であり、やさしい心遣いの表れなのです。
「清め塩」は神道の風習?仏教との関係は?
ここが少しややこしいところですが、清め塩は元々、神道の風習です。
仏教には、本来「死=穢れ」という考え方はありません。仏教の教えでは、魂は輪廻転生を繰り返し、死は次の生への旅立ちと捉えられています。そのため、仏教の宗派の中には、清め塩の習慣を不要とする宗派も多く存在します。
しかし、日本では古くから神道と仏教が共存し、お互いの文化が融合してきた歴史があります。そのため、多くの人が神道的な「穢れ」の概念を自然と受け入れてきました。結果として、仏式の葬儀でも、清め塩が広く用いられるようになったのです。
最近では、「故人を穢れとするのはおかしい」という考え方から、葬儀社によっては清め塩を用意しないところも増えています。故人の意向や、葬儀の形式、地域の風習などによっても異なるため、一概に「これが正しい」とは言えなくなってきているのが現状です。
葬儀の「清め塩」正しい使い方とNGな作法
ここからは、実際に清め塩を使う際の正しい作法について解説します。特に、年配の方やマナーを重んじる方の中には、この作法を大切にされる方もいらっしゃいます。知らないうちに失礼なことにならないよう、ぜひ確認しておきましょう。
清め塩の受け取り方
通常、清め塩は葬儀の最後に、会葬御礼の品と一緒に渡されます。多くの場合、手のひらに乗るくらいの小さな紙袋に入っています。
このとき、特に難しい作法はありません。会葬御礼の品と一緒に、感謝の気持ちを込めて受け取れば大丈夫です。
玄関での正しい作法
自宅に帰ったら、清め塩を使うのは玄関をまたぐ前です。
- 自宅の玄関前で、まず清め塩の袋を開けます。
- 左肩、右肩、そして胸元の順に、ひとつまみずつ塩を振りかけます。このとき、あまり大量に振りかける必要はありません。本当にひとつまみ、パラパラと落ちる程度で大丈夫です。 **「左・右・胸」**の順番を覚えておきましょう。
- 最後に、足元に塩を落とします。これは、体についた穢れを払い落とすイメージです。
- すべて済んだら、清め塩を使い切ります。残った塩は、そのままごみ箱に捨てても問題ありません。
- 塩を振りかけ終わったら、体を清らかな状態に戻したという気持ちで、自宅の玄関をまたぎましょう。
これだけは避けたい!「NGな作法」
- 塩を振りかける前に家に入ってしまうことせっかく清めるための塩ですから、玄関をまたぐ前に使うことが重要です。帰宅したらすぐに塩を使いましょう。
- 清め塩を誰かに振りかけてもらうこと清め塩は、自分自身の身を清めるものです。他の人にやってもらうのではなく、自分で振りかけるようにしましょう。
- 塩を舐めたり、食べたりすること清め塩は、あくまで「穢れを払う」ためのものです。食用ではありませんので、口に入れたりしないように注意してください。
葬儀の服装、もう迷わない!
葬儀に参列する際、「どんな服装で行けばいいのか」と悩む方も多いと思います。特に久しぶりに参列される方や、急な訃報で準備する時間がない方は不安になりますよね。
実は、葬儀の服装にも、知っておきたいマナーがたくさんあります。たとえば、喪服の色やデザイン、小物やアクセサリーの選び方、急な弔問時の平服など、様々な状況に合わせて適切な服装があります。
もし、急な訃報で喪服が手元にない、体型が変わってしまって持っている喪服が入らない、といったお悩みがあるなら、喪服・礼服のレンタルサービスも一つの選択肢です。
質の良いブランド喪服を、必要な時だけレンタルできるサービスがあります。特に【Cariru BLACK FORMAL】のようなサービスは、デザインや質にこだわりながらも、マナーに沿ったアイテムをフルセットで借りられるので、突然の訃報にも慌てずに済みます。
手元に喪服がない、サイズが合わない、という方は、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
清め塩は本当に必要?現代における清め塩の考え方
ここまで清め塩の由来や作法についてお話ししてきましたが、実は最近では、清め塩を使わない葬儀も増えています。
「故人様を穢れとして扱うのは忍びない」「故人様を尊ぶ気持ちを大切にしたい」というご遺族の考え方が背景にあります。
清め塩は必須ではない。大切なのは「故人への想い」
現代では、清め塩を使うかどうかは、個人の考え方や、ご遺族の意向によって判断されることが多くなっています。
- 「故人の魂を穢れとして扱うのは、どうしても抵抗がある」
- 「故人の生前の考え方を尊重したい」
- 「宗教・宗派の教えを大切にしたい」
こうした理由から、葬儀社側から清め塩の提供を辞退するケースも増えているのです。
もしあなたがご葬儀を主催する立場になったとき、参列者の方に清め塩をお渡しするかどうか迷うかもしれません。そのときは、「故人をどう送りたいか」「ご遺族として、どのような気持ちで故人と向き合いたいか」ということを第一に考えてみてください。
「清め塩を使わないからといって、故人の魂が成仏できない」ということはありません。大切なのは、形ではなく、故人を想い、弔う心です。
葬儀プランを立てる際に確認しておきたいこと
ご葬儀を準備する際には、清め塩の有無を含め、様々なことを決めていく必要があります。
「どの宗派の形式で執り行うか」「どんな規模の葬儀にしたいか」「費用はどれくらいかかるのか」など、ご遺族だけで決めるのは、精神的にも時間的にも大きな負担です。
特に、故人が亡くなられてから数時間以内に葬儀社を決めなければならないケースがほとんどです。そんな切羽詰まった状況で、相場もわからないまま決めてしまうと、「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまうことも少なくありません。
もしあなたが、今まさにそのような状況に直面している、あるいは、将来に備えて情報を集めておきたいと考えているなら、複数の葬儀社から見積もりを取って比較することをお勧めします。
東証プライム上場企業のエスエムエスが運営する【安心葬儀】は、全国7000以上の葬儀社の中から、あなたの希望に合った優良な葬儀社を紹介してくれるサービスです。複数の葬儀社から相見積もりを取ることで、費用やサービス内容を比較検討でき、納得のいく葬儀社を短時間で見つけることができます。
人生で何度も経験することではないからこそ、後悔のないお別れのためにも、信頼できる専門家の力を借りるのが一番安心です。
葬儀を終えた後の「もう一つの大切なこと」:遺品整理と香典返し
清め塩や葬儀そのものについてお話ししてきましたが、葬儀を終えた後にも、大切なことはたくさんあります。
特に、遺品整理と香典返しは、多くのご遺族が頭を悩ませるポイントです。
遺品整理:故人の想いを整理する大切な時間
故人が残された遺品は、一つひとつに思い出が詰まっています。しかし、そのすべてをすぐに整理するのは、精神的にも肉体的にも大きな負担です。
「何から手をつけていいかわからない」「大量の荷物をどう処分すればいいのか」「大切な思い出の品をどう残したらいいのか」といったお悩みは尽きません。
ご遺族だけで全てを抱え込む必要はありません。専門の遺品整理サービスを利用することも、一つの有効な手段です。
遺品整理専門の【ライフリセット】のようなサービスは、故人様のお部屋に残された遺品や不要物の整理を、ご遺族に寄り添いながら進めてくれます。ただ物を片付けるだけでなく、故人の想いを大切にしながら、丁寧に作業を行ってくれます。
「自分たちだけではとても手が回らない…」と感じたら、まずは相談だけでもしてみるのが良いでしょう。
香典返し:感謝の気持ちを伝えるマナー
香典返しは、香典をいただいた方々へ、感謝の気持ちを伝える大切な機会です。
「いつまでに、何を贈ればいいのか」「金額の相場は?」「のし紙や挨拶状はどうすればいい?」など、こちらもマナーが気になるところです。
香典返しを選ぶ際には、相手に失礼のないように、そして心から喜んでもらえる品を選ぶことが大切です。最近では、相手が好きなものを選べるカタログギフトも人気です。
ギフト専門店【シャディギフトモール】では、香典返しに最適な品を、豊富な品揃えの中から選ぶことができます。のし紙やメッセージカードも無料で用意してもらえるので、初めての方でも安心して利用できます。
まとめ:清め塩の風習と、現代を生きる私たちの選択
この記事では、葬儀後の「清め塩」という古くからの風習について、その由来から現代の考え方まで、幅広くお話ししてきました。
- 清め塩は、神道の「死=穢れ」という考え方から生まれた風習であること。
- 自宅に入る前に「左肩、右肩、胸」の順に塩を振りかけるのが正しい作法であること。
- 現代では、故人を穢れとする考え方に抵抗がある人も多く、清め塩を使わない葬儀も増えていること。
清め塩を使うかどうかは、もはや「絶対的なルール」ではありません。
大切なのは、古くからの風習を知り、その上で、故人を想う気持ち、ご遺族としての考え方を大切にすることです。
葬儀という、人生で最も大切な儀式の一つだからこそ、後悔のない選択をしたいものです。
そのために、私がお伝えしたいのは、「わからないことをそのままにしない」ということです。
「これはどうすればいいんだろう?」「どうしてこんな風習があるんだろう?」と疑問に感じたことは、遠慮せずに葬儀社のプランナーに相談してみてください。また、私のようなブログを運営している元プランナーも、少しでも力になれればと思っています。
「家族を想うお葬式ガイド」では、他にも葬儀に関する様々な情報を発信しています。ぜひ、今後の備えとして、また、もしもの時に備えて、お役立ていただけたら嬉しいです。
後悔のないお別れのために、今できる準備を一緒に考えていきましょう。
筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。