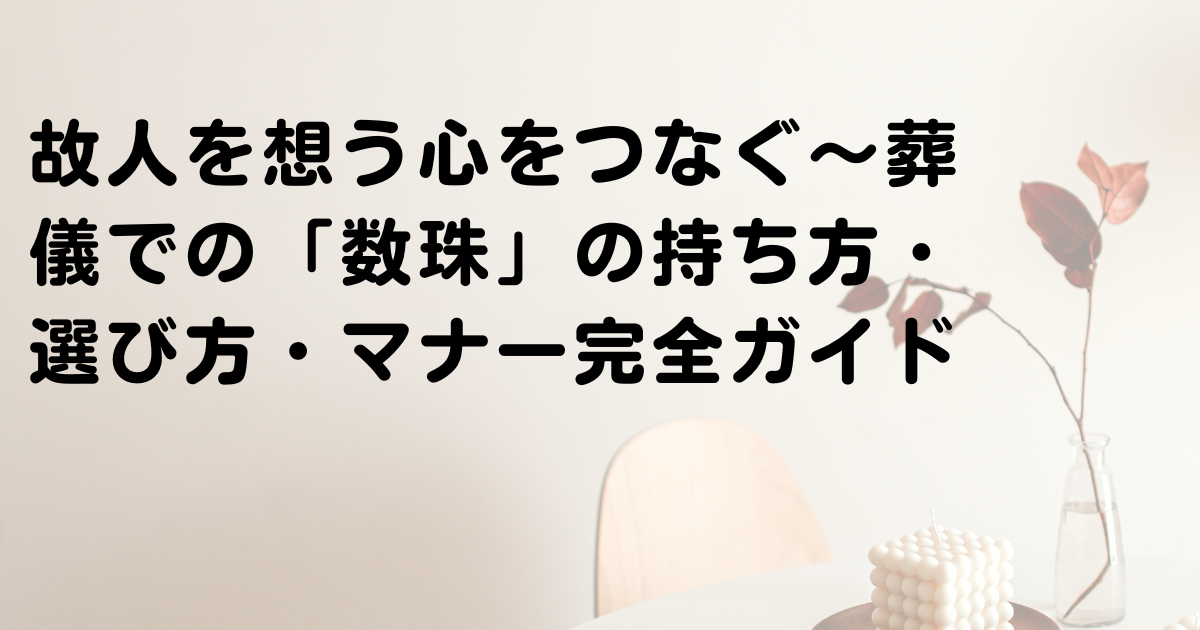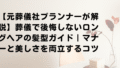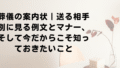こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
はじめに:葬儀で数珠を持つ意味とは
大切なご家族やご友人との別れ。
突然の訃報に接し、心身ともに大変な中で、お通夜やお葬式に参列されることと思います。
その際、「数珠」をどのように扱えばよいか、ふと立ち止まってしまった経験はありませんか?
- 「数珠って、どう持てばいいんだっけ?」
- 「宗派によって違うって聞いたけど、うちの宗派がわからない」
- 「そもそも、なぜお葬式に数珠が必要なの?」
慣れない場面だからこそ、ちょっとした作法やマナーに不安を感じてしまうのは、ごく自然なことです。
このブログは、かつて葬儀社のプランナーとして800件以上のご葬儀に立ち会ってきた私が、皆さまが安心して故人様とのお別れの時間を過ごせるよう、数珠の基本から応用まで、わかりやすく解説するものです。
数珠の正しい持ち方、宗派ごとの違い、選び方、そして忘れてはいけないマナーまで、知っておくべきことをすべて網羅しました。
この記事を最後まで読んでいただければ、もう数珠について迷うことはなくなります。
故人様への想いを込めて、正しい作法でお見送りをするための手助けになれば幸いです。
数珠を持つのは「故人様や仏様への敬意」を表す大切な行為
そもそも、なぜお葬式で数珠を持つのでしょうか。
数珠は、仏教の儀式で用いられる仏具であり、もともとはお経を唱えた回数を数えるために使われていました。しかし、それ以上に大切な意味が込められています。
それは、「故人様や仏様への敬意」、そして**「自分自身を守るためのお守り」**という2つの側面です。
仏教の世界では、数珠は「念珠(ねんじゅ)」とも呼ばれ、煩悩を払うための道具とされています。
108個の珠は、人間の持つ108の煩悩を表しており、これらを数珠で数え、一つ一つ消していくという修行の意味合いがありました。
現代では、そこまで厳密な意味合いを持つ場面は少なくなりましたが、それでも「数珠を手にすることで、心が落ち着き、故人様と向き合うことができる」という方は多くいらっしゃいます。
また、数珠は「仏様との縁を結び、守護していただくための道具」とも考えられています。
ご葬儀という厳粛な場で数珠を手にすることは、仏様に故人様が安らかに旅立てるよう祈り、また、悲しみに暮れる自分自身の心を静めるための、大切な行いなのです。
ですから、数珠はただのアクセサリーではありません。
故人様への敬意と、自身の心を整えるための、大切な「心のよりどころ」なのです。
次に、具体的な持ち方について見ていきましょう。
一口に数珠といっても、宗派によって持ち方や形が異なります。
ご自身の宗派が分からない場合は、後ほどご紹介する「略式数珠」をご利用いただくのが一般的で安心です。
【基本の持ち方】宗派を問わない「略式数珠」の持ち方
まず、もっとも一般的な「略式数珠」の持ち方からご説明します。
略式数珠は、宗派を問わずどなたでもお使いいただける、一重の輪になった数珠です。
珠の数は108個よりも少なく、男女で珠の大きさが異なるのが一般的です。
女性用は珠が小さく華奢なものが多く、男性用は珠が大きめでどっしりとしたものが多いです。
この略式数珠の持ち方は、非常にシンプルです。
- 焼香のとき左手の親指と人差し指の間に数珠を挟むように持ち、房が下に垂れるようにします。 【ポイント】 右手で焼香を行いますので、左手に持つのが基本です。
- 座っているとき・立っているとき左手首にかけます。あるいは、左の手のひらで、房が下になるように軽く握ります。 【ポイント】 数珠を椅子や床、畳の上に直に置くのはマナー違反とされています。必ずご自身の手に持っておくようにしましょう。
これが、もっとも基本的な略式数珠の持ち方です。
では、次に宗派ごとの正式な数珠の持ち方を見ていきましょう。
「うちの宗派はどれだろう?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ご自身の宗派がわからなくても、略式数珠を正しく持っていれば、失礼にはあたりませんのでご安心ください。
ただ、もしご自身の宗派がわかれば、より丁寧に故人様をお見送りすることができますので、この機会に少し学んでみませんか?
宗派ごとの数珠の持ち方と特徴
宗派ごとの数珠は、**「本式数珠」**と呼ばれ、珠の数が108個であることが基本です。
形や持ち方、房の形にも特徴があり、宗派ごとに独自の作法が定められています。
ここでは、主要な宗派の数珠の持ち方と特徴をご紹介します。
ご自身の宗派の欄をぜひご覧ください。
浄土真宗
- 数珠の特徴: 珠が二重の輪になっており、房が蓮の花の形をしています。房が一本のものと二本のものが存在します。
- 持ち方: 合掌するとき 二重になった数珠を両手にかけて合掌します。このとき、房が両手の間にくるように垂らします。 合掌していないとき 左手首にかけておきます。
- 【注意点】 浄土真宗では、数珠を擦り合わせる行為はしません。これは、煩悩を払うという考え方が他宗派とは少し異なるためです。
浄土宗
- 数珠の特徴: 「日課数珠」と「念珠」の2種類を使い分けます。日課数珠は、主玉が2つの輪になっており、その間に木製の平たい珠が通されています。
- 持ち方: 合掌するとき 数珠の輪を親指と人差し指で挟み、両手にかけ、房が下に垂れるようにして合掌します。 合掌していないとき 左手首にかけておきます。
日蓮宗
- 数珠の特徴: 他の宗派と比べて少し特殊な形をしています。珠が二重の輪になっており、房が三本の部分と二本の部分があります。
- 持ち方: 合掌するとき 数珠の房が三本の部分を左手の中指に、房が二本の部分を右手にかけ、両手で挟んで合掌します。このとき、数珠の輪が八の字になるようにするのが特徴です。 合掌していないとき 左手首にかけておきます。
真言宗
- 数珠の特徴: 「振分(ふりわけ)念珠」とも呼ばれ、珠が108個あり、他の宗派に比べて珠が大きめです。
- 持ち方: 合掌するとき 二重の輪を両手にかけて合掌します。このとき、数珠を両手で挟み、親指と人差し指の間に数珠の輪を引っかけるように持ちます。 合掌していないとき 左手首にかけておきます。
曹洞宗・臨済宗
- 数珠の特徴: 珠が二重の輪になっており、金属の輪が通されているのが特徴です。
- 持ち方: 合掌するとき 左手の親指と人差し指の間に数珠を挟み、右手を添えて合掌します。あるいは、二重の輪を両手にかけて合掌します。 合掌していないとき 左手首にかけておきます。
葬儀における数珠の「絶対にしてはいけないこと」
ここまで数珠の正しい持ち方についてご説明してきましたが、実は「これは絶対に避けるべき」というマナー違反がいくつかあります。
故人様への敬意を欠くことのないよう、特に注意すべき点をまとめました。
- 数珠を貸し借りする 数珠は「持ち主の分身」ともいえる、個人的な仏具です。ですから、ご家族であっても、貸し借りは絶対にやめましょう。 もし数珠を忘れてしまったり、持っていなかったりした場合は、無理に借りる必要はありません。数珠を持たずにご焼香をしても、決して失礼にはあたりませんのでご安心ください。
- 数珠をポケットやバッグに直接入れる 数珠は、仏様との縁を結ぶ大切な仏具です。無造作にポケットに入れたり、バッグの中に他の物と一緒に入れたりするのは、敬意を欠く行為とされています。必ず専用の数珠袋に入れるようにしましょう。
- 数珠を椅子や床、畳の上に直に置く これも、数珠を大切に扱っていないと見なされてしまう行為です。座っているときや立っているときは、必ずご自身の手に持っておきましょう。ご自宅などで保管する際も、仏壇の近くなど、清浄な場所に置いておくのが望ましいです。
- 宗派の違う数珠を使う 略式数珠であれば問題ありませんが、ご自身の宗派とは違う宗派の「本式数珠」を使うのは避けるべきです。もしご自身の宗派が分からない場合は、略式数珠を使うのが最も安心な選択です。
これらのマナーは、故人様と、そして仏様と向き合う大切な時間への敬意を表すものです。
ぜひ心に留めておいてください。
数珠を「持っていない」「急な訃報で用意できない」ときの対処法
「急な訃報で数珠を用意する暇がなかった…」
「数珠をどこにしまったか見つからない…」
「そもそも数珠を持っていない」
こんな状況に直面することは、決して珍しくありません。
結論から申し上げますと、数珠を持っていなくても、ご葬儀に参列することは全く問題ありません。
故人様への供養の心こそが最も大切であり、数珠の有無でその想いが決まるわけではありません。
しかし、「できればちゃんとしたものを用意したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、現代では様々なサービスがあります。
例えば、急なご葬儀で喪服と一緒に数珠も用意したい、という場合に便利なのが、喪服や礼服のレンタルサービスです。
ブランド物の喪服や、マナーに沿ったフルセット(喪服、バッグ、数珠、袱紗など)をレンタルできるサービスもあります。
喪服・礼服のレンタル「Cariru BLACK FORMAL」
急なご葬儀でも安心。喪服・礼服のレンタルサービス「Cariru BLACK FORMAL」は、高品質なブランド喪服を、必要な時に必要なだけ借りられる便利なサービスです。
ジャケット、ワンピース、バッグ、サブバッグ、ネックレス、イヤリング、数珠、袱紗まで、弔事のマナーに沿って厳選されたフルセットが豊富に揃っています。
ネットで24時間いつでも申し込め、16時までの注文で最短翌日午前中にお届け可能です。
購入するよりもずっとリーズナブルに、上質なフォーマルを身につけることができます。
急なご不幸に際し、ご準備が間に合わない方、サイズやデザインが合わなくなってしまった方におすすめです。
返却時のクリーニングは不要。安心してご利用いただけます。
このようなサービスを賢く利用すれば、急なご不幸にも慌てずに、きちんと身だしなみを整えて参列することができます。
故人様への想いを、きちんとした作法と装いで伝えるための一つの選択肢として、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
数珠の選び方:ご自身の「一生もの」を見つけるために
数珠は、一度購入したら長く使うものです。
故人様への想いを込めて、ご自身の「一生もの」となる数珠を見つけたいものです。
ここでは、数珠の選び方について、いくつかのポイントをお伝えします。
珠の素材で選ぶ
数珠に使われる珠の素材は、本当に多種多様です。
大きく分けると、「天然石」「木製」「樹脂製」の3つに分類できます。
- 天然石: 水晶、翡翠、虎目石、メノウ、真珠など、美しい輝きを放つものが多く、高級感があります。 【水晶】:浄化の力があるとされ、もっともポピュラーな素材です。 【虎目石(タイガーアイ)】:金運や仕事運を高めるとされ、男性に人気があります。 【翡翠】:古くから魔除けや幸運のお守りとされてきました。
- 木製: 黒檀、紫檀、伽羅(きゃら)、白檀(びゃくだん)など、温かみのある素材です。 【黒檀・紫檀】:耐久性が高く、使い込むほどに艶が増します。 【白檀】:ほのかに香りが漂い、心を落ち着かせる効果があるとされています。
- 樹脂製: 安価で手軽に手に入ります。見た目も天然石や木製に似せて作られているものが多いです。
- 【選び方のポイント】 ご自身の好きな色や素材、あるいは「お守り」として意味のあるものを選んでみてはいかがでしょうか。故人様との思い出の色や、故人様が愛した木材など、想いを込めて選ぶのも素敵なことです。
珠の大きさで選ぶ
数珠の珠の大きさは、性別や手の大きさによって選びます。
- 女性: 一般的に、珠の直径が6〜7mm程度のものが主流です。手のひらに収まる、華奢で上品な印象のものが多いです。
- 男性: 一般的に、珠の直径が10〜12mm程度のものが主流です。手のひらにしっかりと収まる、存在感のあるものが好まれます。
- 【選び方のポイント】 実際に手に取って、ご自身の手に馴染むかどうかを確かめるのが一番です。インターネットで購入する場合は、珠のサイズをよく確認しましょう。
宗派によって選ぶ
先ほどもご説明した通り、ご自身の宗派が分かっている場合は、その宗派の「本式数珠」を選ぶのが最も丁寧です。
もし宗派が分からない場合は、宗派を問わない「略式数珠」を選ぶのが一般的で、失礼にあたることはありません。
これからお葬式に参列する機会が増えていく年代の方は、ご自身の宗派の数珠を一つ持っておくと安心です。
葬儀後に役立つ情報:遺品整理・香典返しについて
お葬式が終わった後も、故人様に関わる手続きや整理は続きます。
悲しみの中で、様々なことに向き合わなければならないのは、本当に大変なことです。
ここでは、ご遺族様が直面されるであろう「遺品整理」と「香典返し」について、少しお話をさせてください。
遺品整理:故人様との思い出を大切に、丁寧に
故人様が残された品々を整理する「遺品整理」。
これは、単なる片付けではありません。
故人様との思い出一つ一つに向き合い、感謝を伝えながら、新たな一歩を踏み出すための大切な時間です。
しかし、お一人で全てをこなすのは、心身ともに大きな負担がかかります。
特に、遠方に住んでいてなかなか実家に帰れない、物が多すぎてどこから手をつけていいかわからない、といったお悩みはよく耳にします。
そんな時は、専門の業者に相談するのも一つの手です。
専門の遺品整理業者は、故人様の尊厳を守りながら、丁寧に遺品を整理してくれます。
また、思い出の品の供養や、形見分けのお手伝いもしてくれる場合が多いです。
遺品整理専門サービス「ライフリセット」
故人様のお部屋に残された遺品や不要物の整理を、専門家がお手伝いします。
遺品整理専門「ライフリセット」は、ご遺族様の心に寄り添い、丁寧かつ迅速な作業を行います。
遠方にお住まいでなかなか実家に帰れない方、作業量が多すぎて困っている方、何から手をつければいいか分からない方など、多くの方にご利用いただいております。
ご遺族様のご負担を少しでも減らし、故人様を心安らかに供養するためのお手伝いをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
専門家の力を借りることも、ご自身と故人様を大切にするための選択です。
ご無理をなさらず、プロに頼むことも視野に入れてみてください。
香典返し:感謝の気持ちを伝える贈り物
お葬式でいただいた香典へのお返し「香典返し」。
これもまた、慣れないことばかりで戸惑われる方が多いのではないでしょうか。
香典返しには、いくつかマナーがあります。
- 時期: 忌明け(一般的には四十九日法要の後)から1ヶ月以内に贈るのが一般的です。
- 金額: いただいた香典の半額〜3分の1程度の金額の品物を選ぶのが一般的です。
- 品物: 日用品や食品など、「不幸が後に残らない」という意味合いで「消えもの」を選ぶのがマナーとされています。 例えば、お茶やコーヒー、お菓子、海苔、洗剤、タオルなどがよく選ばれます。
現代では、弔事の贈り物に特化したギフト専門店を利用する方が増えています。
のし紙やメッセージカード、包装など、マナーに沿って丁寧に対応してくれるので、安心してお任せできます。
香典返しについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
ギフト専門店「シャディギフトモール」
香典返しやお祝いごとのお返しなど、様々な用途に対応できるギフト専門店です。
【シャディ公式】内祝や、お返しも!ギフト専門店【シャディギフトモール】は、創業1926年の実績と信頼で、1万点以上の商品を揃えています。
弔事のマナーに沿ったのし紙や包装、メッセージカードも無料でご用意。
人気のカタログギフトをはじめ、お菓子、コーヒー、洗剤など、故人様への想いを込めた香典返しに最適な品々が豊富に揃っています。
贈り物の専門家が、皆さまの気持ちを形にするお手伝いをいたします。
初めての方でも安心してお任せください。
お葬式に関する不安は、専門家に相談する時代へ
お葬式は、人生で何度も経験するものではありません。
だからこそ、ご準備や手続き、費用のことなど、様々な不安がつきまといます。
ましてや、ご逝去後わずかな時間で葬儀社を決めなければならないことも多く、十分な検討ができないまま進んでしまうケースも少なくありません。
- 「相場はいくらくらいなのだろう?」
- 「信頼できる葬儀社はどうやって見つければいいのだろう?」
- 「家族葬にしたいけど、どうすればいい?」
そういったお葬式に関する疑問や不安は、一人で抱え込まず、専門家に相談するのが一番です。
現在は、インターネット上で複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討できるサービスもあります。
【安心葬儀】全国の斎場・葬儀社を探せる相見積もりサービス
お葬式は、十数万円〜数百万円とまとまった費用がかかる上、葬儀社によってその品質にも差があります。
人生に一度きりの大切な儀式だからこそ、後悔のないお葬式をしたいものです。
全国7000以上の葬儀社からご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社をご紹介する【安心葬儀】は、東証プライム上場企業のエスエムエスが運営するサービスです。
時間がない中でも、複数の葬儀社から相見積もりを取ることができ、費用や内容をじっくり比較検討できます。
信頼できる葬儀社と出会い、故人様との最期の時間を大切に過ごすために、ぜひご活用ください。
事前に情報を集めておくこと、そしていざという時に頼れる場所を知っておくことは、ご自身やご家族の「安心」につながります。
終活の一環として、少しずつお葬式に関する知識を深めていくことをお勧めします。
こちらもぜひ参考にしてください。
まとめ:故人様への想いを込めて、丁寧に数珠を扱うこと
この記事では、葬儀における数珠の持ち方、宗派ごとの違い、選び方、そしてマナーについて詳しく解説してきました。
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 数珠は、故人様や仏様への敬意、そして自分自身のお守りとして持つ大切な仏具です。
- 宗派を問わない略式数珠は、左手に持つのが基本です。
- 宗派ごとの本式数珠は、それぞれの作法に沿って丁寧に扱いましょう。
- 数珠の貸し借りや、床に直に置くことは避けましょう。
- 数珠を持っていない場合は、無理に借りる必要はありません。
数珠は、単なる形式的なものではなく、故人様への想い、そしてご自身の心を静めるための大切な道具です。
形式に縛られすぎず、故人様への敬意を第一に、心からのお見送りをすることが何よりも大切です。
この記事が、皆さまが安心して故人様と向き合うための一助となれば幸いです。