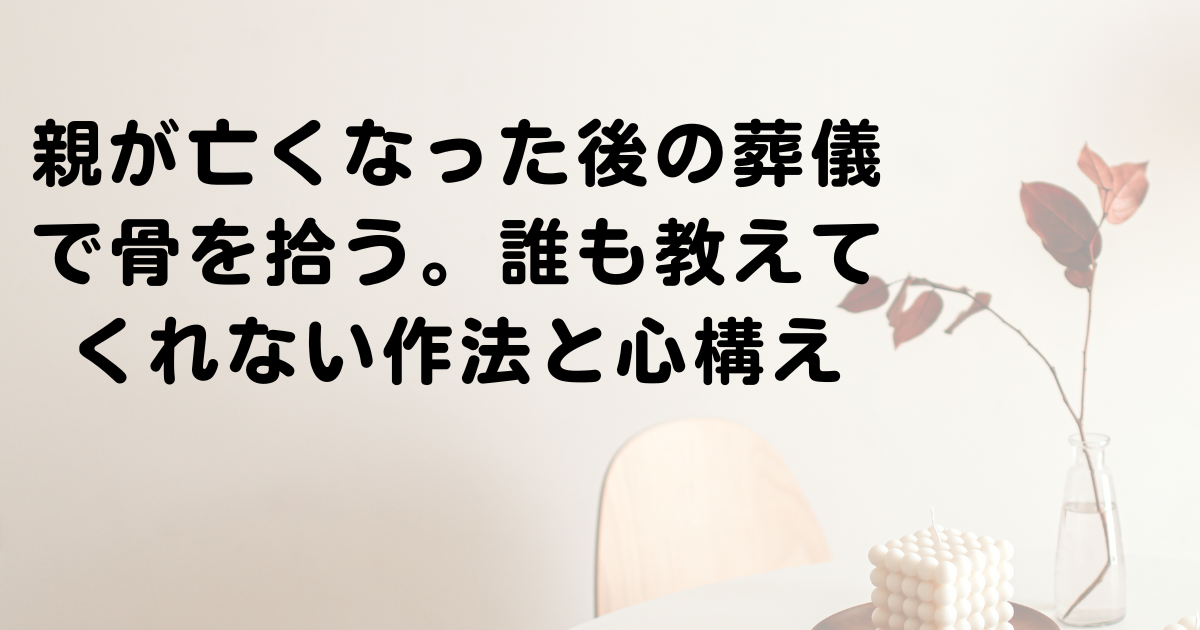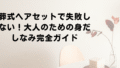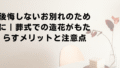こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに800件以上のご葬儀を担当させていただきました。私自身も20代で父を亡くし、何もわからず途方に暮れた経験があります。だからこそ、ご遺族の不安や戸惑いを少しでも和らげたいと、日々このブログを書いています。
さて、ご葬儀のなかでも、多くの人が戸惑われることのひとつに「お骨拾い(こつひろい)」があります。故人様のお骨を、ご遺族で箸を使って骨壷に納める「収骨(しゅうこつ)」の儀式のことですね。
「骨を拾うって、どうやるの?」「なにかマナーはあるの?」
突然のことで、こうした疑問が頭をよぎる方も多いのではないでしょうか。とくに初めて経験される方は、何をどうすればいいのかわからず、不安に感じられるかもしれません。
この儀式は、故人様との最後の、そして最も大切な「お別れ」のひとときです。しかし、事前に予習する機会はほとんどありません。だからこそ、ここではお骨拾いの意味から、具体的な作法、心構えまで、私の経験をもとに詳しくお伝えしたいと思います。
この記事を読んでいただければ、当日の不安が少しでも軽くなり、故人様との最後の時間を穏やかな気持ちで過ごせるようになるはずです。
骨を拾うとは?火葬後の「お骨拾い」のすべて
「お骨を拾う」という言葉はよく聞きますが、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。まずは、この儀式の正式名称や、なぜお骨拾いをするのか、といった基礎知識から見ていきましょう。
「お骨拾い」の正式名称は「収骨」
私たちが日常的に使う「お骨拾い」という言葉は、厳密には「収骨(しゅうこつ)」と呼ばれます。
ご遺体を火葬炉に入れ、火葬が終わった後、ご遺族が骨壷にご遺骨を納める一連の儀式を指します。
火葬炉から出てきたばかりのご遺骨は、まだ熱を帯びていることもあります。お骨拾いは、この熱いご遺骨を、故人様が生きていた証として大切に拾い集める、厳かで重要な儀式なのです。
なぜ骨を拾うのか?その深い意味とは
なぜ、私たちは故人様のご遺骨を拾うのでしょうか。それには、いくつかの意味があります。
1. 故人様との最後の対面と別れ
お骨拾いは、故人様のお姿と触れ合える最後の機会です。
火葬後のご遺骨は、故人様が生きていたことの確かな証。そのご遺骨をひとつひとつ丁寧に拾い上げることは、故人様との思い出をたどり、別れを心で受け入れる大切な時間となります。
2. 故人様の旅立ちを見送る
仏教では、ご遺骨を拾う行為を「拾骨供養(しゅうこつきょうよう)」と呼び、故人様が極楽浄土へ旅立つためのお手伝いだと考えられています。
ご遺族が箸を使ってご遺骨を拾い上げ、骨壷に納めることで、故人様が無事に旅立てるようにとの願いを込めるのです。
3. ご遺族の心の整理
突然の死別の場合、ご遺族は悲しみや混乱のなかで、現実を受け止めきれないことも少なくありません。
お骨を拾うという行為は、故人様が「亡くなった」という事実をあらためて認識し、少しずつ心の整理をつけていくための大切なプロセスでもあります。
ご遺骨に触れることで、「ああ、本当に逝ってしまわれたんだな」と実感し、心のなかで少しずつお別れをしていくのです。
お骨拾いの基本的な流れと作法
では、具体的にどのような流れで、どのような作法でお骨拾いを行うのでしょうか。
火葬場によって多少の違いはありますが、ここでは一般的な流れをご紹介します。
1. 火葬後の準備
火葬が終わり、火葬場のスタッフから声がかかると、ご遺族は収骨室へと案内されます。収骨室の中央には、ご遺骨が残された台が置かれており、その周りにご遺族やご親族が並びます。
スタッフからご遺骨の状態や、どの骨が体のどの部分にあたるかの説明があることが一般的です。
2. 「箸渡し」の儀式
お骨拾いは、通常「箸渡し(はしわたし)」という独特の作法で行われます。これは、2人1組で、箸を使ってご遺骨を骨壷へと渡していく儀式です。
なぜ箸を使うのか?
箸には「故人様をこの世からあの世へ渡すための橋渡し」という意味が込められていると言われています。
また、普段使いの箸とは違い、火葬場では竹製の長い箸が用意されることが多いです。
箸渡しの手順
- ご遺族の代表者(喪主やその配偶者など)から順に、2人1組になります。
- まず、1人が箸でご遺骨を挟みます。
- そのご遺骨を、もう1人が持った別の箸で受け取ります。
- 受け取ったご遺骨を、そのまま骨壷の中に静かに納めます。
これを、ご遺族全員が順番に行っていきます。
注意点
- 「あの世とこの世の橋渡し」という意味合いから、箸から箸へ食べ物を渡す「箸渡し」は、普段の食事では縁起が悪いとして避けられています。
- もし人数が奇数になった場合は、無理に2人組にならず、1人で拾っても問題ありません。大切なのは「故人様を想う気持ち」です。
3. 足元から頭部へ、順番に骨を拾う
お骨を拾う順番には、決まった作法があります。
これは、故人様が立った状態で極楽浄土へ旅立てるようにという願いが込められているからです。
一般的な順番
- 足の骨
- 腕の骨
- 腰の骨
- 背骨
- 歯
- 頭蓋骨
最後に、ご遺族のなかで最も故人様と関係が深い方(喪主など)が、**喉仏(のどぼとけ)**を拾うことが一般的です。
喉仏は、仏様が座禅を組んでいる姿に見えることから、とくに重要視される部位です。この喉仏を最後に納めることで、故人様が安らかに旅立てると考えられています。
すべての骨を拾い終えると、火葬場のスタッフが骨壷の蓋を閉め、専用の袋に納めてくれます。
葬儀のマナーは知っていても、お骨拾いの服装は?
ご葬儀に参列する際の服装は、多くの人が事前に準備されます。
しかし、お骨拾いのときの服装について、とくに意識される方は少ないかもしれません。火葬場での服装は、ご葬儀のときと同じで問題ありません。
喪服を着ていれば大丈夫です。
ご葬儀当日、火葬場まで同行される方は、そのまま喪服を着ていらっしゃるでしょう。
万が一、ご葬儀には参列せず、火葬場から参加される方も、**準喪服(平服)か略喪服(略式喪服)**を着用するのがマナーです。
とくに女性は、急な訃報で喪服を準備する時間がない、ということもあるでしょう。そんなときは、喪服のレンタルサービスを利用するのもひとつの手です。
【Cariru BLACK FORMAL】は、質の高いブランド喪服や礼服をネットで簡単に借りられます。3泊4日から利用でき、ジャケットやワンピース、バッグ、数珠までフルセットで届くので、急なときでも慌てずにすみます。
喪服は年に何度も着るものではないですし、サイズが変わってしまったり、流行のデザインと合わなくなってしまったりすることもあります。レンタルなら、必要なときに、マナーに沿った上質な一着を用意できるので安心ですね。
もし、ご自身の喪服で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひ選択肢のひとつとして検討してみてください。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
もし葬儀の服装全般について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
心構えと注意点:お骨拾いを穏やかに迎えるために
お骨拾いをするときに、どのような心構えで臨めばよいのでしょうか。
私は、プランナーとして多くのご遺族と接してきましたが、この儀式を経験することで、心の整理がつき、前向きな一歩を踏み出される方も少なくありませんでした。
大切なのは、「故人様との最後の時間」だということを意識することです。
1. 故人様への感謝の気持ちを込めて
お骨拾いは、故人様との生前の思い出をたどり、感謝の気持ちを伝える最後の機会です。
「ありがとう」「お疲れ様でした」といった言葉を心の中で唱えながら、ゆっくりと、ひとつひとつ丁寧に骨を拾ってください。
とくに、故人様が生前大切にされていたものや、思い出深いエピソードを思い出しながら行うと、より心温まる時間になるでしょう。
2. 泣いても大丈夫、感情を抑える必要はない
悲しい気持ちは、抑えつける必要はありません。
涙がこぼれても、それは故人様への深い愛情の表れです。火葬場は、故人様を送り出すための場所。周囲の目を気にする必要はありません。
ご遺族が泣く姿を見て、故人様はきっと「自分のことを思ってくれている」と喜んでくださるでしょう。
3. 火葬場のスタッフに遠慮なく質問する
「この骨はどこの部分ですか?」 「どうやって拾えばいいですか?」
わからないことがあれば、遠慮なく火葬場のスタッフに質問してください。
スタッフは、ご遺族が安心して儀式に臨めるよう、丁寧にサポートしてくれます。恥ずかしいことではありませんので、心配なこと、疑問に思うことは、なんでも聞いてみましょう。
葬儀の準備、骨を拾う前の心構え
お骨拾いは、ご葬儀の一連の流れのなかで行われます。そのため、故人様を送り出すための準備も、お骨拾いを迎えるうえで非常に大切になってきます。
突然の訃報で、頭が真っ白になってしまうのは当然のことです。それでも、ご遺族としていくつか決めておかなければならないことがあります。
1. 葬儀社選びが後悔しないお別れへの第一歩
葬儀は、人生で何度も経験するものではありません。そのため、多くの方が「何から始めればいいかわからない」「どの葬儀社を選べばいいの?」と戸惑います。
しかし、葬儀社の決定は、故人様が逝去されてから数時間以内に行うことがほとんどです。時間がないなかで、複数の葬儀社を比較検討するのは非常に難しいのが現実です。
良い葬儀社を選ぶことは、故人様を丁寧に送り出し、後悔のないお別れを迎えるための第一歩となります。
そこでおすすめなのが、東証プライム上場企業のエスエムエスが運営する**【安心葬儀】**です。
このサービスを利用すれば、全国7000以上の提携葬儀社から、ご希望の条件に合った優良葬儀社を無料で紹介してもらえます。
相見積もりを取ることで、費用やサービス内容を比較検討できるため、時間がない中でも、適正価格で質の高い葬儀社を見つけることができます。
「家族を想うお葬式ガイド」のブログでも、葬儀社の選び方について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
2. 葬儀の全体像を知っておく
お骨拾いは、ご葬儀のなかのひとつの儀式です。全体の流れを把握しておくことで、当日の不安が軽減されます。
故人様を自宅から送り出し、お通夜、告別式、火葬、そしてお骨拾いへ。それぞれの儀式がどのような意味を持つのか、事前に知っておくことで、より心を込めて故人様を送り出せるでしょう。
もし、葬儀の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事が参考になります。
お骨拾い後のこと:遺骨の行方と供養
お骨拾いが終わり、骨壷がご遺族の手に渡ると、次の疑問がわいてきます。
「この骨壷、どうすればいいの?」 「いつまで家に置いておけばいいの?」
ここでは、お骨拾い後のご遺骨の供養について、いくつかの選択肢をご紹介します。
1. 納骨までの流れ
納骨とは、ご遺骨をお墓や納骨堂などに納めることです。
一般的には、ご四十九日(しじゅうくにち)の法要を目安に納骨することが多いですが、法律で定められた期限はありません。
ご遺族の気持ちの整理がつくまで、自宅に安置していても問題ありません。
2. 遺骨の供養方法の選択肢
お墓 最も一般的な供養方法です。先祖代々のお墓に納めるか、新しくお墓を建てることになります。
納骨堂 お墓の代わりに、屋内の施設にご遺骨を預ける方法です。お墓を建てるよりも費用が抑えられ、天候を気にせずにお参りできるのが特徴です。
樹木葬 ご遺骨を樹木や草花の下に埋葬する方法です。自然にかえりたいという故人様の意思を尊重する供養方法として、近年注目を集めています。
手元供養 ご遺骨の一部を、自宅で供養する方法です。遺骨ペンダントやミニ骨壷など、故人様を身近に感じられる形で供養できます。
どの方法を選ぶかは、ご遺族の考え方や、故人様の生前の意思によって異なります。
骨を拾うという行為がもたらす心の変化
私自身、父を亡くした際、火葬場でお骨を拾ったときのことは今でも鮮明に覚えています。
幼い頃、父に肩車をしてもらったときのことを思い出しながら、その骨をそっと拾い上げました。その瞬間、悲しみと同時に、父への感謝の気持ちがこみ上げてきたのです。
骨を拾うという行為は、故人様との物理的なお別れであると同時に、心のなかで故人様の存在を永遠のものにする、「心の終活」でもあります。
ご遺骨に触れることで、「この人は、この世に確かに生きていたんだ」という事実を、五感を通して受け止めることができるのです。
そして、その事実を受け入れたとき、私たちは少しずつ前に進む勇気をもらえます。
お骨拾いは、悲しい儀式ではありません。故人様との思い出を確かめ合い、感謝を伝え、そして前向きに生きていくための力をいただく、大切な時間なのです。
この記事が、もしものときに、あなたのお骨拾いに対する不安を少しでも和らげ、故人様との最後の時間を穏やかに過ごすための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
遺品整理も心の整理です
ご葬儀が終わった後、ご遺族を待っているのが遺品整理です。
故人様が大切にされてきた品々を整理する作業は、時間も手間もかかります。また、故人様との思い出が詰まった遺品を前にすると、なかなか作業が進まない、という方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、遺品整理の専門業者に依頼するのもひとつの方法です。
【ライフリセット】は、遺品整理を専門に行うプロフェッショナルです。
「実家の両親が亡くなって、遠方に住んでいるので片付けられない」 「悲しくて、なかなか遺品に手をつけることができない」
そういった方々を、丁寧にサポートしてくれます。
遺品整理は、単なる物の片付けではありません。故人様の人生を振り返り、ご遺族が新たな一歩を踏み出すための「心の整理」でもあります。
無理に自分たちだけで抱え込まず、プロの力を借りることも、ご遺族自身の負担を減らすことにつながります。
終わりに
今回は「葬式 骨を拾う」というテーマで、お骨拾いの作法や意味、心構えについてお伝えしました。
お骨拾いは、ご葬儀のなかでも、故人様と最も深く向き合う時間です。
- 故人様との最後の対面
- 感謝を伝える大切な時間
- 心の整理をつけるための儀式
この記事を読んでくださった方が、もしものときに、少しでも穏やかな気持ちで故人様を送り出せることを心から願っています。
そして、ご葬儀に関するご不安や疑問があれば、いつでもこのブログを訪ねてきてください。
これからも、あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて情報を発信していきます。