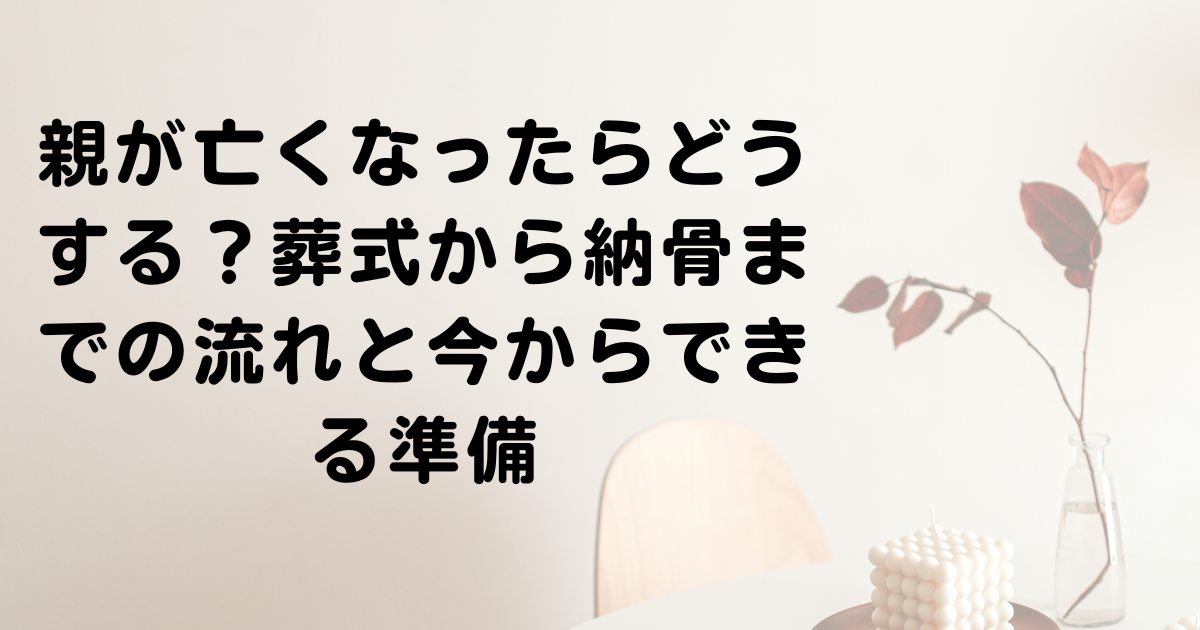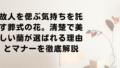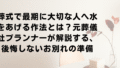筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまで800件を超えるご葬儀を担当してきました。突然父を亡くした経験から「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」という一心で、葬儀の世界に飛び込みました。
葬儀の現場では、ご遺族の不安や戸惑いに寄り添い、多くのご相談を受けてきました。その中で強く感じたのは、情報の差によって、後悔の残るお別れになってしまう方が多いという現実です。
この記事では、ご家族を亡くされた方が直面する「葬式から納骨までの流れ」を、私の経験を交えながら、分かりやすく丁寧に解説していきます。
大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な状況かと思います。この情報が、少しでも皆さまの心の負担を軽くし、「後悔しないお別れ」の準備に役立つことを願っています。
はじめに:突然の別れに備える心構え
ご家族が亡くなることは、誰もが直面する可能性のあることです。しかし、その時になって初めて「何をすればいいのか分からない」と途方に暮れてしまう方がほとんどです。
特に、ご高齢のご両親が遠方で暮らしている場合や、ご本人に持病がある場合など、もしもの時に備えて準備をしておくことは、残されるご家族にとって大きな安心につながります。
この記事では、葬儀から納骨、その後の手続きまで、一連の流れを時系列に沿ってご説明します。一つひとつのステップを理解することで、いざという時の心の準備ができるだけでなく、ご遺族が冷静に対応できるようになります。
葬式当日の流れを把握する前に:まず何をすべきか
大切な方を亡くされた直後、ご遺族は深い悲しみの中にいらっしゃいます。しかし、悲しみに浸る間もなく、さまざまな手続きや手配に追われることになります。
ここでは、まず行うべき重要なステップを3つに分けてご説明します。
- ご臨終の確認と死亡診断書(死体検案書)の受け取り
病院で亡くなられた場合は、医師から死亡診断書が発行されます。ご自宅で亡くなられた場合は、かかりつけ医、または監察医による死体検案が行われ、死体検案書が発行されます。
この書類は、死亡届の提出や火葬許可証の発行に不可欠な、非常に重要な書類です。紛失しないよう、大切に保管してください。
- ご遺体の安置場所の確保
亡くなられた場所からご遺体を運び、安置する必要があります。ご自宅に連れて帰るか、葬儀社の安置施設を利用するか、選択肢はいくつかあります。
- ご自宅での安置:故人が住み慣れた家で最期の時間を過ごさせてあげたいと願うご家族に選ばれています。ただし、安置場所の確保や、暑い時期は冷房管理を徹底するなど、注意が必要です。
- 葬儀社の安置施設:多くの葬儀社は、ご遺体をお預かりする施設を持っています。衛生面やセキュリティ面で安心して預けられるため、ご自宅での安置が難しい場合に適しています。
- 葬儀社の選定と連絡
ご遺体の安置場所を決めたら、すぐに葬儀社に連絡しましょう。多くの場合、ご遺体の搬送から葬儀の準備まで一貫して手配してくれます。
「どの葬儀社に頼めば良いのだろう…」と迷われる方も多いでしょう。時間がない中で焦って決めてしまい、後から後悔するケースも少なくありません。
もしもの時に備えて、あらかじめ複数の葬儀社から見積もりを取っておくことをお勧めします。
【安心葬儀】 のようなサービスを利用すれば、複数の葬儀社から一括で見積もりを取ることができ、比較検討に役立ちます。
「東証プライム上場企業のエスエムエスが運営する【安心葬儀】の相見積もりサービスを利用することで、時間がない中でも、良い葬儀社を安心して見つけることができます。全国7000以上の葬儀社からご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社をご紹介します。」
このサービスは、ご遺族の状況や希望に寄り添い、最適な葬儀プランを提案してくれるので、心強い味方になってくれます。
葬儀の種類とそれぞれの流れ
ひとくちに「葬儀」と言っても、その形式はさまざまです。故人やご家族の意向、費用、参列者の数などを考慮して、最適な形式を選びます。ここでは、主な葬儀の種類とその流れをご説明します。
1. 一般葬
通夜、葬儀・告別式、火葬の順に執り行われる、最も伝統的な形式です。親族や友人、仕事関係者など、幅広い方が参列します。
- 通夜(1日目):夜に行われる儀式で、故人と最期のお別れをします。通夜振る舞い(食事)を設けるのが一般的です。
- 葬儀・告別式(2日目):僧侶による読経や焼香、弔辞の奉読などが行われます。その後、故人との最期のお別れを済ませ、出棺となります。
- 火葬:火葬場へ移動し、ご遺体を荼毘に付します。火葬が終わると、遺骨を骨壺に納める「収骨(拾骨)」が行われます。
2. 家族葬
近親者やごく親しい友人のみで行う、比較的新しい形式です。参列者が少ないため、故人とゆっくりお別れしたいと考える方に選ばれています。
基本的な流れは一般葬と同じですが、規模が小さく、費用を抑えられる傾向があります。
3. 一日葬
通夜を行わず、葬儀・告別式と火葬を一日で済ませる形式です。参列者やご遺族の身体的な負担を減らすことができます。
葬式当日の服装について
ご家族の葬儀となると、準備する時間がない中で、服装に悩む方もいらっしゃるでしょう。
服装は、故人やご遺族への敬意を表す大切な要素です。ここでは、基本的な服装マナーについて解説します。
- 男性:黒のスーツ、白のワイシャツ、黒のネクタイ、黒の靴下が基本です。
- 女性:黒のスーツ、またはワンピースとジャケットのアンサンブル。露出の少ないデザインを選び、ストッキングや靴も黒で統一します。
「でも、急なことで喪服を準備する時間がない…」「体型が変わって、持っている喪服が合わない…」そんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
【Cariru BLACK FORMAL】 は、ネットで簡単に喪服をレンタルできるサービスです。
「質にこだわり、時代に合った高いデザイン性と確かなブランド力。商品はすべて弔事のマナーに沿って厳選しているため、突然の訃報を受けた際でも、お困りなく通夜・葬式などへご参列いただけます。必要な時に必要なものが全て揃う、大人のためのブラックフォーマルレンタルです。」
プロが厳選した高品質な喪服を、必要な時だけ借りられるので、費用を抑えたい方や、急なご不幸に備えたい方におすすめです。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
納骨までの流れと必要な準備
葬儀が終わると、次にご遺族が直面するのは「納骨」です。納骨とは、故人のご遺骨をお墓や納骨堂などに納めることです。
ここでは、納骨までの流れと、その間にすべきことをご説明します。
1. 遺骨の保管
火葬後、ご遺骨は骨壺に納められて自宅に持ち帰ります。四十九日法要まで自宅に安置することが一般的です。
この期間は、故人を偲び、ご家族が集まる大切な時間となります。
2. 納骨場所の検討と準備
納骨は、故人やご家族の意向に合わせて、さまざまな方法があります。
- お墓:先祖代々のお墓に入れるのが一般的です。もし新しいお墓を建てる場合は、墓地の購入や墓石の準備に時間がかかります。
- 納骨堂:遺骨を一時的、または永続的に預けることができる施設です。都市部に多く、お墓を建てるよりも費用を抑えられます。
- 樹木葬:墓石の代わりに樹木を墓標とする新しい形式です。
- 散骨:海や山に遺骨を撒く方法です。
ご家族でよく話し合い、故人の意向も尊重して、最適な方法を選びましょう。
3. 納骨の時期
納骨に明確な期限はありませんが、一般的には四十九日法要を目安に行うことが多いです。
四十九日は、故人の魂が来世へと旅立つとされる重要な節目です。この日を区切りに、納骨式を執り行うことで、ご遺族の気持ちの整理にもつながります。
ただし、納骨の準備が間に合わない場合や、ご遺族の気持ちの整理がついていない場合は、無理に四十九日にこだわる必要はありません。一周忌や三回忌など、ご家族で話し合って決めることが大切です。
葬儀後の手続きと供養
葬儀が終わった後も、さまざまな手続きや供養が続きます。
1. 死亡後の行政手続き
死亡届の提出以外にも、年金や健康保険、生命保険、相続など、多くの手続きが必要です。
葬儀社によっては、これらの手続きの相談に乗ってくれるところもありますが、ご自身で役所や金融機関に足を運ぶ必要があります。
手続きが多岐にわたるため、何から手をつければ良いか分からなくなるかもしれません。落ち着いて、一つずつ進めていきましょう。
2. 香典返し
葬儀でいただいた香典へのお返しです。香典返しは、いただいた金額の半額から3分の1程度が目安とされています。
香典返しは、挨拶状を添えて贈るのが一般的です。
「何を選べば良いか分からない」「たくさんの人に贈るのが大変」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
【シャディギフトモール】 は、香典返しに最適なギフトを豊富に取り扱っています。
「1926年創業のギフト専門店『シャディ』の公式オンラインショップ。様々な用途に対応できる、1万点以上の商品を揃えています。包装やのし紙、紙袋、メッセージカードも、無料で各種豊富にご用意しています。」
カタログギフトや食品、タオルなど、幅広い品揃えの中から、贈る方に合わせて選ぶことができます。また、メッセージカードも付けられるので、感謝の気持ちを伝えることができます。
※関連記事:
3. 遺品整理
故人が残された品々の整理も、ご遺族にとって大きな負担となる作業です。
「故人との思い出の品が多くてなかなか整理が進まない」「遠方に住んでいるため、何度も実家に足を運ぶことが難しい」といったお悩みもよく聞かれます。
【ライフリセット】 のような専門業者に依頼することも、一つの選択肢です。
「故人様がお部屋に残した遺品や不要物を整理します。実家の両親が亡くなられてご家族様が依頼された方が多いです。また生前にご本人様が直接依頼されるケースもあります。」
遺品整理のプロに任せることで、物理的な負担が減るだけでなく、心の整理をする時間も確保できます。
今からできる「もしも」の準備
ここまで、葬儀から納骨までの流れをご説明しました。
この一連の流れをスムーズに進めるためには、事前の準備が非常に大切です。ご家族が困らないように、今からできる準備をいくつかご紹介します。
1. 葬儀に関する希望をエンディングノートに残しておく
「こんなお葬式にしてほしい」「このお花で送ってほしい」といった、ご自身の希望をエンディングノートにまとめておきましょう。
これにより、ご遺族は故人の意思を尊重したお別れをすることができます。また、費用面や手続きについても書き残しておくことで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。
2. 葬儀社に事前相談しておく
葬儀社に事前相談することで、費用やプランを把握できます。複数の葬儀社を比較検討できるので、いざという時に慌てて決める必要がなくなります。
「【安心葬儀】の相見積もりサービスを利用すれば、無料で複数の見積もりを取ることができ、心強いです。」
3. 遺影写真を用意しておく
ご自身の気に入った写真を遺影として準備しておくことも大切です。
「この写真を使ってほしい」という希望があれば、ご家族に伝えておきましょう。
4. 終活に関する情報を集めておく
終活は、ご自身の人生の最期をより良いものにするための活動です。お墓のこと、相続のこと、遺言のことなど、さまざまな情報を集めておきましょう。
このブログでは、今後も終活に関する情報を発信していきますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ:大切なのは「後悔しないお別れ」
葬式から納骨までの流れは、ご遺族にとって心身ともに大きな負担がかかるものです。
しかし、事前に流れを把握し、できる限りの準備をしておくことで、故人との最期のお別れを、より穏やかな気持ちで迎えることができます。
- ご臨終:まず、死亡診断書を受け取り、葬儀社に連絡してご遺体の安置場所を確保する。
- 葬儀:故人やご家族の意向に合わせて、葬儀の形式を決める。
- 納骨:お墓や納骨堂など、納骨場所を事前に検討しておく。
- 葬儀後:行政手続き、香典返し、遺品整理など、さまざまな手続きがある。
もしもの時に備え、ご家族で話し合う時間を持つことも大切です。
このブログが、皆様の「後悔しないお別れ」の準備に役立つことを心から願っています。
ご不明な点があれば、お気軽にコメント欄でご質問ください。
今後とも、このブログ「家族を想うお葬式ガイド」をよろしくお願いいたします。