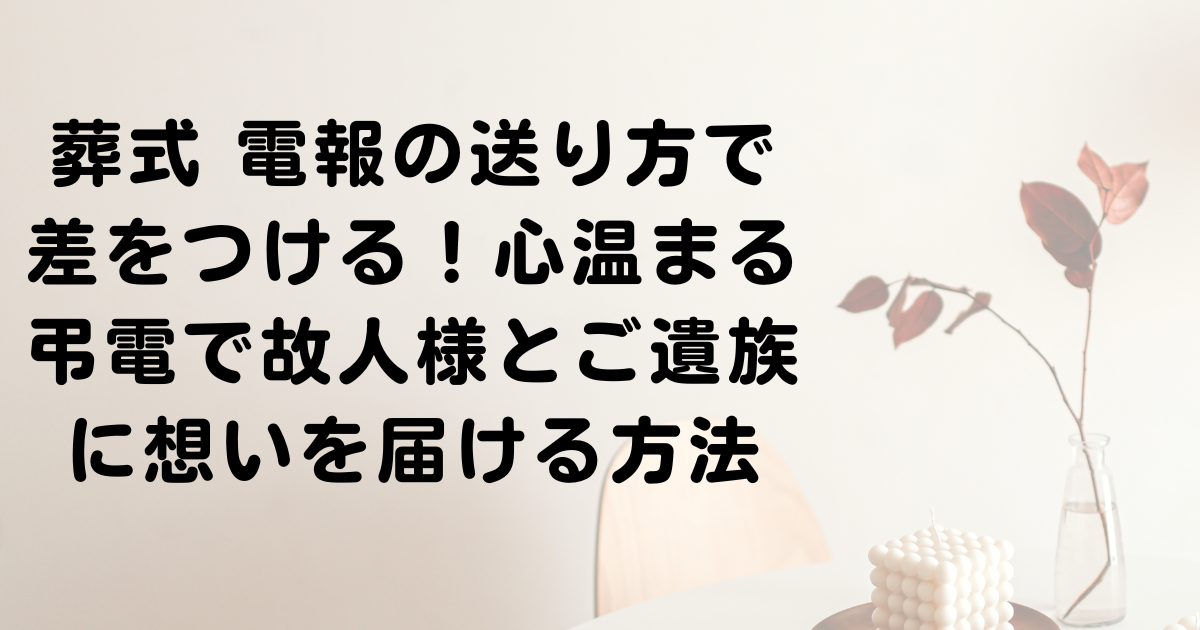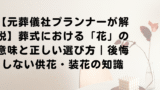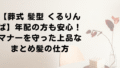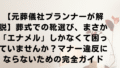はじめまして、ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳、地方都市で妻と2人の子どもと暮らしています。 私は以前、葬儀社で12年間プランナーとして働いており、800件以上のご葬儀に携わってきました。
私がこの業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。 当時、何もわからず葬儀の手配に奔走し、心身ともに本当に苦しい思いをしました。 「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」という一心で、葬儀業界の門を叩きました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添い、たくさんのご相談を受けてきました。 その中で、葬儀に関する「情報の格差」によって、後悔したり損をしてしまう方が多い現実を目の当たりにしてきました。
このブログでは、私が現場で培った知識と経験をもとに、お葬式の基本や費用、トラブルを避けるためのヒント、信頼できるサービスの選び方など、役立つ情報をわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。 人生で何度も経験することではないからこそ、後悔のないお別れを迎えるための準備を一緒に考えていきましょう。
故人様へ、そしてご遺族へ。心を込めた弔電を送る意味とマナー
突然の訃報に接したとき、お通夜やお葬式に参列したくても、どうしても都合がつかないことがありますよね。 「何かお役に立ちたいけれど、何もできない」 「せめてもの気持ちだけでも伝えたい」
そんなとき、遠方からでも、また、どうしても駆けつけられないときでも、ご遺族に弔意を伝えられるのが「弔電(ちょうでん)」です。 弔電とは、お通夜やお葬式の場に宛てて、お悔やみの気持ちを伝える電報のこと。 ご遺族は、受付の際に弔電を受け取り、お式の中でその一部を拝読することで、故人様がどれだけ多くの方に慕われていたかを知ることができます。
弔電は、ご遺族にとって大きな慰めとなり、何よりも「故人様が生きてきた証」そのものです。 お葬式の後、落ち着かれた頃に読み返して、故人様を偲ぶよすがとする方も少なくありません。
しかし、いざ弔電を送ろうとすると、「どんな内容を書けばいいんだろう?」「マナー違反にならないか心配…」と戸惑われる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、そんな皆様のお悩みを解決できるよう、弔電を送る際のマナー、文例、そして送る際の注意点を、私の経験を交えながらわかりやすく解説していきます。
心を込めた弔電で、故人様への感謝の気持ち、そしてご遺族への温かいお心遣いを伝えてみませんか?
弔電を送る前に知っておきたい3つの基本
弔電を送る前に、まず知っておくべき基本的なポイントが3つあります。
- 送るタイミング
- 送る相手と宛先
- 差出人名義
この3つを間違えてしまうと、せっかくの弔意がきちんと伝わらなかったり、ご遺族に余計なご負担をかけてしまうことになりかねません。 一つずつ、丁寧に確認していきましょう。
1. 弔電を送る最適なタイミング
弔電は、お通夜またはお葬式が始まる前に届くように手配するのが基本です。 遅くとも、お通夜の日の午前中、間に合わない場合はお葬式当日の朝一には届くように手配しましょう。 そうすれば、ご遺族は弔電を受け取る時間が確保でき、拝読する弔電を選んだり、準備をする時間もとることができます。
ただし、注意が必要なのは、深夜や早朝に届けてしまうことです。 お葬式準備で忙しいご遺族に、さらに夜中に電話をかけたり、配達で呼び出したりしてしまうのは心苦しいですよね。 多くの電報サービスでは、お届け日時の指定が可能ですので、必ずお通夜やお葬式の日時を確認し、適切な時間帯を指定しましょう。
もし、お通夜やお葬式の日時がわからない場合は、無理に急いで送る必要はありません。 その場合は、後日あらためて弔問に伺うか、お式後にお悔やみの手紙を出すという方法もあります。
2. 弔電の宛先と送る相手
弔電を送る際の宛先は、**ご遺族が喪主様として指定された斎場(葬儀場)**です。 決して、ご自宅に送ってはいけません。 ご自宅に送ってしまうと、ご遺族が斎場まで弔電を運ぶ手間が発生してしまい、ご負担をかけてしまいます。 斎場の住所は、訃報の連絡やお知らせに記載されているはずですので、間違いのないように確認しましょう。
そして、弔電の宛名は「喪主様(○○様)」とするのが一般的です。 喪主様のお名前がわからない場合は、「(故人様の氏名)ご遺族様」とします。 もし、お式を執り行う斎場の名前がわかっている場合は、宛名の前に斎場名を入れるとより親切です。
例: 「〇〇斎場 〇〇様(喪主様) 御侍史」 「〇〇斎場 (故人様の氏名)ご遺族様」
「御侍史(ごじし)」は、「(手紙を)お取り次ぎください」という意味の敬称で、弔電ではよく使われる言葉です。 弔電を直接喪主様にお渡しするわけではないので、このような気配りを示すことで、より丁寧な印象になります。
3. 弔電の差出人名義
弔電の差出人名義は、誰から送られたものかが一目でわかるようにすることが大切です。 ご遺族は、たくさんの弔電の中から、誰が送ってくれたのかを把握しなければなりません。 個人の場合は、**「氏名」「住所」**を記載するのが基本です。
もし、会社関係で送る場合は、「会社名」「部署名」「役職」「氏名」を記載しましょう。 ご友人や親しい関係の方から送る場合は、故人様との関係性を示す一言を添えると、よりご遺族の心に響く弔電になります。
例: 「○○株式会社 営業部 部長 △△△△」 「故人様と大学時代のご学友 〇〇」
【そのまま使える】心を伝える弔電の文例集
ここからは、実際に弔電を作成する際に役立つ文例を、故人様との関係性別にご紹介します。 弔電の文章は、長ければ良いというものではありません。 簡潔に、そして心からの気持ちを伝えることが何よりも大切です。 ここでは、ご遺族への配慮を忘れず、温かみのある文面を意識しました。 ご自身の気持ちに一番近いものを選んで、少しアレンジして使ってみてくださいね。
【文例1】友人・知人・お世話になった方へ
親しい間柄の方に送る弔電は、故人様との思い出を少し盛り込むことで、ご遺族に温かい気持ちを届けることができます。 故人様のお人柄を偲び、ご遺族を励ます言葉を添えましょう。
例文A 「(故人様氏名)様のご逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます。 突然の訃報に接し、驚きと悲しみでいっぱいです。 在りし日のお元気だったお姿が目に浮かびます。 故人様との思い出は、私にとってかけがえのない宝物です。 ご遺族の皆様の悲しみを思うと、胸が張り裂けそうです。 どうぞご無理なさらず、お体を大切になさってください。 心ばかりのお悔やみをお伝えするとともに、故人様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。」
例文B 「〇〇さんの訃報に接し、ただただ驚いております。 学生時代を共に過ごした楽しい日々が、昨日のことのように思い出されます。 優しい笑顔と、周りの人をいつも大切にされるお人柄が忘れられません。 もっとお話したかったと悔やまれてなりません。 ご遺族の皆様におかれましては、さぞかしお力落としのことと存じます。 ご自愛のほどお祈り申し上げます。 〇〇さんの安らかなるご永眠を心よりお祈り申し上げます。」
【文例2】会社の上司・同僚・取引先へ
会社関係の方に送る弔電は、丁寧な言葉遣いを心がけ、故人様への尊敬の念を伝えることが大切です。 故人様の功績を称え、ご遺族への配慮も忘れないようにしましょう。
例文A(上司・目上の方へ) 「(故人様氏名)様のご逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます。 在職中は、ご指導ご鞭撻を賜り、心より感謝申し上げます。 故人様からいただいた温かいお言葉の数々は、今も私の胸に深く刻まれています。 ご遺族の皆様におかれましては、さぞかしご心痛のことと存じます。 皆様のご健康と、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。」
例文B(同僚・部下へ) 「〇〇さんの突然のご逝去の報に接し、社員一同、ただただ驚きを隠せません。 常に周りを明るくするお人柄で、私たちにとってなくてはならない存在でした。 仕事で共に過ごした日々は、決して忘れることはありません。 〇〇さんのご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様のご心痛いかばかりかとお察しいたします。 心よりお悔やみ申し上げます。」
【文例3】故人様のご家族へ
故人様のご家族へ送る弔電は、故人様とご家族の関係性を尊重しつつ、ご遺族への励ましの言葉を添えましょう。 故人様のご家族に寄り添う気持ちを伝えることが大切です。
例文A 「(故人様氏名)様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。 ご生前には大変お世話になり、心より感謝申し上げます。 いつも優しい笑顔で、私を温かく迎えてくださったお姿が忘れられません。 今はただ、安らかにお眠りになられることをお祈りしております。 ご遺族の皆様におかれましては、さぞかしお力落としのことと存じます。 くれぐれもご無理なさらず、お体をご自愛ください。」
例文B 「〇〇さん、本当にありがとうございました。 (故人様氏名)様の訃報に接し、深く悲しんでおります。 〇〇さんのお母様(お父様、など)は、いつも私たちに温かいお言葉をかけてくださり、優しく見守ってくださる存在でした。 今はただ、故人様が安らかにお眠りになられることをお祈り申し上げます。 ご家族の皆様が、この深い悲しみを乗り越えられますよう、心よりお祈り申し上げます。」
弔電を送る際に知っておきたい言葉とNG表現
弔電は、ご遺族への心遣いが何よりも大切です。 そのため、使ってはいけない「忌み言葉(いみことば)」や、宗派によってふさわしくない言葉があります。 せっかくの弔意が、マナー違反になってしまわないよう、注意が必要です。
弔電で避けるべき「忌み言葉」
忌み言葉とは、「不幸が重なる」「繰り返す」ことを連想させる言葉のことです。 弔電の文章にうっかり使ってしまわないよう、しっかり確認しておきましょう。
| 忌み言葉の例 | 言い換えの例 |
| 重ね重ね、たびたび、しばしば | 心より、重ねて、繰り返し |
| 引き続き、追って、ますます | 引き続き、追って、ますます |
| 最後に、再び、再度 | 最後に、再び、再度 |
宗教・宗派によってNGな表現
弔電を送る際には、故人様の信仰している宗教・宗派に合わせた言葉遣いをすることも大切です。
- 仏教:「ご冥福をお祈りいたします」は、一般的に使われますが、浄土真宗では使いません。浄土真宗では、故人様は亡くなるとすぐに仏様になると考えられているためです。その代わりに「心よりお悔やみ申し上げます」や「故人様が安らかにお眠りになられますよう、お祈りいたします」といった言葉を使います。
- 神道:神道では、死は穢れ(けがれ)と考えられており、仏教の言葉は使いません。「御霊(みたま)のご平安をお祈り申し上げます」や「安らかに鎮まりますことをお祈り申し上げます」**といった言葉を使います。
- キリスト教:キリスト教では、「死」は神様のもとへ召される喜ばしいことと考えられています。そのため、「ご冥福」や「成仏」といった仏教の言葉は使いません。**「安らかな眠りをお祈り申し上げます」や「主イエス・キリストの御もとに召されますように」**といった言葉が適切です。
ご遺族に宗教・宗派を尋ねることは難しいかもしれませんが、もしわかれば、それに合わせた言葉を選ぶようにしましょう。 宗派がわからない場合は、「心よりお悔やみ申し上げます」や「安らかなご永眠をお祈り申し上げます」など、どの宗教でも使える表現を選ぶと安心です。
弔電を申し込むなら、電報サービスが便利でおすすめ
ここまで弔電の文例やマナーについて解説してきましたが、いざ弔電を送ろうとなると、どこに頼めばいいのか迷ってしまいますよね。
今では、電話やインターネットで簡単に弔電を申し込める電報サービスが主流です。 電話で申し込むのが不安な方でも、インターネットならゆっくりと文面や台紙を選ぶことができます。
電報サービスを利用するメリットはたくさんあります。
- 24時間いつでも申し込み可能:急な訃報にも対応できます。
- 豊富な台紙やメッセージの種類:故人様やご遺族の気持ちに寄り添ったものを選べます。
- 例文集が豊富:マナーに沿った例文が用意されているので安心です。
- 配送日時指定が可能:ご遺族のご負担にならないよう、最適なタイミングで届けることができます。
電報サービスによっては、弔電の台紙に生花やプリザーブドフラワーが添えられた、より華やかなものも用意されています。 故人様がお好きだった花をイメージして選ぶのも素敵ですね。 お悔やみの気持ちをより丁寧に伝えたい方におすすめです。
葬儀に関するお悩みは「安心葬儀」にご相談ください
弔電の手配だけでなく、お葬式そのものについて不安や疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 葬儀は人生で何度も経験するものではなく、いざというときにどうすればいいかわからないのが当たり前です。 さらに、ご逝去後わずかな時間で葬儀社を決めなければならないことも多く、十分な情報収集が難しいのが現状です。
私も葬儀社のプランナーとして働いていた経験から、**「時間のなさ」と「費用の不安」**が、ご遺族にとって大きな負担になることを痛感しています。 葬儀には十数万円〜数百万円というまとまった費用がかかる上、葬儀社によってその内容や品質には大きな差があるのが現実です。
そんなとき、頼りになるのが【安心葬儀】というサービスです。 こちらは、東証プライム上場企業のエス・エム・エスが運営する、全国の斎場・葬儀社を探せる情報サイトです。
「安心葬儀」の大きな特長は、複数の葬儀社から相見積もりが取れること。 ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を、なんと全国7,000以上の提携葬儀社の中からご紹介してもらえます。
「相見積もり」と聞くと、少し手間がかかるように感じるかもしれませんが、安心葬儀のサービスを利用すれば、時間の限られた中でも複数の選択肢を比較検討することができ、納得のいく葬儀社選びが可能です。
- 「できるだけ費用を抑えたい」
- 「故人の希望を叶えてあげたい」
- 「地元で実績のある葬儀社に頼みたい」
など、様々なご要望に合わせて相談に乗ってもらえます。 専門の相談員が親身になって対応してくれるので、「初めてのことで何もわからない…」という方でも安心して利用できます。
もし、今後に向けて葬儀の情報を収集しておきたい、終活について考えているという方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度【安心葬儀】のサイトを覗いてみてください。 きっと、いざというときの大きな安心につながるはずです。
弔電以外の「お悔やみの気持ち」を伝える方法
弔電は、お通夜やお葬式に参列できないときに大変有効な手段ですが、他にも故人様やご遺族へお悔やみの気持ちを伝える方法はたくさんあります。 ここでは、いくつかご紹介したいと思います。
弔問(ちょうもん)
お通夜やお葬式の後、落ち着いた頃にご自宅へ伺い、お悔やみを伝えることです。 ご遺族の負担にならないよう、事前に連絡を入れてから伺うのがマナーです。 その際には、お供え物としてお菓子や果物、線香などを持っていくのが一般的です。
供花・供物
お通夜やお葬式に、お花や果物などの供物を送る方法です。 供花(きょうか)は、故人様を偲び、祭壇を飾る大切な役割を果たします。 ただし、葬儀社によっては外部からの供花を受け付けていない場合もありますので、事前に確認が必要です。
弔慰金(ちょういきん)
会社関係などから、故人様のご遺族に弔意を表すために贈るお金のことです。 会社規定などで金額が決められていることが多く、こちらも弔電と同様に、お通夜やお葬式の際に渡すのが一般的です。
香典返し
ご遺族から香典をいただいた方へのお礼として、贈り物を送るのが「香典返し」です。 香典返しは、忌明け(四十九日法要後)に行うのが一般的です。 最近では、四十九日を待たずに、お葬式当日に香典返しを渡す「当日返し」も増えています。
香典返しを贈る際には、贈り物の品選びや、のし紙の書き方、手紙の添え方など、様々なマナーがあります。 「どんなものを選べばいいんだろう…」「失礼のない贈り方をしたい」と悩む方も多いですよね。
そんなとき、心強い味方になってくれるのが【シャディギフトモール】です。 1926年創業のギフト専門店シャディの公式オンラインショップで、様々な用途に対応できる1万点以上の商品を揃えています。
香典返しにぴったりの商品も豊富に揃っており、カタログギフトも人気です。 カタログギフトは、受け取った方がご自身の好きなものを選べるので、相手に喜んでもらいたいという気持ちをスマートに伝えることができます。 包装やのし紙、メッセージカードも無料で豊富に用意されているので、手間なく安心して手配できます。
香典返しについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
まとめ:弔電で伝えるのは「故人様への感謝」と「ご遺族への心遣い」
弔電の送り方や文例について、詳しく解説してきました。 弔電は、ただ形式的なお悔やみの言葉を送るものではありません。 そこには、故人様と過ごした大切な思い出、そしてご遺族を思いやる温かい気持ちが込められています。
心を込めて弔電を送ることで、ご遺族は「故人様はこんなにも多くの方に慕われていたんだ」と感じ、深い悲しみの中にある心に、少しでも慰めを見出してくれるはずです。
もし、弔電の文章に悩んだら、この記事の文例を参考に、ご自身の言葉を少し足してみてください。 「故人様のお人柄」「心に残っている思い出」「ご遺族を励ます言葉」など、一言加えるだけでも、ぐっと心のこもった弔電になります。
弔電を送る際は、この記事でご紹介したマナーや注意点を参考に、ご遺族に余計な負担をかけることなく、温かい気持ちを届けてください。 ご自身の想いを込めた弔電が、故人様とご遺族の心に届くことを願っています。
終活のお悩み、お葬式の準備、その他のお役立ち情報について
このブログでは、お葬式に関するさまざまな情報や、終活についてのお役立ち情報を発信しています。 お葬式の後には、遺品整理や相続の手続きなど、やらなければならないことがたくさんあります。
もし、ご遺族として遺品整理にお困りの際は、【遺品整理専門 ライフリセット】のような専門業者に相談するという選択肢も考えてみてください。 故人様がお部屋に残された大切な品々や不用品の整理を、ご遺族に代わって丁寧にサポートしてくれます。 ご実家の両親が亡くなられたご家族の方からの依頼はもちろん、ご本人が生前に整理をしておきたいと依頼されるケースも増えているそうです。
また、急な訃報で「着ていくものが何もない…」とお困りの方もいらっしゃるかもしれません。 そんなときは、【Cariru BLACK FORMAL】という喪服・礼服のレンタルサービスが便利です。 品質にこだわり、マナーに沿って厳選されたブラックフォーマルを、必要な時に必要なだけ借りることができます。 インターネットで申し込めるので、忙しい中でも手軽に準備ができるのが嬉しいポイントです。
人生の「もしも」に備えて、後悔のないお別れを迎えるための準備を一緒に考えていきましょう。 「葬式の服装」「葬式の流れ」「葬式における花」についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
人生で何度も経験することではないからこそ、一つひとつのマナーや準備を丁寧に知っておくことが大切です。 私Keisukeが、皆さまの「後悔しないお別れ」のために、心を込めてお手伝いさせていただきます。