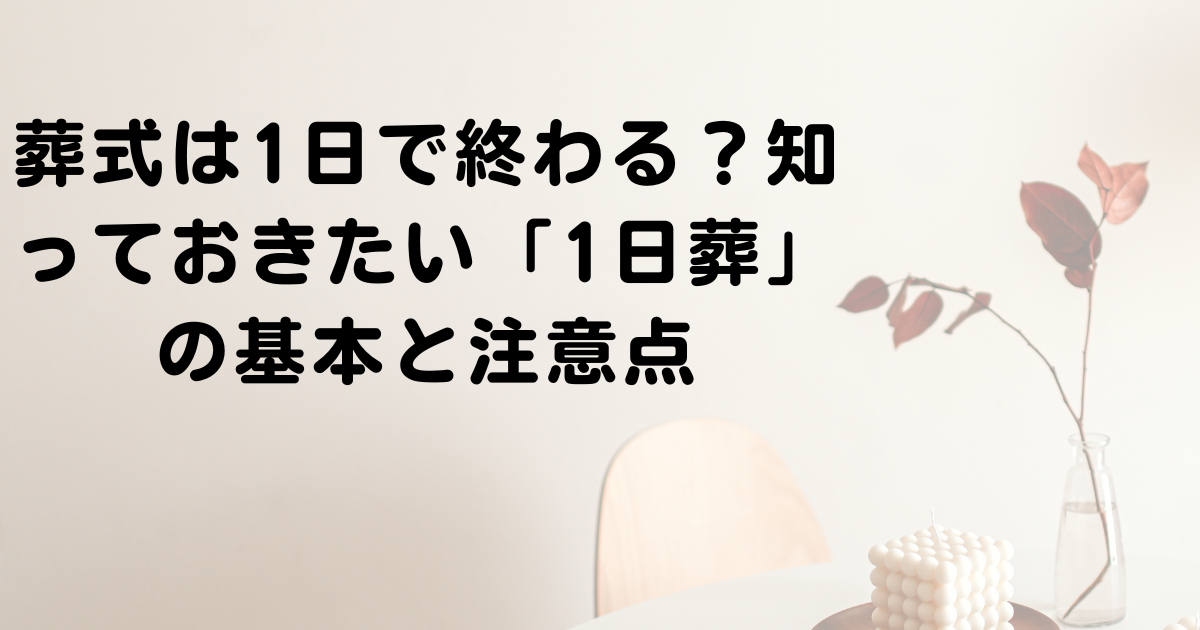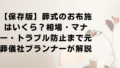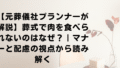こんにちは。「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
「葬式は本当に1日で終わるものなのか?」
「高齢の親のことを考えると、なるべく負担が少ない形にしたい」
「費用面や準備の手間も考えて“簡素なお葬式”を希望している」
近年、こうしたご相談を受ける機会がとても増えました。
私自身、20代後半で父を急に亡くした経験があります。突然の訃報、何から手をつけていいかわからない中で、喪主として動かなければならず、精神的にも体力的にも本当に大変でした。
だからこそ、「無理なく、後悔のない形でお別れができること」を大切にしてほしいと思っています。
本記事では、「葬式 1 日」というキーワードにある通り、近年増えてきた「一日葬」の基本から、一般的な葬儀との違い、メリット・デメリット、実際の流れ、費用相場、注意点まで、分かりやすく解説していきます。
- 第1章:「一日葬」とは?~現代のニーズに合わせた新しい選択肢~
- 第2章:一日葬のメリットとは?
- 第3章:一日葬のデメリット・注意点
- 第4章:信頼できる葬儀社の選び方~時間がない中でも失敗しない方法~
- 第5章:一日葬の当日の流れとは?~タイムスケジュールで見る1日の動き~
- 第6章:突然の訃報…喪服がない!そんな時に頼れる選択肢
- 第7章:一日葬の費用相場と内訳~本当に安い?見えにくいポイントに注意~
- 第8章:実際に一日葬を選んだ方の体験談~リアルな声に学ぶポイント~
- 第9章:葬儀後に待っている大切な作業~香典返しと遺品整理
- 第10章:一日葬に向いている人・向いていない人
- 1. 一日葬は「負担軽減」の選択肢として非常に有効
- 2. 最後に
第1章:「一日葬」とは?~現代のニーズに合わせた新しい選択肢~
「一日葬(いちにちそう)」とは、通夜を行わず、告別式と火葬を1日で完結させる葬儀の形式のことです。
本来、日本の葬儀は「通夜」→「告別式」→「火葬」と2日間にわたって行われるのが一般的でした。しかし、近年では高齢化、家族の少人数化、コロナ禍による簡素化の流れなどもあり、「1日で済ませたい」というニーズが高まっています。
一日葬の特徴
| 内容 | 一般葬 | 一日葬 |
|---|---|---|
| 通夜 | あり | なし |
| 告別式 | あり | あり |
| 火葬 | あり | あり |
| 参列者の数 | 多い傾向 | 家族・親族中心 |
| 所要日数 | 2日以上 | 1日 |
| 費用 | 高くなりやすい | 抑えやすい |
このように、「簡素で負担の少ないお別れ」を望む方にとって、一日葬は非常に有力な選択肢となっています。
第2章:一日葬のメリットとは?
一日葬が選ばれる理由は、ただ「短いから」というだけではありません。以下のような実際のメリットが評価されています。
1. 体力的・精神的負担が少ない
高齢の喪主や参列者にとって、2日間にわたる葬儀は非常に体力を要します。
一日葬であれば、短時間で儀式が終わるため、心身への負担が軽くなります。
2. 費用を抑えられる
通夜を行わないため、式場の使用料、通夜振る舞いの飲食代、人件費などが不要になり、全体的に葬儀費用が抑えられます。
3. 参列者の予定調整がしやすい
一日だけの日程で済むため、遠方から来る方もスケジュールを立てやすく、会社や学校を休まずに参列しやすい点もあります。
第3章:一日葬のデメリット・注意点
一方で、注意すべき点もあります。後悔しない選択のためには、メリットだけでなくデメリットも把握しておくことが大切です。
1. 通夜がないことに抵抗を持つ人も
特にご年配の方や、地域のしきたりを重んじる方の中には、「通夜を行わないなんて失礼だ」と感じる人もいます。
親戚の理解を得られるか、あらかじめ相談しておくことが重要です。
2. 参列者の人数が限定されやすい
「一日だけの葬儀」ということで、どうしても近親者中心の小規模な式になりがちです。
会社関係や近隣の方へのお知らせが難しいこともあるため、**葬儀後のフォロー(香典返しや挨拶)**がより重要になります。
3. 対応していない葬儀社もある
すべての葬儀社が「一日葬」に対応しているわけではありません。また、一日葬向けのプランがあっても、内容や費用の内訳はバラバラです。
第4章:信頼できる葬儀社の選び方~時間がない中でも失敗しない方法~
葬儀は多くの場合、突然必要になるものです。そして、葬儀社選びは「後悔の分かれ道」とも言えます。
特に一日葬のような簡略化された形式は、業者の力量や配慮の有無によって、印象が大きく変わってしまいます。
「費用は安かったけど、対応が雑だった…」
「一日葬って言ってたのに、追加費用が次々に発生した…」
そんなトラブルを防ぐために、相見積もりを取ることが非常に重要です。
私が現場時代から信頼しているのが、
✅ 安心葬儀(株式会社エス・エム・エス)はこちらです。
「安心葬儀」は、東証プライム上場のエス・エム・エスが運営する葬儀情報サイトで、全国7,000社以上の葬儀社から条件に合う業者を紹介してくれます。
特に心強いのは、
- 一日葬プランの有無
- 費用の内訳
- 実際の口コミ
などを比較しながら検討できる点です。
時間がない中でも、焦って高額な葬儀を選ばずに済むため、初めて葬儀を手配する方には特におすすめです。
第5章:一日葬の当日の流れとは?~タイムスケジュールで見る1日の動き~
一日葬といっても、当日はそれなりに時間の余裕が必要です。実際の流れをタイムスケジュール形式で見てみましょう。
一日葬のモデルスケジュール(午前式の場合)
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 8:00〜 | ご遺族・親族が式場に集合 |
| 9:00〜 | 告別式の準備・受付開始 |
| 10:00〜 | 告別式・読経・焼香 |
| 11:30〜 | 火葬場へ出発 |
| 12:00〜 | 火葬(1時間〜1時間半程度) |
| 13:30〜 | 収骨・解散 |
火葬場までの距離や混雑状況にもよりますが、朝から始めて午後には解散できるのが特徴です。
逆に言えば、式の進行はかなりタイトであるため、遅刻や準備不足は大きなトラブルにつながりやすいので注意が必要です。
第6章:突然の訃報…喪服がない!そんな時に頼れる選択肢
「訃報は突然」——これは、葬儀業界にいた私が何度も目の当たりにしてきた現実です。
そして、いざという時に「喪服がない」「サイズが合わない」「礼服の小物が見つからない」というお悩みも非常に多く寄せられました。
特に女性はワンピースやバッグ、アクセサリーなど、用意すべきアイテムが多く、焦って揃えようとするとサイズやデザインに妥協せざるを得ないケースもあります。
そんな時に便利なのが、
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMALです。
こちらは、ドレスレンタルで有名なCariruが手がけるブラックフォーマル専門のレンタルサービスで、次のような特徴があります:
- ネットで24時間申し込みOK、最短翌日午前にお届け
- ブランド喪服やバッグ、数珠などフルセット対応
- 3泊4日〜最大90日まで自由にレンタル可能
- クリーニング不要、返却もラク
高品質でマナーにも配慮されたアイテムが揃っており、急なご葬儀でも「きちんと感」を失わずに対応できます。
実際、現役時代に私がご遺族にご紹介した際も、「本当に助かった」と言われたことが何度もあります。
第7章:一日葬の費用相場と内訳~本当に安い?見えにくいポイントに注意~
「一日葬は費用が安い」と言われることが多いですが、何が含まれていて、何がオプションなのかを理解していないと、思ったより高額になるケースもあります。
一日葬の費用相場(概算)
| 費用項目 | 相場(税込) |
|---|---|
| 式場使用料 | 5万〜15万円 |
| 火葬料(公営) | 0円〜数万円 |
| 霊柩車・搬送費 | 2万〜5万円 |
| 棺・骨壺など物品類 | 3万〜10万円 |
| 祭壇・遺影写真など | 5万〜15万円 |
| 人件費(司会など) | 3万〜7万円 |
| 合計 | 20万〜50万円前後 |
通夜を省くことで、通夜振る舞い(飲食代)や宿泊費、式場2日分の使用料などは削減されます。
見落としがちな「追加費用」
ただし、以下のような費用が別途かかることもあるため、事前の見積もり確認が非常に重要です。
- ドライアイス(安置期間が長い場合)
- 搬送距離が長い場合の加算料金
- 火葬場の休業日対応費用
- オプション(生花、音響設備、会葬礼状など)
これらを含めて総額を比較するためにも、「安心葬儀」のような相見積もりサービスの活用は非常に有効です。
第8章:実際に一日葬を選んだ方の体験談~リアルな声に学ぶポイント~
私が現場で担当したご葬儀の中にも、一日葬を選ばれたご家族は多数いらっしゃいました。ここでは、その中でも印象的だった2つのケースをご紹介します。
ケース1:遠方から集まる親族が多かったKさん(60代・女性)
Kさんのご主人が急逝された際、ご親族の多くが関東圏外に住んでおり、何日も休みを取るのが難しいという状況でした。
「最初は“通夜もやらないなんて”と親戚に言われましたが、説明したら“今はそういうのもあるのね”と理解してくれました。葬儀社の方の進行が丁寧で、時間の中でもきちんとお別れができました。体力的にも本当に助かりました。」
一日葬を選ぶ際には、事前の親族間の共有・説明が重要であると、私も改めて実感したケースでした。
ケース2:お子さんのいないご夫婦のTさん(70代・男性)
「家族だけで静かに見送りたい」との希望から、Tさんはご兄弟と数名だけの一日葬を選ばれました。
「大々的にやる必要はないと思っていたけど、それでもちゃんとお坊さんを呼んで、読経をあげてもらい、区切りをつけることができた。しみじみとした、良い時間でした。」
一日葬=簡素すぎて“味気ない”という印象を持たれがちですが、規模の大小よりも「気持ちのこもった時間」こそが大切なのだと感じさせられました。
第9章:葬儀後に待っている大切な作業~香典返しと遺品整理
一日葬が終わっても、やるべきことはまだ続きます。その中でも特に多くの方が悩まれるのが、香典返しと遺品整理です。
香典返しのタイミングと選び方
香典返しは、一般的には「忌明け(四十九日)」の後に贈るのがマナーです。最近は、即日返し(当日返し)も主流になってきていますが、特に一日葬では香典返しのタイミングや形式に迷う方も多いです。
香典返しでは、次のような点を意識すると良いでしょう:
- 熨斗(のし)の表書きは「志」や「満中陰志」
- 3,000円~5,000円前後の商品が主流
- 故人のイメージに合った品選びをする
こうした点をふまえて、信頼できるギフトショップを使うのが安心です。
私がよくご紹介しているのが、
シャディのカタログギフト!お祝い、内祝い、各種ギフトに です。
1926年創業の老舗で、香典返しや法要返礼品の取り扱いが非常に豊富。さらに、
- 熨斗・包装・メッセージカードも無料対応
- カタログギフトなど幅広い価格帯の商品
- 500円クーポンやキャンペーンあり
など、忙しいご遺族にとって手間が少なく、選びやすいのも魅力です。
遺品整理は「精神的にも時間的にも負担が大きい」
葬儀後に立ちはだかる、もうひとつの大きな課題が遺品整理です。
「何から手をつけていいか分からない」
「思い出の品ばかりで手が止まってしまう」
「実家が遠方で整理に何日も通えない」
そんなご家族を何百人も見てきました。
そうした現場で本当に助かったのが、遺品整理専門の業者です。
中でも評判が良く、私も信頼してご案内しているのが、
✅ 遺品整理のことなら【ライフリセット】 です。
故人様の家財を丁寧に扱い、分別・運搬・処分まで一括対応してくれます。
また、生前整理や仏壇の処分などにも対応しており、次のような方に特におすすめです:
- 実家の整理が遠方で難しい方
- 仕事や育児で時間が取れない方
- 精神的な負担を軽くしたい方
遺品整理は、単なる「片づけ」ではありません。ご家族の心に寄り添うプロの手を借りることで、前向きな一歩を踏み出すことができるのです。
第10章:一日葬に向いている人・向いていない人
一日葬は万能ではありません。最適な選択は、「故人らしい送り方ができるかどうか」です。
一日葬に向いている人
- 高齢の方が多く、体力的な負担を減らしたい
- 親族の人数が少ない・遠方に住んでいる
- 費用を抑えたいが、火葬式(直葬)は避けたい
- 本人が「簡素で静かに送ってほしい」と希望していた
一日葬に向いていない人
- 地域や親族の間で通夜の実施が「常識」とされている
- 会社関係者や友人など、幅広く弔問客が来る予定
- 宗教・宗派の慣習上、通夜の省略が難しい
「簡素化」は便利な選択肢である一方、“ご縁を大切にする気持ち”や“しきたりへの配慮”をないがしろにしないことが、最も大切なのです。
第11章(まとめ):葬式は1日で終わる「一日葬」の選び方と心構え
本記事では、葬儀を「1日で終わらせる一日葬」の基本から、メリット・デメリット、流れや費用、実際の体験談、葬儀後の準備まで幅広く解説しました。
1. 一日葬は「負担軽減」の選択肢として非常に有効
高齢化や家族構成の変化、時代の流れもあり、一日葬は今や確かな選択肢のひとつです。
精神的・体力的な負担が減り、費用も抑えやすいため、特にご高齢の方や遠方の親族が多い場合に向いています。
ただし、通夜がないことに抵抗を持つ人がいること、地域の慣習や親族間の理解も必要である点は押さえておきましょう。
2. 最後に
葬儀は「人生の大切な区切り」です。形式や費用も大事ですが、何よりも「心のこもったお別れ」ができることが最も大切です。
この記事が、あなたやご家族が後悔のない選択をするための一助となれば幸いです。
もし何かお悩みや疑問があれば、いつでもこのブログに戻ってきてください。
心を込めて、情報を発信し続けます。