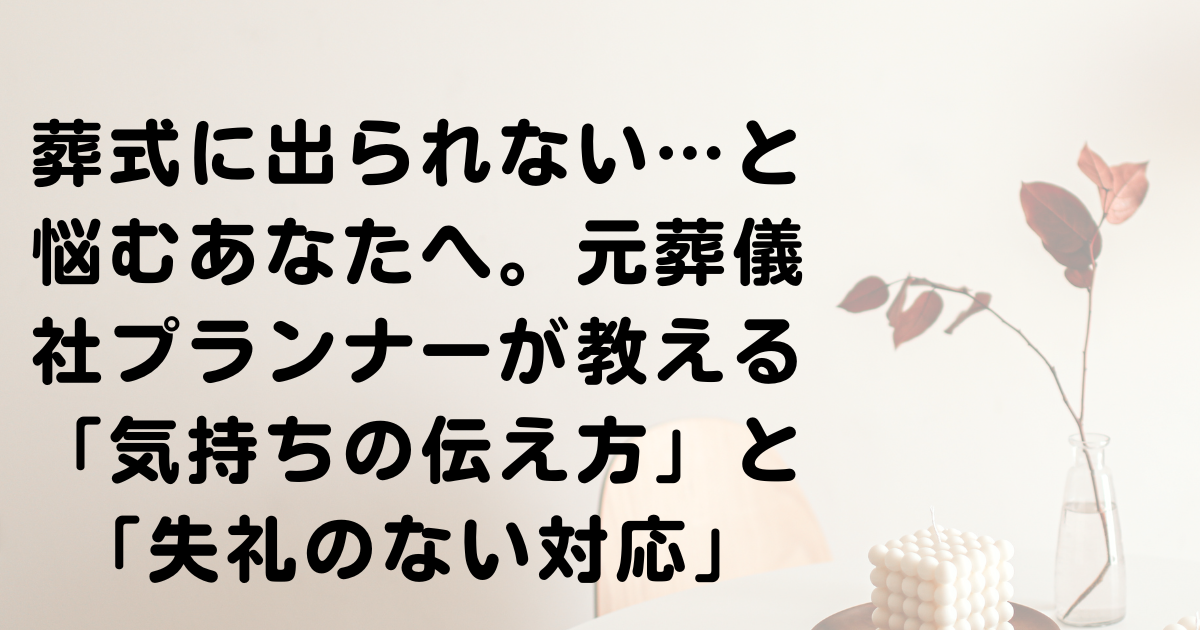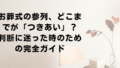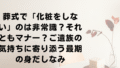こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
この記事を読んでくださっているということは、大切な人との突然のお別れに直面し、心ならずも葬儀に参列できない状況で、どう対応すれば良いか悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。
「仕事が休めない」「遠方に住んでいる」「体調がすぐれない」「家族の介護がある」…人生には、どうしても外せない用事や、どうにもならない事情があります。
私自身、20代後半で父を突然亡くしたとき、葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しい経験をしました。右も左もわからず、ただただ戸惑うばかりでした。
その経験から、「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」という思いで葬儀業界に飛び込み、これまでに800件を超えるご葬儀を担当してきました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添う中で、「大切な人との最後のお別れに立ち会えない」と、ご自身を責めてしまう方をたくさん見てきました。しかし、声を大にしてお伝えしたいのは、「大切なのは、故人を想う気持ち」だということです。
たとえその場に立ち会えなくても、故人への感謝や哀悼の気持ちは、さまざまな形でご遺族に伝えることができます。この記事では、心ならずも葬儀に出られないときに、どのような対応をすれば良いのか、具体的な方法やマナーを、一つひとつ丁寧にお伝えしていきます。
葬式に出られない場合の、具体的な選択肢と対応策
どうしても葬儀に参列できないと決まったら、まず何から始めれば良いのでしょうか。ご遺族は、大切な人を亡くし、悲しみの中にいらっしゃいます。その悲しみに寄り添いつつ、ご自身の弔意をしっかり伝えるためにも、早めの対応が肝心です。
ここでは、具体的な5つの選択肢と、それぞれの対応策についてご紹介します。
1. 弔電を打つ
弔電(ちょうでん)とは、葬儀に参列できない方が、電報を通して故人への哀悼の意を伝えるものです。
【弔電のメリット】
- すぐに手配できる: 電話やインターネットで簡単に申し込むことができます。
- 正式な方法: 弔意を伝える正式な方法として広く知られています。
- ご遺族の手元に残る: 読み上げられた後も、ご遺族の手元に残るため、故人とのつながりを感じられます。
【弔電を送るタイミング】
- 葬儀・告別式の前日までに、会場に届くように手配しましょう。
- 宛名は「喪主様」または「ご遺族様」とし、住所は葬儀会場(斎場)を指定します。
- 差出人名は、フルネームで、故人との関係性(例:株式会社〇〇 部長 山田太郎)を添えると、ご遺族が誰からの電報か分かりやすくなります。
弔電の文面は、定型文もありますが、故人との思い出を添えると、より心のこもったメッセージになります。ただし、「重ね重ね」「くれぐれも」などの重ね言葉や、「迷う」「浮かばれない」などの忌み言葉は避けるのがマナーです。
2. 供花や供物を贈る
供花(くか/きょうか)は祭壇や会場を飾るお花、供物(くもつ)は故人への捧げものとして贈る品物のことです。
【供花・供物のメリット】
- 弔意を形として伝えられる: 故人やご遺族への配慮を形として示せます。
- 葬儀会場を華やかにする: 悲しみの場を和らげる役割も果たします。
【手配の仕方】
- ご遺族や葬儀社に、供花や供物を贈っても良いか、事前に確認することが大切です。
- 多くの場合、葬儀社が手配を代行してくれます。葬儀社に直接連絡し、手配してもらいましょう。
- 花の色や種類、供物の内容には宗教や地域の慣習があるので、葬儀社に相談するのが一番確実です。
供花・供物には、差出人名を書いた札を立てます。会社関係であれば連名にしたり、個人で贈ったりと、ケースに応じて対応しましょう。
3. 弔問に伺う
弔問(ちょうもん)とは、自宅や葬儀会場に伺い、ご遺族にお悔やみを述べることです。
【弔問のタイミング】
- 葬儀の前に伺う場合は、通夜の受付時間中が一般的です。
- ただし、ご遺族は準備などで多忙なため、事前に連絡を入れて、都合の良い時間を伺うのがマナーです。
- 「落ち着いてから改めて伺います」と伝えて、後日改めて弔問することも可能です。
【服装や手土産】
- 通夜に伺う場合は、急な訃報であれば平服でも構いません。ただし、派手な色や柄は避け、地味な色合いの服装を選びます。
- 後日弔問に伺う場合は、略礼服を着用するのが一般的です。
- 手土産は不要です。香典をお渡しするのが一般的ですが、香典の代わりに故人の好物などをお供えする方もいます。
4. 代理を立てる
どうしても参列できない時、信頼できる家族や親戚、親しい友人に代理を依頼することも一つの方法です。
【代理を依頼する際の注意点】
- 事前にご遺族に連絡: 誰が代理で参列するか、事前にご遺族に伝えておきましょう。
- 香典を託す: 香典は、代理人を通じてご遺族にお渡しします。この際、香典袋に自分の名前を明記するのを忘れないようにしましょう。
- 席次への配慮: 代理人は、故人との関係性にかかわらず、自分よりも目上の人の後ろに座るなど、謙虚な姿勢を心がけます。
5. 後日改めてお線香をあげる
葬儀が終わり、ご遺族が落ち着かれた頃に、改めて弔問に伺う方法です。
- いつ頃伺うのが良いか? 四十九日を過ぎてから、遺品整理などが一段落した頃に連絡を取るのが良いでしょう。あまりにも早すぎると、ご遺族の負担になってしまうことがあります。
- 服装や手土産 自宅に伺う際は、略礼服でなくても、地味な平服で構いません。お線香をあげるだけで十分ですが、故人の好物だったお菓子などをお供えとして持参するのも喜ばれます。
葬儀に参列しない場合の、服装と香典のマナー
葬儀に直接参列しなくても、後日弔問に伺ったり、香典を郵送したりする際に、服装や香典のマナーで戸惑う方は少なくありません。ここでは、大人のたしなみとして知っておきたいポイントをご紹介します。
服装について
弔問のタイミングによって、服装の考え方は少し変わります。
- 急な弔問(通夜など): 訃報を急に知らされた場合、喪服を準備する時間がないこともあります。その場合は、地味な平服で伺っても失礼にはあたりません。ただし、派手な色や柄、肌の露出が多い服装は避け、グレーや紺、黒など落ち着いた色のスーツやワンピースを選びましょう。
- 後日改めての弔問: 四十九日より前に、ご自宅に弔問に伺う場合は、略礼服(略式喪服)を着用するのが一般的です。男性なら黒や紺のスーツに白いシャツ、地味なネクタイ、女性なら黒のワンピースやアンサンブルが基本となります。
特に女性の場合、急な訃報で喪服を準備できない、体型が変わって手持ちの喪服が合わなくなってしまった、というお悩みもよく聞かれます。そんな時に便利なのが、喪服のレンタルサービスです。
デザイン・質・マナーにこだわる方の喪服・礼服のレンタル【Cariru BLACK FORMAL】
「Cariru BLACK FORMAL」は、ドレスレンタルで培った実績と信頼を元に、質の高いブラックフォーマルを豊富に取り揃えています。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
【「Cariru BLACK FORMAL」が選ばれる理由】
- 高品質な喪服が手軽に: 上質なブランドの喪服を、購入するよりもリーズナブルな価格でレンタルできます。
- 急な訃報にも安心: 16時までの注文で最短翌日午前中にお届けしてくれるので、急な参列にも対応できます。
- フルセットで準備万端: 喪服だけでなく、バッグ、サブバッグ、ネックレス、イヤリング、数珠、袱紗など、必要な小物がすべて揃ったフルセットが豊富に用意されています。
弔事のマナーに沿って厳選された商品が揃っているので、急なことで慌ててしまっても、安心して参列できるでしょう。また、レンタルなので、返却時のクリーニングは不要です。いざという時のために、こういったサービスがあることを知っておくと、気持ちに少し余裕が生まれるかもしれません。
香典について
香典とは、故人の霊前にお供えする金銭のことです。葬儀に参列できない場合でも、弔意を示すために香典を贈るのが一般的です。
- 郵送で送る場合: 香典袋にお札を入れ、現金書留で送ります。この時、手紙を添えてお悔やみの言葉を伝えるのが丁寧です。
- 代理人に託す場合: 代理人が持参してくれる場合は、代理人の名前を明記した上で、香典袋に自分の名前も記載します。
- 金額の目安: 故人との関係性によって金額は異なります。
- 友人・知人: 5,000円〜10,000円
- 親族: 10,000円〜100,000円
- 会社の同僚・上司: 5,000円〜10,000円
香典を渡す際は、袱紗(ふくさ)に包むのがマナーです。袱紗は、香典袋を汚さないようにするための風呂敷のようなものです。弔事では、紺や緑、グレーなどの落ち着いた色を選びます。
葬儀後の弔意の伝え方
「葬儀に出られなかった…」という気持ちが、後々まで心に残る方もいらっしゃいます。でも、ご遺族への配慮は、葬儀が終わった後も続けることができます。
- お悔やみの手紙を送る: 葬儀から少し時間が経ってから、落ち着いた頃合いを見て、お悔やみの手紙を送るのも一つの方法です。手紙には、故人との思い出や、ご遺族への労りの言葉を綴ると、きっとお気持ちが伝わります。
- 電話やメールでの連絡: ご遺族が落ち着かれた頃に、電話やメールでお悔やみの言葉を伝えるのも良いでしょう。ただし、ご遺族の状況を考えて、長電話になったり、何度も連絡したりするのは避けるべきです。
【特別編】もしも、あなたが葬儀の準備をする側だったら…
ここまで、「葬式に出られない」という状況での対応方法についてお話ししてきました。しかし、もしあなたが、ご家族を亡くされ、葬儀の準備をする側だったらどうでしょうか。
ご遺族は、大切な人を亡くした悲しみの中で、葬儀社との打ち合わせ、親戚への連絡、そして参列者への対応など、やることが山のようにあります。そんな中で、「この葬儀社は本当に信頼できるのだろうか」「費用は適切だろうか」といった不安も尽きないものです。
人生で何度も経験することではないからこそ、葬儀の知識は少なく、ましてや故人が亡くなってから数時間という短い時間で葬儀社を決めなければならないことも少なくありません。
もし、あなたがこの状況に直面したら、焦らずに複数の葬儀社から見積もりを取ることをお勧めします。しかし、一つひとつ問い合わせる時間も、心の余裕もないかもしれません。
そんな時、ぜひ活用していただきたいのが、東証プライム上場企業のエス・エム・エスが運営する「安心葬儀」です。
葬儀に関する情報や全国の斎場・葬儀社を探せる【安心葬儀】
【「安心葬儀」が選ばれる理由】
- 信頼できる葬儀社が見つかる: 全国7,000社以上の中から、ご希望の条件に合った優良葬儀社を無料で紹介してくれます。
- 相見積もりが可能: 時間がない中でも、複数の葬儀社から見積もりを一度に取ることができます。これにより、費用の比較検討がしやすくなり、納得のいく葬儀社選びが可能です。
- 専門家によるサポート: 葬儀に関する疑問や不安を、専門のスタッフが丁寧にサポートしてくれます。
私も葬儀社のプランナーとして働いていた経験から、情報の差で損をしてしまうご遺族をたくさん見てきました。しかし、今は「安心葬儀」のような、信頼できるサービスがあります。いざという時に備え、まずは情報だけでも集めておくことは、ご家族のためにも、ご自身のためにも大切なことだと思います。
葬儀後の「遺品整理」と「香典返し」について
葬儀が終わると、ご遺族は故人が残された遺品の整理や、香典返しといった、たくさんのやるべきことに直面します。特にご高齢の方にとっては、大きな負担になることも少なくありません。
遺品整理
故人様がお部屋に残された品々は、ご遺族にとって大切な遺品であり、一つひとつに思い出が詰まっています。しかし、その数が多すぎたり、遠方に住んでいてなかなか実家に帰れないといった事情があったりすると、遺品整理は大きな課題となります。
「何から手をつけていいか分からない」「量が多くて自分たちだけでは難しい」「遠方に住んでいるので何度も足を運べない」といったお悩みは、よく耳にする話です。
そういった場合、遺品整理を専門とする業者に依頼することも一つの選択肢です。
遺品整理専門【ライフリセット】
「ライフリセット」は、故人様のお部屋に残された遺品や不要物の整理を専門に行うサービスです。
【「ライフリセット」が選ばれる理由】
- 専門家による丁寧な対応: 故人様の大切な遺品を、専門のスタッフが心を込めて整理してくれます。一つひとつに丁寧に向き合ってくれるので、安心してお任せできます。
- 実家が遠方でも安心: 遠方にお住まいで、何度も足を運べないご家族から多く利用されています。
- 遺品整理だけでなく、生前整理も: ご自身の終活の一環として、元気なうちに整理を依頼される方も増えています。生前に整理しておくことで、ご家族に負担をかけたくないという想いを形にできます。
遺品整理は、ただ物を片付けるだけでなく、故人との思い出と向き合う大切な時間でもあります。ご家族だけで抱え込まず、プロの力を借りることも視野に入れてみてください。
香典返し
葬儀でいただいた香典へのお返しである「香典返し」も、大切なマナーの一つです。
香典返しの相場は、いただいた香典の金額の「半返し(3分の1〜半分程度)」が目安とされています。また、贈る時期は、一般的に四十九日法要が終わった後、一ヶ月以内を目安に手配します。
どのような品物を贈ればよいのか迷う方も多いでしょう。
内祝や、お返しも!ギフト専門店【シャディ公式】ギフトモール
「シャディギフトモール」は、1926年創業のギフト専門店の公式オンラインショップです。
【「シャディギフトモール」が選ばれる理由】
- 品揃えが豊富: 1万点以上の商品から、香典返しにふさわしい品物を選ぶことができます。
- 用途に合わせたサービス: 無料の包装やのし紙、メッセージカードも各種豊富にご用意。
- カタログギフトも人気: 先方が好きなものを選べるカタログギフトは、香典返しの定番です。特に年配の方への贈り物としても喜ばれます。
「シャディギフトモール」は、相手に失礼のない贈り物を選びたいという気持ちに応えてくれます。また、お得なキャンペーンも実施されていることがあるので、ぜひチェックしてみてください。
最後に
今回の記事では、「葬式に出られない」という状況で、どのように対応すべきか、そしてその後のマナーや、ご遺族側の配慮についてもお話ししました。
故人との最後のお別れに立ち会えないことは、辛いことです。しかし、大切なのは、故人を想う気持ちを、形を変えてでもご遺族に伝えることです。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、落ち着いて行動する一助となれば幸いです。
そして、いつか来るその日のために、今からできる準備もあります。 例えば、葬儀に関する知識を深めておくことです。
これらの記事も、ぜひご一読ください。
ご自身の終活を考える際にも、これらの知識は必ず役に立ちます。後悔のないお別れのために、今できることから少しずつ始めてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。