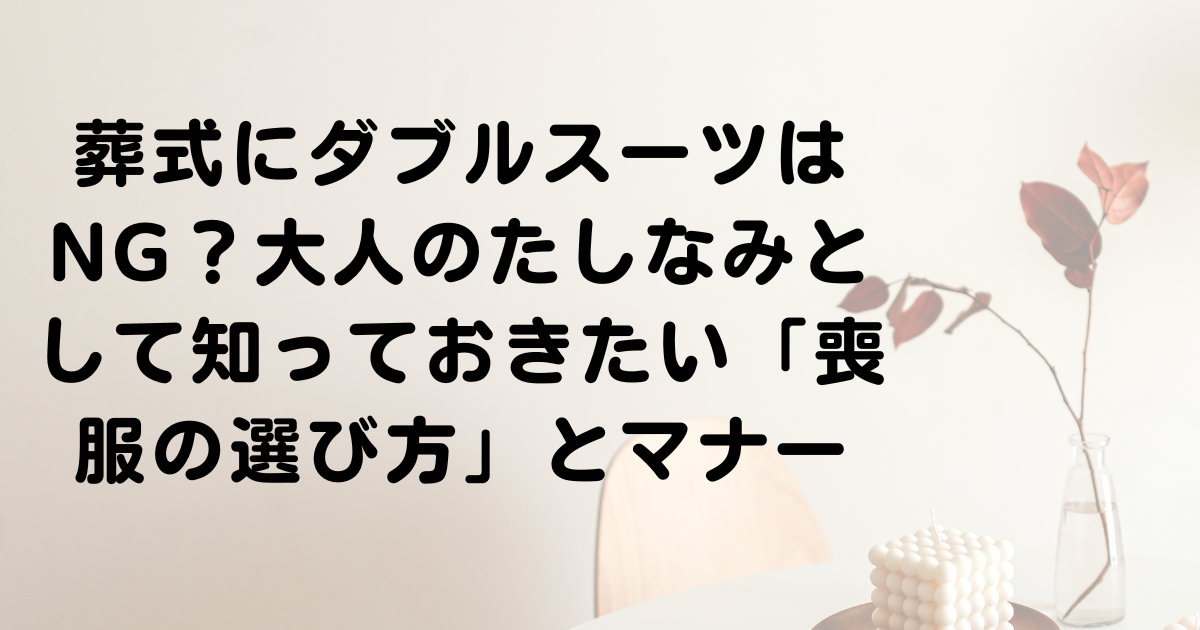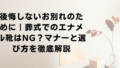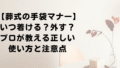皆さん、こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
私はこれまで12年間、葬儀社でプランナーとして働いてきました。担当させていただいたご葬儀は800件以上。その中で、ご遺族の皆様が故人様とのお別れに集中できるよう、服装やマナーについてご相談を受ける機会が数多くありました。
特に男性の場合、「喪服」と言われても、どんなものを選べばいいのか迷う方が少なくありません。
「昔はダブルスーツが主流だったけど、今はどうなんだろう?」 「急なことで、手持ちの服で間に合わせたいけど大丈夫かな?」 「略礼服って、どんな服のこと?」
ご葬儀は突然やってくるものです。大切な人を亡くされた悲しみの中で、服装のことでさらに悩んでしまうのは辛いことですよね。
そこで今回は、男性の喪服について、特に「ダブルスーツ」に焦点を当てながら、その歴史や現在のマナー、そしていざという時に困らないための準備について、元葬儀社プランナーの視点から詳しくお伝えしたいと思います。
この記事を読んでいただければ、もう喪服選びで迷うことはありません。ご自身のことはもちろん、ご家族のためにも、ぜひ最後までお付き合いください。
1. 葬式における「ダブルスーツ」の歴史と現在の立ち位置
まずは、皆さんが最も気になっているであろう「ダブルスーツ」についてお話ししましょう。
ご年配の方の中には、「喪服といえばダブルのスーツ」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。実際に、昭和の時代には、男性の喪服としてダブルのスーツが主流でした。
これは、日本の喪服の歴史と深く関係しています。
戦後、日本の西洋化が進む中で、それまでの和装から洋装へ喪服も変化していきました。その際、礼服として定着していたダブルのスーツが、そのまま喪服としても定着していったのです。
ダブルのスーツは、前身頃が二重になっており、ボタンを留めると重厚で厳かな印象を与えます。この「重厚さ」が、故人様への敬意を表すのにふさわしいとされ、長く親しまれてきました。
しかし、時代は変わり、現代ではシングルのスーツが主流となっています。
ファッションのトレンドも影響していますが、大きな要因として「利便性」が挙げられます。シングルのスーツは、ダブルに比べてスリムで軽快な印象があり、冠婚葬祭だけでなく、ビジネスシーンでも幅広く使えるデザインが増えました。
では、現在の葬儀でダブルのスーツを着ていくのは「NG」なのでしょうか?
結論から言うと、決して「NG」ではありません。
ダブルのスーツを着用されている方も、まだまだ多くいらっしゃいますし、それがマナー違反と見なされることはありません。故人様やご遺族への敬意を払った服装であることは間違いありません。
ただし、注意していただきたい点があります。
それは、「地域性」や「家」の慣習です。
例えば、由緒ある家柄や、地域によっては、今でもダブルのスーツが正式な喪服とされている場合があります。逆に、若い世代が多いご葬儀では、シングルのスーツがほとんどということも珍しくありません。
大切なのは、「故人様への想い」を第一に考えることです。
ご自身の年齢や立場、そしてご葬儀の雰囲気に合わせて、どちらがよりふさわしいかを判断するのが、大人のたしなみと言えるでしょう。
2. 葬式で恥をかかない!男性の喪服の種類と選び方
ここからは、葬儀における男性の喪服について、さらに詳しく見ていきましょう。
喪服には、大きく分けて3つの種類があります。
- 正喪服(せいもふく)
- 準喪服(じゅんもふく)
- 略喪服(りゃくもふく)
それぞれの特徴と、どのような場面で着用するべきかを解説します。
2-1. 正喪服(せいもふく)
正喪服は、喪主やご遺族といった、故人様と最も近い関係の方が着用する、最も格式の高い喪服です。
男性の場合、和装であれば「五つ紋付きの黒紋付羽織袴」、洋装であれば「モーニングコート」がこれにあたります。
モーニングコートは、昼間の葬儀や告別式で着用されます。黒のジャケットに、縞模様のコールパンツを合わせるのが一般的です。
ただし、現代ではモーニングコートを着用する機会は減っており、喪主やご親族でも、準喪服を着用することが増えています。
2-2. 準喪服(じゅんもふく)
準喪服は、一般参列者が着用する、最も一般的な喪服です。
男性の場合、黒の「ブラックスーツ」がこれにあたります。
ブラックスーツとビジネススーツの黒いスーツは全くの別物です。ブラックスーツは、冠婚葬祭用に作られた深い黒色をしており、光沢がありません。ビジネス用のスーツは、光沢があったり、生地に織り柄が入っていたりするため、弔事には不向きです。
準喪服として、シングルでもダブルでも、どちらのスーツでも問題ありません。ただし、着用する際は、以下の点に注意しましょう。
- ジャケット:シングル、ダブルどちらでも可。
- パンツ:シングルの場合はワンタック、ツータックなど、ゆったりとしたシルエットがおすすめ。ダブルの場合は、裾上げをシングルにすることがマナーとされています。
- シャツ:白無地のワイシャツを着用します。ボタンダウンや色柄の入ったものは避けましょう。
- ネクタイ:黒無地のものを着用します。
- 靴下:黒無地のものを着用します。
- 靴:黒の革靴を着用します。金具や装飾のない、シンプルなストレートチップやプレーントゥがふさわしいでしょう。
準喪服は、通夜、告別式、四十九日法要など、ほとんどの場面で着用することができます。
2-3. 略喪服(りゃくもふく)
略喪服は、ご葬儀の規模が小さい場合や、急な訃報で喪服の準備が間に合わない場合に着用します。
男性の場合、黒、グレー、紺などの地味な色のスーツを指します。
急な通夜などで、仕事帰りに駆けつける場合などは、略喪服でも失礼にはあたりません。ただし、その場合も以下の点に注意しましょう。
- スーツ:黒、紺、グレーなど、地味な色のスーツ。ストライプやチェック柄は避けましょう。
- シャツ:白無地のワイシャツ。
- ネクタイ:地味な色のネクタイ(黒、紺、グレーなど)。できれば黒無地のものを用意しましょう。
- 靴下:黒無地。
- 靴:黒の革靴。
略喪服は、あくまでも「やむを得ない場合」に着用するものです。できる限り、準喪服を着用することが望ましいとされています。
3. いざという時のために!喪服の準備と選び方のポイント
ご葬儀は、いつ、誰に訪れるかわかりません。
いざという時に慌てないためにも、喪服の準備をしておくことは非常に大切です。
ここでは、喪服を選ぶ際のポイントと、具体的な準備方法についてお話しします。
3-1. 喪服を購入する際のポイント
「喪服」として一着持っておくなら、やはり「ブラックスーツ(準喪服)」がおすすめです。
シングルでもダブルでも構いません。ご自身の体型や好みに合わせて選びましょう。
購入する際には、以下の点に注目してください。
- 生地の色:深い黒色かどうか。光沢がないか。
- 生地の素材:シワになりにくい素材だと、いざという時にすぐに着られて便利です。
- サイズ:長年着用することを考えて、少しゆとりのあるサイズを選んでおくと安心です。
- デザイン:シングル、ダブルどちらでも可。流行に左右されない、シンプルなデザインがおすすめです。
最近では、春夏用、秋冬用、そしてオールシーズン用など、季節に合わせた喪服も販売されています。オールシーズン用を一着持っておくと、どんな季節でも対応できて便利です。
3-2. 喪服のレンタルという選択肢
「喪服を買うのはもったいない」 「体型が変わって、昔の喪服が着られなくなった」 「子ども用の喪服は、すぐにサイズが変わるから、買うのはちょっと…」
そんな風にお考えの方には、「喪服のレンタル」という選択肢があります。
最近は、ネットで手軽に喪服をレンタルできるサービスが増えています。
特に女性の場合、流行のデザインやサイズの変化に対応するのが大変ですよね。
そんな時におすすめなのが、喪服・礼服のレンタルサービス「Cariru BLACK FORMAL」です。
こちらは、ドレスレンタルで培った信頼と実績をブラックフォーマルへと展開したサービス。弔事のマナーに沿って厳選された、質の良い人気ブランドの喪服が多数取り揃えられています。
ワンピース、ジャケット、バッグ、数珠、袱紗など、必要なものが一式揃ったフルセットもあるので、急な訃報でも安心です。
ネットで24時間いつでも申し込め、16時までの注文なら最短で翌日午前中に届けてもらえるスピーディさも魅力です。
いざという時に、慌ててお店に駆け込む必要もありません。
デザインや質にこだわりたいけれど、購入するのは気が引けるという方は、ぜひ一度、Cariru BLACK FORMALを検討してみてはいかがでしょうか。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
3-3. 喪服の手入れ方法
購入した喪服は、いざという時にすぐに着られるよう、日頃から手入れをしておきましょう。
- 着用後:着用後は、ホコリを払い、風通しの良い場所で陰干しをします。
- 保管方法:防虫剤を入れ、湿気の少ない場所に保管します。
喪服は、ほとんど着る機会がないため、タンスの奥にしまいっぱなしになりがちです。しかし、定期的に風を通したり、虫干しをしたりすることで、長く良い状態を保つことができます。
4. 葬儀に関する素朴な疑問を解決!
ここからは、喪服以外の、ご葬儀に関する素朴な疑問にお答えしていきましょう。
4-1. 「平服でお越しください」と言われたら?
ご葬儀の案内で「平服でお越しください」と書かれている場合があります。
この「平服」とは、「普段着」のことではありません。
故人様への敬意を表すため、略喪服(地味な色のスーツなど)を着用するのがマナーです。
「平服」という言葉に惑わされず、TPOをわきまえた服装を心がけましょう。
4-2. 喪服のレンタルサービスは、本当に大丈夫?
「ネットで喪服を借りるなんて、なんだか不安…」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現代のレンタルサービスは、非常に高品質で安心です。
- 品質:専門のクリーニング業者で徹底的に手入れされており、清潔な状態のものが届きます。
- マナー:弔事のマナーに沿ったアイテムが厳選されているため、安心して着用できます。
- 利便性:ネットで申し込め、自宅まで届けてもらえるため、時間がない時でも安心です。
現代のライフスタイルに合わせた、新しい選択肢として、ぜひ検討してみてください。
5. 故人様とのお別れを後悔しないために
ご葬儀は、故人様とのお別れの場であると同時に、故人様と向き合い、ご自身の人生を振り返る大切な時間でもあります。
そんな大切な時間を、服装のことで悩んだり、慌てたりして過ごすのは、とてももったいないことです。
私自身、20代後半に父を突然亡くし、右も左もわからず葬儀の手配に奔走しました。その時、精神的にも経済的にも本当に苦しい思いをしました。
だからこそ、「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」という思いで、このブログを立ち上げています。
ご葬儀の準備は、決してネガティブなことではありません。
大切な人との最後のお別れを、心穏やかに迎えられるように、今のうちにできることを考えておく「終活」の一つなのです。
服装のこと、費用のこと、葬儀社の選び方、そして葬儀後のこと…。
考えることはたくさんあります。しかし、一人で悩む必要はありません。
もし、ご葬儀のことで何かお困りごとがあれば、全国の葬儀社を比較検討できるサービス「安心葬儀」を頼ってみるのも一つの方法です。
こちらは、東証プライム上場企業である株式会社エス・エム・エスが運営するサービスで、全国7,000以上の葬儀社の中から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を無料で紹介してくれます。
ご遺族は、逝去後数時間以内に葬儀社を決定しなくてはならない場合が多いと言われています。そんな時間がない中でも、複数の葬儀社の見積もりを比較できる「相見積もりサービス」を利用すれば、納得のいく葬儀社を見つけられる可能性が高まります。
「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うような些細な疑問でも、専門のスタッフが丁寧に対応してくれるので、安心して相談できます。
大切な人との最後のお別れを後悔しないためにも、いざという時のために、信頼できる葬儀社の情報を集めておくことは、とても大切なことです。
終活の一環として、ぜひ一度、安心葬儀の公式サイトを覗いてみてください。
6. 葬儀後も続く「整理」という大切な時間
ご葬儀を終えると、少し落ち着いた時間を持てるかもしれません。しかし、故人様が残された「遺品」の整理が待っています。
遺品整理は、故人様との思い出を振り返る大切な時間であると同時に、ご遺族にとっては大きな負担となることも少なくありません。
「どうやって手をつければいいのかわからない」 「思い入れがありすぎて、なかなか捨てられない」 「遠方に住んでいて、なかなか片付けに行けない」
このようなお悩みを抱える方は、非常に多くいらっしゃいます。
遺品整理は、無理をして一人で抱え込む必要はありません。
専門の業者に依頼することも、一つの選択肢です。
遺品整理専門の業者「ライフリセット」は、故人様が残されたお部屋の片付けや、不要物の整理を専門に行っています。
「遺品整理」と聞くと、なんだか寂しい響きに聞こえるかもしれませんが、これは「故人様が大切にしてきたものを、新しい形で活かす」という前向きな作業でもあります。
ライフリセットでは、故人様の想いを尊重しながら、ご遺族に寄り添った丁寧なサービスを提供しています。
ご家族が亡くなられた後だけでなく、生前ご自身で「生前整理」として依頼される方も増えているそうです。
遺品整理は、故人様の人生を振り返り、ご遺族がこれからの人生を歩むための、大切な区切りです。
もし、遺品整理でお困りのことがあれば、ライフリセットのような専門の業者に相談してみるのも良いでしょう。
7. 葬儀後の「お返し」にも心を込めて
ご葬儀を終えると、次は香典返しなどの「お返し」を準備するタイミングがやってきます。
香典返しは、故人様のご葬儀に際して、お香典やお供え物をいただいた方々へ、感謝の気持ちを込めて贈るものです。
「何を贈ればいいのか」 「どのように贈れば失礼にならないか」
慣れないことばかりで、戸惑う方も少なくありません。
香典返しは、いただいた金額の半額から3分の1程度が目安とされています。品物としては、お茶やコーヒー、お菓子、タオルなど、後に残らない「消えもの」が一般的です。
最近では、相手が好きなものを選べる「カタログギフト」も人気があります。
ギフト専門店の「シャディギフトモール」は、1926年創業の老舗で、香典返しにふさわしい商品を数多く取り扱っています。
包装やのし紙、メッセージカードも無料で用意してもらえるので、初めての方でも安心して利用できます。
香典返しは、故人様とご遺族の気持ちを伝える大切な贈り物です。
心から感謝を伝えられるよう、心を込めて選びたいものですね。
8. まとめ
今回は、男性の喪服「ダブルスーツ」を中心に、葬儀の服装やマナーについてお伝えしてきました。
- ダブルスーツは、決してマナー違反ではありませんが、現代ではシングルのブラックスーツが主流となっています。
- 喪服には、正喪服、準喪服、略喪服の3種類があり、ご自身の立場や状況に合わせて使い分けることが大切です。
- 喪服の準備は、いざという時に慌てないための「終活」の一つです。購入だけでなく、レンタルという選択肢もあります。
ご葬儀は、故人様との最期のお別れをする、非常に大切な時間です。
服装のことで悩んだり、心配したりするのではなく、故人様を偲ぶことに集中できるよう、今できる準備を少しずつ始めてみませんか?
もし、ご葬儀のことで他にも知りたいことがあれば、以下の記事も参考にしてみてください。
この記事が、皆さんにとって少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
執筆者プロフィール:
Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。