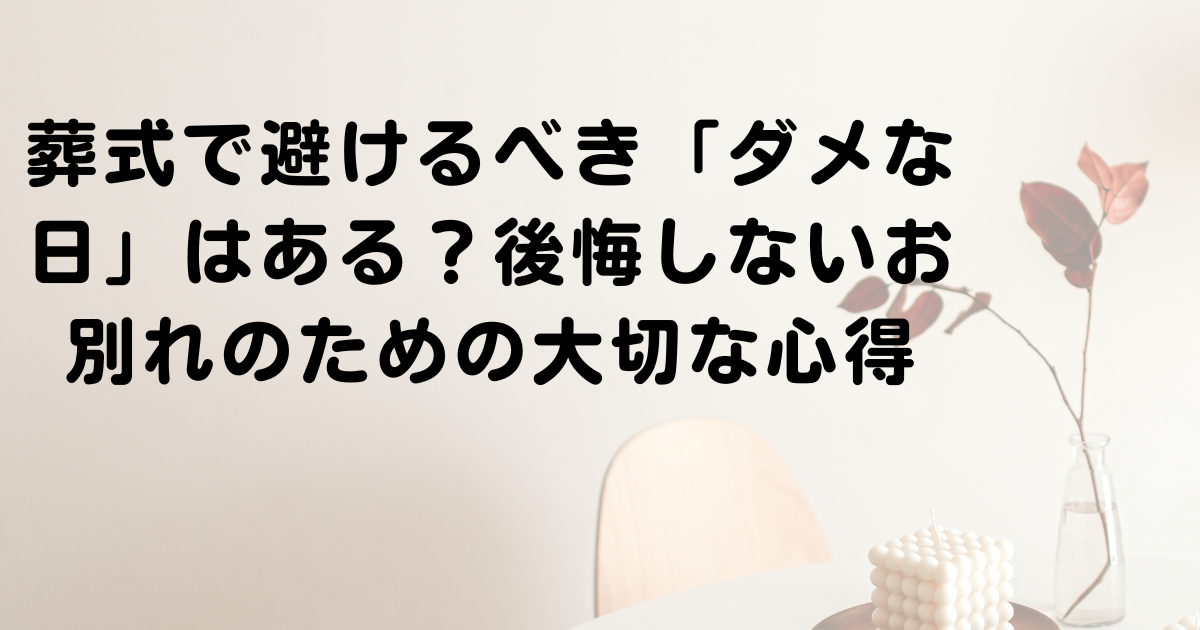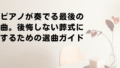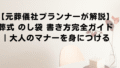はじめに:大切な人を送る日だからこそ知っておきたいこと
こんにちは。元葬儀社プランナーのKeisukeです。 私はこれまで12年間、800件以上のご葬儀に携わってきました。葬儀の現場で、ご遺族の「どうしたらいいかわからない」という不安や戸惑いに何度も触れてきました。特に、故人様を心安らかに送り出すために「何が正しいのか」「何をしてはいけないのか」というご質問は、本当によくいただきます。
「葬式をしてはいけない日、いわゆる葬式で『ダメな日』ってあるのでしょうか?」
もしかすると、あなたも一度はこんな疑問を抱いたことがあるかもしれません。 大切なご家族との最期のお別れ。その日を後悔なく迎えるためには、準備段階で知っておくべきことがたくさんあります。特に、日程に関する迷いは、多くの方が直面する問題です。
結論から申し上げますと、「絶対に葬式をしてはいけない日」というものは、ほとんどありません。 しかし、地域の風習や宗教的な慣習、そして火葬場の都合など、いくつかの理由から「避けた方が無難な日」や「注意が必要な日」は確かに存在します。
この記事では、元葬儀社プランナーとしての経験と知識をもとに、以下の3つのポイントについて詳しくお話ししていきます。
- 知っておきたい!友引・仏滅など「六曜」と葬儀の関係
- 地域によって異なる「葬儀を避ける日」の風習
- 葬儀日程を決める上で本当に大切なこと
大切な方を亡くされたばかりで、お心も体も大変な時期かと思います。専門的な内容も含まれますが、なるべく分かりやすく、丁寧にご説明いたします。 この記事が、あなたの大切な方とのお別れの時間を、少しでも穏やかに迎えるための一助となれば幸いです。
葬式で「ダメな日」って?六曜と火葬場の関係を徹底解説
「友引の日に葬儀をしてはいけない」 この言葉は、多くの方が耳にしたことがあるのではないでしょうか。 なぜ、友引に葬儀をしてはいけないと言われるのか。その背景には、日本の文化に深く根付いた「六曜(ろくよう)」という考え方があります。
1. 六曜(ろくよう)とは?
六曜とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つの日のことを指します。もともとは中国で生まれた占いが日本に伝わったもので、暦に記載されるようになりました。 特に結婚式や入籍などのお祝い事では「大安」、お祝い事を避ける日として「仏滅」が知られていますね。
そして、葬儀のようなお悔やみ事と関連が深いのが「友引(ともびき)」です。
- 友引(ともびき)の意味
友引はもともと「共引」と書き、「勝負事で引き分けになる日」という意味でした。しかし、後に「友を引く」という字が当てられるようになり、「友を死の世界に引き込んでしまう」という迷信が生まれました。 このため、大切な方を亡くされたご遺族が「友引に葬儀を行うと、故人様が友人や家族を連れて行ってしまうのではないか」と心配されるようになったのです。
この考え方は、仏教や神道といった宗教的な教えとは一切関係がありません。 あくまでも民間信仰であり、迷信のひとつに過ぎません。
しかし、この迷信が広まったことで、日本の多くの地域では友引の日に「火葬場がお休みになる」という慣習が定着しました。 現在でも、全国のほとんどの火葬場が友引の日を休業日としています。
- 友引を避けるのは、火葬場がお休みだから
つまり、友引に葬儀を避ける最大の理由は、「故人様の火葬ができないから」です。 火葬を伴う葬儀の場合、ご家族が友引を避けたかったとしても、火葬場が休業している以上、物理的にその日に葬儀を行うことは非常に困難です。
このため、お通夜は友引に行い、火葬と告別式は友引明けの日に行うというケースが一般的です。 もし、ご遺族が「友引でも気にしない」とお考えであっても、火葬場の都合があるため、日程調整の際には注意が必要です。
2. 六曜と葬儀に関するその他の日
友引以外にも、六曜には葬儀にまつわる考え方があります。
- 仏滅(ぶつめつ)
仏滅は「仏も滅するような最悪の日」とされ、お祝い事は大凶とされています。 しかし、葬儀のようなお悔やみ事は「仏が滅する」という考えから、**「これ以上悪いことは起こらない日」**として、むしろ好んで葬儀を行うという地域や考え方もあります。 仏滅に葬儀を行うこと自体に問題はありませんし、火葬場が休業になることもありません。
- 赤口(しゃっこう、しゃっく)
赤口は「赤」という文字から「血」「火」を連想させ、刃物や火事を扱うことを避ける日とされています。 午前と午後の時間帯に注意が必要で、正午だけが吉とされています。 葬儀に関しては、特に避けるべきという慣習はありませんが、一部の地域や個人の考え方によっては、気になる方もいらっしゃるかもしれません。
【まとめ】 六曜の中で、特に葬儀と関連が深いのは「友引」です。 友引の日は「火葬場がお休みになる」ため、物理的に葬儀ができないということを覚えておきましょう。 それ以外の六曜については、特に気にする必要はありませんが、ご親族の中に六曜を重んじる方がいらっしゃる場合は、事前に相談しておくと安心です。
地域の風習で決まる「葬儀を避ける日」
六曜以外にも、日本には地域特有の風習や慣習によって、葬儀の日程を調整することがあります。
1. 地域の慣習「葬儀を行ってはいけない日」
ごく稀ですが、特定の地域では、「葬儀を行ってはいけない日」が存在する場合があります。 例えば、正月三が日や、お盆期間中は、ご親戚が集まる時期であるため、葬儀を避ける慣習がある地域もあります。 これは、ご親戚が集まる場を、故人様との最後の別れの場にすることは、少し気が引けるという考え方があるからです。
また、特定の神社の祭礼日や、地域の大きな行事がある日なども、参列者の都合を考慮して葬儀を避けることがあります。 このような地域の風習は、ご家族やご近所の方に聞いてみないと分からないことが多いです。 もし、故郷でのご葬儀を検討されている場合は、事前に地域の詳しい方や、葬儀社に相談してみると良いでしょう。
2. 仏教・神道の教えから見た葬儀の日程
宗教的な観点から「ダメな日」はあるのでしょうか。
- 仏教
仏教には、「この日に葬儀をしてはいけない」という教えはありません。 しかし、宗派によっては、特定の日に特別な法要があるため、僧侶の都合がつかない場合があります。 ご葬儀の日程を決める際には、菩提寺のご住職様と相談することが不可欠です。
- 神道
神道でも、「葬儀を避けるべき日」という決まりはありません。 神道では、故人様を「神様」としてお祀りする「神葬祭」を行います。 このため、お正月や神社の祭礼期間中は、神職の都合がつかない場合があるため、日程を調整することがあります。
【まとめ】 六曜の友引以外にも、地域の風習や宗教者の都合によって、日程を調整する必要がある場合があります。 これらの事情は、ご自身で調べるのが難しいことが多いので、葬儀社の担当者と密に相談しながら進めていくのが一番安心です。 経験豊富なプロに相談することで、思わぬトラブルを避けることができます。
葬儀の日程を決める上で、本当に大切なこと
ここまで、葬儀を避けるべき日についてお話ししてきました。 しかし、現実的な視点に立つと、日程調整で最も重要なことは、「故人様やご家族の意向」と「関係者の都合」をいかにうまく調整するかです。
1. 故人様とご家族の想いを第一に
ご葬儀は、故人様とご家族にとって、最後の思い出を作る大切な時間です。 故人様が生前、どのようなお見送りを望んでいたか。そして、ご家族がどのような気持ちで送り出したいか。 まずは、その想いを一番に尊重することが大切です。 「この日が良い」という風習や迷信にとらわれすぎず、ご家族が納得できる日程を最優先に考えましょう。
2. 関係者の都合を考慮する
ご葬儀は、ご家族だけで行うものではありません。 ご親戚やご友人、会社関係の方など、多くの方が故人様とのお別れのために駆けつけてくださいます。
- 僧侶や神職 菩提寺や故人様と縁のある寺院の僧侶、または神職の方の都合は、最優先で確認する必要があります。 宗派によっては、特定の日に法要がある場合もあるため、必ず相談して決めましょう。
- 親族 遠方からいらっしゃるご親族がいらっしゃる場合は、移動時間や宿泊の手配を考慮した日程が必要です。 ご親族間で日程について話し合い、全員が納得できる日を見つけることが大切です。
- 火葬場 前述の通り、友引は火葬場がお休みです。 また、火葬場の予約は非常に混み合います。特に、年末年始や友引明けは予約が集中し、数日待ちになることも珍しくありません。 ご逝去から葬儀までの日数が長くなる場合は、故人様を安置する場所の手配も必要になります。
3. スムーズな日程調整のために「信頼できる葬儀社」選びが重要
大切な方を亡くされたばかりで、悲しみの中でこれらのことをすべてご自身で判断し、手配するのは非常に大変なことです。 だからこそ、信頼できる葬儀社の存在が不可欠になります。
経験豊富な葬儀社であれば、ご家族の想いを丁寧に聞き取り、六曜や地域の風習、そして火葬場の空き状況などを総合的に判断して、最適な日程を提案してくれます。
しかし、葬儀社は全国に数えきれないほど存在し、その品質や費用は様々です。 突然のことで時間がない中、どこに依頼すれば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
「いい葬儀社ってどうやって見つければいいの?」
そんな不安をお持ちの方には、東証プライム上場企業が運営する【安心葬儀】のようなサービスを活用することをおすすめします。
このサービスは、全国7,000以上の提携葬儀社の中から、ご希望の条件に合った優良葬儀社を複数社ご紹介し、相見積もりを取ることができます。 費用やサービス内容を比較検討できるため、時間がない中でも、納得のいく葬儀社を冷静に選ぶことが可能になります。
- 【安心葬儀】のメリット
- 全国7,000社以上の優良葬儀社から最適な業者を厳選
- 費用やサービス内容を比較検討できる相見積もり
- 24時間365日、専門スタッフがサポート
相見積もりを取ることは、決して失礼なことではありません。 十数万円から数百万円という高額な費用がかかる葬儀だからこそ、後悔しないためにも、複数の選択肢を比較することは非常に大切です。 ご自身やご家族のためにも、ぜひ一度検討してみてください。
葬儀の日程以外で、後悔しないお別れのために知っておきたいこと
葬儀の日程は、お別れの一部分に過ぎません。 ここからは、私が葬儀プランナーとして経験した中で、ご遺族が「もっと早く知っておきたかった」と話されることの多い、大切なポイントをいくつかご紹介します。
1. 葬儀の服装「喪服」のマナー
ご葬儀に参列する際、特に女性の方が悩まれるのが「喪服」です。 「手持ちの喪服のデザインが古くなってしまった」「サイズが合わなくなってしまった」「急なことで準備が間に合わない」 このようなお悩みは、本当にたくさんお聞きしました。
喪服は、故人様への敬意を示す大切なものです。 しかし、頻繁に着るものではないため、いざという時に困ってしまうのは仕方のないことです。
そこで便利なのが、喪服のレンタルサービスです。 ネットで簡単に申し込めて、最短で翌日に届けてくれるサービスもあります。 特に、【Cariru BLACK FORMAL】のようなサービスは、デザイン性や質にこだわった人気ブランドの喪服を、購入するよりもリーズナブルに利用できるため、多くの方に喜ばれています。 フルセットレンタルも可能なので、バッグやアクセサリー、数珠まで、必要なものがすべて揃うのは心強いですね。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
- 【Cariru BLACK FORMAL】のメリット
- 人気のブランド喪服が豊富
- ネットで24時間いつでも申し込み可能
- 最短翌日にお届け
- クリーニング不要で返却
ご自身で喪服を準備するのが難しい場合は、このようなサービスを賢く利用するのもひとつの選択肢です。 服装に関する詳しいマナーについては、こちらの記事も参考にしてみてください。
2. 葬儀後の手続き「遺品整理」
ご葬儀が終わった後も、ご遺族には多くの手続きが待っています。 その中でも、特に精神的・肉体的な負担が大きいのが「遺品整理」です。
故人様が大切にされていた品々を整理するのは、非常に辛い作業です。 また、家財道具や不用品の処分など、物理的な作業も多岐にわたります。 「悲しみの中で、とても一人では片付けられない」 「遠方に住んでいて、頻繁に実家に行けない」 このようなお悩みをお持ちの方も少なくありません。
そんな時に頼りになるのが、遺品整理の専門業者です。 専門業者に依頼することで、遺品を丁寧に整理・分別してもらえるだけでなく、不用品の処分や清掃まで一貫して任せることができます。 特に【ライフリセット】のようなサービスは、故人様のお部屋に残された大切な遺品や不要物を、ご家族の気持ちに寄り添いながら丁寧に整理してくれます。 生前にご自身で依頼される方もいらっしゃいます。 ご遺族の負担を軽減するためにも、専門家の手を借りることは非常に有効な手段です。
- 遺品整理業者に依頼するメリット
- ご遺族の精神的・肉体的負担を軽減
- プロの手で丁寧に整理・分別してくれる
- 不用品の処分や清掃まで任せられる
遺品整理は、ご自身で抱え込まず、専門家に相談することも視野に入れてみてください。
3. 葬儀後の贈り物「香典返し」
ご葬儀でお香典をいただいた方へのお礼として贈る「香典返し」。 「失礼のないようにしたいけれど、何を贈ればいいの?」 「いつまでに贈るべき?」 このような質問も、ご葬儀の後に多く寄せられます。
香典返しは、忌明け(四十九日法要後)に、いただいたお香典の半額〜3分の1程度の品物を贈るのが一般的です。 しかし、遠方にお住まいの方や、会社関係の方など、状況によって対応が異なります。
香典返しを選ぶ際には、様々な品物の中から、贈る相手に喜んでもらえるものを見つけることが大切です。 【シャディギフトモール】のようなギフト専門店は、香典返しにふさわしい品物が豊富に揃っており、のし紙や包装、メッセージカードなども無料で対応してくれるため、安心して選ぶことができます。 特に、贈る相手の好みがわからない場合は、カタログギフトも喜ばれます。
- 【シャディギフトモール】のメリット
- 香典返しにふさわしい品物が豊富
- 包装、のし紙、メッセージカードが無料
- カタログギフトなど幅広い選択肢
香典返しのマナーや選び方については、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
4. 葬儀の流れと心構え
故人様との突然のお別れに直面したとき、「まず何をすればいいのか分からない」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。 葬儀の流れを事前に知っておくことで、いざという時も冷静に対応することができます。
こちらの記事で、葬儀の全体の流れと、ご遺族が知っておくべき心構えについて詳しく解説しています。
最後に:後悔しないお別れのために、今できること
大切な方を亡くされたとき、悲しみに暮れる中で、様々な決断を迫られます。 日程、費用、服装、そして故人様をどのような形で送り出すか。 「もし、あのときこうしていればよかった」 後悔の念は、時間が経っても心に残ってしまうものです。
私は、父を突然亡くした経験から、この業界に飛び込みました。 右も左も分からず、葬儀の手配に奔走した苦しい経験があったからこそ、今、あなたに伝えたいことがあります。
「後悔しないお別れのために、情報を集め、専門家の手を借りること」
そして、なによりも「故人様との最後の時間を大切にすること」です。
この記事が、少しでもあなたの不安を和らげ、故人様とのお別れの時間を、心穏やかに過ごすための一助となれば幸いです。
ご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて情報を発信していきます。 何かご不明な点やご不安なことがありましたら、いつでもご相談ください。
筆者プロフィール
Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。 現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。 業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。 現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。 退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。 終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。 「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか? あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。