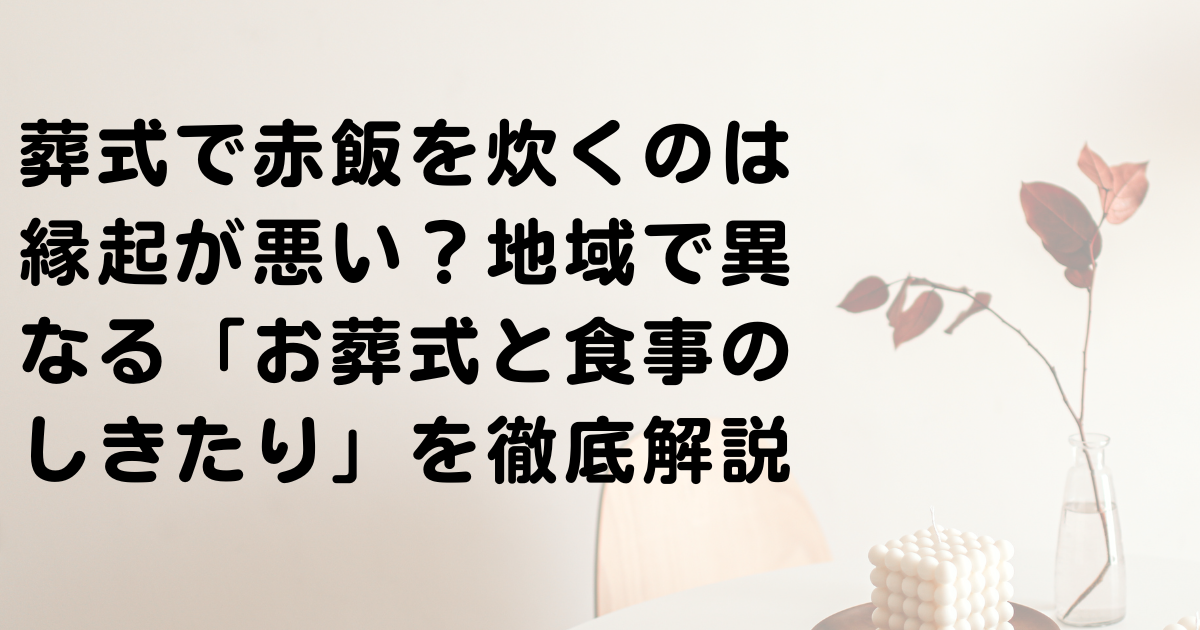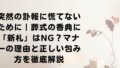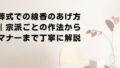こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前は12年間、葬儀社のプランナーとして働いており、これまでに800件以上のご葬儀に携わってきました。
ご家族を亡くされ、深い悲しみの中にいらっしゃるご遺族の皆様に寄り添う中で、費用や手続き、そして何より日本の文化や慣習にまつわる「なぜ?」という疑問をたくさんお聞きしてきました。特に食事に関するしきたりは、地域や家庭によって違いが大きく、戸惑われる方が少なくありません。
「葬式なのに、なぜ赤飯を炊くの?」
「お葬式に持ち寄る料理は、どうすればいい?」
今回は、そんな疑問にお答えするため、お葬式と食事にまつわるしきたりについて、私が実際に現場で見てきたこと、学んできたことを踏まえながら、丁寧に解説していきたいと思います。
ご自身の、またはご家族の「終活」を考えられている方、今後のお葬式に向けて情報を集めていらっしゃる方にとって、少しでも安心につながる情報となれば幸いです。
葬式で赤飯を炊くのは「縁起が悪い」のか?
お葬式で赤飯を炊くことについて、皆様はどのような印象をお持ちでしょうか?
多くの方が「赤飯はおめでたい席で食べるものだから、お葬式のような悲しい席にはふさわしくない」と思われるかもしれません。たしかに、一般的にはそのように考えられています。しかし、実は一部の地域やご家庭では、お葬式の後に赤飯を炊くという慣習が、古くから今もなお大切に受け継がれているのです。
これは、非常に興味深い日本の文化の一つです。なぜ、悲しみの場であるお葬式の後に、お祝い事に使われる赤飯を炊くのでしょうか?
その背景には、いくつかの説があります。
- 「血の穢れ(けがれ)」を清めるため日本では古くから、死を「穢れ(けがれ)」と捉える考え方がありました。この「穢れ」を清める力があると信じられていたのが、「赤色」です。古代から、赤色には邪気を払う力があるとされてきました。お葬式の後に赤飯を炊くことで、故人様を送り出した後の家の穢れを清め、日常へと戻っていくための区切りとしていた、という説です。
- 「悲しみに区切りをつける」ため亡くなられた直後は、ご遺族は深い悲しみに包まれています。しかし、いつまでも悲しみに暮れているわけにはいきません。故人様のご冥福を祈りつつ、残された家族は前を向いて歩んでいかなければならないのです。赤飯を炊くことで、「お葬式という大きな区切りを終え、日常へと戻っていく」という意思表示をしていた、という説です。
- 「無事にお役目を終えた」ことを祝うためこれは少し意外な説かもしれません。お葬式は、残されたご遺族にとって非常に大きな「お役目」です。慣れない手続きや、ご会葬者への対応など、心身ともに疲労困憊する方も少なくありません。すべてのお役目を無事に終えられたことを「めでたい」とし、赤飯を炊いてねぎらい合った、という説も存在します。
これらの説からもわかるように、お葬式で赤飯を炊くという慣習は、決して「縁起が悪い」という単純なものではなく、故人様への想いと、残された家族の心の区切りを大切にする、深い意味合いが込められているのです。
ただし、この慣習はあくまでも一部の地域やご家庭に限定されたものです。もし、ご自身やご親戚のお葬式で赤飯を炊くという話が出た場合、周囲の状況や、その地域の慣習をよく確認することが大切です。
知らないままに他地域の慣習を取り入れてしまうと、誤解を招く可能性もありますので注意が必要です。もし、ご心配なことやご不明な点があれば、お葬式のプロである葬儀社に相談するのが一番安心でしょう。
葬式と食事のしきたり:地域によって大きく異なる「通夜振る舞い」
お葬式における食事のしきたりとして、もう一つ、地域によって違いが顕著に現れるのが「通夜振る舞い(つやぶるまい)」です。
通夜振る舞いとは、通夜式の後に参列者に食事を振る舞うことを指します。これは故人様を偲び、思い出話を語り合いながら、残されたご家族が故人様と共に最後の夜を過ごすという意味合いが込められています。
この通夜振る舞いの料理についても、地域や家庭によって様々な慣習があります。
- 一般的な通夜振る舞い多くの地域では、通夜振る舞いの料理として、お寿司やオードブル、揚げ物などが用意されることが多いです。大勢の人が一度に集まるため、箸でつまみやすく、取り分けやすい料理が好まれます。
- 「精進料理」が基本となる地域仏教の教えでは、お葬式や法要の際には「精進料理」をいただくのが一般的です。肉や魚などの殺生を避けた、野菜や穀物中心の料理が基本となります。特に年配の方が多いご親戚の中には、この精進料理を大切にされる方もいらっしゃるかもしれません。
- 故人様の好きだったものを用意する地域最近は、形式に縛られず、故人様が大好きだった料理や、思い出の料理を用意するご家庭も増えてきました。故人様を偲ぶ会として、形式にとらわれず、温かい雰囲気で故人様を送りたい、というご遺族の想いが反映されています。
このように、通夜振る舞いの料理一つとっても、様々な考え方や慣習があります。
ご自身の地域の慣習がよくわからない、という場合は、やはりご親戚や、お葬式のプロである葬儀社に相談するのが良いでしょう。
葬式に関する様々な「しきたり」と「変化」
食事のしきたりだけでなく、お葬式には様々な慣習が存在します。
- 「友引(ともびき)」にはお葬式をしない?カレンダーの六曜(ろくよう)の一つである「友引」の日は、「友を引く」という言葉から、故人様が親しい人をあの世に連れて行ってしまう、と考えられ、お葬式を避ける慣習があります。これは仏教の教えとは関係のない、日本の民間信仰の一つです。そのため、最近では「友引」でもお葬式を行うご家庭も増えてきています。
- 香典返しの慣習香典返しは、香典をいただいた方へのお礼として贈る品物です。一般的には、四十九日の忌明け(きあけ)後にお贈りするのが慣習とされています。しかし、最近は葬儀当日に香典返しを渡す「当日返し」が増えてきました。これは、遠方からお越しになった方への配慮や、忌明け後の準備の手間を省くという、ご遺族の負担を減らす目的があります。
- 喪服のマナーお葬式に参列する際の服装にも、様々なマナーがあります。かつては、ご遺族は和装の喪服を着るのが一般的でした。しかし、最近では、洋装のブラックフォーマルが一般的です。ただし、ブラックフォーマルにもいくつかのマナーがあります。
- 肌の露出を避ける(夏場でも、半袖のワンピースの上にジャケットを羽織るなど)光沢のある素材は避けるバッグや靴も、金具の少ないシンプルなものを選ぶアクセサリーは、結婚指輪以外は真珠のネックレスや一粒のイヤリング程度にとどめる
- こうしたマナーは、故人様やご遺族への敬意を表すために、とても大切なことです。もし、喪服をお持ちでない方や、サイズが合わなくなってしまったという方は、レンタルサービスを利用するのも一つの手です。
- 例えば、Cariru BLACK FORMALのようなサービスを利用すれば、高品質でマナーに沿った喪服や小物一式を、手軽にレンタルできます。お葬式は、突然の訃報で慌ただしくなることがほとんどです。そうした時でも、しっかりとした喪服を準備できるのは、とても心強いことだと思います。✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
- お葬式は、故人様を送り出す大切な儀式であると同時に、残されたご遺族が故人様と向き合い、心の整理をするための時間でもあります。こうした慣習やマナーは、その大切な時間をより良く過ごすための、一つの指針となるのです。
葬儀の準備:故人様のため、そしてご家族のためにできること
お葬式にまつわる様々な慣習やマナーについてお話してきましたが、最も大切なのは、故人様を想う気持ちと、ご家族が安心して見送れることです。
お葬式は、人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、わからないことや不安なことがたくさんあるのが当然です。
「どこに相談したらいいかわからない」
「費用がどれくらいかかるのか心配」
「故人様の希望に沿ったお葬式にしてあげたいけれど、どうすればいい?」
そうした不安を抱えながら、故人様を亡くされたばかりの状態で、短時間のうちに葬儀社を決めなければならないことも少なくありません。
しかし、何も知らずに葬儀社を一つだけ見て決めてしまうと、後から「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまうことにも繋がりかねません。
そうならないためにも、事前にしっかりと情報を集めておくことが大切です。
「終活」という言葉が広まり、ご自身の最期をどう迎えるか、ご家族にどのような負担をかけたくないか、事前に準備される方が増えてきました。
終活の一環として、事前に複数の葬儀社から見積もりをとっておくことは、非常に有効な手段です。
- 複数の葬儀社から見積もりをとるメリット
- 費用の比較ができる:葬儀の費用は、葬儀社やプランによって大きく異なります。事前に相見積もりをとることで、適正な費用を把握することができます。サービス内容の比較ができる:葬儀社によって、プランに含まれるサービスや、オプションの内容は様々です。比較検討することで、ご自身の希望に合ったサービスを見つけられます。担当者の人柄や対応を見極められる:お葬式は、葬儀社の担当者と二人三脚で進めていくものです。事前に相談することで、担当者の人柄や対応を確かめることができます。
お葬式の後も続く「終活」:遺品整理と香典返し
お葬式を無事に終えられた後も、ご遺族には、故人様が残された様々な手続きや作業が待っています。
その中でも、特に大きな負担となるのが「遺品整理」です。
故人様が生前大切にされてきたもの、思い出の品、そして膨大な量の生活用品。これらを一つひとつ整理していく作業は、時間的にも精神的にも、非常に大きな負担となります。
- 遺品整理の難しさ
- 膨大な量:長年住み慣れた家には、想像以上のモノが残されています。
- 精神的な負担:故人様との思い出が詰まった品々を前に、なかなか手がつけられない。
- 専門的な知識が必要:大型家具や家電の処分、貴重品の仕分けなど、専門的な知識や手続きが必要となる場合があります。
- ✅ 遺品整理のことなら【ライフリセット】そしてもう一つ、お葬式後に大切なのが「香典返し」です。香典返しは、香典をいただいた方へのお礼として、四十九日の忌明け後に贈るのが一般的です。品物を選ぶ際にも、いくつかの注意点があります。
- 相場:いただいた香典の半額から3分の1程度の品物を選ぶのが一般的です。品物の選び方:弔事の品物には「不幸を後に残さない」という意味合いがあるため、消耗品(お茶や洗剤、タオルなど)が好まれます。最近は、贈る相手が好きなものを選べる「カタログギフト」も人気があります。
- ✅ シャディのカタログギフト!お祝い、内祝い、各種ギフトに
最後に:お葬式は「後悔しないお別れ」のために
お葬式に関する「しきたり」や「慣習」は、時代とともに少しずつ変化しています。
しかし、その根底にある「故人様を想う気持ち」と「残された家族が前を向いて生きていくための区切り」という、大切な部分は決して変わりません。
お葬式は、故人様との最期のお別れをする、一生に一度の大切な時間です。だからこそ、後から「こうすればよかった」と後悔することのないように、事前にしっかりと準備しておくことが、とても重要になります。
もし、今「終活」を始めようと考えていらっしゃる方、または「今後のお葬式について少し不安がある」という方は、ぜひこのブログの他の記事も参考にしてみてください。
私自身も、20代後半で父を突然亡くし、何もわからないまま葬儀の手配に奔走した経験があります。その経験から、同じような思いをする人を少しでも減らしたいと、このブログを立ち上げました。
お葬式は、悲しいことばかりではありません。故人様との思い出を振り返り、ご家族やご友人との絆を再確認する、大切な時間でもあります。
ご自身の、またはご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、これからも心を込めて情報を発信していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。