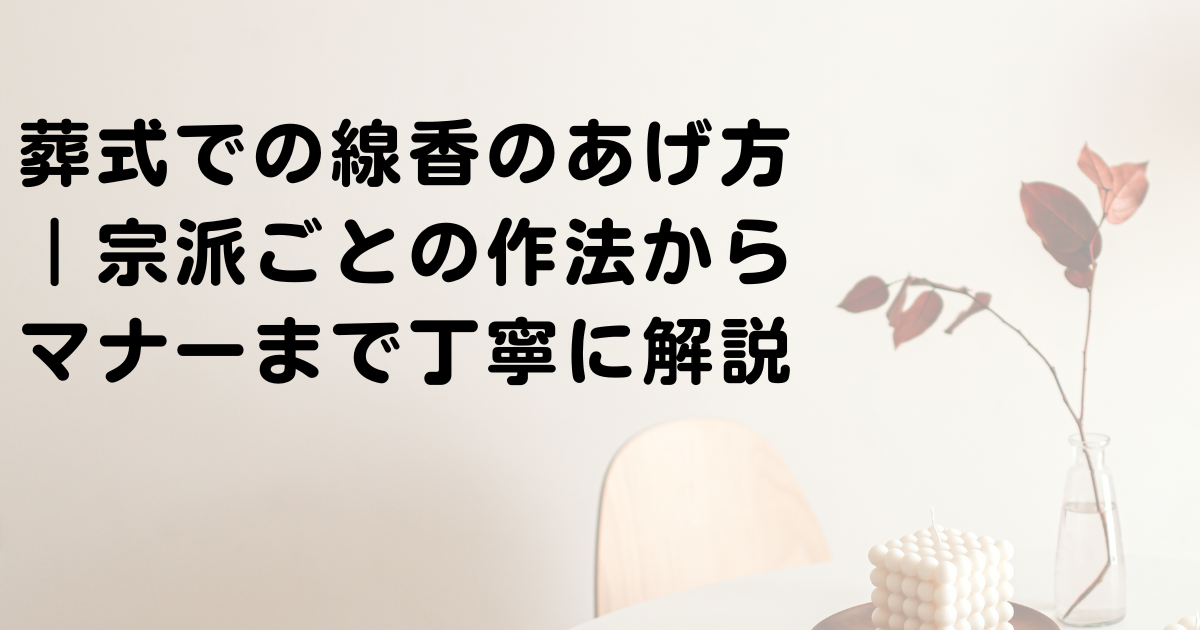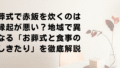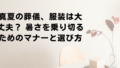こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
この度は、大切な方を亡くされ、お葬式に参列されることになった皆さま、心よりお悔やみ申し上げます。
お葬式は、故人様との最期のお別れをする大切な時間です。しかし、突然のことで、何から手をつけて良いかわからない、どう振る舞えばいいのかわからないと、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
特に、普段の生活ではあまり馴染みのない「お線香をあげる」という行為。いざ、ご焼香の順番が回ってきたときに、「これで良いのだろうか?」と戸惑ってしまう方も少なくありません。
この記事では、元葬儀社プランナーである私が、ご遺族や参列者の皆さまが安心して、故人様への感謝や追悼の気持ちを込めてお線香をあげられるよう、その意味合いから、宗派ごとの正しい作法、そして気をつけたいマナーまで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
この記事が、大切な方へ心を込めて手を合わせるための一助となれば幸いです。
なぜお葬式で線香をあげるの?|その深い意味と役割
お葬式で線香をあげることは、単なる儀式ではありません。そこには、仏教の教えに基づいた深い意味と、故人様、そして私たち生きている者に対する大切な役割が込められています。
お線香が持つ意味を理解することで、より一層、心を込めて手を合わせることができるでしょう。
1. 故人様の食事
仏教では、故人様が亡くなられてから四十九日の間は、**「香食(こうじき)」**といって、香りを召し上がると考えられています。つまり、お線香の香りは、故人様の食事なのです。
故人様が旅立つにあたり、お腹を空かせてしまわないように、心を込めてお線香をあげる。この行為は、故人様への温かい思いやりそのものと言えるでしょう。
2. 心と身体を清める
お線香の香りは、私たちの心を落ち着かせ、邪気を払う力があると考えられています。お葬式という非日常的な空間で、悲しみや不安で乱れがちな心を鎮め、故人様と向き合うための清らかな心身を整える役割も担っています。
3. 故人様の導き
煙は、この世からあの世へ、故人様の魂を導く道しるべになると信じられています。お線香の煙が天高く立ち上っていく様子は、故人様が安らかに旅立っていく姿を象徴しているのです。
4. 故人様との対話
お線香をあげるときは、故人様のご冥福を祈り、感謝の気持ちを伝える大切な時間です。静かに立ち上る煙を眺めながら、故人様との思い出を振り返り、心の中で語りかける。このひとときが、故人様との最後の対話となり、ご遺族や参列者の心の整理にも繋がります。
このように、お線香をあげるという行為には、故人様への供養だけでなく、私たち自身の心を整えるための大切な意味が込められているのです。
お葬式での線香のあげ方|基本の流れと手順
ここからは、実際に斎場などで線香をあげる際の、一般的な流れと手順について解説します。
宗派や地域によって多少の違いはありますが、基本的な流れは共通していますので、まずはこの基本をしっかりと覚えておきましょう。
1. 順番を待つ
お葬式では、ご遺族や親族、そして参列者の順に焼香(線香をあげることも含みます)をしていきます。自分の順番が来るまでは、静かに待ちます。
2. 遺族に一礼する
自分の順番が来たら、遺族に向かって一礼します。「本日はお招きいただきありがとうございます」という気持ちを込めて、深くお辞儀をしましょう。
3. 祭壇へ進み、故人に一礼する
遺族に一礼した後、祭壇の前に進みます。ご遺影に向かって一礼します。この時も、故人様への敬意を込めて、丁寧にお辞儀をしましょう。
4. 着火・消火
線香台の前に座り、ろうそくから火をつけます。この時、線香の先に息を吹きかけて火を消すのはマナー違反とされています。手であおぐか、軽く振って火を消しましょう。
5. 線香を立てる(あるいは寝かせる)
線香を香炉に立てます。宗派によっては、線香を折って寝かせる場合もあります。この後、宗派ごとの作法について詳しく解説しますので、そちらも参考にしてください。
6. 合掌・一礼
線香をあげた後、故人様のご冥福を祈り、合掌します。そして、祭壇に向かって一礼します。
7. 遺族に一礼して戻る
祭壇を離れる前に、もう一度遺族に向かって一礼し、自分の席に戻ります。
この一連の流れを覚えておけば、いざという時にも慌てず、落ち着いて故人様と向き合うことができるでしょう。
宗派ごとの線香のあげ方|正しい作法で心を込めて
実は、線香のあげ方は宗派によって異なります。
「どの宗派かわからない」「初めて参列する宗派のお葬式で、どうすればいいか不安」という方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、前の人がどのようにしているかを見て、それに倣うのが最も良いでしょう。
ここでは、主な宗派の線香のあげ方をご紹介します。
天台宗
天台宗では、線香を1本、香炉の中央に立てます。
特に回数は定められていませんが、丁寧に1本立てるのが一般的です。
真言宗
真言宗では、線香を3本、香炉に立てます。
3本立てることで、「仏・法・僧」の三宝を敬うという意味が込められています。
立て方は、手前から順に1本、その奥に2本立てるのが正式な作法です。
浄土宗
浄土宗では、線香を1本、香炉に立てます。
ただし、浄土宗では焼香が中心となるため、線香を立てる機会は少ないかもしれません。
浄土真宗本願寺派(お西)
浄土真宗では、線香を立てるという習慣がありません。
線香を香炉に入る長さに2つに折り、火をつけてから寝かせます。
浄土真宗の教えでは、「故人様はすぐに仏様になる」という考え方があるため、線香の煙で道しるべを作る必要がないとされています。
真宗大谷派(お東)
真宗大谷派も、本願寺派と同様に、線香を香炉に入る長さに2つに折り、火をつけてから寝かせます。
臨済宗
臨済宗では、線香を1本、香炉の中央に立てます。
焼香の回数も1回とすることが多いですが、線香も1本と覚えておくと良いでしょう。
曹洞宗
曹洞宗も、線香を1本、香炉の中央に立てます。
特に回数は定められていません。
日蓮宗
日蓮宗では、線香を1本、香炉の中央に立てます。
しかし、焼香の回数が1回または3回と定められていることが多いため、それに倣って線香を立てる回数を決めることもあります。
これらの宗派ごとの作法を知っておくことで、いざという時に戸惑うことなく、故人様への弔意を示すことができるでしょう。
お葬式での線香マナー|気をつけたい5つのポイント
線香をあげる際の作法だけでなく、周囲への配慮も忘れてはなりません。
ここでは、お葬式で気をつけたい5つのマナーについて解説します。
1. 匂いの強い線香は避ける
ご家庭で使う線香は、様々な香りのものがありますが、お葬式では香りの控えめなものを選ぶのがマナーです。
特に、香水のような強い香りの線香は、周囲の迷惑になる可能性があるため避けましょう。斎場が用意している線香を使うのが無難です。
2. 火を消す際は息を吹きかけない
先ほども触れましたが、線香の火を消す際に息を吹きかけるのはマナー違反です。
人の息には「不浄」なものが含まれると考えられているため、手であおぐか、軽く振って火を消しましょう。
3. 服装はマナーを守る
お葬式に参列する際は、喪服を着用するのが基本です。
急な訃報で喪服がない場合でも、ダークカラーのスーツやワンピースを選ぶなど、派手な服装は避けるようにしましょう。
特に女性の場合、露出の多い服装や、華美なアクセサリーは避けるのがマナーです。
喪服をお持ちでない方、急な訃報で準備する時間がない方、また「上質な喪服をリーズナブルに用意したい」とお考えの方には、喪服のレンタルサービスもおすすめです。
最近では、デザイン性の高いブランド喪服から、マナーに沿ったフルセットまで、幅広い選択肢が用意されています。
株式会社トレジャー・ファクトリーが運営する【Cariru BLACK FORMAL】は、質の高いブランド喪服をレンタルできるサービスです。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
質の良い喪服を、必要な時に必要なだけ借りられるので、費用も抑えられますし、保管場所に困ることもありません。
バッグや数珠、袱紗などの小物もセットでレンタルできるので、急な訃報でも慌てずに対応できるでしょう。
Cariru BLACK FORMALなら、弔事のマナーに沿って厳選された喪服を、ネットで簡単にレンタルできます。ぜひ一度、公式サイトをチェックしてみてください。
4. 故人様との関係性で言葉を選ぶ
ご遺族に声をかける際は、故人様との関係性を考慮し、「この度はご愁傷さまでございます」といった、丁寧な言葉を選びましょう。
「頑張って」などの励ましの言葉は、かえってご遺族を追い詰めてしまう可能性があるため、避けるのが無難です。
5. 故人様への敬意を払う
お葬式は、故人様を偲び、ご冥福を祈るための場です。
私語は慎み、携帯電話の電源は切るなど、故人様とご遺族への敬意を払った行動を心がけましょう。
喪主・ご遺族側の線香マナー|知っておきたい「枕飾り」と「枕飯」
ここまで、参列者の立場での線香マナーについて解説してきましたが、ここからは、喪主やご遺族側の線香マナーについても触れておきたいと思います。
故人様が亡くなられた後、ご遺体を安置し、その枕元に置く飾りを「枕飾り」といいます。
この枕飾りには、枕飯、枕団子、水、そして線香とろうそくが含まれます。
枕飾りは、故人様が旅立つ前に、安心して旅路につけるようにと願いを込めて用意されるものです。
特に、線香とろうそくは、「寝ずの番」といって、お通夜の間、絶やしてはいけないとされてきました。
これは、「線香の煙が故人様の食事だから」「ろうそくの光が故人様の足元を照らすから」という理由からです。
しかし、最近では火災の危険性を考慮し、電気式の線香やろうそくが使われることも増えてきました。
もし、ご自宅で線香を絶やさないようにと言われた場合は、火の元に十分注意し、安全を第一に考えてください。
また、枕飾りの詳細や、お葬式全体の流れについて知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
葬儀社の選び方|後悔しないお葬式のために
大切な方を亡くされた後、ご遺族は悲しみの中で、葬儀の手配という大きなタスクをこなさなければなりません。
葬儀社選びは、その中でも特に重要な決断です。しかし、時間がない中で、どのようにして良い葬儀社を見つければ良いのか、悩んでしまう方も多いでしょう。
私は、元葬儀社プランナーとして、多くのご遺族と接してきました。その中で、**「情報の格差」**によって、不当に高い費用を支払ってしまったり、希望通りの葬儀ができなかったりするケースを何度も見てきました。
「もっと早く、信頼できる葬儀社に出会えていれば…」と後悔される方も少なくありません。
良い葬儀社を見つけるためには、いくつかのポイントがあります。
1. 複数の葬儀社から見積もりをとる(相見積もり)
葬儀費用は、葬儀社によって大きく異なります。必ず複数の葬儀社から見積もりをとり、比較検討しましょう。
2. 費用明細が明確か確認する
見積書は、項目ごとに明確に記載されているか確認しましょう。「一式」とまとめられている場合は注意が必要です。
3. 担当者の対応や人柄を見る
葬儀は、担当者との二人三脚で進めていくものです。親身になって相談に乗ってくれるか、質問に丁寧に答えてくれるかなど、担当者の人柄も重要な判断基準になります。
4. 家族の希望をしっかりと伝える
故人様の遺志や、家族の希望をしっかりと伝え、それが反映されるようなプランを提案してくれるか確認しましょう。
しかし、これらのポイントを押さえて自力で探すのは、時間も労力もかかります。
特に、故人様が亡くなられてから数時間以内に葬儀社を決めなければならないケースがほとんどです。
そのような状況で、良い葬儀社を見つけるのは至難の業です。
そこで、私がおすすめしたいのが、株式会社エス・エム・エスが運営する【安心葬儀】というサービスです。
このサービスは、全国7,000以上の葬儀社の中から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を複数社ご紹介してくれます。
相見積もりを自分で行うのは大変ですが、【安心葬儀】を利用すれば、時間がなくても、簡単に複数の葬儀社の比較検討ができます。
東証プライム上場企業が運営しているサービスなので、安心して利用できる点も大きなメリットです。
ご家族の葬儀をご検討されている方、また終活の一環として事前に情報を集めておきたい方は、ぜひ一度、【安心葬儀】の公式サイトを覗いてみてください。
きっと、皆さまの「後悔しないお別れ」のお手伝いをしてくれるはずです。
葬式後のことまで考えておく|遺品整理とお香典返し
お葬式が終わった後も、ご遺族には多くのやることが残されています。
特に、故人様が遺された遺品の整理や、お香典返しは、精神的にも肉体的にも負担の大きい作業です。
遺品整理について
故人様が住んでいたお部屋の遺品整理は、ご家族だけで行うには大変な作業です。
思い出の品も多く、なかなか手がつけられなかったり、何から手をつけて良いかわからなかったりする方も多いでしょう。
そんな時は、専門の業者に依頼するのも一つの方法です。
株式会社アシストが運営する【ライフリセット】は、遺品整理を専門に行う業者です。
ご家族の気持ちに寄り添いながら、故人様のお部屋を丁寧に整理してくれます。
実家のご両親が亡くなられた方、また、生前整理をご検討されているご本人様も利用されているようです。
遺品整理や生前整理でお困りの際は、ぜひ【ライフリセット】にご相談されてみてはいかがでしょうか。
お香典返しについて
お香典返しは、お香典をくださった方へ、無事に四十九日を終えたご報告と、感謝の気持ちを伝える大切な贈り物です。
お香典返しを贈る時期や、金額の目安、品物の選び方には、いくつかのマナーがあります。
詳しくは、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
お香典返しの品物選びには、シャディ株式会社が運営する【シャディギフトモール】がおすすめです。
1926年創業のギフト専門店で、お香典返しにふさわしい商品を1万点以上も取り揃えています。
様々な価格帯のカタログギフトも充実しており、贈る相手に好きなものを選んでもらうこともできるので、相手に喜ばれること間違いなしです。
包装やのし紙、メッセージカードも無料で豊富に用意されているので、きっとご希望に沿ったお香典返しが見つかるはずです。
お香典返しの準備は、精神的にも疲れている中で行う作業です。
【シャディギフトモール】のような信頼できるサービスを利用して、少しでも負担を減らすことをおすすめします。
まとめ|心を込めてお線香をあげるために
今回は、お葬式での「線香のあげ方」について、その意味合いから宗派ごとの作法、そして気をつけたいマナーまで、幅広く解説しました。
線香をあげるという行為には、故人様への深い愛情と、私たちの心を清める大切な意味が込められています。
故人様との最期のお別れの時間、この記事で得た知識が、皆さまが安心して、心を込めて故人様と向き合うための一助となれば幸いです。
これからも、「家族を想うお葬式ガイド」では、皆さまのお役に立てるような情報を発信していきます。
お葬式に関して、何か不安なこと、わからないことがあれば、いつでもお気軽にブログを訪れてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。