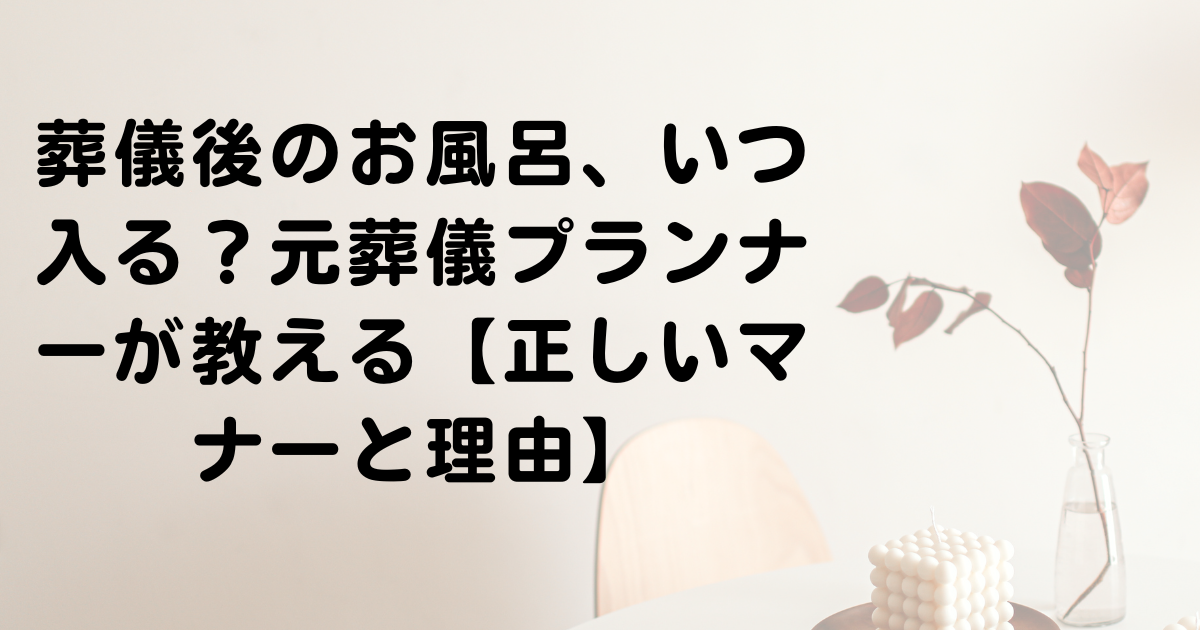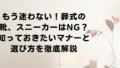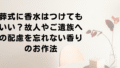はじめに:大切な方を見送った後に、そっと自分を労わる時間
大切な方を亡くされたとき、私たちは深い悲しみの中に身を置きながらも、葬儀という慣れない儀式に立ち向かわなければなりません。気がつけば、通夜から葬儀、火葬と、怒涛のような時間が過ぎていくことでしょう。
ご葬儀が終わって自宅に戻られたとき、心身ともに疲れ切っている方がほとんどです。
「ああ、やっと終わった…」
そう思いながらも、故人様を偲ぶ気持ちと、張り詰めていた緊張から解放された安堵感が入り混じり、何とも言えない空虚感を抱くかもしれません。そんなとき、ふと頭をよぎるのが、「この後、どうすればいいんだろう?」という疑問です。
その中でも、特に多くのご遺族が悩まれるのが、**「葬儀後、すぐにお風呂に入ってもいいのだろうか?」**という疑問です。
「故人様の匂いがついてしまう」「穢れ(けがれ)を洗い流す」といった、古くからの言い伝えや習慣を耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、本当にそれで良いのでしょうか?
この記事では、長年葬儀プランナーとして多くのご遺族と接してきた私の経験をもとに、葬儀後のお風呂について、その起源や現代における考え方、そして何より大切な「ご自身の心と体を労わる時間」について、丁寧に解説していきます。
この記事を読めば、あなたが抱えている疑問や不安がきっと解消され、心穏やかに故人様との思い出を振り返る時間を持てるようになるでしょう。
葬儀後のお風呂:なぜ「すぐに入らない」という風習があるのか?
まず、なぜ「葬儀後すぐにお風呂に入らないほうが良い」という風習が生まれたのか、その背景を理解することから始めましょう。この風習には、主に二つの理由があるとされています。
- 「穢れ(けがれ)」の概念
かつての日本では、「死」は特別な状態であり、死に関わることは「穢れ」と見なされていました。この「穢れ」は、単なる不潔さを指すのではなく、日常とは異なる「非日常」の状態を意味します。葬儀に参列することは、その「穢れ」に触れることと考えられていたのです。
この「穢れ」を自宅に持ち帰らないように、家に入る前には塩で体を清める「清め塩」の習慣が生まれました。お風呂に入ることは、その「穢れ」を洗い流す行為であり、ご遺族にとっては「穢れを洗い流す=故人様との別れを認める」ことにつながると考えられ、故人様への想いを断ち切ることになるとして忌み嫌われた、という説があります。
また、神道においては、死は穢れとされており、死に触れた人は一定期間、穢れを清めるための「忌中(きちゅう)」に入ります。この期間は、お祝い事への参加や、神棚のお参りなどを避けるのが一般的です。
- 「故人様との最後の別れ」を惜しむ気持ち
もう一つの理由は、より感情的なものです。
葬儀という大切な儀式を通じて、故人様との最後の時間を過ごします。ご遺族にとっては、故人様がこの世に存在していたことの「痕跡」を感じていたい、という強い思いがあります。お風呂に入ることは、その痕跡を洗い流してしまう行為だと考えられ、故人様との別れを惜しむ気持ちから、入浴をためらう方が多かったのです。
特に、ご自宅でご遺体を安置されていた場合、故人様がまだ家にいらっしゃるような感覚が強く残るため、入浴によってその感覚が薄れてしまうことを恐れる気持ちは、非常に自然なことと言えるでしょう。
現代における「清め塩」の役割
「穢れ」の概念と関連して、葬儀から帰宅した際に「清め塩」を使う習慣も、現代では少し意味合いが変わってきています。
清め塩は、元々は神道に由来する風習で、文字通り穢れを祓うためのものでした。しかし、仏教にはこの習慣はなく、本来は仏教式の葬儀で用いるものではありません。それでも、日本人の間で古くから根付いた習慣として、葬儀社が用意してくれることが多く、多くの方が受け取ります。
現代の清め塩は、「穢れを祓う」という本来の意味よりも、「気持ちを切り替えるための儀式」としての役割が強くなっています。
葬儀という特別な空間から、日常の生活に戻るための心のスイッチ。
故人様を想いながらも、遺された私たちは明日へと進んでいかなければならない。そうした気持ちの区切りをつけるための行為として、清め塩を手に取る方が多いのです。
葬儀後、すぐにお風呂に入っても良い?【元プランナーの結論】
では、現代においてはどう考えるべきなのでしょうか?
結論から言うと、「ご自身の判断で、無理せずお風呂に入って大丈夫です」。
これまでの説明で、なぜ「すぐに入らない」という風習が生まれたのか、その理由はおわかりいただけたかと思います。しかし、これらの風習はあくまで古くからの慣習であり、医学的・衛生的な根拠はありません。
むしろ、ご葬儀は心身ともに大きな負担がかかる行事です。
- 長時間立ちっぱなしだったり、正座をしていたり…
- 慣れない喪服で身体が締め付けられたり…
- 深い悲しみや緊張で、精神的な疲労もピークに達している…
このような状態のままでは、体調を崩してしまう可能性も考えられます。
故人様を大切に思う気持ちは、決して洗い流されるものではありません。
しかし、遺された私たちが健康でい続けることも、また故人様への供養につながると私は信じています。だからこそ、ご自宅に戻られたら、まずは温かいお風呂にゆっくりと浸かり、心と体を休めてあげてください。
家族の気持ちを尊重することが大切
ご自身は「お風呂に入りたい」と思っても、同居しているご家族の中には、「故人様がかわいそうだ」と、昔ながらの風習を大切にしたいと考える方がいらっしゃるかもしれません。
その場合は、ご家族の気持ちを尊重してあげることが大切です。
「お風呂には入らないけれど、温かいシャワーを浴びて、体をさっぱりさせてからゆっくり休もう」
「今日だけは我慢して、明日からゆっくり入ろう」
といったように、ご家族みんなが納得できる方法を話し合ってみるのも良いでしょう。
故人様を偲ぶ気持ちは、人それぞれです。大切なのは、周りの意見に流されるのではなく、故人様との思い出を大切にするご自身の気持ちと、ご家族の気持ちを尊重することです。
葬儀後の服装はどうすればいい?【喪服の扱い方】
葬儀後のお風呂問題と同じくらい、多くの方が悩むのが喪服の扱い方です。
特に、ご親族として参列された方は、正喪服や準喪服を着用されていることがほとんどでしょう。これらは一般的な洋服とは異なり、デリケートな素材で作られていることが多いため、取り扱いには注意が必要です。
喪服のお手入れ方法
- 脱いだらすぐにハンガーにかける 葬儀から戻ったら、まずは喪服を脱ぎ、風通しの良い場所に干しましょう。脱いだまま放置しておくと、シワやカビの原因になります。
- ブラシでほこりを落とす 喪服には、ホコリやチリ、花粉などが付着していることが多いです。柔らかい洋服ブラシを使って、丁寧に払い落としましょう。
- 汗や汚れは放置しない ご葬儀では、夏場はもちろん、冬場でも暖房が効いた式場内では汗をかきやすいものです。喪服に汗や汚れが付着したまま放置しておくと、黄ばみやシミの原因になります。
- クリーニングに出すタイミング ご自宅での簡単なケアだけでは不安な場合は、クリーニング店に依頼するのが一番安心です。ただし、故人様を火葬場までお見送りする場合は、その日のうちにクリーニングに出すのは難しいかもしれません。その場合は、数日後に改めてクリーニングに出すようにしましょう。
【元プランナーからのアドバイス】
喪服は頻繁に着るものではありません。次にいつ必要になるかわからないからこそ、きちんとお手入れしておくことが大切です。また、喪服は「いつか必要になるかも」と用意していても、久しぶりに出したらサイズが合わなくなっていた、というケースも少なくありません。
そこで、私がお勧めしたいのが喪服のレンタルサービスです。✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
喪服を新しく購入したり、久しぶりに着ようと思ったらサイズが合わなかったり…そんな時にお勧めしたいのが、【Cariru BLACK FORMAL】です。このサービスは、必要な時に必要なものがすべて揃う、高品質なブラックフォーマルレンタルです。上質なブランドの喪服を、購入するよりもリーズナブルに利用できます。
デザイン・質・マナーにこだわる 弔事のマナーに沿って厳選された商品なので、突然の訃報にも慌てずに対応できます。
フルセットレンタルも可能 ジャケット、ワンピースはもちろん、バッグ、サブバッグ、ネックレス、イヤリング、数珠、袱紗といった小物まで、すべてセットでレンタルできるプランが豊富に用意されています。
ネットで簡単予約、最短翌日お届け 24時間いつでもネットで申し込めて、16時までの注文なら最短で翌日午前中にお届けしてもらえます。急なご不幸にも安心です。
返却時クリーニング不要 返却時のクリーニングは不要なので、手間がかかりません。「デザインや質にこだわりたいけど、購入するのはもったいない」「久しぶりに着る喪服がサイズアウトしていないか不安」という方は、ぜひ一度【Cariru BLACK FORMAL】のサービスを検討してみてはいかがでしょうか。
葬儀後の「あれこれ」:手続きや準備はどのように進めるべき?
ご葬儀が終わると、一息つく間もなく、様々な手続きや後片付けが待っています。特に、ご家族を亡くされたばかりの時期は、精神的にも肉体的にも負担が大きいため、何から手をつけていいかわからなくなってしまう方も多いことでしょう。
ここでは、ご葬儀後の主な手続きや準備について、簡単に解説します。
1. 遺品整理
故人様のお部屋に残された遺品や不要物を整理する作業です。故人様との思い出が詰まった品々を前に、なかなか手が進まないという方も多いと思います。
しかし、賃貸物件の場合は、早めに整理を進めなければなりませんし、ご自宅の場合でも、そのままにしておくわけにはいきません。
遺品整理には、故人様の意思を尊重しながら、ご家族でゆっくりと時間をかけて行う方法と、専門の業者に依頼する方法があります。
専門業者に依頼するメリットは、
- 精神的な負担が軽減される
- 不用品の処分や形見分けのサポートをしてもらえる
- 清掃まで含めて依頼できる場合がある
などです。
もし、ご自身で遺品整理を進めるのが難しいと感じたら、専門の業者に相談するのも一つの手です。
【ライフリセット】は、故人様が残された遺品や不用品の整理を専門に行うサービスです。ご家族はもちろん、生前にご本人様が直接依頼されるケースも増えています。
遺品整理は、故人様との最後の向き合いの時間でもあります。無理をして一人で抱え込まず、プロの手を借りることで、心穏やかに故人様を偲ぶ時間を確保することも大切です。
2. 香典返し
葬儀でいただいた香典に対して、感謝の気持ちを込めてお返しをするのが香典返しです。
香典返しの時期や相場、品物選びには、地域や宗派によって様々なマナーがあります。
一般的には、
- 時期:忌明け(四十九日法要後)
- 相場:いただいた香典の金額の3分の1から半分程度
- 品物:お茶、お菓子、タオル、洗剤などの「消えもの」が一般的
とされています。
香典返しは、故人様のためにお香典をくださった方々への感謝の気持ちを伝える大切な機会です。マナーを守って失礼のないようにしたいものです。
【元プランナーからのアドバイス】
香典返しの準備は、ご葬儀の直後から始めることができます。忌明けが近づいてから慌てて準備するよりも、少しずつ進めておくと安心です。
香典返しについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。 [【元葬儀社プランナーが解説】葬式後の香典返し|失礼のない贈り方・選び方ガイド]
香典返しの品物選びに迷ったら、ギフト専門店のオンラインショップを利用するのが便利です。
【シャディギフトモール】は、1926年創業のギフト専門店の公式通販サイトです。お香典返しに最適な商品が1万点以上揃っており、カタログギフトも豊富に扱っています。
- 豊富な品揃え お茶やコーヒー、お菓子、タオル、洗剤など、香典返しに人気の品物が多数揃っています。
- 包装やのし紙も無料 用途に合わせた包装やのし紙、メッセージカードを無料で選べます。
- カタログギフトも人気 相手の好みがわからない場合は、カタログギフトを贈るのも良いでしょう。
3. その他の手続き
ご葬儀後には、故人様の公共料金の名義変更、銀行口座の解約、生命保険の請求など、様々な手続きが待っています。
これらの手続きは、期限が設けられているものもあるため、早めに着手する必要があります。
- 年金:受給停止の手続き
- 健康保険:資格喪失の手続き
- 生命保険:保険金請求の手続き
- 遺言書の確認:遺言書がある場合は、内容に沿って相続手続きを進めます。
- 相続:遺産分割協議書の作成など、専門家(司法書士や税理士)に相談する方が安心です。
これらの手続きは非常に複雑で、ご遺族だけで全てを行うのは大変な負担となります。
わからないことがあれば、市役所や専門家に相談しながら、無理のない範囲で進めていきましょう。
後悔しないお別れのために:今できること
ここまで、葬儀後のお風呂や、その後の手続きについてお話ししてきました。
私が長年、葬儀プランナーとして働いてきた中で感じてきたのは、「ご葬儀に後悔を残さないためには、事前の準備が何よりも大切だ」ということです。
しかし、多くの方は「家族が元気なうちに、そんな話は縁起が悪い」と、ご葬儀の話を避けてしまいがちです。その結果、いざという時になって、
- 「故人様らしいお葬式にしてあげたかったけど、時間がなくてできなかった」
- 「費用が思った以上にかかって、経済的に苦しくなってしまった」
- 「どの葬儀社を選べばいいかわからず、不安な気持ちのまま決めてしまった」
といった後悔を抱えてしまうケースを、数多く見てきました。
ご葬儀は、人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、わからないことや不安なことがあって当然です。
しかし、その不安な気持ちのまま、故人様の逝去後、わずか数時間という限られた時間の中で、大切な葬儀社を決めなければならないのが現実です。
「もし、事前に信頼できる葬儀社を探すことができたら…」
「もし、いくつかの葬儀社から見積もりをとって、費用を比較することができたら…」
そうすれば、もっと納得のいくお別れができたはず。
そうした思いから、私は長年この業界に携わってきました。
ご葬儀は、故人様とのお別れの儀式であると同時に、遺されたご家族が、故人様との思い出を胸に、前向きに生きていくための「心の区切り」をつける大切な時間です。
後悔しないお別れのために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
ご葬儀について不安な気持ちを抱えている方にお勧めしたいのが、【安心葬儀】というサービスです。
これは、全国7,000以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を紹介してくれるサービスです。
- 東証プライム上場企業が運営 運営会社は東証プライム上場企業の株式会社エス・エム・エス。信頼と実績のある企業が運営しているので、安心して利用できます。
- 相見積もりで比較検討できる 複数の葬儀社から見積もりを取る「相見積もり」を利用することで、費用やサービス内容を比較検討できます。
- 時間がない中でも安心 逝去後、慌てて葬儀社を決めなければならない状況でも、専門の相談員がサポートしてくれるので安心です。
終活の一環として、事前にご葬儀について調べておくことや、信頼できる葬儀社を見つけておくことは、決して「縁起が悪いこと」ではありません。むしろ、それはご自身やご家族の「安心」に繋がります。
【安心葬儀】は、そうした「安心」を手に入れるための、頼もしい味方になってくれるはずです。
もし、ご家族の葬儀をご検討されている方、今後に向けて情報を集めている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度サイトを覗いてみてください。
さいごに:故人様との思い出を胸に、ご自身の体を大切に
この記事では、葬儀後のお風呂の風習や、喪服の扱い方、そしてご葬儀後の手続きについてお話ししました。
改めて、大切な方を亡くされたご遺族の皆様に、私からお伝えしたいことがあります。
ご葬儀は、本当に大変なものです。心身ともに疲れ切っていることでしょう。
だからこそ、ご自宅に戻られたら、ご自身の体を一番に大切にしてあげてください。温かいお風呂にゆっくりと浸かり、美味しいものを食べ、心ゆくまでゆっくりと休んでください。
故人様は、きっとあなたの健康を一番に願っているはずです。
「お風呂に入ってさっぱりしてから休みなさい」
「無理せず、ゆっくりと休んでね」
きっと、そう言ってくれているのではないでしょうか。
故人様との思い出は、お風呂に入っても、喪服を脱いでも、決して消えることはありません。
どうか、ご自身の心と体を労わり、ゆっくりと前へ進んでいってください。
このブログが、あなたの心の支えに、そして、後悔のないお別れのためのヒントになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。