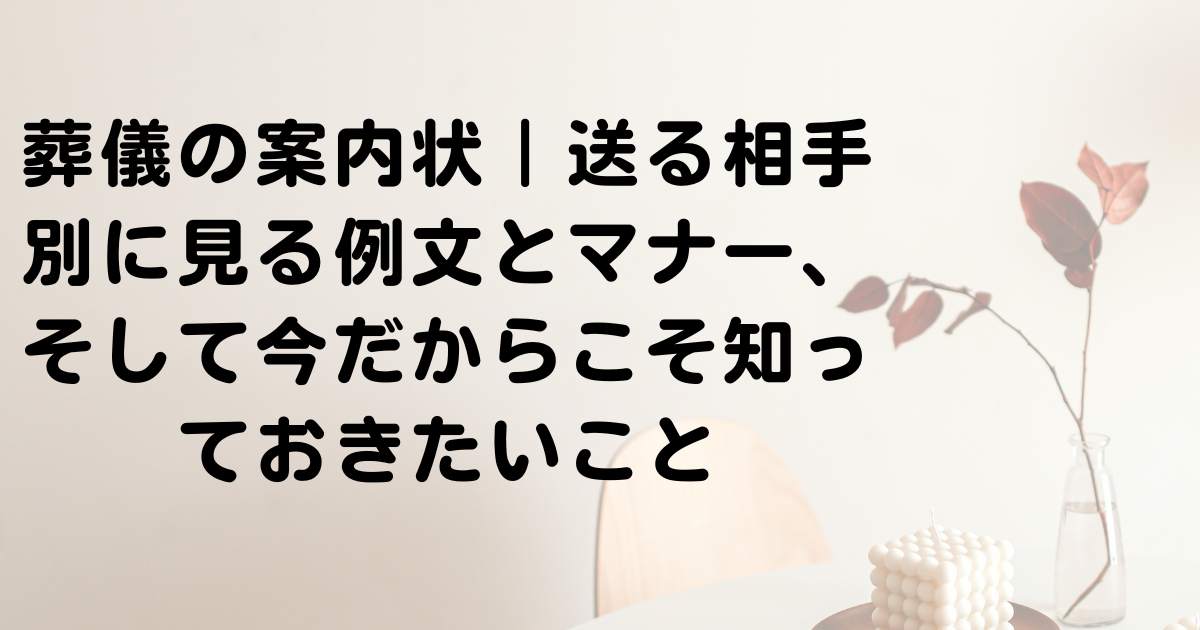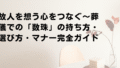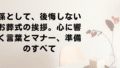筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
はじめに:大切な方とのお別れに際して
人は誰しも、いつか大切な方との別れを経験します。それは、突然訪れることもあれば、心の準備をする時間を与えられることもあります。しかし、いずれの場合であっても、その悲しみの中で、私たちは様々なことを決め、手配しなければなりません。
その一つが、「葬儀の案内状」です。
昔は、訃報を聞きつけ、多くの方がお参りに来てくださるのが当たり前でした。しかし、現代では家族のあり方も変わり、葬儀の形式も多様化しています。また、訃報を知らせる手段も、電話やメール、SNSなど多岐にわたるようになりました。
それでもなお、正式な書面である「案内状」は、故人様への敬意を表し、参列してくださる方々への配慮を示す上で、非常に重要な役割を果たします。特に、お世話になった方々、遠方にお住まいの方々、ご高齢の方々にとっては、案内状が唯一の情報源となることも少なくありません。
このブログでは、葬儀の案内状について、送る相手別の注意点、具体的な例文、そして現代ならではの新しい形まで、元葬儀社プランナーとしての経験をもとに、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
第1章:そもそも葬儀の案内状はなぜ必要なのか?
「電話やメールで十分ではないか?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、親しい間柄であれば電話で訃報を伝えるのが一般的です。しかし、電話一本では伝えきれない情報もありますし、相手がメモを取る手間も発生します。
また、メールやSNSは便利ですが、目上の方やご高齢の方には失礼にあたる場合もあります。そして何より、正式な書面として残る「案内状」には、故人様とご遺族の想いを伝えるという大切な役割があります。
案内状には、主に以下の3つの役割があります。
- 訃報を正確に伝える:誰が亡くなったのか、喪主は誰か、といった基本情報を正確に伝えます。
- 参列を促す(あるいは辞退する):日時や場所、形式などを伝えることで、参列の判断をしてもらうための情報を提供します。
- 故人様への敬意を示す:故人様の生前の功績や人柄を偲び、参列者への感謝の気持ちを伝えます。
特に、会社関係の方や、遠方にお住まいの方、ご高齢の方にとっては、案内状がなければ詳細な情報がわからず、かえってご迷惑をかけてしまうことになりかねません。
第2章:案内状を送るタイミングと相手別の注意点
葬儀の案内状は、大きく分けて2つのタイミングで送ることが多いです。
- 通夜・葬儀の前に送る「訃報案内」:主に親族や親しい友人・知人、会社関係者など、参列してほしい方に向けたものです。
- 葬儀後に送る「会葬御礼」:葬儀に参列してくださった方、香典をくださった方へ、感謝の気持ちを伝えるためのものです。
今回は、特に「訃報案内」に焦点を当ててお話しします。
訃報案内を送る相手は、故人様との関係性や、葬儀の形式によって異なります。
1. 親族への案内状
親族には、まずは電話で訃報を伝えるのが一般的です。その後、改めて書面で案内状を送ることで、詳細な情報を正確に伝えます。
【注意点】
- 故人様の関係性を明確に:「誰の」訃報なのかを冒頭で明確に記します。
- 返信の有無:参列の可否を返信してもらうかどうかを明記します。
- 服装について:特に指定がない場合は「平服でお越しください」と記載することも増えています。
2. 友人・知人への案内状
故人様の交友関係が広かった場合、全ての方に電話で連絡するのは難しいものです。案内状を送ることで、一度に多くの人に正確な情報を伝えることができます。
【注意点】
- 故人様の人柄を偲ぶ一文:故人様との思い出を少し添えると、受け取った方の心に響きます。
- 供花・供物・香典の辞退について:辞退する場合は、その旨を明確に記載します。
- 家族葬の場合:家族葬の場合は、参列を辞退してもらう旨を丁寧な言葉で伝えます。
3. 会社関係への案内状
会社関係者への案内は、特にマナーが重要です。故人様の上司や同僚、取引先など、立場によって文章を使い分ける必要があります。
【注意点】
- 肩書を正確に:故人様の部署や役職、会社名などを正確に記載します。
- 弔電や香典の辞退について:会社によっては、香典や弔電を辞退するケースも多いです。その場合は、明確に記載します。
第3章:失敗しない案内状の書き方と具体的な例文
案内状を書く上で、守るべき基本的なルールがあります。
1. 案内状の基本的な構成
案内状は、以下の要素で構成されます。
- 頭語:「謹啓」「拝啓」など。
- 時候の挨拶:季節に応じた挨拶。
- 訃報:誰が、いつ、何歳で亡くなったかを伝えます。
- 葬儀の詳細:通夜、葬儀の日時、場所、宗教・宗派などを記載します。
- 喪主:喪主の氏名、故人様との続柄を記載します。
- 結びの言葉:「敬具」「敬白」など。
- 日付
2. 例文:一般葬の場合
謹啓
この度 かねてより病気療養中の父 〇〇儀 去る〇月〇日午前〇時〇分 享年〇〇歳をもって永眠いたしました
生前はひとかたならぬご厚情を賜り 故人に代わりまして厚く御礼申し上げます
つきましては 通夜並びに葬儀・告別式を下記の通り執り行いたく 謹んでご案内申し上げます
敬具
記
一、通夜式
日時:〇月〇日(〇) 午後〇時~
場所:〇〇斎場
一、葬儀・告別式
日時:〇月〇日(〇) 午前〇時~
場所:〇〇斎場
喪主 〇〇 〇〇
故人長男
3. 例文:家族葬の場合
家族葬の場合は、参列を辞退する旨を丁寧に伝える必要があります。
謹啓
この度 かねてより病気療養中の父 〇〇儀 去る〇月〇日午前〇時〇分 享年〇〇歳をもって永眠いたしました
生前はひとかたならぬご厚情を賜り 故人に代わりまして厚く御礼申し上げます
葬儀は故人の遺志により 近親者のみにて執り行いました
つきましては 誠に勝手ながら ご香典ご供花ご供物の儀は固くご辞退申し上げます
何卒ご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
喪主 〇〇 〇〇
故人長男
第4章:現代ならではの案内状の形と準備の重要性
最近では、メールやSNSで訃報を伝えることも増えました。しかし、特にご高齢の方や、目上の方に対しては、やはり正式な書面での案内が丁寧な印象を与えます。
また、葬儀の形式も多様化しています。
- 家族葬:ごく近しい身内だけで行う葬儀。
- 一日葬:通夜を行わず、一日で葬儀・告別式を行う形式。
- 直葬(火葬式):通夜・告別式を行わず、火葬のみを行う形式。
どの形式を選択するかによって、案内状の内容も大きく変わってきます。
大切なのは、「どのようなお別れをしたいか」をあらかじめ考えておくことです。
突然の訃報に際して、遺族は深い悲しみと同時に、時間がない中で様々なことを決めなければなりません。葬儀社選びもその一つです。
第5章:いざという時に後悔しないために知っておきたいこと
多くの人が経験しないことだからこそ、葬儀には不安がつきものです。
「どこの葬儀社に頼めばいいかわからない」 「費用はどれくらいかかるのだろうか」 「急なことで、ゆっくり考える時間がない」
私自身、父を亡くした際、右も左もわからず、本当に苦しい思いをしました。
そんな時、もし複数の葬儀社の見積もりを比較できるサービスがあったなら、もっと安心して葬儀を執り行えたのではないか、と今でも思います。
東証プライム上場企業のエスエムエスが運営する「安心葬儀」は、全国7000以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせた最適な優良葬儀社を無料で紹介してくれるサービスです。複数の葬儀社の相見積もりを比較することで、納得のいく葬儀社を、時間がない中でも見つけることができます。
料金体系が不明瞭な葬儀社も少なくない中、このようなサービスを利用すれば、不当に高額な費用を請求される心配もありませんし、故人様やご家族の意向に沿った質の高い葬儀社を見つけることができるでしょう。
詳細はこちらからご確認いただけます。
第6章:葬儀の準備は案内状だけではない
葬儀の準備は、案内状だけではありません。
参列してくださった方々へのお礼である「香典返し」も、大切なマナーの一つです。
香典返しは、忌明け後に行うのが一般的ですが、最近では当日返しも増えています。香典の金額によって品物を変えるのが本来のマナーですが、当日返しでは一律の品物をお渡しすることが多いです。
どのような品物を選ぶか、どのように送るか、悩む方も多いでしょう。
シャディ株式会社が運営する「シャディギフトモール」は、1926年創業のギフト専門店です。1万点以上の商品を揃えており、お香典返しにぴったりのカタログギフトや、お菓子、タオルなど、様々な商品を見つけることができます。
また、包装やのし紙、メッセージカードも無料で用意してくれるので、安心して利用できます。
「お香典返し、何を贈ればいいの?」とお悩みの方は、一度サイトを覗いてみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちらをご覧ください。
第7章:葬儀後の手続きと遺品整理
葬儀が終わった後も、様々な手続きが残されています。
- 役所への届け出
- 社会保険や年金の変更手続き
- 金融機関の名義変更
- 遺産相続の手続き
そして、忘れてはならないのが、「遺品整理」です。
故人様が残された品々は、一つひとつに思い出が詰まっています。しかし、そのすべてを保管しておくのは難しいのが現実です。
「何から手をつければいいのかわからない」 「一人ではとてもやりきれない」 「遠方に住んでいて、なかなか実家に行けない」
そんなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
株式会社アシストが運営する「ライフリセット」は、遺品整理を専門に行うサービスです。故人様のお部屋に残された遺品や不要物を、ご遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に整理してくれます。
私も、父の遺品整理の際、何から手をつけていいかわからず途方に暮れました。プロにお願いすることで、精神的な負担を軽減し、故人様との思い出と向き合う時間を大切にできることもあります。
遺品整理でお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてください。
詳細はこちらからご確認いただけます。
第8章:葬儀における服装のマナー
葬儀に参列する際、服装に迷う方も多いでしょう。
特に、急な訃報の場合、準備する時間がないこともあります。
葬儀の服装は、故人様やご遺族への敬意を示す上で非常に重要です。
- 男性:ブラックスーツ、白いワイシャツ、黒いネクタイ、黒い靴下が基本です。
- 女性:ブラックフォーマルスーツ、黒いワンピース、黒いストッキング、黒い靴が基本です。
もし、手持ちの喪服のサイズが合わなくなってしまったり、新しいものを買う余裕がなかったりする場合もあるかもしれません。
株式会社トレジャー・ファクトリーが運営する**「Cariru BLACK FORMAL」**は、デザイン・質・マナーにこだわった喪服・礼服のレンタルサービスです。ネットで簡単に申し込むことができ、16時までの注文で最短翌日午前中にお届けしてくれるので、急な訃報でも安心です。
ジャケット、ワンピース、バッグ、サブバッグ、ネックレス、イヤリング、数珠、袱紗のフルセットも豊富に揃っており、必要なものが全て揃います。購入するよりもリーズナブルに、上質なフォーマルウェアを着用できます。
「大人として恥をかきたくない」 「マナーを守って故人様を見送りたい」
そうお考えの方は、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちらをご覧ください。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
第9章:葬儀後の挨拶状と手続き
葬儀後には、会葬御礼の挨拶状を送ることもあります。
これは、葬儀に参列してくださった方、お香典をくださった方へ、感謝の気持ちを伝えるためのものです。
1. 会葬御礼の挨拶状の書き方
会葬御礼の挨拶状は、できるだけ早く送るのがマナーです。
基本的な構成は、以下の通りです。
- 頭語:「謹啓」「拝啓」など。
- 会葬へのお礼:参列してくれたことへの感謝を伝えます。
- 生前のお礼:故人様が生前お世話になったことへの感謝を伝えます。
- 結びの言葉:「敬具」「敬白」など。
- 日付
- 差出人:喪主の氏名、故人様との続柄を記載します。
2. 例文:会葬御礼の挨拶状
謹啓
この度は 亡父 〇〇儀 葬儀に際しまして ご多忙中にもかかわらずご会葬賜り ご丁重なるご香典ご供花を賜りまして 誠にありがとうございました
故人もさぞかし喜んでいることと存じます
生前は一方ならぬご厚情を賜り 故人に代わりまして厚く御礼申し上げます
今後とも何卒よろしくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
まずは書中をもちましてご挨拶申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
喪主 〇〇 〇〇
故人長男
第10章:葬儀を終えて
お葬式は、故人様とのお別れの儀式であると同時に、残されたご家族が故人様との思い出を振り返り、悲しみを乗り越えるための大切な時間でもあります。
私自身、父を亡くした経験から、葬儀の手配や手続きがいかに大変かを身をもって知っています。
その中で、一つひとつの準備に心を込めることが、故人様への最大の供養になると信じています。
このブログが、葬儀の案内状について悩んでいる方、そしてこれからお葬式を経験されるかもしれない方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
終活は、自分自身や家族のために、今からできる準備です。
私もこのブログを通して、皆さんの「後悔しないお別れ」のお手伝いができればと思っています。
「葬儀の服装」や「香典返し」、「葬式の流れ」についてもっと詳しく知りたい方は、別の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
大切なご家族のため、そしてご自身のために、今できることを一緒に考えていきましょう。
何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。