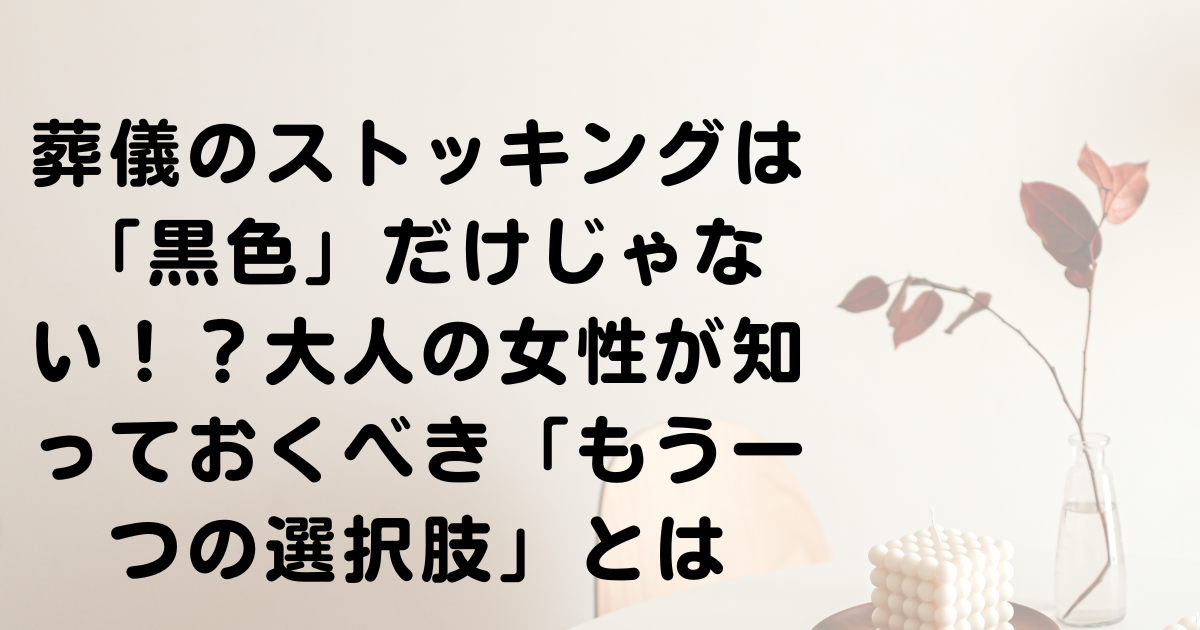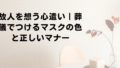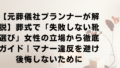筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
はじめに:突然の訃報に戸惑う心と、「当たり前」の疑問
突然の訃報は、誰にとっても心穏やかではいられません。悲しみや驚き、そして「これからどうすればいいのだろう?」という不安で頭がいっぱいになることでしょう。通夜や葬儀に参列する際、ご遺族の方にご迷惑をおかけしないよう、失礼のない身だしなみを心がけるのは大切なことです。しかし、普段あまり意識することのない「葬儀の服装マナー」となると、戸惑ってしまう方も少なくありません。特に、女性の服装には細かいマナーが多く、その一つひとつに気を配る必要があります。
「葬儀には黒い服を着ていく」というのは、多くの方がご存知でしょう。しかし、それだけでは十分ではありません。ストッキングの色はどうすればいいのか、靴は?バッグは?と、次から次へと疑問が湧いてきます。この記事では、特に多くの方が悩む「葬儀のストッキング」について、元葬儀社プランナーとしての経験を交えながら、色のマナーから選び方のポイントまで、詳しく解説していきます。
特に、インターネットで「葬儀 ストッキング」と検索された方がこの記事にたどり着いたということは、「ストッキングの色」に関して、何か特別な理由や疑問をお持ちなのではないでしょうか。実は、この「色」というキーワードには、葬儀の場における深い意味と、大人の女性が知っておくべき大切なマナーが隠されています。
この記事を読み終える頃には、突然の訃報にも慌てず、故人様への最後の敬意を払うことができるよう、自信を持って身だしなみを整えられるようになるはずです。
葬儀のストッキング、本当に「黒色」しかダメ?
まず、一番気になるのが「ストッキングの色」ですよね。結論から言うと、葬儀の場では**「黒色」**のストッキングを着用するのが一般的で、最も無難な選択です。これは、喪服が黒色であることと同様に、故人様を悼む気持ちを表す「喪の色」として定着しているからです。黒色は、悲しみを表すとともに、控えめで慎ましい印象を与えます。
しかし、ここで一つ考えていただきたいことがあります。なぜ私たちは、葬儀の場で「黒色」を着用するのでしょうか。それは、故人様やご遺族に敬意を払い、悲しみに寄り添う姿勢を示すためです。つまり、大切なのは「故人様を悼む心」であり、その心を表現するための手段として「黒色」のストッキングが選ばれるのです。
では、ストッキングの「色」が持つ意味について、もう少し深く掘り下げてみましょう。
「黒」 最も一般的で、正式な喪服に合わせる色です。透け感のない30デニール以下の薄手のものを選ぶのがマナーとされています。これは、肌が透けることで不謹慎な印象を与えるためです。しかし、近年では寒冷地や冬の時期など、防寒のために少し厚手のものを選ぶ方も増えています。このあたりは、時代の変化とともにマナーも柔軟になってきていると言えるでしょう。
「肌色(ベージュ)」 「黒色のストッキングは寒そうで…」「急なことで黒いストッキングが手元にない」といった理由から、肌色のストッキングを着用しても良いのか、と迷う方もいらっしゃいます。 実は、地域や宗派によっては、「肌色(ベージュ)」のストッキングを着用しても良いとされている場合があります。これは、「素足は避けるべき」というマナーが根底にあるからです。昔ながらの考え方では「生」を連想させる肌色を避けるべきだという意見もありますが、特に夏場などでは、肌色のストッキングを選ぶ方もいらっしゃいます。 ただし、正式な弔事の場では、やはり黒色が最も無難です。肌色のストッキングを着用する場合は、ご親族や親しい間柄の方に相談するなど、状況に応じて判断することが大切です。
「それ以外の色」 白や柄物、ラメ入りのストッキングは、お祝い事を連想させるため、葬儀の場では絶対に避けるべきです。また、網タイツや膝上までのストッキングも、カジュアルすぎるため不適切です。
このように、葬儀のストッキングには、ただ「黒色」を着用するだけでなく、「なぜその色を選ぶのか」という理由が大切になってきます。故人様への敬意と、ご遺族への配慮を第一に考えることが、最も重要なマナーと言えるでしょう。
葬儀の服装マナー、年齢を重ねた女性が知っておくべきこと
葬儀の服装マナーは、年齢を重ねるごとに、より深く意識すべきものになります。特に、40代、50代、60代以上となると、ご自身がご遺族の立場になることも増え、若い頃とは異なる配慮が求められます。
1. 突然の訃報に備えて、喪服と小物を一式準備しておく 「いつか使うかも…」と先延ばしにしている方も多いのではないでしょうか。しかし、いざという時には、悲しみの中で準備をする余裕はありません。喪服は、身体に合ったサイズを、できれば一式揃えておくことをお勧めします。 「昔買った喪服が体型に合わなくなってしまった」「トレンドに合わせたデザインの喪服が欲しい」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。そんな時は、レンタルサービスを活用するのも一つの手です。たとえば、「Cariru BLACK FORMAL」のようなサービスでは、質の良い喪服を必要な時だけ借りることができます。人気ブランドの喪服や、バッグ、ネックレス、数珠といった小物までフルセットでレンタルできるので、急な訃報でも安心です。クリーニングも不要なので、返却も簡単です。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
2. 派手なアクセサリーは避ける 結婚指輪以外のアクセサリーは、原則としてつけません。パールの一連ネックレスや、一粒パールのイヤリング・ピアスは、涙を連想させることから唯一認められています。ただし、二連のネックレスは「不幸が重なる」と連想させるため、避けるのがマナーです。
3. バッグや靴も黒色で統一する バッグは布製や革製で、光沢のないものを選びましょう。殺生を連想させる毛皮や爬虫類柄はNGです。靴も同様に、光沢のないシンプルなパンプスが基本です。ヒールは高すぎず、歩きやすいものを選びましょう。
このように、葬儀の服装には細かなマナーがあります。しかし、大切なのは、故人様への想いとご遺族への配慮です。服装が完璧でなくても、その心が伝われば、それが一番の供養になるはずです。
葬儀の準備は「色」から見えてくる
ストッキングの「色」から始まった今回の記事ですが、ここまでお読みいただいた方の中には、「葬儀の準備って、もっとたくさんあるんじゃない?」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。その通りです。葬儀には、服装以外にも、やるべきこと、考えるべきことがたくさんあります。
突然の訃報に接した時、何から手をつければ良いのか、誰に相談すれば良いのか分からなくなるのは当然のことです。特に、ご遺族の方は、悲しみの中、限られた時間で葬儀社の手配や手続き、参列者への対応など、多くのことをこなさなければなりません。
「いざという時に、後悔のないお別れをしてあげたい」「でも、費用や葬儀社の選び方が分からない」といったお悩みをお持ちの方には、【安心葬儀】のような相見積もりサービスを利用することをお勧めします。東証プライム上場企業が運営しており、全国7,000以上の葬儀社の中から、ご希望の条件に合った優良な葬儀社を紹介してもらえます。複数の葬儀社から見積もりを取ることで、費用やサービス内容を比較検討できるため、時間がない中でも安心して葬儀社を選ぶことができます。
また、葬儀を終えた後にも、故人様のお部屋の整理という大きな作業が待っています。遺品整理は、思い出の品と向き合う大切な時間であると同時に、精神的にも肉体的にも大きな負担になります。そんな時は、【ライフリセット】のような専門業者に相談することも一つの選択肢です。ご遺族の気持ちに寄り添いながら、丁寧に遺品整理を行ってくれます。
「後悔のないお別れ」のために、そして、残されたご家族の負担を少しでも減らすために、今できることを少しずつ考えておくことが大切です。
香典返しと贈り物のマナー:感謝の気持ちを伝える「色」
葬儀が終わった後、参列してくださった方々への感謝の気持ちを伝えるために、香典返しを贈るのが一般的です。この香典返しにも、色に関するマナーがあります。
香典返しに選ぶ品物は、「消え物」と呼ばれる、使ってなくなるものや、食べ物などが良いとされています。これは、「不幸を後に残さない」という意味が込められているからです。また、品物を包むのし紙には、「黒白の水引」または「黄白の水引」を使用します。これは、弔事専用の水引の色です。
ここで、一つ大切なことをお伝えします。
実は、この「色」のマナーは、香典返しだけでなく、あらゆる贈り物に共通するものです。たとえば、お祝い事には「紅白」や「金銀」の水引を、弔事には「黒白」や「黄白」の水引を使い分けます。これは、贈り物に込められた「気持ちの色」を表現するための日本の伝統的な文化なのです。
「お香典返し、何を贈ればいいのかしら?」「のし紙のマナーがよく分からない」といったお悩みをお持ちの方には、シャディギフトモールのようなギフト専門店が便利です。お香典返しにふさわしい品物が豊富に揃っており、のし紙やメッセージカードも無料で付けてくれるサービスもあります。プロが選んだ品物の中から、故人様やご遺族の気持ちに寄り添った贈り物を選ぶことができるでしょう。
まとめ:色に込められた「想い」と「マナー」
今回の記事では、葬儀のストッキングの「色」から始まり、葬儀の服装マナー、そして葬儀にまつわる様々な「色」の意味についてお話してきました。
- 葬儀のストッキングは「黒色」が基本。 しかし、地域や状況によっては「肌色」も許容される場合がある。大切なのは、故人様への敬意とご遺族への配慮。
- 喪服や小物も「黒色」で統一する。 突然の訃報に備えて、喪服のレンタルサービスなどを活用するのも良い選択肢。
- 香典返しは「消え物」を選び、水引の色にも配慮する。
「葬儀の服装」や「葬儀の準備」について、もっと詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。
故人様を偲び、心を込めてお見送りするために、正しいマナーを身につけておくことは、私たちに残された者として大切なことです。この記事が、皆さまの心の準備の一助となれば幸いです。
そして、最後に、私からもう一つ、お伝えしたいことがあります。それは、**「終活」**についてです。
「終活」と聞くと、「まだ早い」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご自身の死後のことをあらかじめ決めておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。
エンディングノートに、ご自身の葬儀やお墓、財産のことなどを書き留めておく。そして、ご家族と話し合う時間を持つ。これは、ご自身が安心して人生の終末を迎えられるだけでなく、ご家族にとっても「故人の意思を尊重したお見送りができた」という大きな安心につながります。
もし、終活について考え始めた方がいらっしゃいましたら、ぜひご家族と一緒に、ゆっくりと時間をかけて話し合ってみてください。
【家族を想うお葬式ガイド】では、今後も終活やお墓、エンディングノートなど、皆さまのお役に立つ情報を発信していきます。
「後悔のないお別れ」のために、そして、ご自身とご家族の未来のために、今できることから始めてみませんか?
補足:読者の皆さまへ
今回、この記事を書くにあたり、私自身の経験や思いを込めて執筆しました。
特に、故人様を亡くされたご遺族の方々が、悲しみの中、不安や戸惑いを感じることなく、心穏やかにお別れができるよう、少しでもお力になれたらと願っています。
また、普段から「終活」を意識している方も、そうでない方も、この記事がご自身の、そしてご家族の未来について考えるきっかけになれば幸いです。
私は、葬儀社でプランナーとして働いていた12年間、数えきれないほどの「お別れ」に立ち会ってきました。
その中で感じたのは、故人様への想い、そしてご遺族の心に寄り添うことの大切さです。
葬儀の形式やマナーも重要ですが、一番大切なのは、故人様への感謝の気持ちと、その想いを伝えることです。
「後悔のないお別れ」とは、決して高価な葬儀をすることではありません。
それは、故人様との最後の時間を大切に過ごし、心からの感謝を伝えること。そして、ご遺族が故人様との思い出を大切にしながら、前向きに生きていけること。
私は、このブログを通じて、そのお手伝いができればと思っています。
これからも、皆さまの心の支えとなれるような情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 葬儀のストッキングは、何デニールまで大丈夫ですか?
A1. 一般的には、30デニール以下がマナーとされています。これは、肌が透けることで不謹慎な印象を与えないようにするためです。しかし、冬場や寒冷地では、少し厚手のものを選ぶ方も増えています。大切なのは、厚手であっても、光沢のない、マットな質感のものを選ぶことです。
Q2. ストッキングを履き忘れてしまった場合はどうすればいいですか?
A2. 最も良いのは、コンビニエンスストアなどで黒いストッキングを購入して着用することです。もしどうしても見つからない場合は、素足で参列するのは失礼にあたるため、黒いタイツや靴下で代用することも一つの選択肢です。ただし、できる限り、肌が隠れるように配慮することが大切です。
Q3. 子どもの葬儀の服装は、どのような点に注意すれば良いですか?
A3. 子どもの場合、制服があれば制服を着用するのが最も無難です。制服がない場合は、黒、紺、グレーなどの地味な色の服装を選びましょう。白いブラウスやシャツに、黒や紺のスカートやズボンを合わせるのが良いでしょう。靴下も黒色や白色のシンプルなものを選びます。
Q4. 葬儀のマナーは、宗派や地域によって違いはありますか?
A4. はい、宗派や地域によって、細かいマナーや風習が異なる場合があります。例えば、仏式の葬儀では数珠を持参するのが一般的ですが、神式やキリスト教式の葬儀では数珠は使用しません。また、通夜ぶるまいの形式なども地域によって違いがあります。不安な場合は、ご親族や、葬儀を執り行う葬儀社に相談するのが一番確実です。
終わりに
今回の記事では、葬儀のストッキングの「色」という、一見些細な疑問から、葬儀のマナーや、故人様への想い、そして残されたご家族の未来について、深く掘り下げてきました。
「色」というキーワードは、私たちの感情や文化、そして大切な人への想いを象徴する、非常に奥深いものです。
葬儀のストッキングの色に悩んだ時、それはきっと、故人様を大切に思う心、そして、ご遺族に失礼のないようにという、優しい気持ちの表れなのでしょう。
その優しい気持ちを、正しい知識とマナーで、より美しく表現できるよう、これからもこのブログを通じて、皆さまのお力になれれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
筆者:Keisuke(元葬儀社プランナー)