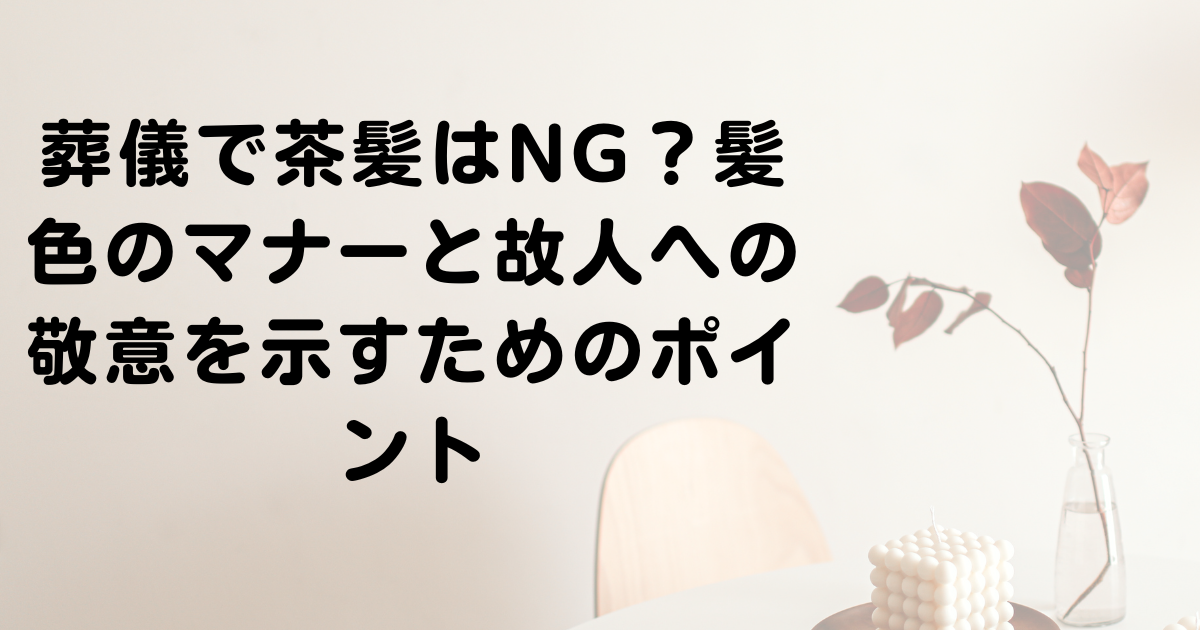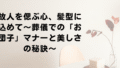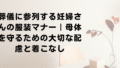こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
葬儀の準備や参列で、服装や持ち物のマナーについて不安になる方は多いのではないでしょうか。特に、最近は髪の色を明るくされている方も増えており、「葬儀に茶髪で参列しても大丈夫?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、葬儀に茶髪で参列することは、絶対にNGというわけではありません。しかし、故人やご遺族への配慮が求められる場であるため、いくつかの注意点があります。
この記事では、元葬儀社プランナーとして800件以上のお葬式に携わってきた経験をもとに、葬儀における髪色のマナーについて、具体的なポイントや対処法を解説します。大切な方とのお別れの時間を、後悔なく、そして心穏やかに過ごすための参考にしていただければ幸いです。
葬儀における「茶髪」の考え方
まず、葬儀に茶髪で参列することについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
結論:厳密なルールはないが、配慮は必要
日本のお葬式には、服装や髪型に関して法律や条例で定められた厳格なルールはありません。そのため、「茶髪は絶対にダメ」と決めつけることはできません。しかし、葬儀は故人を悼み、ご遺族に哀悼の意を示すための大切な儀式です。華美な服装や髪型は、その場の雰囲気にそぐわないと判断される可能性があります。
髪の色が明るすぎると、周りの参列者やご遺族に不快感を与えてしまうことも考えられます。特に年配の方の中には、明るい髪色を「マナー違反」と捉える方も少なくありません。
ご遺族は、大切な方を亡くされたばかりで、精神的にも肉体的にも疲弊されています。そのような状況で、参列者の髪色が気になってしまうような事態は避けたいものです。故人やご遺族への最大限の配慮をすることが、葬儀に参列する上で最も大切なことと言えるでしょう。
どこまでが許容範囲?
では、具体的にどの程度の明るさなら許容されるのでしょうか。一般的には、自然な黒髪や、それに近い落ち着いた色合いが望ましいとされています。美容室でよく使われる「トーン」という単位で言えば、6〜7トーンくらいまでの、一見して茶色だとわからない程度の明るさが無難です。
逆に、8トーン以上の、明らかに茶色や金髪とわかるような明るい髪色は、避けるべきだと考えた方が良いでしょう。もちろん、故人やご遺族の意向によって変わることもありますが、多くのケースで「派手すぎる」と判断される可能性があります。
特に、職場関係や地域のお葬式など、普段からあまり親交のない方が多く集まる場では、より慎重な判断が求められます。
髪色が明るい場合の具体的な対処法
「急な訃報で、髪を染める時間がない…」「どうしても髪を染めたくない」という方もいらっしゃるでしょう。そんな方のために、髪色が明るい場合の具体的な対処法をいくつかご紹介します。
1. 市販のヘアカラースプレーを利用する
最も手軽で、かつ効果的なのが、市販の一日用ヘアカラースプレーを使う方法です。黒色のカラースプレーを髪全体に吹き付けるだけで、簡単に髪の色を黒く見せることができます。
メリット:
- 手軽にできる
- 費用が安い
- 髪を傷めない
- 洗髪すれば元に戻る
デメリット:
- 衣服や顔に付着しないよう注意が必要
- 汗や雨で色落ちする可能性がある
- 髪質によってはムラになりやすい
使用する際は、必ず使用説明書をよく読み、換気の良い場所で行いましょう。特に、前髪や耳の後ろなど、細かい部分まで丁寧にスプレーするのがポイントです。
2. ウィッグを着用する
髪の長さやスタイルによっては、**ウィッグ(部分かつら)**を利用するのも一つの手です。特に、ショートヘアやボブスタイルの方は、違和感なく自然な仕上がりになります。
メリット:
- 髪を傷めずに済む
- 完璧に髪色を隠せる
- スプレーのように色落ちの心配がない
デメリット:
- 自分の髪とウィッグの色や質感に差があると不自然に見える
- サイズが合わないとズレてしまうことがある
- 長い髪の場合、地毛をどうまとめるか工夫が必要
最近は、医療用ウィッグなど、非常に自然で高品質なウィッグも増えています。手持ちのウィッグがあれば、一度試してみるのも良いでしょう。
3. 美容院で一時的にトーンダウンする
時間的余裕がある場合は、美容院で一時的に髪色をトーンダウンしてもらうことも可能です。美容師さんに「お葬式があるので、一時的に落ち着いた色にしたい」と伝えれば、適切なカラーリング剤を選んでくれます。
メリット:
- 自然で綺麗な仕上がりになる
- プロに任せられるので安心
- ムラになりにくい
デメリット:
- 費用がかかる
- 美容院の予約が必要
- 一時的なトーンダウンでも、元の髪色に戻す際に手間がかかる場合がある
ただし、急な訃報では美容院に行く時間がないことが多いかもしれません。そうした場合は、前述のカラースプレーやウィッグを活用しましょう。
髪色以外にも気をつけたい身だしなみのマナー
髪色だけでなく、葬儀に参列する際は、他にも気をつけたい身だしなみのマナーがいくつかあります。
髪型について
- 清潔感:髪はきちんと整え、清潔感を第一に考えましょう。
- まとめる:肩にかかる長さの髪は、お辞儀をした際に邪魔にならないよう、低い位置で一つにまとめるのが基本です。髪ゴムやバレッタは、黒や茶色など、目立たないシンプルなものを選びましょう。
- 装飾品:髪飾りはつけないのがマナーです。どうしても必要な場合は、黒や紺のシンプルなリボンやバレッタなどに留めましょう。
服装について
一般的に、**喪服(ブラックフォーマル)**を着用するのがマナーです。
- 男性:ブラックスーツ、白無地のシャツ、黒無地のネクタイ、黒の靴下、黒の革靴。
- 女性:黒のワンピース、またはアンサンブル、黒のストッキング、黒のパンプス。
急な訃報で喪服がない場合は、地味な色(黒、紺、グレーなど)のスーツや、控えめなデザインの服装で代用することもありますが、可能であれば喪服を用意するのが望ましいです。
喪服を用意しておらず、急に必要になった際は、喪服のレンタルサービスを活用するのも良い方法です。デザイン・質・マナーにこだわった喪服・礼服のレンタル【Cariru BLACK FORMAL】は、ネットで簡単に申し込みができ、最短翌日には届けてくれます。急な訃報で時間がない時でも、マナーに沿った服装を整えることができるので安心です。ジャケット・ワンピースから、バッグや数珠までフルセットで借りられるプランもあるので、必要なものがすべて揃います。
メイクやアクセサリーについて
- メイク:薄化粧が基本です。「片化粧」と言って、口紅をつけずにファンデーションと眉毛だけ整える程度にするのが一般的です。
- アクセサリー:結婚指輪以外は外すのがマナーです。どうしても身につけたい場合は、一連の真珠のネックレスやイヤリングなど、控えめなものにしましょう。二連のものは「不幸が重なる」という意味合いがあるため、避けるべきです。
- 香水:香水はつけないのがマナーです。お線香の香りの邪魔になったり、気分を悪くされる方がいらっしゃるかもしれません。
これらのマナーは、すべて「故人やご遺族への敬意」を表すためのものです。一つ一つを丁寧に確認し、故人との最後のお別れの時間を大切に過ごしましょう。
葬儀の準備で困ったときは
訃報は突然やってくるものです。大切な方を亡くされた悲しみの中で、葬儀の準備を進めるのは心身ともに大きな負担となります。
「何から手をつけていいか分からない」「どこの葬儀社に頼めば良いのか…」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そんな時は、まず専門のサービスに相談してみることをお勧めします。
例えば、全国7000以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を紹介してくれる✅ 安心葬儀(株式会社エス・エム・エス)はこちらのような相見積もりサービスを利用すると、時間がない中でも、複数の葬儀社を比較検討することができます。東証プライム上場企業のエスエムエスが運営しているので、安心して相談できるのも大きなメリットです。
葬儀後の準備も忘れずに
無事に葬儀を終えた後も、ご遺族にはやるべきことがたくさんあります。
- 遺品整理
- 香典返し
- 各種手続き
これらも、一人で抱え込まず、必要に応じて専門のサービスを活用することを検討しましょう。
- 遺品整理:故人のお部屋に残された遺品や不要物を整理する✅ 遺品整理のことなら【ライフリセット】のような専門業者に依頼することで、物理的な負担だけでなく、精神的な負担も軽減できます。
- 香典返し:葬儀後にいただく香典へのお返しは、失礼のないよう慎重に選ぶ必要があります。シャディのカタログギフト!お祝い、内祝い、各種ギフトにでは、香典返しにふさわしい商品を多数取り扱っており、包装やのし紙、メッセージカードも無料で用意してくれるので安心です。
こうしたサービスをうまく利用することで、心身ともに余裕を持って、故人との思い出を振り返る時間を大切にすることができます。
まとめ
葬儀に茶髪で参列することについて、改めてまとめます。
- 厳密なルールはないが、故人やご遺族への配慮が最も大切
- 派手すぎる明るい髪色は避けるのが無難
- どうしても髪色を変えられない場合は、一時的な対処法を活用する
- 髪色以外にも、服装やメイクなど、身だしなみのマナーに気を配る
葬儀は、故人様とのお別れの時間を、皆で静かに、そして心穏やかに過ごすための儀式です。髪色一つ、服装一つにも、故人への敬意とご遺族への思いやりが込められています。
この記事が、大切な方とのお別れの時間を、後悔なく、心穏やかに迎えるための助けになれば幸いです。
また、葬儀に関するより詳しい情報やマナーについては、以下の記事も参考にしてください。
何かご不安なことがあれば、いつでも私Keisukeにご相談ください。皆様が心穏やかに、大切な方とのお別れを迎えられるよう、これからも情報発信を続けていきます。