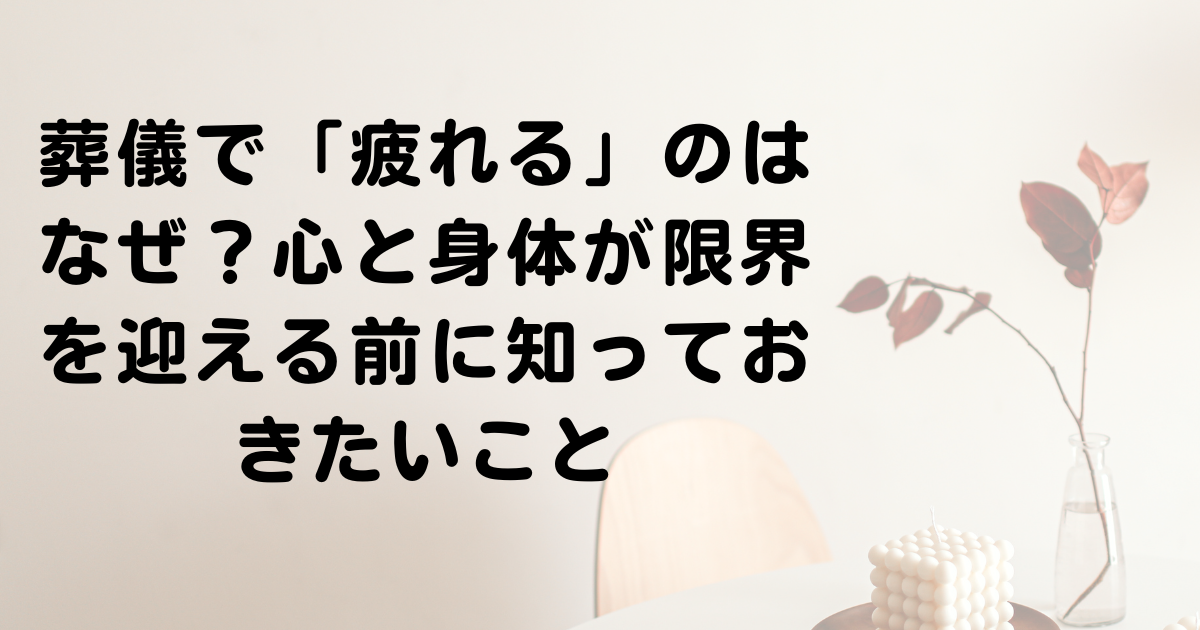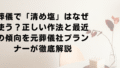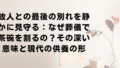こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前は12年間、葬儀社のプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。20代後半に父を突然亡くし、右も左もわからず苦労した経験から、少しでも同じ思いをする方を減らしたいと、この仕事に飛び込みました。
今日お話しするのは、「葬儀が心身ともに疲れるものだ」という、多くの方が共感するであろうテーマについてです。
大切な人を亡くした悲しみの中で、葬儀はまるで怒涛のように過ぎていきます。次から次へと決断を迫られ、慣れない作法や人間関係に気を遣い、気づけば心も体もへとへとになってしまう。
そんな経験、あなたも身に覚えがあるのではないでしょうか。
この記事では、なぜ葬儀はこれほどまでに疲れるのか、そしてその疲れを少しでも軽減するために、事前に知っておくべきこと、備えておけることについて、私の経験を交えながらお伝えしていきます。
第1章:なぜ葬儀は心身ともに疲れるのか?その根本的な理由
「葬儀は疲れる」という感覚は、単なる体力的な疲れだけではありません。そこには、複合的な要因が絡み合っているのです。
1-1. 予測不能な「死」という出来事がもたらす精神的な負荷
ご家族の「死」は、多くの場合、心の準備ができていないまま突然訪れます。たとえご病気で闘病されていたとしても、「その日」が来ると、人は大きな衝撃を受けます。
この精神的なショックは、心身に多大なストレスを与えます。悲しみ、後悔、不安、そしてこれからどうなるのだろうという漠然とした恐怖。これらが一気に押し寄せ、精神的なエネルギーを急速に消耗させてしまうのです。
この心理状態で、葬儀という一大イベントを執り行うのは、想像以上の負担となります。普段なら冷静に判断できることも、感情が揺れ動いている状態では難しくなるのは当然のことです。
1-2. 時間的制約と慣れない手続きによるプレッシャー
ご逝去から葬儀まで、ほとんどの場合、わずか数日という短い期間で執り行われます。特に都市部では火葬場の空き状況から、ご逝去当日に通夜、翌日に葬儀・告別式という流れになることも少なくありません。
この限られた時間の中で、ご遺族は矢継ぎ早に決断を迫られます。
- 葬儀社の決定:どこの葬儀社にするか、費用はどれくらいか。
- プランの選択:祭壇の種類、棺、骨壺、返礼品、料理など。
- 参列者への連絡:親戚や知人に訃報を伝える。
- 役所への手続き:死亡届の提出。
- 宗教者との打ち合わせ:お寺や神社、教会との連絡。
これらはすべて、初めての経験である方がほとんどです。
「この選択で本当に良かったのか」「もっと良い方法があったのではないか」という不安を抱えながら、次々とタスクをこなしていかなければなりません。このプレッシャーが、精神的な疲れを加速させる大きな要因となります。
特に、ご逝去後すぐに葬儀社を決めなければならない状況は、大きなストレスとなります。
「信頼できる葬儀社を、十分な比較検討もできないまま選ばなければならない」
これが、多くの方が直面する現実です。
もし、事前に複数の葬儀社から見積もりを取り、じっくりと検討できる時間があれば、精神的な負担はかなり軽減されるはずです。
しかし、現実はそうはいきません。
そんな時こそ、第三者の力を借りることをお勧めします。例えば、東証プライム上場企業のエスエムエスが運営する【安心葬儀】のようなサービスを活用すれば、全国7000以上の提携葬儀社の中から、ご希望の条件に合った優良葬儀社を比較検討できます。時間がない中でも、適正価格で質の高い葬儀社を見つけられるのは大きな安心材料となるでしょう。
第2章:身体的な疲れを引き起こす具体的な要因
精神的な疲れだけでなく、身体的な疲れも深刻です。
2-1. 睡眠不足と不規則な食生活
ご逝去から葬儀が終わるまでの間、ご遺族はほとんど眠れません。病院や施設からご遺体を自宅や斎場へ搬送する手配、その後も故人様のおそばにいるため、夜を通して起きていなければならないことも多いです。
また、食事も不規則になりがちです。出されたお弁当を食べる機会はあっても、なかなか喉を通らないという方も少なくありません。栄養が偏り、体力が低下していくのは当然のことです。
2-2. 長時間座り続けることと立ち仕事
葬儀中は、僧侶のお話を聞いたり、焼香に並んだり、参列者の方々への挨拶をしたりと、長時間座りっぱなしだったり、立ちっぱなしだったりすることが多くなります。
特にご高齢のご遺族にとっては、この身体的な負担は想像以上に大きいものです。腰痛や足のむくみなど、身体の不調を訴える方も少なくありません。
2-3. 慣れない服装と靴
通夜や葬儀・告別式では、喪服を着用します。普段着慣れない服は、それだけでも身体に窮屈さを感じさせるものです。特に、長時間正座をしたり、椅子に座ったり、立ったりを繰り返すことで、身体は大きな負担を感じます。
また、靴も普段履き慣れていない革靴やパンプスを履くことが多いため、足が痛くなったり、疲れたりする原因となります。
第3章:葬儀の疲れを軽減するために事前にできること
葬儀は避けては通れない道ですが、その疲れを少しでも軽減するために、事前に準備できることがあります。
3-1. ご家族で「もしもの時」について話しておく
「縁起でもない」と思うかもしれませんが、これからの時代、ご家族と「もしもの時」について話し合っておくことは非常に大切です。
- 誰が喪主になるか:誰が中心になって動くのか、あらかじめ決めておくとスムーズです。
- 葬儀の規模や形式:家族葬、一般葬、一日葬など、どのようなお葬式にしたいか。
- 費用について:どれくらいの予算を考えているか。
- 宗教・宗派:菩提寺(お付き合いのあるお寺)の有無や、宗派の確認。
これらのことを事前に話し合っておくだけで、いざという時の迷いや負担は大幅に軽減されます。
3-2. 喪服の準備と小物類の確認
突然の訃報に慌てないよう、喪服や礼服を事前に用意しておくことも有効です。
特に女性の場合、喪服はサイズやデザインの流行もありますし、長く着ていないと体型が変わっていることもあります。いざという時に「サイズが合わない」「デザインが古い」となると、余計な心配が増えてしまいます。
そうはいっても、「今から喪服を準備するのは気が引ける」「買うと高いし、収納場所にも困る」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな時は、【Cariru BLACK FORMAL】のような、喪服・礼服のレンタルサービスを利用するのも一つの手です。質の高いブランドのブラックフォーマルを、必要な時にだけリーズナブルに利用できます。デザインや質にこだわった商品を、プロのマナーに沿って厳選しているため、安心して利用できますよ。ジャケット、ワンピースだけでなく、バッグや数珠、袱紗などのフルセットも豊富なので、あれこれ揃える手間も省けます。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
第4章:葬儀後も続く「疲れ」と、乗り越えるためのヒント
葬儀が終われば、すべてが終わりではありません。むしろ、ここからが本当の始まりだと言う人もいます。
4-1. 葬儀後の手続きと「グリーフケア」
葬儀後も、やらなければならないことは山積みです。
- 香典返し:いただいた香典へのお返し。
- 四十九日法要の手配:お寺や斎場との調整。
- 遺産相続手続き:銀行や役所での手続き。
こうした事務的な作業も、心身ともに疲れている中で行うのは非常に大変です。
特に、香典返しについては、どなたに、どのような品を、いつまでに贈るかなど、慣れないことばかりで悩んでしまう方も多いでしょう。
そういったお返し物の手配には、ギフト専門店のオンラインショップが便利です。例えば、1926年創業のギフト専門店【シャディギフトモール】なら、香典返しにぴったりの品を、豊富なラインナップから選ぶことができます。のし紙やメッセージカードも無料で付けられるので、マナーに沿った丁寧な対応が可能です。
また、肉体的な疲れが癒えても、心に残る悲しみはすぐには消えません。
「グリーフケア」という言葉をご存知でしょうか。これは、「深い悲しみ(グリーフ)」を抱える人を支えるためのケアのことです。
- 無理に明るく振る舞わない:悲しいときは悲しいと、素直な感情を表現しましょう。
- 誰かに話を聞いてもらう:家族や友人、信頼できる人に話すだけでも、心が軽くなることがあります。
- 専門家の力を借りる:悲しみが深すぎて日常生活に支障が出ている場合は、専門のカウンセラーに相談することも検討しましょう。
グリーフケアは、一人で抱え込まないことが何よりも大切です。
4-2. 遺品整理という大きなタスク
葬儀が終わった後、ご遺族を待ち受けるのが「遺品整理」です。
故人様のお部屋に残された品々は、一つひとつに思い出が詰まっています。しかし、そのすべてをすぐに整理するのは、精神的にも肉体的にも非常に負担が大きいものです。
「思い出の品をどうしよう」「自分たちだけではとても片付けられない」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。
もし、遺品整理に困っている方がいらっしゃれば、専門業者に依頼することも検討してみてください。
【ライフリセット】のような遺品整理専門の業者に依頼すれば、故人様の思い出を大切にしながら、専門的な知識と経験で、丁寧かつ迅速に整理を進めてくれます。ご遺族の精神的な負担を軽減するためにも、プロの手を借りることは非常に有効です。
第5章:【元プランナーの視点】葬儀の疲れを乗り越えるために
最後に、元葬儀社プランナーとしての視点から、疲れを乗り越えるためのメッセージをお伝えします。
5-1. 「完璧な葬儀」を目指さなくていい
多くの方は、「立派な葬儀をしなければならない」「故人のためにも、恥ずかしくない葬儀にしたい」と考えがちです。
もちろん、故人様を想う気持ちは素晴らしいものです。しかし、そのためにご自身が無理をして、心身ともに疲れ果ててしまっては意味がありません。
大切なのは、「故人様を心から悼む気持ち」です。
豪華な祭壇や、たくさんの料理がなくても、故人様とご家族が心を通わせる、温かいお別れができれば、それ以上のことはないのです。
「完璧な葬儀」を目指すのではなく、「後悔のないお別れ」を目指してください。
5-2. 助けを求めることをためらわないで
「私がしっかりしなければ」「家族に心配をかけられない」と、一人で頑張りすぎてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、葬儀は一人でできるものではありません。
親戚や友人、葬儀社の担当者、そして時には専門家など、頼れる人には頼ってください。
「助けてください」
そう口にすることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、周囲との信頼関係を築き、みんなで故人様を送るための第一歩なのです。
おわりに
この記事では、葬儀で「疲れる」のはなぜか、そしてその疲れを軽減するためにできることについてお話ししました。
「葬儀は、人生で何度も経験するものではない」という言葉をよく聞きます。だからこそ、多くの人が不安や戸惑いを感じてしまいます。
もし、この記事が少しでもあなたの心の負担を軽くする手助けになれば幸いです。
そして、この記事を読んで、葬儀の準備や服装、葬儀後の手続きについて、もっと詳しく知りたいと思った方は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。
私も父を亡くした経験から、情報の格差によって損をしてしまう人が多い現実を見てきました。だからこそ、このブログを通じて、少しでも多くの方が「後悔しないお別れ」を迎えられるよう、これからも心を込めて情報発信を続けていきたいと思います。
Keisukeのプロフィール
筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか? あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。