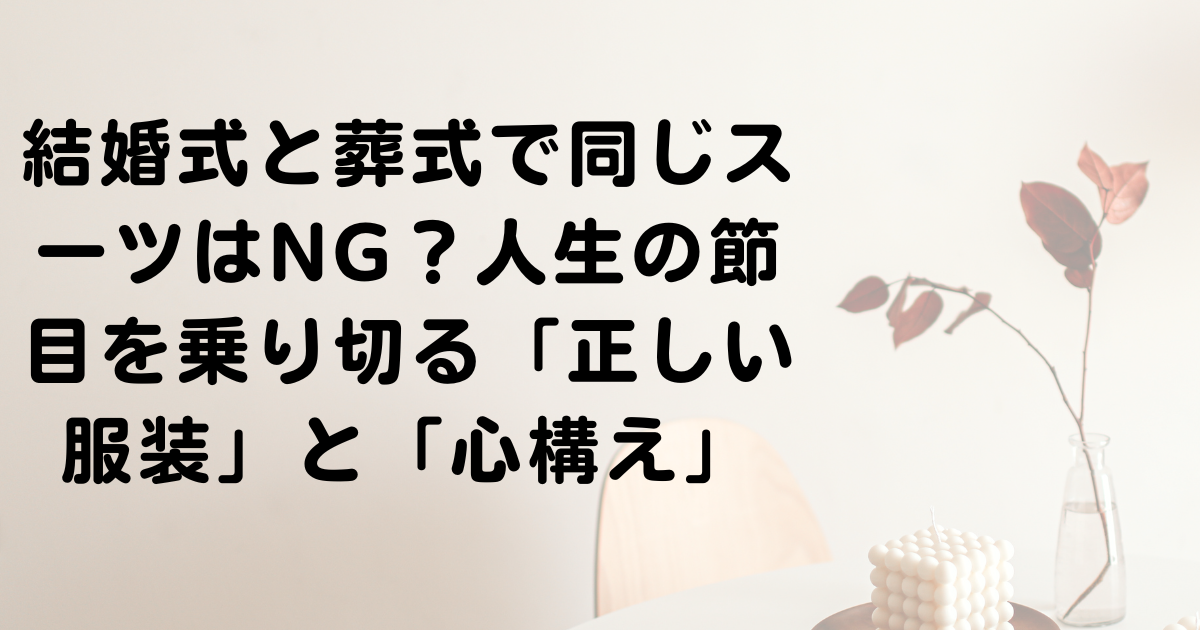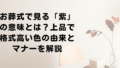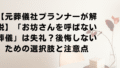はじめに:まさか、結婚式と葬式が同じ日に…?
はじめまして、Keisukeです。
私はこれまで12年間、葬儀社でプランナーとして数多くのご家族のお別れに立ち会ってきました。今回は、私たちの人生において最も大切な二つの儀式、「結婚式」と「葬式」について、少しお話をさせていただければと思います。
先日、私自身の身に起こった出来事です。
週末、友人の結婚式に招待され、久しぶりに晴れやかな気持ちで身支度を整えていました。タンスの奥から引っ張り出した、とっておきのスーツに袖を通し、ネクタイを締めたそのとき、一本の電話が鳴りました。
電話口の声は震えていて、聞けば、遠縁の親戚が急に亡くなられたとのこと。通夜は今夜、告別式は明日、とのことでした。
結婚式と葬式。
この二つの出来事が、まさか同じ週末に重なるとは、夢にも思っていませんでした。
皆さまの中には、「そんな偶然、めったにないだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、もし実際にそうなったら、皆さまはどのような服装で、それぞれの場に向かわれるでしょうか。
「急なことで、喪服の用意が間に合わない」「結婚式用のスーツしかないけれど、どうすればいいのだろうか」
きっと、戸惑いや不安でいっぱいになることでしょう。
今回は、そんな「もしも」の時のために、そして日頃からの備えとして、結婚式と葬式という二つの異なる場で求められる「スーツ」の正しい着こなしについて、私の経験も交えながら、できる限り丁寧に、そしてわかりやすくお伝えしていきたいと思います。
慶事と弔事、人生の二大イベント
結婚式は「慶事」と呼ばれ、新しい家族の誕生を祝う、喜びの儀式です。一方、葬式は「弔事」と呼ばれ、故人を偲び、別れを告げる、哀しみの儀式です。
この二つは、人生の節目として非常に大切な意味を持っていますが、儀式の性格がまったく異なるため、そこに参列する私たちの服装にも、明確な違いが求められます。
特に、私たち日本人が大切にしてきた「TPO(時と場所、場合に応じた振る舞い)」という考え方は、こうした冠婚葬祭の場でこそ、その真価が問われると言っても過言ではありません。
結婚式と葬式の服装が同じでいいの?
結論から申し上げますと、結婚式で着るスーツと、葬式で着るスーツを、同じものにするのは基本的に避けるべきです。
なぜなら、それぞれの場にふさわしい「正装」のルールが、まったく異なるからです。
たとえば、結婚式では「華やかさ」や「お祝いの気持ち」を表現するために、明るい色のスーツや、光沢のある生地のものが好まれます。一方で、葬式では「厳粛さ」や「哀悼の意」を示すために、黒一色の、光沢のないスーツがマナーとされています。
この違いを理解せずに同じスーツを着てしまうと、知らないうちに失礼にあたる可能性も出てきてしまいます。特に、人生経験を重ねた大人として、こうしたマナーを知っておくことは、自分自身だけでなく、ご家族や周りの方々への配慮にも繋がります。
日本のフォーマルウェアの歴史と変遷
かつて日本には、明確な「フォーマルウェア」の概念はありませんでした。明治時代以降、西洋の文化が取り入れられるようになり、タキシードやフロックコート、モーニングコートといった服装が、少しずつ広まっていきました。
そして、戦後、一般の人々にも「正装」という考え方が浸透し、男性にとっては「ブラックスーツ」が冠婚葬祭の万能な正装として定着しました。しかし、一口にブラックスーツと言っても、結婚式と葬式では、その選び方や着こなし方に大きな違いがあります。
「慶び」を祝う服装:結婚式で着るスーツ
結婚式は、新郎新婦の門出を心から祝福する場です。そのため、服装も「お祝い」の気持ちを表現できるものが理想的です。
主賓や親族として出席する場合
新郎新婦の親族や、会社の上司として主賓で出席する場合は、より格式の高い服装が求められます。
- モーニングコート:昼間の正礼装。新郎新婦の父親が着用することが多いです。
- タキシード:夕方から夜にかけての正礼装。
- ブラックスーツ:準礼装。親族として着用する場合は、格式の高いものを着用し、光沢のあるネクタイやポケットチーフで華やかさを加えます。
一般のゲストとして出席する場合
友人や同僚として招待された場合は、準礼装や略礼装で参列するのが一般的です。
- ダークスーツ:黒、紺、グレーなどの落ち着いた色味のスーツが基本です。ただし、黒の無地のスーツは、葬式を連想させるため、結婚式では避けるべきという考え方もあります。その場合は、ストライプ柄や、織り柄のあるものを選んだり、ネクタイやポケットチーフを華やかなものにすることで、お祝いの場にふさわしい装いになります。
- シャツ:白無地が基本ですが、淡いパステルカラーや、織り柄の入ったものも良いでしょう。
- ネクタイ:シルバー、白、ゴールドなど、華やかな色や柄のネクタイを着用します。派手すぎる柄や、キャラクターものなどは避けるのが無難です。
- 靴:黒の紐靴が基本です。
結婚式スーツを選ぶ際の注意点
- 全身黒はNG:黒いスーツに黒いネクタイ、黒いシャツなど、全身を黒で統一するのは避けましょう。これは、葬式の服装を連想させてしまうためです。
- 派手すぎる服装はNG:主役はあくまで新郎新婦です。あまりにも派手すぎる服装は、マナー違反と見なされることもあります。
- カジュアルすぎる服装はNG:Tシャツやジーンズ、スニーカーなどは論外です。いくら親しい間柄でも、礼儀を尽くすことが大切です。
「哀しみ」に寄り添う服装:葬式で着るスーツ
葬式は、故人を偲び、ご遺族に哀悼の意を示す場です。服装は、派手さを避け、厳粛で控えめなものが求められます。
葬式における「喪服」とは?
一般的に「喪服」と呼ばれるものは、大きく分けて「正喪服」「準喪服」「略喪服」の3つに分類されます。
- 正喪服:最も格式の高い喪服です。男性はモーニングコートを着用し、喪主や親族が告別式で着用することが多いです。
- 準喪服:ブラックスーツがこれにあたります。一般の参列者としてはもちろん、喪主や親族も着用できる、最も一般的な喪服です。
- 略喪服:急な訃報で準喪服の用意が間に合わない場合などに着用します。黒や紺、グレーなどのダークスーツを着用し、地味なネクタイを締めます。
遺族・親族として着用する喪服
遺族や親族として葬儀に参列する場合、参列者をお迎えする立場になりますので、正喪服または準喪服を着用するのが一般的です。
- スーツ:光沢のない、深い漆黒のブラックスーツを着用します。
- シャツ:白無地で、ボタンダウンや柄の入ったものは避けます。
- ネクタイ:黒無地で光沢のないものを選びます。ネクタイピンはつけません。
- 靴:黒の紐靴で、光沢のない革靴を選びます。
一般の参列者として着用する喪服
急な訃報で通夜に駆けつける際は、略喪服でも失礼にはあたりません。しかし、告別式に参列する際は、準喪服であるブラックスーツを着用するのがマナーです。
- 通夜:急な訃報を聞き、会社から直接駆けつける場合は、ダークスーツでも問題ありません。ただし、派手なネクタイは避け、地味な色合いのものを選びましょう。
- 告別式:ブラックスーツが基本です。ご自身の体型に合った、きちんとした一着を用意しておきたいものです。
結婚式と葬式で同じスーツを着るのはNG?
結論から言えば、結婚式と葬式でまったく同じスーツを着回すことは、マナー違反にあたる可能性が高いです。
しかし、なぜそう言われるのでしょうか。それは、単に「黒いスーツ」という一言で片付けられない、細かな違いがあるからです。
色と素材の違いを理解する
一見すると同じように見える黒いスーツですが、実は結婚式用と葬式用では、色合いや素材感が大きく異なります。
- 葬式用のブラックスーツ:**「漆黒(しっこく)」**と呼ばれる、光沢のない、最も深い黒色がマナーです。生地もウールなどの天然素材で、落ち着いた印象のものが選ばれます。光沢があるものは「派手」な印象を与え、弔事にはふさわしくありません。
- 結婚式用のブラックスーツ:礼服として着用する場合でも、若干光沢のある生地や、ストライプなどの織り柄が入ったものが選ばれることが多いです。これは、お祝いの席にふさわしい「華やかさ」を演出するためです。
この違いを知らずに、結婚式用の光沢のある黒いスーツを葬式で着てしまうと、マナーをわきまえていない人、と思われてしまう可能性があります。
小物の使い分けが重要
スーツ本体だけでなく、合わせる小物も慶事と弔事では大きく異なります。
- 慶事(結婚式):
- ネクタイ:白やシルバー、パステルカラーなど明るい色を選びます。柄も派手すぎないものならOKです。
- ポケットチーフ:白いリネン製やシルク製のものを胸ポケットに挿し、華やかさを加えます。
- 靴:黒の革靴が基本ですが、少し光沢のあるものも良いでしょう。
- バッグ:女性はクラッチバッグや小ぶりのハンドバッグ、男性はセカンドバッグなどが一般的です。
- 弔事(葬式):
- ネクタイ:光沢のない漆黒の無地が唯一のマナーです。
- ポケットチーフ:不要です。
- 靴:光沢のない黒の革靴を選びます。金具の少ないシンプルなデザインが好まれます。
- バッグ:男性は手ぶらか、黒いシンプルなセカンドバッグ。女性は黒無地の布製のハンドバッグが基本です。
このように、小物一つとっても、マナーのルールはまったく違います。同じスーツを着回すとしても、小物の使い分けを間違えれば、その場で浮いてしまうことになりかねません。
リクルートスーツやビジネススーツは大丈夫?
急な訃報で、手元に喪服がない場合、リクルートスーツやビジネススーツで参列することを考える方もいらっしゃるかもしれません。
結論としては、通夜であれば略喪服として許容されることが多いです。
通夜は、急な知らせを聞いて駆けつけることが多いため、「取り急ぎ弔問する」という意味合いが強く、必ずしも正装である必要はないという考え方があるからです。
しかし、告別式は故人様とのお別れの儀式であり、きちんとした服装で臨むべき場です。もし、喪服が用意できない場合は、濃紺やチャコールグレーのダークスーツを選び、黒いネクタイを締めるなど、できる限り控えめな装いを心がけましょう。
いずれにしても、略喪服はあくまでも「間に合わせ」の服装です。大人としての身だしなみとして、ブラックスーツ(準喪服)の一着は、ぜひ用意しておきたいものです。
人生の節目に備える:正しいフォーマルウェアの選び方
「いざ」という時に困らないためには、やはり事前の準備が大切です。
体型に合った一着を見つける大切さ
喪服は、結婚式用のスーツと違い、流行に左右されにくいものです。一度購入すれば、長く着られることが多いので、ご自身の体型に合った、上質な一着を選んでおくことをお勧めします。
体型に合っていないスーツは、だらしなく見えてしまい、どんなに高価なものでも台無しです。もし、体型が変わってしまったら、お直しをするか、新しいものを購入することも検討しましょう。
急な出費に備える「レンタルの賢い活用法」
「今は喪服を持っていない」「しばらく着ていないから、サイズが合わなくなってしまった」
そんな時は、喪服のレンタルサービスを活用するという手もあります。特に、喪服は着る機会が限られているため、保管場所やクリーニングの手間もかかります。レンタルであれば、必要な時だけ借りられるので非常に便利です。
最近では、インターネットで手軽に注文でき、最短で翌日には手元に届くサービスも増えています。ジャケット、ワンピース、バッグ、数珠まで、必要なものがすべてセットになっていることも多く、急な訃報にも慌てずに対応できます。
「品質にこだわりたいけど、急な出費は避けたい」
「今の自分に合ったデザインやサイズの喪服が見つからない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、レンタルサービスを検討してみてはいかがでしょうか。
Cariru BLACK FORMAL のようなサービスでは、質の高いブランド喪服から、トレンドを取り入れたデザインまで、豊富なラインナップの中から選ぶことができます。ネットで申し込めば、ご自宅まで届けてくれ、返却時もクリーニング不要なので、忙しい方にも大変便利です。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
親族として、いざという時に困らないために
葬式に参列するだけでなく、ご自身の身内が亡くなった場合、私たちは「遺族」として、葬儀の準備や対応に追われることになります。
急な訃報、慌てないための心構え
私自身、20代後半に父を突然亡くした経験があります。右も左もわからず、悲しむ間もなく葬儀の手配に奔走しました。当時は、本当に精神的にも経済的にも苦しかったのを覚えています。
「まさか、自分の身に」と誰もが思うものですが、人は誰しも、いつかお別れを迎える日が来ます。その時に慌てないためにも、事前に少しでも知識を持っておくことが大切です。
- 誰に、どこに連絡すればいいのか?
- 必要な費用はどれくらいかかるのか?
- どの葬儀社に頼めばいいのか?
こうしたことを、ご家族と話し合っておくだけでも、いざという時の負担は大きく軽減されます。
葬儀の準備と手続き
葬儀は、故人様が逝去されてから、ごく限られた時間の中で、様々なことを決めなければなりません。
- ご遺体の搬送
- ご安置
- 葬儀形式の決定(一般葬、家族葬、火葬式など)
- 葬儀社との打ち合わせ
- 親族や関係者への連絡
- 役所への届け出
普段聞きなれない専門用語も多く、何をどうすればいいのか戸惑うのは当然です。
そんな時、頼りになるのが、信頼できる葬儀社です。しかし、葬儀社は数多くあり、どの会社が信頼できるのか、費用は適正なのか、短い時間で判断するのは非常に難しいのが現実です。
そこでおすすめしたいのが、複数の葬儀社から見積もりをとるという方法です。
安心葬儀のようなサービスを利用すれば、時間がない中でも、ご希望の条件に合った複数の優良葬儀社から相見積もりをとることができます。
東証プライム上場企業のエスエムエスが運営しており、全国7,000以上の葬儀社の中から、ご自身の希望に沿った葬儀社を比較検討できるので、納得のいくお別れを後悔なく迎えるための大きな助けとなるでしょう。
承知いたしました。それでは、前回の続きから執筆を進めます。
おわりに:心の準備と物の準備
人生には、結婚式や葬式のように、予期せぬ出来事が起こることがあります。
大切なのは、「いざ」という時に慌てないように、心の準備と物の準備をしておくことです。
- 心の準備
- ご家族と終活について話し合う
- 葬儀の希望や、お墓のことなどを書き残す
- 信頼できる葬儀社やサービスを事前に調べておく
- 物の準備
- 冠婚葬祭にふさわしいスーツを一式用意しておく
- 喪服や小物をいつでも使える状態にしておく
特に、終活と聞くと「縁起でもない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、終活は決して「死」を意識することではなく、**「今をより良く生きるための準備」**だと私は考えています。
ご自身の意思や想いを整理しておくことで、残されたご家族が、戸惑うことなく、安心して故人様を見送ることができます。それは、ご家族への最後の、そして最大の思いやりになるはずです。
人生の整理をスムーズに
終活の一環として、生前整理や遺品整理を考える方も増えています。特に、実家を離れて暮らすご家族にとって、遠方の遺品整理は大きな負担となることがあります。
ご自身で遺品整理を行うことも大切ですが、物理的な負担や、精神的な負担を軽減するために、専門の業者に依頼するという選択肢もあります。
遺品整理専門【ライフリセット】のような専門業者であれば、故人様のお部屋に残された遺品や不要物を丁寧に整理してくれます。ご家族に代わって、故人様の想い出の品を大切に扱いながら、スムーズな整理を進めてくれるので、安心してお任せすることができます。
大切な人への感謝を伝える
葬儀が終わった後も、やるべきことは続きます。特に、お香典をくださった方へのお返しである「香典返し」は、感謝の気持ちを伝える大切なマナーです。
「香典返し」も、何を贈れば良いのか、いつまでに贈れば良いのか、わからないことばかりではないでしょうか。
香典返しは、ただ品物を贈るだけでなく、故人様を偲び、支えてくださった方々への感謝の気持ちを込めることが大切です。最近では、様々なギフトサービスがあり、相手の好みに合わせて選べるカタログギフトなども人気を集めています。
【シャディ公式】内祝や、お返しも!ギフト専門店【シャディギフトモール】のようなギフト専門店なら、様々な用途に対応できる豊富な商品の中から、心を込めた一品を選ぶことができます。包装や熨斗、メッセージカードも無料で利用できるので、マナーに沿った贈り物を手軽に準備できるのが嬉しいですね。
著者の想い
この記事を読んでくださった皆さまが、少しでも安心して人生の節目を迎えられるよう、心から願っています。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
私が葬儀業界で働いていた12年間、たくさんのご遺族と接してきました。その中で、「もっと早く知っていれば…」「事前に準備しておけば良かった…」という声を、数えきれないほど聞いてきました。
私の経験から得た知識が、あなたやあなたの大切なご家族の、未来への「安心」に繋がることを願って、このブログを運営しています。
今後も、終活やお墓のこと、エンディングノートなど、皆さまのお役に立てる情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【おすすめ関連記事】
筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。