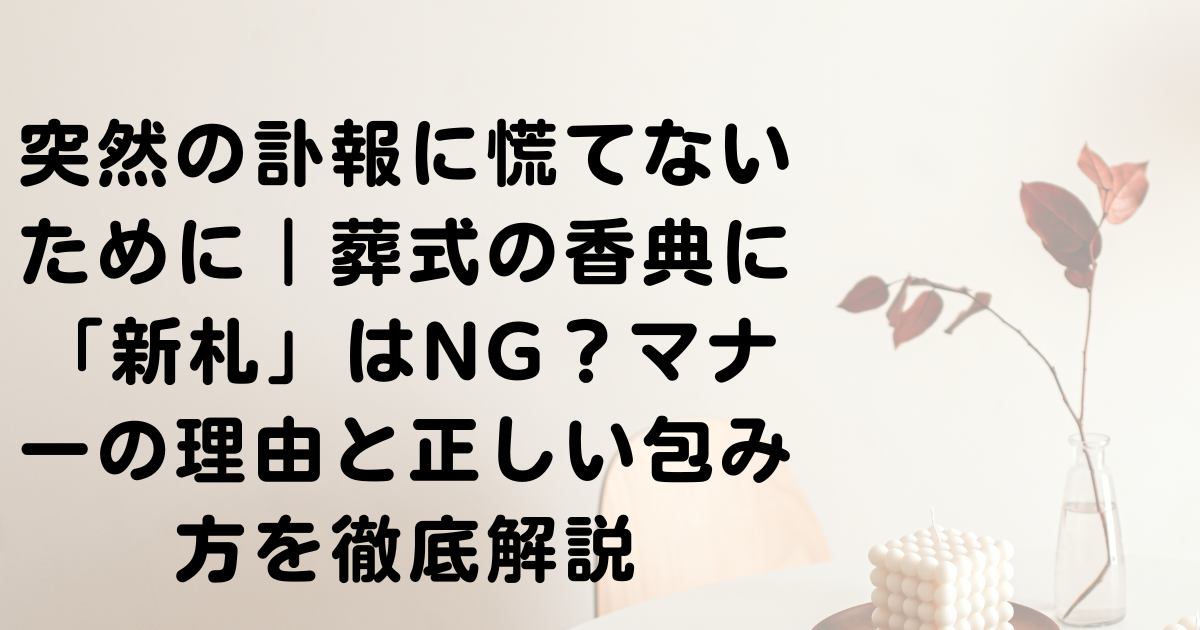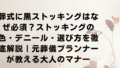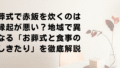Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
20代後半に父を突然亡くし、右も左もわからないまま葬儀の手配に奔走した経験から、「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」という思いで、葬儀業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。
このブログでは、私が実際に見てきた「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実を踏まえ、お葬式の基本や費用、トラブルを避けるための知識、信頼できるサービスの選び方などを、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
突然の訃報。まず何をすれば?
電話が鳴り、相手の声が少し震えている。「もしもし、Keisukeさん?実は、母が……」。
こんな突然の電話で、大切な人との永遠のお別れを知らされる。
私たちの人生において、葬儀はそう何度も経験することではありません。だからこそ、いざその時が来てしまうと、ほとんどの人は何をどうすれば良いのかわからず、途方に暮れてしまいます。
ましてや、病院から「すぐにお迎えに来てください」と連絡があった場合、悲しみや動揺の中で、葬儀社をどうやって探せば良いのか、どういう基準で選べば良いのか、考える時間さえほとんどありません。
「とにかく早く決めないと」と焦ってしまい、十分に比較検討する時間がないまま、病院と提携している葬儀社にそのまま依頼してしまうケースも少なくありません。
しかし、葬儀費用は決して安いものではありません。十数万円から数百万円という、まとまった費用がかかります。
限られた時間の中で、納得のいく葬儀社を見つけることは本当に大変なことです。
後になって「もう少し安くできたのではないか」「もっと丁寧な対応をしてくれる葬儀社があったのではないか」と後悔してしまうご遺族を、私はこれまで数えきれないほど見てきました。
そんな時、もし事前に信頼できる葬儀社の情報をいくつか知っていれば、心に少しの余裕が生まれます。
東証プライム上場企業のエスエムエスが運営する【安心葬儀】は、全国7000以上の葬儀社の中から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を紹介してくれるサービスです。複数の葬儀社から見積もりを取る「相見積もり」も簡単にできるので、時間をかけずに、信頼できる葬儀社を比較検討することができます。もしもの時に慌てないためにも、事前にこういったサービスがあることを知っておくのは、とても大切なことだと私は考えています。
葬式の準備とマナー:香典の「新札」はなぜNG?
葬儀の準備をする中で、多くの方が悩むことの一つが「香典(こうでん)」です。
香典とは、故人の霊前に供える金銭のこと。お線香やお花の代わりに、故人を偲び、遺族を想って贈るものです。
お悔やみの気持ちを表すものですから、失礼のないようにしたいですよね。
しかし、この香典、普段あまり意識しない「お金」のマナーがいくつかあります。
その中でも、特に多くの方が疑問に感じるのが「新札(しんさつ)は使ってはいけない」というマナーです。
「え、お祝い事なら新札を使うのがマナーじゃないの?」
そう思われた方も多いのではないでしょうか。実際、結婚式などのお祝い事では、ピカピカの新しいお札を使うのが一般的です。
しかし、お葬式ではそれが逆になります。
では、なぜお葬式の香典に新札は使ってはいけないのでしょうか?
その理由は、日本の文化や人々の心情に深く根ざしています。
新札が「不幸を予期していた」という誤解を生む理由
私たちが香典を包むお金を選ぶとき、少しシワのついた、古すぎず新しすぎないお札を選ぶのが良いとされています。
これは、「急な訃報で慌てて駆けつけたため、手元にあるお札をそのまま包みました」という、ご遺族への配慮の気持ちを表しているからです。
新札をわざわざ用意する、ということは、まるで「この不幸をあらかじめ予期して、事前に準備していました」というふうに受け取られてしまう可能性があります。
ご遺族にとって、大切な人の死は、何よりもつらく悲しいことです。その悲しみに寄り添うべき場で、そのような誤解を与えてしまうのは、マナー違反とされています。
もちろん、悪意があるわけではありません。しかし、相手の気持ちを慮ることが何よりも大切なお悔やみの場では、こうした細やかな配慮が求められるのです。
では、もし手元に新札しかない場合はどうすれば良いのでしょうか?
そのまま新札を包んでしまっては、先ほどの理由から失礼にあたると言われています。
一番簡単な方法は、新札に折り目をつけることです。
お札を一度、軽く二つ折りにするだけでも構いません。そうすることで、「急いで用意しました」という気持ちを伝えることができます。
このマナーは、地域や家庭によって考え方が異なる場合もありますが、一般的には広く知られている作法です。
もしもの時に慌てないよう、ぜひ覚えておいてください。
葬式の香典にまつわるギモンを徹底解説
ここからは、香典にまつわるよくある疑問について、元葬儀社プランナーの視点から、一つひとつ丁寧に解説していきます。
1. 香典袋の選び方|水引の種類と色の意味
香典を包む袋は、ご祝儀袋とは異なります。
一般的には、「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」と呼ばれます。
不祝儀袋には、様々な種類がありますが、特に重要なのが「水引(みずひき)」です。
水引とは、袋の表面にかけられている飾りの紐のこと。色や結び方によって、意味合いが異なります。
お葬式で使われる水引は、主に以下の3種類です。
- 結び切り(むすびきり):一度結ぶとほどけにくい結び方です。「二度と繰り返すことのないように」という意味が込められており、お葬式や結婚式など、一度きりであることを願う場面で使われます。
- あわじ結び:結び切りの一種で、両端を引っ張るとさらに強く結ばれることから、「末永く」という意味が込められています。こちらも、繰り返さないことが望ましい場面で使われます。
- 輪結び:仏教などで使われる結び方で、結び目の形が輪になっているものです。
水引の色は、主に以下の2種類です。
- 黒白(くろしろ):最も一般的で、広く使われています。
- 双銀(そうぎん):黒白よりも格が高く、高額な香典を包む場合に使われます。
また、宗教によっても適切な不祝儀袋が異なります。
- 仏教:黒白または双銀の水引がついた袋。蓮の絵が描かれているものもあります。
- 神道:黒白または双銀の水引がついた袋。蓮の絵は使わず、無地を選びます。
- キリスト教:十字架や百合の花が描かれた袋。水引は不要です。
最近では、水引が印刷されたタイプのものも多く、手軽に使うことができます。
2. 香典袋の書き方|表書きと名前の正しい書き方
香典袋の表面に書く文字を「表書き(おもてがき)」と呼びます。
この表書きも、宗教によって書き方が異なりますので注意が必要です。
- 仏教:「御霊前(ごれいぜん)」、「御香典(おこうでん)」が一般的です。ただし、浄土真宗では「御仏前(ごぶつぜん)」と書きます。
- 神道:「御玉串料(おんたまぐしりょう)」、「御榊料(おさかきりょう)」と書きます。
- キリスト教:「御花料(おはなりょう)」と書きます。
もし故人の宗教がわからない場合は、「御霊前」と書くのが無難です。
表書きの下には、自分の名前をフルネームで書きます。
薄墨(うすずみ)の筆ペンやサインペンを使うのがマナーとされています。
「悲しみの涙で墨が薄くなってしまった」という気持ちを表している、と言われています。
3. 香典の金額相場|故人との関係性で変わる金額
香典の金額は、故人との関係性によって大きく異なります。
あくまで一般的な目安ですが、以下の表を参考にしてください。
| 故人との関係性 | 金額相場 |
| 両親 | 5万円〜10万円 |
| 兄弟姉妹 | 3万円〜5万円 |
| 祖父母 | 1万円〜3万円 |
| 親戚 | 1万円〜2万円 |
| 友人・知人 | 5千円〜1万円 |
| 会社の上司・同僚 | 5千円〜1万円 |
| 近所の方 | 3千円〜5千円 |
金額に関する注意点
- 「四」や「九」の数字は避ける:「死」や「苦」を連想させるため、縁起が悪いとされています。
- 偶数の金額も避ける:「割り切れる」ことから、故人との縁が切れてしまう、という考え方から避ける傾向にあります。
しかし、最近ではあまり厳密に気にしない方も増えていますので、あまり神経質になりすぎる必要はありません。
大切なのは、あくまでも故人を想い、ご遺族に寄り添う気持ちです。
葬式後の準備:香典返しとお礼状
無事に葬儀を終えた後、今度は香典をいただいた方へのお返しである「香典返し」の準備が始まります。
香典返しは、香典をいただいたことへのお礼と、無事に忌明けを迎えたことのご報告を兼ねています。
一般的には、いただいた金額の半額(半返し)が目安とされています。
香典返しは、四十九日の法要を終えた忌明け(きあけ)後に贈るのが一般的です。
葬儀の当日にお返しをする「即日返し」も増えてきていますが、その場合はいただいた金額に関わらず、一律で同じ品物を贈ることが多いです。
香典返しを贈る際には、お礼状も添えるのがマナーです。
お礼状には、以下の内容を簡潔に書きます。
- 故人のために、お忙しい中ご会葬いただいたことへのお礼
- 香典をいただいたことへのお礼
- 無事に忌明けを迎えたことのご報告
- 故人が生前お世話になったことへの感謝
- 今後のお付き合いについて
丁寧な言葉遣いを心がけ、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
【シャディ公式】のようなギフト専門店は、香典返しに最適な商品や、無料の包装・のし紙、メッセージカードを豊富に取り揃えています。
香典返しは、慣れない作業で大変ですが、こういったサービスを上手に利用することで、ご遺族の負担を少しでも減らすことができます。
喪主として葬儀を執り行う際の流れと注意点
もしあなたが喪主として葬儀を執り行うことになったら、一体何から手を付ければ良いのでしょうか?
ここでは、一般的な葬儀の流れと、その中で特に注意すべきポイントについて解説します。
1. 訃報連絡と葬儀社への連絡
大切な人が亡くなった直後、まず行うべきことは、親族や関係者への訃報連絡です。
そして、同時に葬儀社へ連絡し、ご遺体を安置してもらう場所を確保します。
この時、もし事前に葬儀社を決めていない場合は、複数の葬儀社から話を聞き、比較検討することが大切です。
前述の通り、【安心葬儀】のようなサービスを利用すれば、短時間で複数の優良葬儀社を比較検討できます。
2. 葬儀形式と費用の決定
葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀の形式や費用について話し合います。
葬儀には、家族葬、一般葬、一日葬、火葬式など、さまざまな形式があります。
ご自身の希望や故人の意思、そして予算に合わせて、最適な形式を選びましょう。
この時、費用については、できるだけ詳細な見積もりを出してもらい、追加料金が発生する可能性がないか、しっかりと確認しておくことが重要です。
3. 通夜・葬儀・告別式の進行
通夜、葬儀、告別式を滞りなく進めます。
この間、喪主は弔問客への挨拶や、お坊さんや司会者との打ち合わせなど、多岐にわたる役割を担います。
もし何か不安なことがあれば、葬儀社の担当者に遠慮なく相談しましょう。
プロのプランナーが、細やかな心配りを持ってサポートしてくれます。
4. 葬儀後の手続きと供養
葬儀が終わった後も、やるべきことはたくさんあります。
役所への届け出、遺産相続の手続き、お墓の準備、香典返しなど、様々な手続きが必要です。
こうした手続きは、すべてご遺族だけで行うのは大変なことです。
専門のサービスを利用したり、親族に協力を仰いだりして、一人で抱え込まないようにすることが大切です。
葬式の服装マナー|喪服・礼服の準備
葬儀に参列する際、特に気を使うのが「服装」です。
弔事には弔事の服装マナーがあります。
特に女性の場合、和装か洋装か、そして小物まで、細やかな配慮が必要です。
1. 喪服の種類と選び方
喪服は、正式な儀式にふさわしい「正喪服(せいそうふく)」、通夜や三回忌までの法要で着用する「準喪服(じゅんそうふく)」、それ以降の法要や弔問に着用する「略喪服(りゃくそうふく)」の3種類に分かれます。
一般的に、私たちが葬儀に参列する際に着用するのは「準喪服」です。
女性の準喪服は、黒のワンピースやアンサンブル、スーツが一般的です。
デザインは、襟元が詰まったもの、袖丈が長めのものなど、肌の露出を抑えたものを選びます。
男性の準喪服は、ブラックスーツが一般的です。
白のシャツに、黒のネクタイ、黒の靴下、黒の革靴を合わせます。
2. 喪服の準備とレンタルサービス
喪服は、着る機会が少ないため、「いざという時にサイズが合わない」「流行遅れのデザインになってしまった」ということも少なくありません。
また、急な訃報で喪服を用意する時間がない、というケースもあります。
そんな時におすすめなのが、喪服・礼服のレンタルサービスです。
【Cariru BLACK FORMAL】は、デザインや質、マナーにこだわった喪服・礼服をレンタルできるサービスです。
ネットで24時間いつでも申し込めて、最短で翌日午前中には届けてくれます。
ジャケット、ワンピース、バッグ、サブバッグ、数珠、袱紗など、必要なものがすべて揃ったフルセットもあるので、突然の訃報にも慌てずに対応できます。
購入するよりもリーズナブルに、上質な喪服をレンタルできるのは、とても便利なサービスですね。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
遺品整理と生前整理
葬儀が終わった後、ご遺族にとって大きな負担となるのが「遺品整理」です。
故人のお部屋に残された大切な品々や、不要なものを整理する作業は、時間も労力もかかります。
そして何より、故人との思い出に触れるたびに、悲しみがこみ上げてくる、精神的にもつらい作業です。
1. 遺品整理の現状と課題
最近では、核家族化が進み、遠方に住んでいるご家族が遺品整理をしなければならない、というケースが増えています。
また、故人が一人暮らしだった場合、ご遺族だけで膨大な量の遺品を整理するのは、現実的に難しいこともあります。
そんな時、頼りになるのが「遺品整理専門業者」です。
2. 遺品整理専門業者に依頼するメリット
専門の業者に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 時間と労力の節約:専門のスタッフが効率的に作業を進めてくれるため、ご遺族の負担が軽減されます。
- 精神的な負担の軽減:故人の思い出に触れながら作業をするつらさから解放されます。
- 不用品の適正な処分:不用品のリサイクルや、故人のお部屋の清掃まで、一貫して任せることができます。
遺品整理専門【ライフリセット】は、故人のお部屋に残された遺品や不要物を、ご遺族に代わって整理してくれる専門サービスです。
ご家族が亡くなられたご遺族の方々はもちろん、最近ではご本人様が、将来ご家族に負担をかけないようにと「生前整理」を依頼されるケースも増えています。
後悔しないお別れのために、今できること
ここまで、葬式の香典マナーから、葬儀の準備、服装、そして遺品整理まで、幅広いテーマでお話してきました。
私が葬儀社で働いていた時、ご遺族からよく聞かれた言葉があります。
「もっと早くから知っていれば、こんなに苦労しなかったのに」
突然の訃報に直面した時、私たちはあまりにも多くのことを一度に考え、決めなければなりません。
葬儀社の選び方、費用のこと、親族への連絡、そして香典のマナー。
日々の生活の中では、なかなか考える機会のないことばかりです。
しかし、人生で一番大切な人との「最後の時間」を、後悔なく、心穏やかに過ごすために、今できる準備があります。
例えば、
- エンディングノートを書いておく:ご自身の意思を明確にしておくことで、ご家族の負担を減らすことができます。
- 葬儀に関する情報を集めておく:信頼できる葬儀社の情報をいくつか知っておくだけでも、心の余裕が生まれます。
- 終活に関する相談をしておく:お墓のこと、遺産のこと、専門家に相談することで、不安を解消できます。
私たちは、いつか必ず、愛する人との別れを経験します。
その時が来た時に、「もっとこうしていれば良かった」と後悔することがないように。
そして、大切な人との最後の時間を、心から穏やかに、大切に過ごせるように。
それが、私のブログを通して、皆さまにお伝えしたい一番のメッセージです。
このブログが、あなたやあなたのご家族の未来が、少しでも安心に近づくための、ささやかな助けになれば幸いです。
また、葬儀に関するより詳しい情報や、服装のマナー、香典返しのことについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を通して、少しでも皆さまの不安が解消され、心穏やかな日々を過ごせることを願っています。