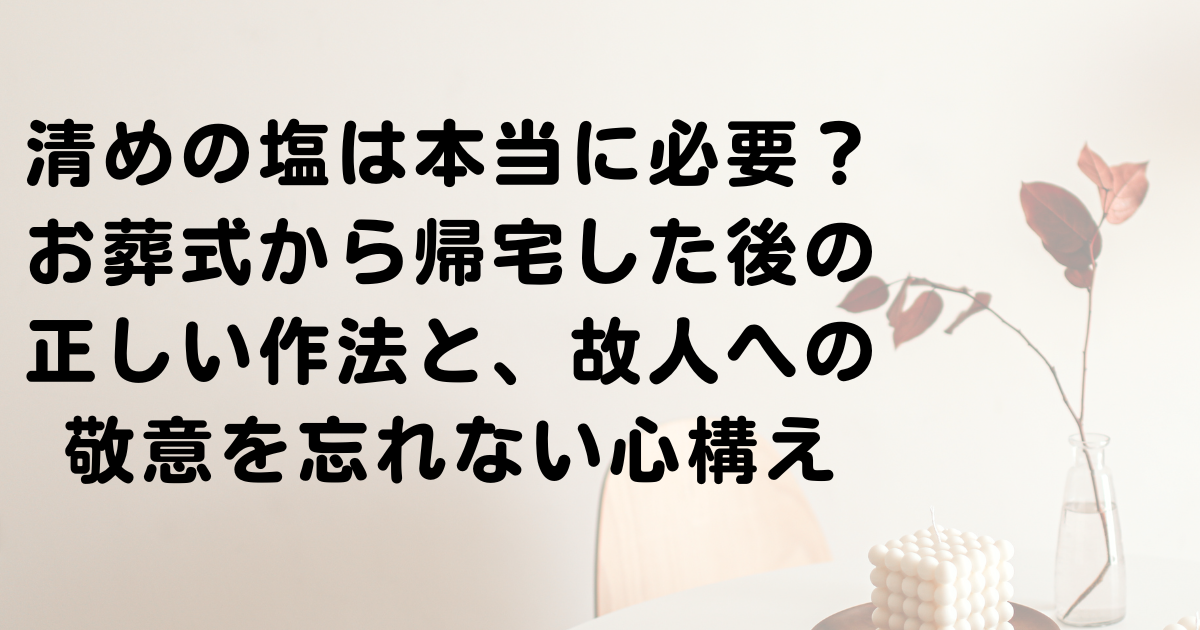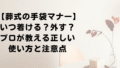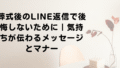こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営している、元葬儀社プランナーのKeisukeです。
私はこれまで12年間、800件を超えるお葬式に携わってきました。
突然のお別れに直面し、不安や戸惑いを抱えながらも、大切な方のために精一杯務めようとするご遺族の姿を数えきれないほど見てきました。
そんなご遺族からよくいただく質問の一つに、「お葬式の後に、清めの塩は本当に必要ですか?」というものがあります。
「清めの塩」は、日本の昔ながらの風習として、多くの方にとって馴染みのあるものかもしれません。
しかし、その意味や、現代のお葬式における捉え方について、はっきりとした答えを知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、この「清めの塩」という慣習について、その由来から現代における考え方、そしてご遺族が本当に大切にすべきことまで、元葬儀社プランナーとしての経験と知識をもとに、丁寧にお伝えしていきたいと思います。
ご自身やご家族の終活を考えている方、また、これからお葬式に参列される方にとって、少しでも心の準備に役立つ内容となれば幸いです。
清めの塩はなぜ必要? その由来と意味を紐解く
まず、そもそも「清めの塩」がなぜ存在するのか、その歴史的な背景から見ていきましょう。
故人の「穢れ」を清めるための慣習
「清めの塩」の風習は、神道における「穢れ(けがれ)」という考え方が深く関わっています。
神道では、死は「穢れ」であるとされてきました。この「穢れ」は、単に不潔なものという意味ではなく、生命力が失われた状態を指します。そして、この「穢れ」が、生きている人間に移ってしまうことを恐れていました。
そのため、お葬式という「死」に触れた場所から帰ってきた際、その「穢れ」を家の中に持ち込まないように、玄関先で体に塩を振りかけることで清める、という慣習が生まれたのです。
この考え方は、仏教にはもともとありません。仏教では、死は単なる生命の終わりであり、穢れとは捉えません。そのため、お葬式に清めの塩を用意するのは、日本の文化と仏教が融合した、独自の慣習と言えるでしょう。
塩は昔から「魔除け」として使われてきた
神道だけでなく、昔から塩には「魔除け」や「清浄なもの」としての力が信じられてきました。
・お相撲さんが土俵に塩をまく ・お店の入り口に盛り塩をする
これらはすべて、塩が持つ「清める力」への信仰が元になっています。
お葬式から帰ってきた人に塩を振るのも、同じように「悪いもの」がついてこないように、という願いが込められていたのです。
現代における「清めの塩」の考え方
では、現代の私たちにとって、この「清めの塩」はどのように捉えるべきなのでしょうか。
清めの塩は「絶対」ではない
最も大切なのは、「清めの塩は絶対に必要なものではない」ということです。
宗教や宗派によっては、清めの塩を配布しないところも増えていますし、仏教の考え方からすると、そもそも清めの塩は不要であると考える僧侶の方も少なくありません。
特に浄土真宗では、「人は亡くなるとすぐに仏様になる」という教えがあるため、「穢れ」という概念がなく、清めの塩は用いられません。
もし、お葬式に参列して清めの塩が配られなかったとしても、それは決して失礼なことではありませんので、ご安心ください。
大切なのは「故人への敬意」と「心の区切り」
清めの塩を使うかどうかにかかわらず、一番大切なのは、故人への敬意を忘れないことです。
清めの塩は、あくまで「心の区切りをつけるための儀式」と捉えるのが、現代においては自然かもしれません。
お葬式という非日常の場から日常に戻る際、気持ちを切り替え、故人を偲びつつも、自分の生活を再び歩み始める。そのための「心のけじめ」として、清めの塩を使う、という考え方です。
無理に使う必要はありませんし、もし使わないと決めたとしても、それは故人を軽んじていることにはなりません。ご自身の気持ちと向き合い、納得できる方法を選ぶことが大切です。
実際に清めの塩を使う時の正しい作法
それでも、「やはり昔からの慣習に倣って清めの塩を使いたい」という方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、清めの塩を使う際の一般的な作法と、その意味についてお伝えします。
1. 玄関先で、家に入る前に
お葬式から帰宅したら、まずは玄関の外で立ち止まりましょう。家の中に塩を持ち込まないことが大切です。
2. 振りかける順番
塩は、以下の順番で体に振りかけるのが一般的です。
- 胸元
- 背中
- 足元
自分で塩を体に振りかけるのが難しい場合は、同居のご家族に頼んでも構いません。この時、塩を体に直接すり込んだりする必要はなく、軽く振りかけるだけで十分です。
3. 塩を払い落とす
塩を振りかけたら、手で軽く払い落とします。これで「穢れ」が取り払われた、という気持ちの区切りをつけます。
4. 手を洗い、うがいをする
塩を使った後は、手を洗い、うがいをして、身を清めます。
これは、昔から伝わる風習であると同時に、現代においても感染症予防などの観点から、衛生的な面でも大切な行為と言えるでしょう。
葬儀後の手続き・準備で後悔しないために
お葬式が終わった後も、ご遺族には多くの手続きや準備が待っています。
しかし、大切な方を亡くされた直後で、心も体も疲れている状態では、なかなか落ち着いて物事を進めることが難しいものです。
「故人との最期のお別れを、悔いのないものにしたかった」
「もっと故人のことを考えて、葬儀社を選べばよかった」
私が葬儀プランナーをしていた頃、そうしたご相談をいただくことも少なくありませんでした。
お葬式は、人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、後悔のないよう、信頼できる葬儀社と出会うことがとても大切です。
もし今、ご家族の終活を考えている方や、急な訃報で葬儀社を探さなければならない状況にある方は、ぜひ【安心葬儀】の相見積もりサービスをご利用になってみてはいかがでしょうか。
全国7,000社以上の優良葬儀社の中から、ご希望にぴったりの葬儀社を最大5社までご紹介してくれます。
複数の葬儀社から見積もりを取ることで、費用やサービス内容を比較検討でき、納得のいくお葬式を実現できます。
東証プライム上場企業が運営しているサービスなので、安心してご相談いただけるのも大きなポイントです。
葬儀後の生活で、故人を偲ぶ心を大切にするために
清めの塩は、あくまで儀式の一つです。本当に大切なのは、故人を偲び、感謝の気持ちを持ち続けることではないでしょうか。
ここからは、お葬式後の生活を、故人のことを想いながら穏やかに過ごすためのヒントをいくつかご紹介します。
1. 故人の好きなものを食べる
故人が好きだった料理や、お菓子、飲み物を、仏壇にお供えしたり、ご家族で一緒に食べてみてはいかがでしょうか。
「お父さんが好きだった卵焼き、今日も美味しくできたよ」
「おばあちゃんの作ってくれたおはぎ、また食べたかったな」
そうした日常のささやかな瞬間に、故人の存在を身近に感じることができます。
2. 故人の思い出の品を整理する
遺品整理は、故人との思い出を振り返る大切な時間です。
遺品整理と聞くと、大変な作業だと感じるかもしれません。
しかし、故人の愛用していたものを一つひとつ手に取り、思い出話に花を咲かせる時間を持つことで、悲しみだけでなく、たくさんの感謝の気持ちが湧いてくるはずです。
もし、ご自身で遺品整理をすることが難しい場合は、専門の業者に依頼するという方法もあります。
3. 遺品整理を専門業者に依頼する
遺品整理専門の業者に依頼すれば、専門のスタッフが丁寧に対応してくれるため、ご家族の負担を大きく減らすことができます。
特に、故人が残されたものがたくさんある場合や、遠方に住んでいてなかなか実家に帰れない、という方にとって、遺品整理業者の存在は心強いものです。
ご遺族のお気持ちに寄り添い、一つひとつ丁寧に作業を進めてくれる業者を選ぶことが大切です。
故人様のお部屋に残された大切な品々を、丁寧に整理してくれる【遺品整理専門 ライフリセット】のようなサービスを利用するのも、一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。
故人との最後の「お片付け」を、プロの力を借りて、心の負担なく進めていくことができます。
葬儀後の感謝の気持ちを伝える「香典返し」
お葬式では、多くの方からお香典をいただきます。その感謝の気持ちを伝えるのが「香典返し」です。
香典返しは、四十九日の法要を終えた後に贈るのが一般的です。
贈り物のマナーと選び方
香典返しには、いくつか守るべきマナーがあります。
・金額の目安: いただいたお香典の3分の1から半額程度が目安とされています。 ・品物: 消え物(洗剤、石鹸、お茶、コーヒー、海苔など)や、商品券、カタログギフトなどが選ばれることが多いです。 ・のし: 「志(こころざし)」や「満中陰志(まんちゅういんし)」と書かれた掛け紙(のし)を使います。
香典返しを選ぶ際、どのようなものを選べば良いか迷ってしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、【シャディギフトモール】のようなギフト専門サイトを利用するのが便利です。
豊富な品揃えの中から、予算や贈る相手に合わせて最適な品物を見つけることができますし、のし紙やメッセージカード、包装まで丁寧に手配してくれるので、安心して香典返しを贈ることができます。
シャディは1926年創業の老舗ギフト専門店なので、マナーについても相談できるのが心強いですね。
意外と知らない「喪服・礼服」のマナー
お葬式に参列する際、服装に迷う方も多いのではないでしょうか。
特に女性の場合、喪服のデザインや、小物の選び方など、気を配るべき点がたくさんあります。
・「自分の持っている喪服は、マナーに沿っているだろうか?」 ・「急な訃報で、手持ちの喪服がサイズアウトしていた」 ・「これから喪服を買うのはもったいない」
そんな時におすすめなのが、喪服のレンタルサービスです。
【Cariru BLACK FORMAL】は、デザインや質、マナーにこだわった上質な喪服をレンタルできるサービスです。
ジャケットやワンピースだけでなく、バッグ、サブバッグ、ネックレス、数珠、袱紗まで、必要なものがすべて揃ったフルセットも豊富に用意されています。
急なご不幸でも、16時までの注文で最短翌日午前中にお届け可能なので、お通夜や告別式にも安心して参列できます。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
まとめ:大切なのは「故人を想う心」
「清めの塩」は、日本の文化と神道の考え方が融合した慣習であり、その意味や必要性は、現代において変化しつつあります。
大切なのは、「清めの塩」を使うかどうか、という形式にこだわることではなく、故人との最期のお別れの時間を大切にし、故人を偲ぶ気持ちを持ち続けることです。
お葬式の準備から、その後の手続き、遺品整理、香典返しに至るまで、ご遺族には多くの負担がかかります。
しかし、一つひとつの出来事を故人への感謝の気持ちを込めて丁寧に行うことで、きっと心の整理をつけ、前を向いて歩き出すことができるはずです。
もし、葬儀やその後の手続きに関してご不安なことがあれば、いつでもご相談ください。
私の経験が、少しでも皆様のお力になれば幸いです。
【あわせて読みたい】
葬儀についてもっと詳しく知りたい方へ、こちらの記事も参考にしてみてください。