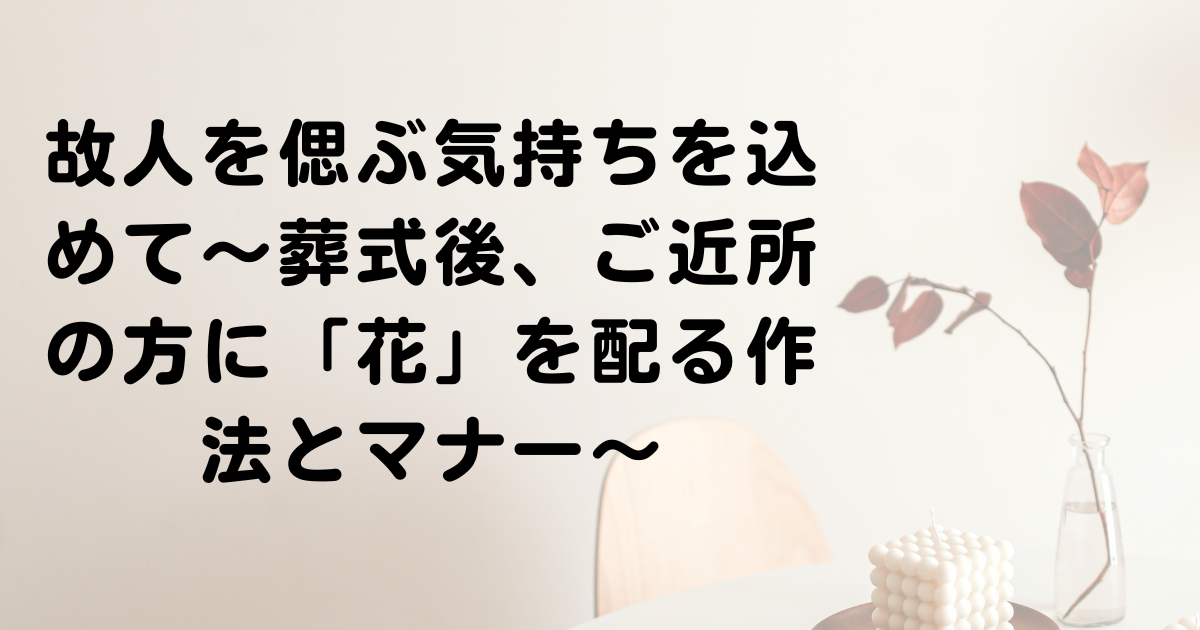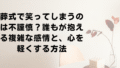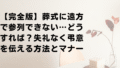はじめに:大切な方とのお別れを終えられた皆様へ
この度は、心よりお悔やみ申し上げます。大切な方を亡くされ、ご葬儀を無事に終えられたことと存じます。今は、お疲れがピークに達していらっしゃるのではないでしょうか。どうか、ご無理をなさらず、少しでもゆっくりとお過ごしいただけますように。
葬儀を終えた後も、ご遺族様にはさまざまな手続きやご挨拶が待っています。その一つに、故人様と生前親しくしてくださったご近所の方々へのご挨拶があります。
「葬式後、近所の方にお花を配ると聞いたけれど、どうすればいいの?」 「花を配るタイミングは?どんな花を選べばいいの?」 「そもそも、配るべきものなの?」
きっと、そうした疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご近所の方へのご挨拶は、故人様が地域で築き上げてきたご縁を、ご遺族様が引き継いでいく大切な作法です。
このブログでは、元葬儀社プランナーであるKeisukeが、ご近所の方に葬式でいただいた花を配る際のマナーや、その意味について、わかりやすく丁寧にご説明します。
プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
葬儀で使われた花を近所に配る作法:その意味と背景
大切な故人様をお見送りする葬儀は、多くの場合、ご家族や親しい方々だけでなく、ご近所の方々にも支えられて成り立ちます。特に昔からの風習が色濃く残る地域では、ご近所の方が葬儀のお手伝いや、様々な面でご協力くださることが少なくありません。
そのようなお気持ちに対し、ご遺族様が感謝の気持ちを表す方法の一つとして、「葬式 花 近所に配る」という習慣があります。これは、単に余った花を配るという行為ではありません。そこには、故人様がこの世に残した「縁」を、ご近所の方々と分かち合い、感謝を伝えるという深い意味が込められています。
故人様がお世話になった感謝、そして「これからもどうぞよろしくお願いいたします」という、ご遺族様からのご挨拶の意味も含まれています。
では、なぜ「花」なのでしょうか。花は、故人様を偲ぶ気持ちの象徴であり、故人様を華やかに飾り、弔いの心を表現するために使われます。葬儀を終え、その場を飾った花を分かち合うことは、「故人様を偲ぶ気持ちを共有する」という、温かい心の交流でもあるのです。
また、ご葬儀の祭壇を飾る花は、故人様の旅立ちを美しく彩るために、丁寧に選ばれたものです。それを「おすそ分け」することで、ご近所の方々にも、故人様との最後の別れの場を少しでも感じていただく機会になるという考え方もあります。
この作法は、地域によって慣習が異なり、行う・行わないの判断も様々です。しかし、大切なことは、形式に囚われることではなく、故人様を想い、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えるという、その「心」です。
ご自身の地域の慣習や、ご近所の方々との関係性を考慮しながら、この温かい作法について考えてみましょう。
葬式で使われた花を配るときの「時期」と「タイミング」
葬儀を終え、ご自宅に戻られた後、いつ頃にご近所の方に花をお配りすれば良いのでしょうか。ここでは、そのタイミングについてお話しします。
1. 葬儀を終えた「当日中」
最も一般的なタイミングは、葬儀を終えた当日の夕方から夜にかけてです。ご近所の方がお仕事などから帰宅され、ご自宅にいらっしゃる時間帯を狙って伺うのが良いでしょう。
このタイミングで配る利点は、葬儀の余韻が残る中で、感謝の気持ちを伝えることができる点です。また、花もまだ鮮やかで美しい状態を保っています。ご近所の方も、葬儀に参列されたり、遠くから見守ってくださったりと、故人様を偲ぶお気持ちがまだ心の中に残っていることでしょう。その気持ちに寄り添うように、お花をお渡しすることが大切です。
ただし、ご遺族様は、ご葬儀の疲れが最も出やすい時期でもあります。無理をしてまでこのタイミングにこだわる必要はありません。ご自身の体調を第一に考えて行動しましょう。
2. 葬儀から「数日以内」
葬儀当日が難しかった場合は、翌日、もしくは数日以内に伺っても失礼にはあたりません。ご近所の方も、ご遺族様の状況を察してくださることでしょう。
この場合も、お相手がご在宅の時間帯を見計らって伺うことが大切です。事前に「少しお花をお持ちしたいのですが、ご都合はいかがでしょうか?」と、電話などで確認してから伺うのがより丁寧な対応となります。
3. 「四十九日」や「納骨」のタイミングで
最近では、核家族化や地域の人間関係の変化から、葬儀後のご近所付き合いも様変わりしています。もし、葬儀直後に花を配ることが難しかったり、地域的な慣習が薄れている場合は、四十九日の法要や納骨のタイミングで、改めてご挨拶に伺う際に、何か別の形で感謝を伝えるという方法も考えられます。
例えば、故人様が生前好きだったお菓子などをお持ちすることも、感謝の気持ちを伝える一つの方法です。
大切なのは、「時期」や「タイミング」に縛られすぎることなく、ご遺族様が無理のない範囲で、心からの感謝を伝えることです。
葬儀で使われた花を近所に配る際の「花の選び方」と「渡し方」
では、実際にどのような花を選び、どのようにしてお渡しすれば良いのでしょうか。
1. 花の選び方
葬儀後にお配りする花は、主に「祭壇を飾った花」の中から、まだ美しい状態を保っているものを選びます。
- 1. 菊、百合、カーネーションなどの花が一般的です。 葬儀では、白や淡い色の花が使われることが多いです。お渡しする際は、これらの花を数本ずつ、小さな束にしてお渡しするのが良いでしょう。
- 2. 見た目を整えることも大切です。 茎の部分が傷んでいないか、花びらに傷みがないかなどを確認し、少しでも元気で美しい状態のものを選びましょう。
- 3. 持ち帰りやすいように工夫しましょう。 花束を小さなビニール袋に入れたり、新聞紙で包んであげたりすると、お相手も持ち帰りやすくなります。
- 4. 造花やプリザーブドフラワーは避ける。 葬儀で使われた生花を配ることが一般的です。造花などを配る慣習はほとんどありません。
2. 渡し方のマナー
- 1. 一軒一軒、直接お伺いする。 インターホンを押して、ご自身が直接お渡しすることが大切です。集合住宅の場合は、玄関先で顔を合わせてお渡ししましょう。
- 2. 感謝の気持ちを伝える言葉を添える。 花をお渡しする際は、「この度は、大変お世話になりました。故人も、皆様に見送っていただけて喜んでいると思います。ささやかではございますが、葬儀で使われたお花を少しおすそ分けさせてください。どうぞ、お仏壇にお供えいただければ幸いです」などと、感謝の気持ちと今後のご挨拶を伝えましょう。
- 3. 渡す範囲について。 故人様が生前特にお世話になっていた方、葬儀でお手伝いをしてくださった方、近隣にご挨拶すべき方々など、渡す範囲を決めておくと良いでしょう。
- 4. 弔事に関するお返しは不要です。 花を受け取った側から「何かお返しを」と言われることがあるかもしれませんが、「お気持ちだけで結構です」と丁寧にお伝えしましょう。
葬儀後のご挨拶〜花を配る以外の選択肢〜
地域によっては、「葬式で使われた花を配る」という習慣がない場合もあります。そのような場合や、ご遺族の負担を考慮して、別の形でのご挨拶を検討するのも良いでしょう。
例えば、故人様が生前お好きだったお菓子や、日持ちするお品物など、ご挨拶の品としてお渡しすることも考えられます。その際も、感謝の気持ちを込めた言葉を添えることが大切です。
また、ご近所へのご挨拶は、故人様が遺された「縁」をつなぐ大切な機会です。ご自身が今後もその地域で暮らしていく上で、良好な関係を築いていくための第一歩にもなります。
お葬式に関する疑問や不安、ありませんか?
大切な方を亡くされたばかりのご遺族様は、葬儀後の様々な手続きや、これからの生活に対する不安など、心身ともに大変な時期を過ごされています。特に、お香典返しなど、マナーや作法が気になることも多いでしょう。
お香典返しについては、こちらのブログ記事で詳しく解説しています。ご興味があればぜひご一読ください。
また、葬儀を終え、ご自宅での供養の準備を始める方もいらっしゃるかもしれません。その際、故人様が残された品々の整理、いわゆる遺品整理についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
「何をどこから手をつければいいのかわからない」 「自分たちだけでは、とても整理しきれない」 「故人の思い出の品を、どうすればいいのか…」
遺品整理は、ご遺族様にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となります。そんな時は、専門の業者に相談するという選択肢もあります。専門業者に依頼することで、故人様を偲びながら、丁寧に、そしてスムーズに整理を進めることができます。
私たち家族も、父を亡くした際、遺品整理に大変苦労しました。慣れない作業に加え、故人の思い出の品に触れるたびに感情が揺さぶられ、なかなか作業が進まなかったことを覚えています。そんな時、プロの力を借りることで、心の整理もつき、前向きな気持ちで故人を偲ぶことができました。
もし、遺品整理でお困りでしたら、一度専門の業者に相談してみてはいかがでしょうか。
遺品整理専門【ライフリセット】は、故人様のお部屋に残された遺品や不要物を、ご遺族様の心に寄り添いながら丁寧に整理してくれるサービスです。生前整理のご相談もできるので、ご自身の終活を考えている方にもおすすめです。
葬儀後の様々な手続きとご挨拶
ご葬儀を終えた後も、ご遺族様には様々な手続きやご挨拶が待っています。今回は、その中でも特に重要となる「お香典返し」について、もう少し詳しくお話ししましょう。
お香典返しの基本
お香典返しは、葬儀の際にいただいたお香典に対するお礼として贈る品物のことです。いただいた金額の半額から3分の1程度の品物を贈るのが一般的とされています。
- 品物の選び方:
- 消えもの:お茶、コーヒー、お菓子、石鹸、洗剤など、使ったり食べたりするとなくなるものが選ばれることが多いです。「不幸が後に残らないように」という意味が込められています。
- カタログギフト:贈る相手が自由に品物を選べるため、年代や好みを問わず喜ばれることが多いです。最近は、お香典返しの定番となりつつあります。
- 時期:
- 当日返し:葬儀当日に、お香典をいただいた方全員に一律の品物を渡す方法です。
- 忌明け返し:四十九日の法要を終えた後、いただいた金額に応じてお返しを贈る方法です。
お香典返しを贈る際は、ご挨拶状を添え、故人様が旅立ったこと、そしてご厚情への感謝を伝えることが大切です。
まとめ:大切なのは「お気持ち」を伝えること
今回は、葬式 花 近所に配るという習慣を中心に、葬儀後のご挨拶についてお話ししました。
故人様を大切に想い、ご近所の方々への感謝の気持ちを伝えるという、この温かい作法は、故人様が遺してくれた「ご縁」を、ご遺族様が引き継いでいく大切な儀式でもあります。
形式に囚われすぎることなく、ご自身の地域の慣習や、ご近所の方々との関係性を考慮しながら、無理のない範囲で心を込めて行うことが何よりも大切です。
そして、ご葬儀後も様々な手続きが待っています。どうか、ご無理なさらず、一つずつゆっくりと進めていってください。
もし、葬儀の準備段階で、どこに相談したらいいのか迷われたり、信頼できる葬儀社を探すことに不安を感じたりする方がいらっしゃいましたら、ぜひ専門のサービスを活用することをおすすめします。
例えば、【安心葬儀】は、東証プライム上場企業が運営する、全国7000以上の葬儀社から最適な葬儀社を比較検討できるサービスです。人生で何度も経験するものではない葬儀だからこそ、後悔しないお見送りのために、時間がない中でも複数の葬儀社の見積もりを比較できることは、大きな安心につながります。
これからも、このブログでは、皆様が「後悔しないお別れ」を迎えられるよう、心を込めて情報をお届けしていきます。
何かご不明な点がありましたら、お気軽にお声がけください。