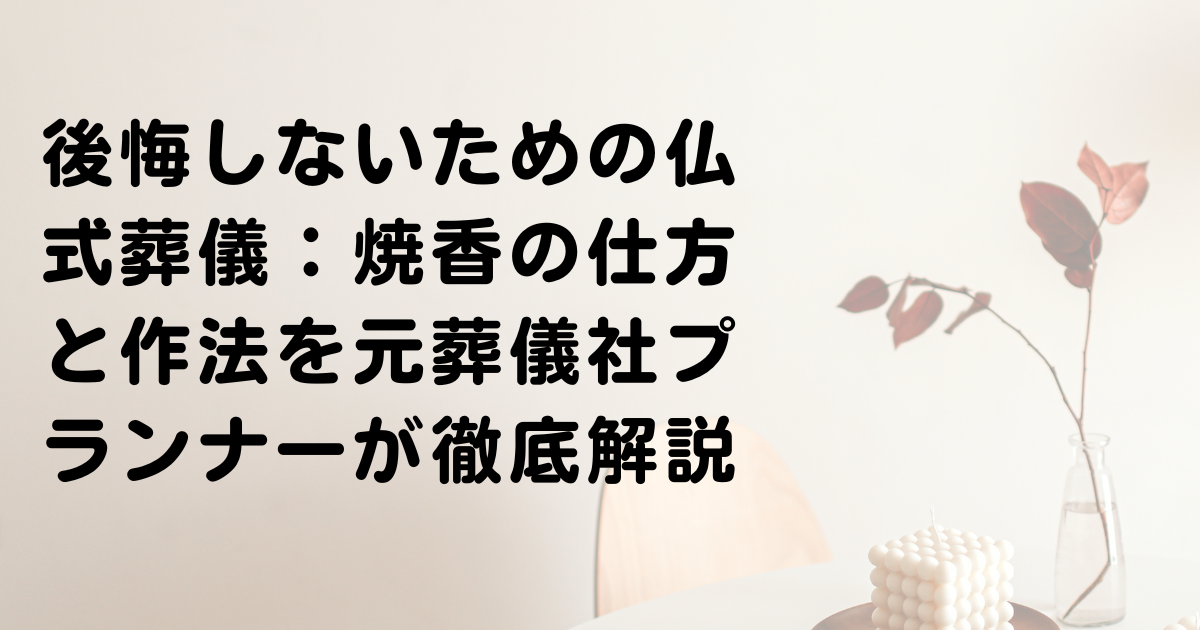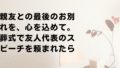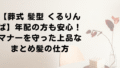はじめまして。元葬儀社プランナーのKeisukeです。私は12年間、葬儀の現場で800件以上のご葬儀に立ち会ってきました。その中で、ご高齢の方から若い方まで、本当に多くの方が「お焼香の仕方」について不安や疑問を抱えていらっしゃるのを目の当たりにしてきました。
「お焼香って、どうやるのが正解なの?」 「抹香を何回つまめばいいの?」 「順番が分からなくて、いつもドキドキしてしまう」
こういった声は、葬儀の現場では日常茶飯事でした。
ご葬儀は、故人様との最期のお別れをする大切な儀式です。そんな厳粛な場で、作法に気を取られてしまい、故人様と向き合う時間が少なくなってしまうのは、とても残念なことです。
この記事では、ご高齢の方にも分かりやすいように、仏式葬儀におけるお焼香の仕方と、その意味、そして作法について、どこよりも丁寧に解説していきます。葬儀の作法は宗派によって違いがあるため、代表的な宗派のお焼香の回数もまとめました。
人生経験の豊富な読者の皆様には、すでに様々な知識をお持ちのことと存じますが、ご自身の再確認のため、また、若いご家族に教える際の参考にしていただければ幸いです。
そして、この記事を読んで、もしもご自身の終活や、ご家族の葬儀について具体的な不安が芽生えたなら、ぜひお気軽に相談できる場所を見つけておくことも大切です。
なぜ、お焼香をするのでしょうか?その深い意味を理解する
お焼香の作法を学ぶ前に、まずは「なぜお焼香をするのか」という、その根本的な意味について考えてみましょう。意味を理解することで、ただ作法を真似るだけでなく、より心から故人様を偲ぶことができます。
お焼香は、仏教における大切な供養のひとつです。
1. 故人様を供養し、仏様を供養する お線香やお香の香りは、仏様の食事であると考えられています。そのため、お焼香は、故人様の霊魂を慰め、仏様を敬うための大切な供養となります。
2. 自身の心身を清める お香には、心を落ち着かせ、身を清める力があるとされています。お焼香を行うことで、故人様と対面する前に、自分の心身の穢れを払い、心を鎮めてから故人様と向き合うことができるのです。
3. 空間を清める お香の香りは、故人様を弔う場所の邪気を払い、清らかな空間を作り出す役割も持っています。
このように、お焼香は単なる儀式ではなく、故人様への供養、自分自身の心の準備、そして空間の浄化という、深い意味が込められた神聖な行為なのです。
この深い意味を心に留めてお焼香を行うことで、より一層、故人様への感謝の気持ちや、安らかな旅立ちを願う心が伝わることでしょう。
焼香の基本的な流れを画像で解説:誰でもできる「正しい作法」
それでは、いよいよ具体的なお焼香の仕方について見ていきましょう。ここでは、立礼焼香(椅子席での焼香)を例にご説明します。
- 順番が来たら、祭壇へ向かう ご自分の順番が来たら、祭壇の前に進みます。祭壇の手前で、遺族に一礼(座っている場合は、立ち上がって会釈)します。
- 祭壇の前で一礼 焼香台の前に来たら、故人様の位牌や遺影に向かって合掌し、一礼します。
- 焼香をあげる (1)抹香を右手の親指、人差し指、中指の3本で軽くつまみます。 宗派によっては、つまむ回数が決まっていますが、一般的には1〜3回です。回数については後ほど詳しく解説します。 (2)つまんだ抹香を、目の高さまで捧げ持ちます(「押しいただく」と言います)。 この時、故人様への感謝や冥福を祈る気持ちを込めます。 (3)香炉の炭の上に、抹香を静かに落とします。
- 再び合掌し、一礼する 焼香が終わったら、故人様の位牌や遺影に向かって合掌します。心の中で「安らかにお眠りください」と、静かに故人様を偲びます。その後、一礼します。
- 遺族に一礼して席に戻る 祭壇を離れ、遺族に再び一礼(会釈)してから、自席に戻ります。
これで、一連のお焼香の流れは完了です。いかがでしょうか?一つ一つの動作には、故人様への敬意と、心を込めた供養の気持ちが込められています。
「回数がわからなくても、気持ちが大切」とよく言われますが、作法を知っていることで、ご自身の心も落ち着き、故人様と向き合う時間もより穏やかになるものです。
宗派別!お焼香の回数と作法の違いを徹底解説
「お焼香の回数は、宗派によって違う」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。知らない宗派のお葬式に参列した時、「何回つまめばいいんだろう?」と悩んでしまうのは当然のことです。
ここでは、日本の代表的な仏教宗派のお焼香の回数と作法の違いをまとめました。
天台宗(てんだいしゅう)
焼香の回数: 1回、または3回 作法: 天台宗では、お焼香の回数に厳密な決まりはありません。心を込めて1回、または3回抹香をくべます。3回の場合は、「仏・法・僧」の三宝を敬う意味が込められています。
真言宗(しんごんしゅう)
焼香の回数: 3回 作法: 真言宗では、3回のお焼香が一般的です。これは「身・口・意」の三密を清めるという意味があります。 1回目:故人様を供養する 2回目:ご自身の心身を清める 3回目:仏様を敬う 一つ一つの動作に意味があることを知っていると、より厳粛な気持ちでお焼香に臨むことができますね。
浄土宗(じょうどしゅう)
焼香の回数: 特に決まりなし 作法: 浄土宗では、お焼香の回数に特別な決まりはありません。心を込めて1回から3回、抹香をくべます。
浄土真宗(じょうどしんしゅう)
焼香の回数: 1回 作法: 浄土真宗では、お焼香の回数は1回です。**「押しいただかずに、そのままくべる」**という作法が特徴です。これは、「仏様から授かった香を、そのまま仏様にお供えする」という意味合いが込められています。 浄土真宗の葬儀に参列する際は、この点に注意しましょう。
臨済宗(りんざいしゅう)
焼香の回数: 1回 作法: 臨済宗では、お焼香の回数は1回が基本です。ただし、抹香をくべる前に、右手の親指、人差し指、中指でつまんだ抹香を、左手の掌に一旦乗せてから、香炉にくべるという、少し独特な作法があります。
曹洞宗(そうとうしゅう)
焼香の回数: 2回 作法: 曹洞宗では、お焼香の回数は2回です。 1回目:**「主香(しゅこう)」と呼ばれ、抹香をくべてから押しいただきます。 2回目:「従香(じゅうこう)」**と呼ばれ、押しいただくことなく、そのままくべます。 この2回のお焼香には、「仏様と故人様への供養」という意味が込められています。
日蓮宗(にちれんしゅう)
焼香の回数: 1回、または3回 作法: 日蓮宗では、お焼香の回数に厳格な決まりはありませんが、心を込めて1回から3回、抹香をくべます。
宗派ごとの違いを簡単に覚えるコツ
様々な宗派の作法をご紹介しましたが、「すべて覚えるのは大変だ」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。
もし、参列した葬儀の宗派が分からない場合は、**「1回、または3回」**のお焼香が一般的です。迷った時は、まず1回くべ、周りの方が何回くべているかをそっと確認するのも良い方法です。一番大切なのは、故人様を想う気持ちですから、回数に気を取られすぎず、心を込めてお焼香をあげてください。
お焼香の種類と、その作法
お焼香には、座って行う「座礼焼香」や、香炉が回ってくる「回し焼香」など、いくつかの種類があります。それぞれの作法についても確認しておきましょう。
1. 立礼焼香(りつれいしょうこう)
最も一般的なお焼香の方法です。椅子席で行われ、焼香台の前まで進んで行います。 作法:
- 自分の順番が来たら、焼香台の前まで進み、遺族と故人様に一礼します。
- 焼香台の前で一礼し、抹香を宗派の回数に従ってくべます。
- 焼香後、合掌し、一礼します。
- 遺族に一礼して自席に戻ります。 先ほど詳しくご説明した通り、この方法が一般的です。
2. 座礼焼香(ざれいしょうこう)
畳の部屋などで行われるお焼香です。 作法:
- 自分の順番が来たら、焼香台の手前まで進み、遺族と故人様に向かって正座で一礼します。
- 膝行(しっこう)と呼ばれる、膝を立てたまま移動する作法で、焼香台まで進みます。
- 焼香台の前で一礼し、抹香を宗派の回数に従ってくべます。
- 焼香後、合掌し、一礼します。
- 再び膝行で元の位置に戻り、遺族に一礼して着席します。 畳の部屋での作法に不安がある方は、周囲の方の動きを参考にすると良いでしょう。
3. 回し焼香(まわししょうこう)
広い会場や、参列者が多い場合などに行われるお焼香です。香炉が、参列者の席を回ってきます。 作法:
- 香炉が自分の前に回ってきたら、受け取ります。
- 自分の膝の上に香炉を乗せるか、座ったまま行います。
- 故人様の位牌や遺影の方を向き、一礼します。
- 抹香を宗派の回数に従ってくべます。
- 焼香後、合掌し、一礼します。
- 香炉を次の人に回します。 回し焼香は、椅子に座ったままで行えるため、ご高齢の方や足腰の弱い方にも優しい方法です。
お焼香の服装マナー:大人のたしなみとして知っておきたいこと
お焼香の作法だけでなく、服装もまた、故人様への敬意を示す大切なマナーです。
「喪服」と聞くと、難しく考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、基本さえ押さえておけば、慌てることはありません。
男性の喪服
- ブラックスーツ: 黒無地のスーツ。シングルでもダブルでも可。
- Yシャツ: 白無地で、レギュラーカラーまたはワイドカラー。
- ネクタイ: 黒無地。光沢のないもの。
- 靴下・靴: 黒色。革靴は光沢のないものを選びます。
女性の喪服
- ブラックフォーマル: 黒のワンピース、アンサンブル、スーツ。
- インナー: 黒無地で、襟ぐりが開きすぎていないもの。
- ストッキング: 黒の無地。
- 靴: 黒のパンプス。ヒールは3〜5cm程度で、太めのものが良いでしょう。
葬儀の服装で特に注意したいポイント
- アクセサリー: 結婚指輪以外は、基本的に外します。どうしてもつけたい場合は、一連の真珠のネックレスやイヤリング、一粒のダイヤの指輪などに限られます。
- バッグ: 黒無地で、光沢のない布製や革製のものが良いでしょう。
- 数珠: 仏式のご葬儀に参列する際は、数珠は必須アイテムです。片手念珠、略式数珠など、宗派を問わず使えるものを用意しておきましょう。
もし、急な訃報で手持ちの喪服がない場合や、体型が変わってしまって手持ちの喪服が着られなくなった場合はどうすればいいでしょうか?
実は、最近はインターネットで高品質な喪服をレンタルできるサービスが充実しています。特に、デザインや質にこだわりたい方、サイズが合わない方には、**【Cariru BLACK FORMAL】**のようなサービスがおすすめです。
【Cariru BLACK FORMAL】では、人気ブランドのブラックフォーマルを、購入するよりも手軽な価格で借りることができます。 「必要な時に必要なものが全て揃う」ように、ジャケット・ワンピース・バッグ・数珠まで、フルセットでレンタルできるプランも豊富です。 24時間いつでも申し込みが可能で、急な訃報にも対応できるよう、16時までの注文で最短翌日午前中には届けてくれます。
急な葬儀で慌てないためにも、一つ持っておくと安心なサービスですね。ご自身の服装だけでなく、ご家族の分も合わせて準備しておくと、いざという時に慌てずに済みます。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
葬儀全般に関するご不安を解消するための情報と、信頼できるサービス
お焼香の作法や服装マナーについて解説してきましたが、ご葬儀に関する不安は、それだけではないはずです。
- 「ご葬儀の費用はどれくらいかかるの?」
- 「どの葬儀社に頼めばいいのか分からない」
- 「葬儀後の手続きが複雑そうで不安」
私も葬儀社のプランナーとして働いていた経験から、これらの不安がご遺族にとってどれほどの負担になるか、痛いほど理解しています。
特に、葬儀社選びは非常に重要です。人生で何度も経験するものではなく、知識がない中で、故人様の逝去後、わずか数時間以内に決めなければならないことがほとんどです。費用も高額になりがちで、葬儀社によって品質にも大きな差があります。
そんな時に頼りになるのが、【安心葬儀】のようなサービスです。
【安心葬儀】は、東証プライム上場企業の株式会社エス・エム・エスが運営する、全国7,000社以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を紹介してくれる相見積もりサービスです。
- 透明性の高い料金体系: 見積もりを比較することで、不透明な費用をなくし、適正な価格で葬儀を執り行えます。
- 複数の葬儀社から比較検討できる: 時間がない中でも、複数の葬儀社のプランや費用を比較することで、ご自身に最適な葬儀社を見つけることができます。
- 専門の相談員がサポート: 葬儀に関するあらゆる疑問や不安に、専門の相談員が丁寧に答えてくれます。
私も現役時代に感じていた「情報の格差」という問題は、このようなサービスを利用することで大きく解消されます。終活を考えているご本人様、またはご家族の葬儀を検討されている方は、一度検討してみることをおすすめします。
葬儀後のお返しや遺品整理、生前整理について
ご葬儀が終わると、今度は「香典返し」や「遺品整理」といった、次なる大きな課題が待っています。
香典返し 香典返しは、香典をいただいた方へのお礼として、お葬式から四十九日の法要後を目安に贈るのが一般的です。 何を贈れば良いのか、どのくらいの金額のものを贈れば良いのか、悩んでしまう方も多いでしょう。 香典返しに関する詳しいマナーや選び方については、以下の記事も参考にしてみてください。
- 【元葬儀社プランナーが解説】葬式後の香典返し|失礼のない贈り方・選び方ガイド
お返し選びに迷った時は、【シャディギフトモール】のようなギフト専門店の利用がおすすめです。シャディギフトモールは、1926年創業のギフト専門店『シャディ株式会社』の公式通販サイトで、様々な用途に対応できる1万点以上の商品を揃えています。
遺品整理・生前整理 故人様がお部屋に残した品々の整理も、ご遺族にとって大きな負担となります。 特に、生前整理を希望されるご高齢の方は年々増えてきています。 「まだまだ元気だけど、いざという時のために身の回りのものを整理しておきたい」 「子どもたちに迷惑をかけたくない」 このようなお気持ちから、ご自身で生前整理をされる方も多いです。
遺品整理や生前整理を専門に行う【ライフリセット】のようなサービスは、そうした方々にとって大きな助けとなります。 遺品整理専門のスタッフが、故人様のお部屋の整理・片付けを丁寧にサポートしてくれます。遺品をただ処分するのではなく、買取や供養なども行ってくれるため、故人様を大切に想う気持ちにも寄り添ってくれます。
遺品整理だけでなく、生前整理としてご自身のお部屋を整理したいという方も増えており、幅広い年代の方が利用しています。
まとめ:大切なのは「故人様を想う心」
この記事では、仏式葬儀におけるお焼香の仕方と、宗派別の作法、そして葬儀にまつわる様々なマナーについて解説してきました。
お焼香は、単なる儀式ではありません。故人様を供養し、感謝の気持ちを伝えるための、尊い行為です。宗派による作法の違いはありますが、一番大切なのは、故人様を心から偲ぶ気持ちです。
もし、作法がわからなかったり、不安を感じたりしたときは、周りの方と同じように振る舞うだけでも大丈夫です。故人様との最期のお別れの時間を、心穏やかに過ごすことこそが、何よりも大切なことなのです。
この記事が、読者の皆様のご不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。
終活や、ご家族の葬儀、そして葬儀後のことまで、私たちは避けて通れない問題と向き合わなければなりません。しかし、事前に知識をつけ、信頼できるサービスを知っておくことで、いざという時に慌てず、後悔のない選択をすることができます。