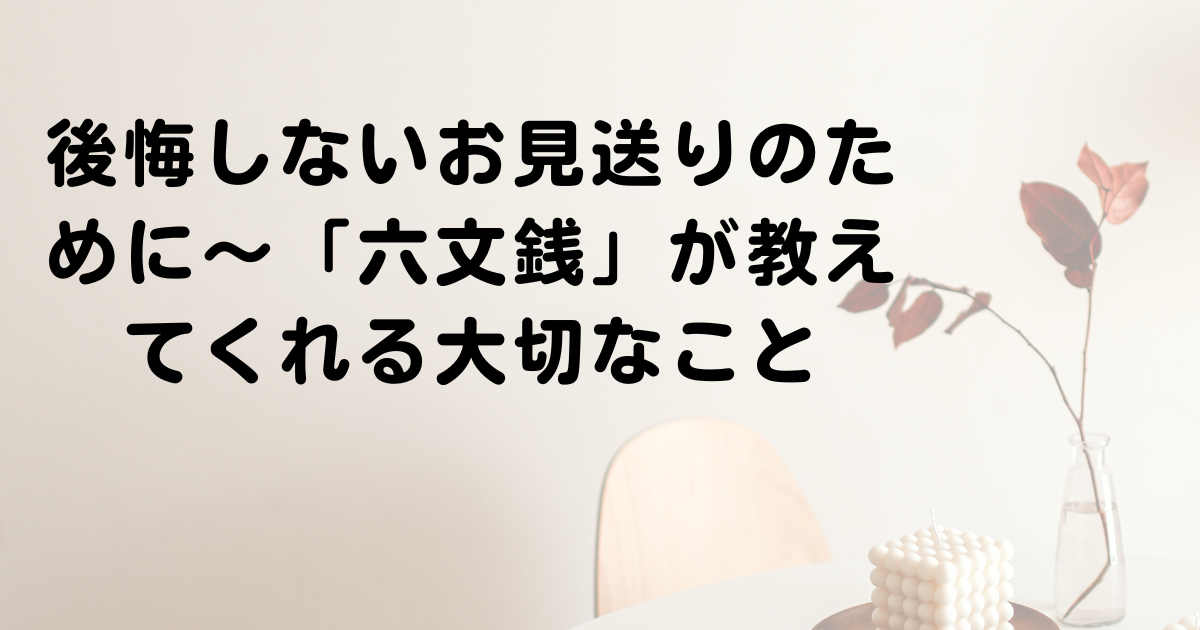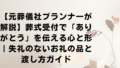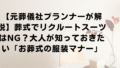はじめに:大切な方との最期の別れに際して
人生の終焉に立ち会うことは、誰にとってもつらく、心細い経験です。特に、突然の訃報に接したとき、私たちは悲しみに暮れる間もなく、葬儀という大きな出来事に直面します。慣れない手続きや、さまざまな決断を迫られる中で、「これで良かったのだろうか」と、後から後悔の念に駆られる方も少なくありません。
私自身、20代で父を亡くした際、まさに右も左もわからず、途方に暮れました。葬儀社の担当者の方に言われるがままに物事を進め、後になって「もっとこうすれば良かった」と思うことが多々ありました。その経験から、「同じように苦しむ方を少しでも減らしたい」という思いで、葬儀業界に飛び込み、今日までこのブログで情報をお届けしています。
今回は、葬儀の際に耳にすることがあるけれど、その本当の意味を知る機会は少ない「六文銭(ろくもんせん)」について、深く掘り下げていきたいと思います。ただの風習ではなく、そこには故人を想う遺族の深い祈りが込められています。この知識が、皆様の大切な方とのお別れを、心穏やかなものにする一助となれば幸いです。
そもそも「六文銭」とは?
「六文銭」と聞いて、まず頭に浮かぶのは、戦国時代の武将・真田家の家紋ではないでしょうか。旗印に掲げられた六つの銭は、「いつでも死ぬ覚悟がある」という不惜身命(ふしゃくしんみょう)の精神を表すものとして有名です。しかし、葬儀における六文銭は、真田家の家紋とは少し異なる、より古くから伝わる意味を持っています。
葬儀で用いられる六文銭とは、故人の棺に納める副葬品の一つです。具体的には、亡くなった方が冥土へ旅立つ際に必要となる「三途の川の渡し賃」とされています。
この世からあの世へと渡る三途の川には、渡し守がいると考えられており、その船に乗るための運賃が六文銭なのです。もし渡し賃を持っていなければ、奪衣婆(だつえば)と懸衣翁(けんえおう)という二人の番人に衣服を剥ぎ取られてしまう、という恐ろしい言い伝えもあります。
ですから、ご遺族は、故人が無事に旅路を進めるようにと願いを込めて、この六文銭を旅支度の一つとして棺に納めてきたのです。
六文銭の由来と込められた想い
六文銭のルーツをさらに遡ると、仏教の教えにある「六道(ろくどう)」という考え方にたどり着きます。六道とは、私たちが死後、生前の行いによって生まれ変わるとされる6つの世界(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道)のことです。
この六つの世界を輪廻転生する私たちを、常に救ってくれるのが「六地蔵(ろくじぞう)」という仏様です。六文銭は、この六地蔵へのお賽銭、つまり「六道銭(ろくどうせん)」がもとになっているとも言われています。
時代とともに、この六道銭が三途の川の渡し賃という考えと結びつき、「六文銭」と呼ばれるようになりました。単なるお金ではなく、「どうか故人が迷わず、安らかに旅立てますように」という、残された家族の切なる願いが、六文銭には込められているのです。
現代の葬儀における「六文銭」の扱い
古くからの習わしである六文銭ですが、現代の葬儀では、本物の硬貨を棺に入れることはありません。これは、火葬の際に硬貨が燃え残ってしまい、火葬炉の故障の原因となるためです。
そのため、現代では紙に六文銭が印刷されたものや、木製の模造品を使用するのが一般的です。多くの葬儀社では、死装束(しにしょうぞく)の一部である頭陀袋(ずだぶくろ)に、すでに用意された模造の六文銭を入れてくれますので、ご遺族が特別に準備する必要はありません。
ただし、宗派や地域の慣習によっては、六文銭の風習がない場合もあります。特に浄土真宗では、亡くなった方はすぐに仏様になると考えられているため、死後の旅路という概念自体がなく、六文銭を入れないのが一般的です。もしご不安な点があれば、葬儀社の担当者の方に相談してみると良いでしょう。
葬儀という儀式が持つ「意味」を考える
六文銭の話は、故人の旅支度という風習を通じて、私たちが「葬儀」という儀式にどのような意味を見出してきたのかを教えてくれます。
葬儀は、単に亡くなった方を火葬する手続きではありません。それは、遺された家族が故人の死を受け入れ、悲しみを乗り越えるための、大切な区切りです。故人の好きだったものを棺に入れたり、お花でいっぱいにしてあげたりする行為も、六文銭と同じように、**「故人への最後の愛情表現」**と言えるでしょう。
費用だけではない「お葬式の本質」
葬儀と聞くと、その高額な費用を思い浮かべる方も多いかもしれません。確かに、十数万円から数百万円というまとまった費用がかかるため、経済的な負担は大きなものです。しかし、大切なことは「いかに費用を抑えるか」だけではありません。
「故人をどのような形で送ってあげたいか」、そして「自分たちが後悔しないお別れをするにはどうしたら良いか」を考えることこそが、最も重要なのです。
私の父の葬儀では、十分な知識がないまま、目の前の選択肢を漠然と決めてしまいました。後から考えれば、もっと父らしいお見送りができたのではないか、という後悔が残りました。
だからこそ、ご自身やご家族の「終活」として、事前に葬儀について知識を深めておくことは、とても価値のあることです。
例えば、葬儀社の選び方一つをとっても、選択肢はたくさんあります。大手から地域に根差した中小企業まで、費用やサービス内容、得意とする葬儀の形もさまざまです。
「逝去後、慌てて葬儀社を探すことになった」という話はよく聞きますが、時間がない中で、何社もの見積もりを比較検討するのは至難の業です。そんな時、複数の葬儀社から一度に見積もりを取れるサービスが非常に役立ちます。
葬儀に関する情報や全国の斎場・葬儀社を探せる【安心葬儀】 葬儀の相場やマナー、手続きなどの情報を豊富に提供しており、複数の葬儀社から一括で見積もりを取ることも可能です。東証プライム上場企業が運営しており、安心して利用できるのも大きなポイントです。もしもの時に備え、一度目を通しておくと良いでしょう。
このようなサービスを事前に知っておくだけでも、いざという時の安心感が全く違ってきます。
六文銭に見る「死後の世界」と向き合う心
六文銭の風習は、日本人にとって「死後の世界」が身近な存在であったことを示しています。私たちは、故人が旅立つ先のことを想像し、少しでも安らかであってほしいと願う心を持っていました。
現代では、宗教や死生観も多様化し、六文銭の風習を知らない方も増えました。しかし、故人への想いを形にするという心そのものは、今も昔も変わりません。
例えば、故人の好きだった音楽を流したり、愛用していた品を棺に入れたり。こうした行為は、まさに現代の六文銭と言えるのではないでしょうか。「故人のために何かしてあげたい」という気持ちを大切にすることが、私たち自身の心を癒し、前向きに生きる力にもなるのです。
六文銭と「終活」:人生の最期に備えること
六文銭の風習が、いつの時代も変わらず受け継がれてきたのは、人が死を前にしたときに抱く「不安」と「願い」に寄り添うものだからです。
私たちは、いつか来る「その日」のために、どのように準備すれば良いのでしょうか。
「終活」と聞くと、まだまだ先のことに感じる方もいるかもしれません。しかし、ご自身の最期をどう迎えるか、ご家族にどのような負担をかけたくないか、といったことを考えるのは、決して後ろ向きなことではありません。むしろ、残された時間をより豊かに生きるための、前向きな活動です。
終活には、遺言書の作成や財産整理、お墓のことなど、さまざまな項目がありますが、特に多くの方が悩まれるのが「遺品整理」です。
故人が残された品々には、たくさんの思い出が詰まっています。しかし、ご遺族にとっては、その整理が大きな負担となることも少なくありません。物理的な作業に加え、精神的なつらさも伴います。
もしご自身が、ご家族にそうした負担をかけたくない、とお考えであれば、**「生前整理」**という選択肢もあります。ご自身のペースで少しずつ身の回りのものを整理していくことで、ご家族の負担を減らすだけでなく、自身の人生を振り返る良い機会にもなります。
遺品整理専門【ライフリセット】 遺品整理や生前整理を専門とするプロフェッショナルなサービスです。ご家族が亡くなられた後の整理はもちろん、ご自身が元気なうちに整理を済ませておきたいという方にもおすすめです。専門のスタッフが丁寧に対応してくれるので、安心して任せられます。
遺品整理は、故人の想いを整理する大切な時間でもあります。一人で抱え込まず、プロの力を借りることも、時には必要です。
葬儀を彩る「形」の多様性
六文銭の他にも、葬儀にはさまざまな伝統や風習があります。それらはすべて、故人への敬意と、遺族の想いを形にするために存在します。
例えば、葬儀の服装もその一つです。
「お通夜は地味な平服でも良い」「お葬式には喪服を着るべき」といったマナーは、昔から受け継がれてきました。しかし、現代では葬儀の形式も多様化し、それに伴って服装のマナーも少しずつ変化しています。
昔ながらのしきたりを大切にするのも良いですが、故人の生前の希望や、遺族の気持ちを優先することも大切です。例えば、「お別れ会」のような形式であれば、平服で参列することもありますし、故人が好きだった色を取り入れたりすることもあります。
葬儀の服装については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご興味があればご覧ください。
喪服と「六文銭」が示す伝統の価値
さて、葬儀の服装、特に女性の喪服について考えてみましょう。
以前は、一張羅の喪服を一枚持っていれば良い、という考えが一般的でした。しかし、時代とともにデザインのトレンドも変わり、体型も変化します。また、急な訃報で「手持ちの喪服が合わない」「昔の喪服はデザインが古くて…」と悩む方も少なくありません。
そんな時、「喪服のレンタルサービス」は非常に便利な選択肢となります。
特に若い世代の方や、久しぶりに喪服を着る方にとっては、新しい喪服を購入するよりも経済的で、何より手軽です。
私が葬儀社にいた頃、喪服がなくて困っているというご相談をよく受けました。急なことでデパートに行く時間もなく、焦っているご遺族の姿を見て、レンタルの選択肢を提案したこともありました。
六文銭が故人の旅路の準備を助けるように、喪服のレンタルは、遺族が心穏やかに故人と向き合うための準備を助けてくれます。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
デザイン・質・マナーにこだわる方の喪服・礼服のレンタル【Cariru BLACK FORMAL】 弔事のマナーに沿って厳選された、質の高いブラックフォーマルをレンタルできるサービスです。人気ブランドの喪服も豊富に取り揃えられており、ジャケット、ワンピース、バッグ、数珠まで、必要なものが全て揃ったフルセットも選べます。ネットで手軽に申し込めるので、急な訃報にも安心です。
伝統的な喪服の価値を守りつつ、現代のニーズに合わせたサービスを利用することで、私たちは故人とのお別れの時間を、より心置きなく過ごすことができます。
故人を想う気持ちを伝える「香典返し」
葬儀後に行うことの一つに、「香典返し」があります。香典は、故人の冥福を祈り、ご遺族への気持ちを表すものです。それに対して、ご遺族が感謝の気持ちを込めて贈るのが香典返しです。
六文銭が故人への最後の贈り物であるように、香典返しは、私たちを支えてくれた方々への感謝の贈り物です。
香典返しにも、「半返し」という慣習や、「のし」の書き方、「時期」など、さまざまなマナーがあります。しかし、最も大切なのは、「感謝の気持ちを伝える」という心です。
以前、あるご遺族の方が、香典返しに悩んでいました。故人が生前お世話になった方々へ、感謝の気持ちを込めて、何か喜ばれるものを贈りたい、と。
そんな時、ギフト専門店のオンラインストアは、非常に便利な選択肢です。様々な価格帯の商品が揃っており、のしや包装も丁寧に手配してくれるので、安心して任せることができます。
【シャディ公式】内祝や、お返しも!ギフト専門店【シャディギフトモール】 創業1926年のギフト専門店です。香典返しはもちろん、内祝いや季節の贈り物まで、幅広い用途の商品を1万点以上取り揃えています。メッセージカードやのし紙、包装も無料なので、心のこもった贈り物を手軽に準備できます。
香典返しは、故人のご縁を大切に守っていく、最後の儀式とも言えるかもしれません。
終わりに:心穏やかに旅立ちを願うために
六文銭の風習から始まり、葬儀、喪服、香典返しと、お別れにまつわる様々なことを見てきました。
これらすべてに共通しているのは、「故人への想い」と、「遺された人々の心」を大切にするという精神です。
人生の最期を迎える時、大切な人がそばにいてくれること、そして、安らかな旅立ちを願ってくれること。これほど心強いことはありません。
私はこのブログを通じて、皆様が後悔のないお別れを迎えるための知識と、心の準備をお手伝いしたいと願っています。
今回ご紹介した六文銭や葬儀の風習は、昔ながらのしきたりかもしれません。しかし、その根底にあるのは、いつの時代も変わらない「故人への深い愛情」です。
もしもの時に備え、葬儀のこと、終活のこと、そしてご家族のこと、ぜひ一度じっくりと考えてみてください。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
この記事が、皆様にとって少しでもお役に立てれば幸いです。