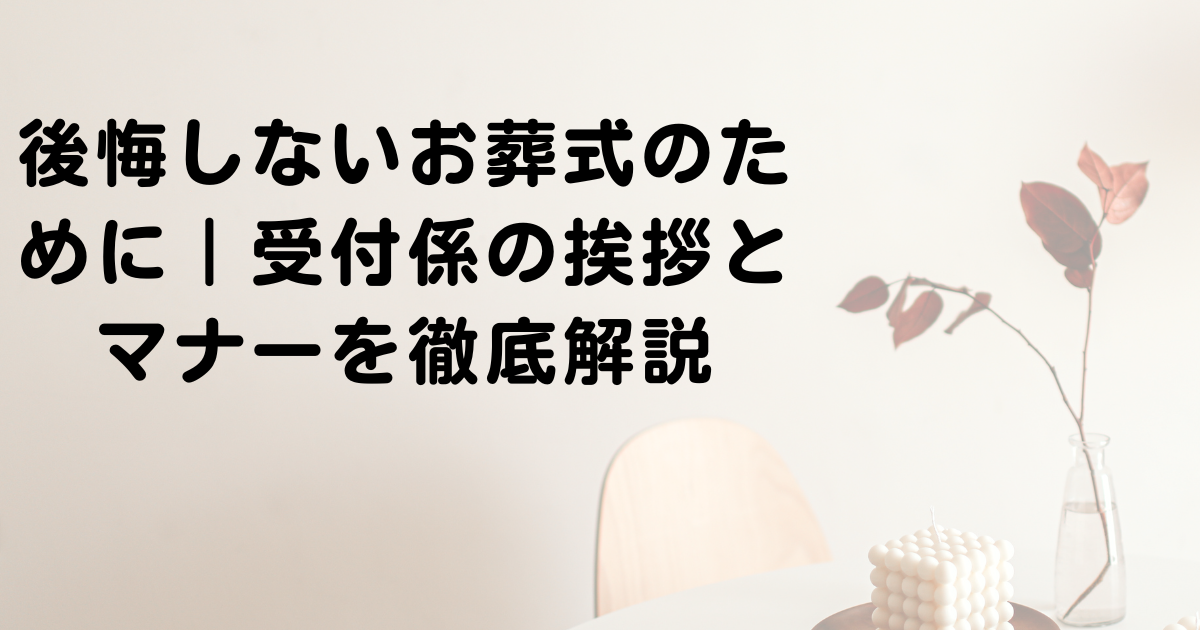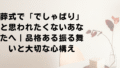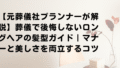こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに800件以上のご葬儀を担当させていただきました。右も左もわからないまま父を亡くし、葬儀で苦労した経験から、「同じ思いをする人を一人でも減らしたい」という一心でこの道に進みました。
現在は、ご家族との時間を大切にするため在宅でこのブログを運営しています。
お葬式は、多くの方にとって初めての経験であり、予期せぬ出来事の連続です。その中でも、ご遺族やご親族として「受付」を任されることは、大変重要な役割でありながら、多くの方が不安に感じられるのではないでしょうか。
「どんな挨拶をすればいいのか」「失礼のないようにするにはどうすればいいのか」
受付係は、弔問に訪れる方々が故人様と最後のお別れをするための、いわば「最初の窓口」です。参列される方への配慮と、ご遺族の気持ちを代弁する大切な役割を担っています。
この記事では、そんなお葬式の受付係を任された方が、自信をもって役割を果たせるよう、受付の挨拶から具体的なマナー、服装、準備まで、私がこれまでの経験で培ってきた知識を余すところなくお伝えします。
葬儀の受付係、その重要な役割
ご葬儀の受付係は、単に香典を受け取るだけの役割ではありません。故人様を偲び、ご遺族を想い、遠方から駆けつけてくださった方々への感謝の気持ちを伝える大切な役割を担っています。
受付係の対応一つで、弔問にいらした方々の故人様への想いや、ご遺族への心遣いの受け止め方が大きく変わってしまいます。
だからこそ、受付係を任された方は、「何から準備すれば良いのだろう」と不安に感じるかもしれません。しかし、ご安心ください。一つひとつの手順と、心構えをしっかりと知っておけば、どなたでも落ち着いて務めることができます。
まずは、受付係に求められる心構えから見ていきましょう。
受付係に求められる心構え
ご遺族から受付を頼まれた際は、故人様とご遺族の想いを胸に、責任を持って務めることが大切です。
1. 故人様とご遺族への敬意
受付係は、故人様を偲び、ご遺族に代わって弔問客をお迎えする立場です。故人様への敬意を払い、ご遺族に寄り添う気持ちを持つことが何よりも大切です。
2. 参列者への丁寧な対応
弔問にいらっしゃる方々は、故人様との思い出を胸に、遠方から時間をかけて来られる方も少なくありません。丁寧で、心温まる対応を心がけましょう。参列者一人ひとりに感謝の気持ちを伝えることが大切です。
3. 落ち着いた振る舞い
受付は、ご葬儀の顔となる場所です。たとえ慌ただしくても、落ち着いて、一つひとつの作業を丁寧に行うことが大切です。参列者が不安を感じないよう、冷静に対応しましょう。
受付係の役割は、受付の業務だけではありません。ご葬儀全体が滞りなく進むよう、他のスタッフやご親族と連携しながら、臨機応変に対応することも求められます。
ご葬儀の受付は、一人で任されることはほとんどなく、複数人で担当することが一般的です。役割分担を事前に決めておくことで、当日の混乱を避けることができます。
受付係の基本的な仕事内容
ご葬儀の受付係の仕事は、主に以下の通りです。
- 弔問客への挨拶:参列者がいらしたら、まずは丁寧な挨拶でお迎えします。
- 記帳のお願い:芳名録に、お名前、ご住所などを記入していただきます。
- 香典・供物のお受け取り:香典や供物を受け取り、お預かりします。
- 返礼品(会葬御礼品)のお渡し:弔問客に、お礼の品をお渡しします。
- 会場案内:式場や待合室、お手洗いなどの場所を案内します。
これらの業務をスムーズに進めるために、受付開始前に必ず受付周りの状況を確認し、必要なものが揃っているか確認しておきましょう。
【受付に備え付けられているもの】
- 芳名録(または名刺受け)
- 筆記用具(予備も用意しておきましょう)
- 香典盆
- 返礼品(会葬御礼品)
- 受付係の名札
- 会場案内図(ある場合)
- 弔電を預かるための用紙(ある場合)
- その他、宗教や地域の慣習によって必要なもの
これらが受付開始までに揃っているか、葬儀社のスタッフに確認しておくことが大切です。
受付での挨拶、具体的な言葉遣いとポイント
受付での挨拶は、参列される方への感謝の気持ちを込めて、簡潔に、丁寧に伝えることが大切です。
弔問客がいらしたら、まずは丁寧にお辞儀をしてお迎えします。
1. 一般的な挨拶の言葉
「本日はお忙しいところ、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。恐れ入りますが、こちらにご記帳をお願いいたします。」
記帳が終わったら、香典を受け取ります。
2. 香典をお受け取りする際の言葉
「お香典、ありがとうございます。故人もさぞ喜んでいるかと存じます。ありがとうございます。」
この時、「恐れ入ります」や「恐縮です」といった言葉を使うと、より丁寧な印象になります。
3. 返礼品をお渡しする際の言葉
「こちらはほんの心ばかりの品でございます。どうぞお受け取りください。」
返礼品を渡す際は、両手で丁寧に差し出すようにしましょう。
状況に応じた挨拶の言葉
状況によっては、上記以外の挨拶が必要になることもあります。
1. 弔電を預かる場合
「恐れ入りますが、弔電はこちらでお預かりいたします。」
弔電を預かった際は、差出人のお名前を控え、必ずご遺族に渡すようにしましょう。
2. 参列者が香典を辞退している場合
ご遺族によっては、香典を辞退される場合があります。その際は、失礼のないように丁寧にお断りする言葉を準備しておきましょう。
「ご厚意、誠に恐縮でございます。ただ、故人の遺志により、ご香典は辞退させていただいております。何卒ご理解くださいませ。」
香典辞退の旨を伝えられた際も、相手の厚意には感謝の気持ちを伝えることが大切です。
3. 参列者が旧知の仲の場合
久しぶりに会う親しい友人や知人が弔問にいらっしゃった場合でも、あくまで受付係としての立場をわきまえ、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
「お久しぶりです。お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。」
受付係は、ご遺族の代わりに弔問客をお迎えする立場です。個人的な感情を出すことは控え、丁寧な対応に徹することが大切です。
葬儀受付のマナーと注意点
受付係は、挨拶だけでなく、立ち居振る舞いや服装にも細やかな配慮が必要です。
1. 服装と身だしなみ
服装は、男女ともに喪服が基本です。
- 男性:黒のスーツ、白のワイシャツ、黒のネクタイ、黒の靴下、黒の革靴。
- 女性:黒のワンピースやアンサンブル、黒のストッキング、黒のパンプス。
故人様やご遺族への敬意を表すため、派手な装飾品や華美なメイクは避け、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。
喪服は、突然の訃報で慌てて用意することが多いものです。持っていない方や、サイズが合わなくなってしまった方は、レンタルサービスを利用するのも一つの方法です。
[Cariru BLACK FORMAL]というサービスは、デザインや質にこだわった喪服をレンタルできます。急なご不幸でも、ネットで申し込めば最短翌日には届くので、大変便利です。
また、数珠や袱紗、バッグ、サブバッグ、アクセサリーまで、必要なものがすべて揃ったフルセットもあるので、「何を用意すればいいのかわからない」と不安な方にもおすすめです。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
2. 受付での立ち居振る舞い
受付では、常に背筋を伸ばし、丁寧な姿勢を保つことが大切です。
- お辞儀:弔問客がいらしたら、深々と丁寧にお辞儀をします。
- 笑顔:悲しみの場ではありますが、参列者を迎える立場として、暗い表情ではなく、落ち着いた穏やかな表情を心がけましょう。
- 香典の扱い:受け取った香典は、香典盆の上に丁寧に置くか、丁重に受け取るようにしましょう。決して、乱雑に扱うことは避けてください。
3. 受付中の会話
受付中は、参列者との長話は避け、簡潔な挨拶に留めるようにしましょう。また、私語は慎み、受付の雰囲気を乱さないよう注意が必要です。
受付係の準備、当日までの流れ
受付係を頼まれたら、当日慌てないように、事前に準備しておくべきことがあります。
1. ご葬儀の詳細を確認
まずは、ご葬儀の日時、場所、故人様のお名前、宗派などを確認します。 受付開始時間や、役割分担についても、事前にご遺族や他の受付係の方と話し合っておきましょう。
2. 香典辞退の有無を確認
ご遺族の意向で香典を辞退している場合があるので、必ず確認しておきましょう。
3. 持ち物の確認
ご自身の喪服の準備はもちろん、数珠、袱紗、ハンカチ、筆記用具など、必要な持ち物をチェックリストにして用意しておくと安心です。
これらの準備をしっかりしておけば、当日は落ち着いて受付に臨むことができます。
葬儀全体を考える、受付係からの一歩
受付係は、ご葬儀の一部分を担う役割ですが、その先に「後悔のないお別れ」という、ご遺族と故人様にとって最も大切な時間があります。
私が葬儀社プランナーとして働いていた経験から、ご葬儀は「知っているか、知らないか」で、その内容が大きく変わってしまうということを痛感しています。
例えば、「葬儀社の選び方」一つとっても、相場やサービス内容を比較検討する時間がなく、焦って決めてしまい、後で後悔される方が非常に多いのです。
私自身、父の葬儀で右も左もわからないまま、慌てて葬儀社を決めてしまい、費用や内容について十分に納得できないままお別れを迎えた苦い経験があります。
このような経験から、ご遺族には、後悔のないお別れをしていただきたいと強く願っています。
「安心葬儀」というサービスは、複数の葬儀社から無料で相見積もりを取ることができ、事前に費用やサービス内容を比較検討することができます。 東証プライム上場企業が運営しており、全国7000以上の優良葬儀社から、ご希望の条件に合ったところを紹介してもらえるので、安心して利用できます。
葬儀は人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、後悔のないお別れのために、事前に情報を集めておくことが何よりも大切です。
葬儀後の大切な手続きとマナー
ご葬儀が終わった後も、大切な手続きやマナーが続きます。受付係を務めた方も、ご遺族を支える立場として、これらの知識を持っておくことは非常に役立ちます。
1. 香典返し
ご葬儀でいただいたご厚志に対しては、香典返しというかたちでお礼を伝えるのがマナーです。
香典返しの相場や贈り方、品物の選び方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご参考にしてください。
2. 遺品整理
ご葬儀が終わると、故人様が残された遺品の整理が始まります。この遺品整理も、ご遺族にとっては心身ともに負担の大きい作業です。
私も、父を亡くした際、遺品整理に大変苦労しました。思い出の品々を前に、なかなか手がつけられず、途方に暮れたことを覚えています。
もし、ご自身で遺品整理をすることが難しい場合は、専門の業者に依頼することも一つの選択肢です。
[遺品整理専門【ライフリセット】]というサービスは、故人様のお部屋に残された遺品や不要物の整理を専門に行っています。 ご遺族の気持ちに寄り添いながら、丁寧に対応してくれるので、安心して任せることができます。 「両親が亡くなって遺品整理を頼みたい」「生前に自分の持ち物を整理したい」といった様々なニーズに対応しています。
遺品整理は、故人様との最後の思い出を整理する大切な時間でもあります。無理をせず、プロの力を借りることも視野に入れてみてください。
葬儀に関わること、一つひとつを大切に
お葬式は、故人様とのお別れの場であると同時に、故人様が生きてきた証を、多くの人々で分かち合う大切な時間です。
受付係という役割を任された方は、その大切な時間を支える一人です。
この記事が、ご葬儀の受付を務める上で、少しでも不安を解消し、自信をもって役割を果たすための一助となれば幸いです。
そして、この記事を読んでくださった方が、後悔のないお別れのために、今できる準備を少しずつでも始めていただければ、これ以上の喜びはありません。
これからも、このブログ「家族を想うお葬式ガイド」を通して、皆様の終活やご葬儀に関する不安や疑問を解消できるよう、心を込めて情報を発信してまいります。
葬儀に関するその他の情報
ご葬儀には、受付以外にも様々なマナーや準備が必要です。 以下の記事も、ぜひご参考にしてください。
お香典返しを贈る際は「シャディギフトモール」が便利
ご葬儀後、ご遺族は香典返しを手配する必要があります。
香典返しの品物選びは、弔事のマナーに沿ったものを選ぶ必要があり、悩まれる方も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、ギフト専門店のオンラインショップ「シャディギフトモール」です。 1926年創業の歴史あるギフト専門店で、様々な用途に対応できる1万点以上の商品が揃っています。
香典返しにぴったりの品物はもちろん、包装やのし紙、メッセージカードも無料で豊富に用意されているので、安心して手配することができます。
カタログギフトも多数取り扱っており、相手に好きなものを選んでもらうことも可能です。
[シャディギフトモール]の公式サイトはこちら。
まとめ
- 受付係の役割は、単なる事務作業ではなく、故人様とご遺族の気持ちを代弁する大切な役割。
- 丁寧な挨拶と、落ち着いた振る舞いを心がける。
- 服装は喪服を着用し、清潔感のある身だしなみを心がける。
- 事前にご葬儀の詳細や、香典辞退の有無を確認しておく。
- 受付係の役割を終えた後も、ご遺族をサポートする気持ちを持つことが大切。
ご葬儀は、人生の節目であり、故人様への最後の想いを伝える大切な時間です。
受付係という役割を通して、その大切な時間を、皆様が心穏やかに過ごせるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
これからも、皆様の不安を少しでも和らげられるような情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
筆者プロフィール
Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。