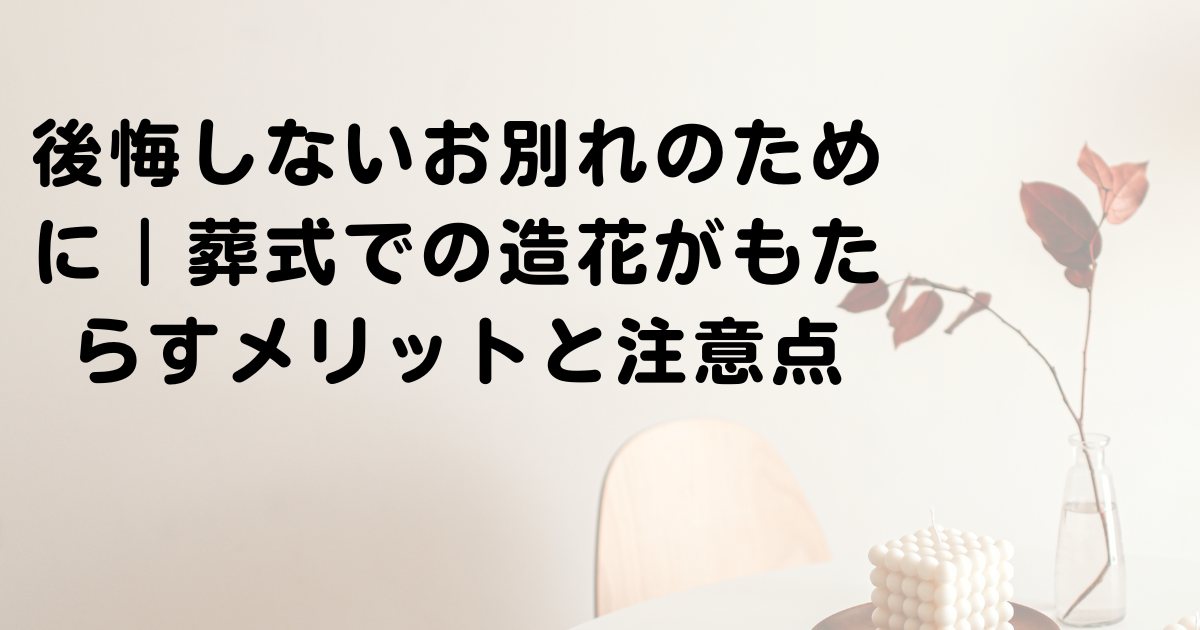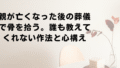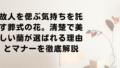こんにちは。元葬儀社プランナーのKeisukeです。
このブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しています。
突然ですが、あなたは「葬式に造花なんて失礼だ!」という言葉を聞いたことはありませんか?
もしそう思われているとしたら、それは少し古い時代の考え方かもしれません。
実は近年、家族葬や一日葬といった小規模なお葬式が増える中で、「造花」が葬儀の現場で大きな役割を担うようになってきました。
私が葬儀業界にいた12年間でも、造花の使われ方は目まぐるしく変化していったのを肌で感じています。
この記事では、葬式で造花が使われる理由やメリット、そして故人様やご遺族に失礼のないように使うための注意点について、元葬儀社プランナーの視点から徹底的に解説していきます。
大切な方とのお別れに際し、「何が正しくて、何が間違っているのか」と不安な気持ちを抱えている方もいらっしゃるかと思います。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、後悔のないお別れを迎えるためのヒントになれば幸いです。
はじめに:なぜ今、葬儀で造花が注目されているのか?
かつて、葬儀の花といえば、生花が主役でした。
しかし、時代の流れとともに、葬儀の形は多様化しています。
従来の格式高い一般葬から、家族だけで静かに見送る家族葬、告別式のみを行う一日葬、お通夜や葬儀・告別式といった儀式を省略した直葬など、故人様やご遺族の意向を尊重したさまざまな形式が選ばれるようになりました。
それに伴い、葬儀で使われるお花も変化しています。
特に、祭壇を彩る「供花」や「花祭壇」において、造花が積極的に取り入れられるようになったのです。
この背景には、生花にはない造花ならではの利便性や経済性があります。
しかし、一方で「造花は安っぽい」「弔事にはふさわしくない」といったネガティブなイメージを持つ方も少なくありません。
そこで、まずは葬儀における生花と造花の役割を整理し、それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。
1. 葬儀における生花と造花の役割とメリット・デメリット
生花がもたらす力と課題
お葬式で生花が使われるのには、とても大切な意味があります。
生花には、故人様の旅立ちを美しく飾り、ご遺族の心を癒す力があります。
また、香りが故人様の安らかな眠りを導き、生きた証を象徴する役割も担ってきました。
しかし、生花には以下のような課題も存在します。
- 費用が高くなりがち:花の種類や量、季節によって変動しますが、生花で豪華な祭壇を組むとなると、かなりの費用がかかります。
- 管理が大変:生花は、温度や湿度に敏感です。特に夏場は枯れやすく、美しい状態を保つために頻繁な水やりや手入れが必要です。
- アレルギーの問題:ご親族の中には、花粉症やアレルギーを持つ方もいらっしゃいます。
- 廃棄の手間:葬儀が終わった後の生花の廃棄は、かなりの手間がかかります。
造花がもたらす新たな選択肢
一方、造花はこれらの課題を解決する新たな選択肢として注目されています。
造花には、生花にはない多くのメリットがあるのです。
- コスト削減:生花に比べてコストを抑えることができます。特に、大規模な花祭壇を組む場合、造花をうまく取り入れることで、予算内で見栄えのする祭壇を設えることが可能です。
- 手間がかからない:水やりや枯れる心配がないため、管理が非常に楽です。
- アレルギーの心配がない:花粉症やアレルギーのある方も、安心して参列できます。
- 再利用が可能:造花は繰り返し使えるため、環境にも優しい選択肢と言えます。
しかし、造花にはデメリットもあります。
- 生花に比べて質感が劣る場合がある:安価な造花は、どうしても本物と見分けがつきにくく、安っぽく見えてしまうことがあります。
- 香りがない:生花の持つ香りは、故人様への想いを込める大切な要素の一つです。造花にはこの香りがないため、寂しく感じる方もいらっしゃるかもしれません。
- 「失礼だ」と感じる方がいる:冒頭でもお伝えしたように、造花に対して否定的な感情を持つ方も、特にご年配の方の中にはいらっしゃいます。
このように、生花と造花にはそれぞれ一長一短があります。
大切なのは、これらのメリットとデメリットを理解した上で、故人様やご遺族の想いに寄り添ったお花を選ぶことです。
「お葬式で造花を使うこと」は、決して失礼なことではありません。
故人様を想い、限られた予算の中で最善を尽くそうとする、ご遺族の愛情の表れだと私は考えます。
2. 葬式における造花の種類と用途
葬儀で使われる造花は、主に以下の3つの用途に分けられます。
用途1:祭壇を彩る「花祭壇」
近年、花祭壇は主流になりつつあります。
祭壇全体を生花で飾る方法もありますが、より壮大で華やかな祭壇を希望される場合、生花と造花を組み合わせることが一般的になってきました。
造花は、祭壇の骨格や土台となる部分を飾るのに使われることが多く、その上から生花を配置することで、より立体感のある美しい祭壇を創り出すことができます。
また、造花は生花に比べて耐久性が高いため、遠方からのご親族が到着するまで時間がかかる場合でも、美しい状態を保つことができます。
用途2:供花(きょうか)やアレンジメント
供花とは、故人様を弔うために供えるお花のことです。
親族や会社関係の方々が、お悔やみの気持ちを込めて贈るのが一般的です。
この供花にも、造花が使われることがあります。
特に、遠方から参列できない方や、長期間飾っておきたいというご遺族の要望に応える形で、造花の供花やアレンジメントが選ばれるケースが増えてきました。
ただし、供花に造花を用いる際は、事前に葬儀社に相談し、マナー違反にならないか確認することが大切です。
用途3:枕花(まくらばな)や仏壇飾り
枕花とは、故人様がお亡くなりになった直後に枕元に飾るお花です。
生花を用いるのが一般的ですが、最近では、お葬式後も長く故人様を偲びたいという想いから、造花の枕花を希望される方もいらっしゃいます。
また、仏壇に供えるお花としても、造花が広く使われています。
生花と違って枯れる心配がないため、毎日お仏壇にお花を供えるのが難しいご家庭でも、故人様を大切に想う気持ちを形にすることができます。
3. 造花を選ぶ際のポイントと注意点
葬儀で造花を使うことは、決して悪いことではありません。
しかし、故人様やご遺族に失礼のないよう、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
ポイント1:品質にこだわる
「造花は安っぽい」というイメージを払拭するためには、高品質な造花を選ぶことが最も重要です。
最近の造花は、まるで本物と見間違うほど精巧に作られています。
手触りや質感、花びらの色合いなど、細部までこだわって作られた造花であれば、生花に劣らない美しさで祭壇を彩ることができます。
葬儀社を選ぶ際も、造花の品質にもこだわっているか、実績や評判を確認することが大切です。
信頼できる葬儀社を選ぶことで、故人様への想いを込めた、美しいお別れの場を創り上げることができます。
信頼できる葬儀社を探すなら、株式会社エス・エム・エスが運営する【安心葬儀】の相見積もりサービスがおすすめです。全国7000以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を紹介してくれます。東証プライム上場企業が運営しているため、安心して利用できるのも大きなポイントです。突然の訃報で時間がない中でも、複数の葬儀社を比較検討できるので、後悔のないお葬式選びに役立ちます。
ポイント2:生花と組み合わせる
造花を単独で使うのではなく、生花と組み合わせることで、より美しい空間を創り出すことができます。
祭壇の骨格や背景に造花を使い、故人様の周りや遺影の横など、特に想いを伝えたい部分に生花を配置することで、生花と造花それぞれの良さを活かすことができます。
生花の持つみずみずしさや香り、造花の持つ華やかさと耐久性。
これらを組み合わせることで、故人様への想いをより深く表現できるのではないでしょうか。
ポイント3:ご親族への配慮を忘れない
ご親族の中には、造花に対して抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
特に、ご年配の方は、「お葬式は生花で飾るもの」という伝統的な考えをお持ちの場合が多いです。
造花の使用を決める前に、必ずご親族に相談し、同意を得ておくことが大切です。
故人様を想う気持ちはみな同じです。
しかし、お葬式はご遺族だけのものではなく、ご親族や故人様を想うすべての方々が参加する大切な儀式です。
コミュニケーションをしっかりと取ることで、後悔のないお別れを迎えることができます。
4. 葬儀後の造花の活用方法
お葬式が終わった後、生花は枯れてしまい、処分しなければなりません。
しかし、造花であれば、その後の活用方法がたくさんあります。
- ご自宅の仏壇に飾る:生花は毎日交換する必要がありますが、造花であればお手入れの心配がありません。
- お墓に供える:お墓参りが頻繁にできない場合でも、造花を供えることで、常に美しい状態を保つことができます。
- 故人様の思い出の場所に飾る:故人様が好きだった場所に飾ることで、故人様を身近に感じることができます。
このように、造花は故人様への想いを長く形に残すことができる、とても心強い存在です。
特に、故人様が生花がお好きだった場合、その花に似た造花を選んで飾ることで、故人様を偲ぶ気持ちをより深く表現できます。
5. お葬式で造花以外の準備も忘れてはいけない
お葬式の準備は、お花だけではありません。
ご葬儀全体の流れを理解し、準備しておくべきことは多岐にわたります。
私が葬儀社でプランナーとして働いていた経験から、特におさえておきたいポイントをいくつかご紹介します。
5-1. 葬儀全体の流れを把握する
お葬式の流れは、地域や宗教、葬儀の形式によって異なりますが、一般的な流れを把握しておくことで、いざという時にも慌てず対応できます。
お葬式の流れをやさしく解説|後悔しない準備と心構えという記事では、葬儀の流れをわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
5-2. 葬儀の服装を準備する
お葬式に参列する際の服装は、故人様やご遺族に失礼のないよう、マナーを守る必要があります。
喪服は、突然の訃報で慌てて用意するケースが多いですが、普段着る機会が少ないため、サイズが合わなくなっていたり、デザインが古くなっていたりすることがあります。
ご自身の喪服を事前に確認し、必要であれば新調しておくことをおすすめします。
また、喪服は高価なものが多く、購入するのに躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方には、株式会社トレジャー・ファクトリーの喪服・礼服のレンタル【Cariru BLACK FORMAL】がおすすめです。デザインや質にこだわった人気ブランドの喪服を、リーズナブルな価格でレンタルできます。ジャケット・ワンピース・バッグ・ネックレス・数珠などがフルセットで借りられるプランもあるので、急な訃報でも安心です。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
5-3. 遺品整理について考えておく
お葬式後には、故人様が残された遺品を整理する「遺品整理」が待っています。
遺品整理は、ご遺族だけで行うには精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
無理のない範囲で進めるためにも、専門の業者に依頼することも検討してみてください。
株式会社アシストが運営する遺品整理専門【ライフリセット】は、故人様のお部屋に残された遺品や不要物の整理を専門に行っています。ご遺族の気持ちに寄り添いながら、丁寧な作業でサポートしてくれるので、安心して任せることができます。
6. 葬式後のことまで見据えた準備が大切
お葬式は、故人様とのお別れの儀式であると同時に、ご遺族が新たな一歩を踏み出すための大切な区切りでもあります。
お葬式が終わった後も、やるべきことはたくさんあります。
6-1. 香典返しについて
ご香典をいただいた方へのお返しである「香典返し」も、大切なマナーの一つです。
香典返しの相場や贈り方、品物選びには、地域や宗教によって異なるマナーがあります。
葬式後の香典返し|失礼のない贈り方・選び方ガイドの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
香典返しを選ぶ際には、贈る相手の好みを考慮するのはもちろんのこと、弔事にふさわしい品物を選ぶ必要があります。
シャディ株式会社のギフト専門店【シャディギフトモール】は、香典返しに最適なカタログギフトや、タオル・お茶などのギフト商品が豊富に揃っています。包装やのし紙、メッセージカードも無料で用意してくれるので、安心して利用できます。
6-2. 終活について
故人様とのお別れを通して、「終活」について考える方も多いのではないでしょうか。
終活は、ご自身の人生の最期をより良い形で迎えるための準備です。
エンディングノートを作成したり、お墓や葬儀について考えたり、生前整理を進めたりと、内容は多岐にわたります。
7. まとめ:造花を活用し、後悔のないお別れを
今回は、葬式で造花が使われる理由やメリット、そして故人様やご遺族に失礼のないように使うための注意点について、元葬儀社プランナーの視点から詳しく解説しました。
造花は、生花にはない多くのメリットを持ち、現代の多様な葬儀の形に適した選択肢となりつつあります。
「造花は安っぽい」「弔事にはふさわしくない」というイメージを払拭するためには、品質にこだわり、生花と組み合わせるなど、工夫を凝らすことが大切です。
そして何よりも、故人様やご遺族の想いを尊重し、ご親族としっかりコミュニケーションを取ることで、後悔のないお別れを迎えることができます。
私自身、父を亡くした経験から、お葬式という非日常の出来事に直面したご遺族の不安な気持ちを痛いほど理解しています。
だからこそ、このブログを通して、少しでもあなたの不安を和らげ、心穏やかに故人様との最期のお別れができるよう、お手伝いができればと願っています。
大切な方とのお別れを、愛情と感謝の気持ちを込めて送り出す。
そのために、造花をうまく活用することも、一つの選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。
プロフィール
筆者プロフィール:Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。