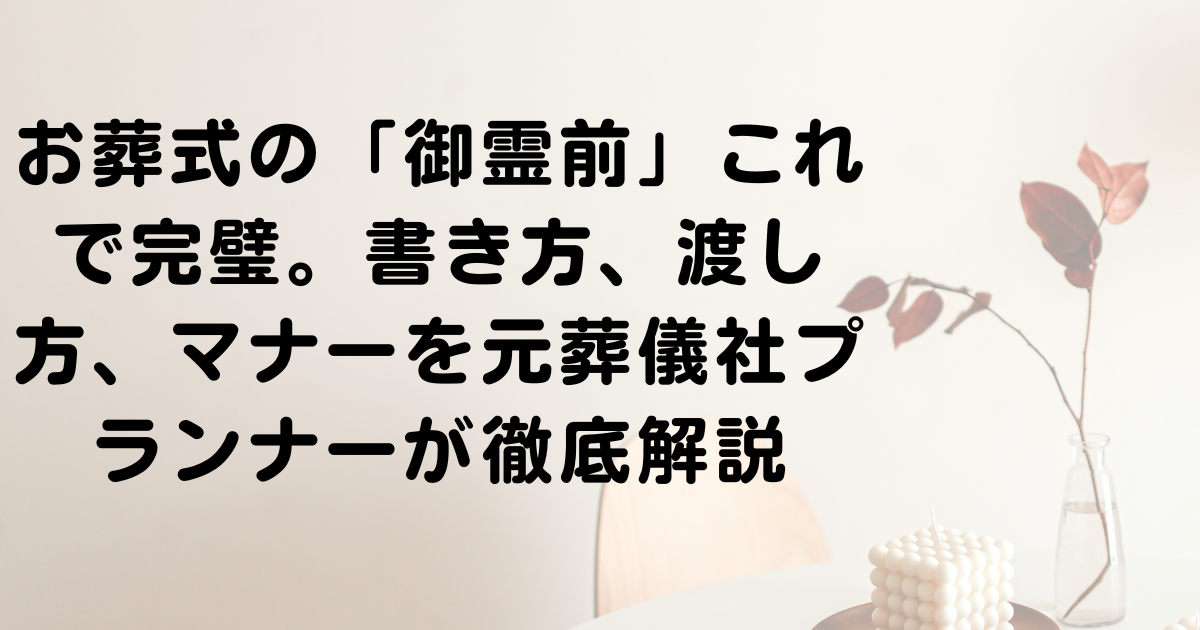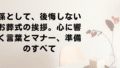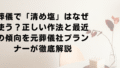はじめまして。元葬儀社プランナーのKeisukeです。
このブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しています。
私自身、20代の頃に父を突然亡くした経験があります。その時、何から手をつけて良いのか分からず、精神的にも経済的にも非常に苦しい思いをしました。その経験から、同じように不安を抱えている方々の力になりたいと思い、葬儀業界に飛び込みました。
12年間の勤務の中で、800件以上のご葬儀に携わり、ご遺族の皆様のさまざまな疑問やお悩みに寄り添ってきました。
特に、お通夜やお葬式の場で頻繁に出てくる「御霊前(ごれいぜん)」という言葉。
「どう書いたらいいの?」「いつ、誰に渡すのが正しいの?」「マナー違反にならないか心配…」
きっと、多くの方がそうした不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
お葬式は、故人様との最後のお別れの場であると同時に、ご遺族の悲しみに寄り添い、敬意を表す大切な機会です。そのため、失礼のないようにと、一つひとつの作法に気を遣うのは当然のことです。
この記事では、私が長年の現場経験で培った知識をもとに、「御霊前」に関するあらゆる疑問を、分かりやすく丁寧に解説していきます。
「御霊前」の正しい書き方から、お金の包み方、渡し方のマナー、宗派による違いまで、この記事を最後までお読みいただければ、もう迷うことはありません。
大切な方とのお別れに際し、心穏やかに故人様を見送るための一助となれば幸いです。
そもそも「御霊前」とは?その意味と使い方を丁寧に解説
まず、基本の「き」からご説明しましょう。
「御霊前(ごれいぜん)」とは、故人様の「霊」の前に供える、という意味を持つ言葉です。
お通夜やご葬儀に参列する際、ご遺族に対してお渡しする弔意(ちょうい:故人様を悼み、ご遺族を慰める気持ち)を示す金品のこと、つまり**香典(こうでん)**の表書きとして最も一般的に使われる言葉です。
「御仏前」や「御香典」との違いは?
「御霊前」と似た言葉に「御仏前(ごぶつぜん)」や「御香典(ごこうでん)」があります。これらの言葉は、それぞれ使われるタイミングや宗派が異なります。
- 御霊前(ごれいぜん):
- 意味: 故人様の霊前に供える、という意味です。
- 使うタイミング: 故人様が亡くなられてから、四十九日の法要を迎えるまでの期間に使います。仏教では、この期間、故人様の魂はまだこの世をさまよっていると考えられているためです。
- 注意点: 浄土真宗ではこの言葉は使いません。浄土真宗では、人は亡くなるとすぐに仏様になると考えられているため、「霊」という概念がないからです。この場合は「御仏前」を使います。
- 御仏前(ごぶつぜん):
- 意味: 故人様が仏様となられた後にお供えする、という意味です。
- 使うタイミング: 四十九日の法要以降に使います。ご法事やお盆などで、故人様のご供養をする際に用いられます。
- 注意点: 故人様が亡くなってから四十九日までは「御霊前」、それ以降は「御仏前」と覚えると分かりやすいでしょう。
- 御香典(ごこうでん):
- 意味: 香(お香)を供える代わりにお金をお供えする、という意味です。
- 使うタイミング: 宗派を問わず、お通夜やご葬儀の際に幅広く使えます。
- 注意点: 宗教や宗派が分からない場合は、「御香典」と書くのが無難です。
仏教以外の宗教ではどうする?宗派による表書きの違い
「御霊前」は主に仏教で使われる言葉ですが、日本にはさまざまな宗教があります。もし故人様の宗教が仏教でなかった場合、どのような表書きを使えば良いのでしょうか。
神道の場合
- 表書き: 「御玉串料(おんたまぐしりょう)」または「御榊料(おさかきりょう)」
- 注意点: 神道では仏教のように「霊」や「仏」という概念がありません。玉串(たまぐし)や榊(さかき)は神事において神様にお供えするものであり、その代わりにお金を供える、という意味で使われます。
キリスト教の場合
- 表書き: 「お花料(おはな)」
- 注意点: キリスト教では香典という習慣がなく、供花(きょうか)を供えるのが一般的です。その代わりにお金をお渡しする場合は、「お花料」とします。
まとめ:これで迷わない!表書きの選び方
もし、故人様の宗教や宗派が分からない場合は、**「御香典」または「御霊前」**と書くのが最も無難です。
ただし、ごくまれに「御霊前」と「御仏前」を厳密に使い分ける地域やご家庭もあります。心配な場合は、事前にご親族や親しい知人の方に確認してみるのも良いでしょう。
筆記用具から水引まで。正しい「御霊前」の書き方
次に、実際に不祝儀袋(のし袋)に「御霊前」と書く際の手順について、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
1.筆記用具は「薄墨」で書くのがマナー
お通夜やご葬儀に持参する不祝儀袋の表書きは、**「薄墨(うすずみ)」**の筆や筆ペンで書くのが正式なマナーです。
これは「突然の訃報に、悲しみの涙で墨が薄くなってしまった」「墨を磨る時間も惜しんで駆けつけた」という故人様を悼む気持ちを表すためだと言われています。
現在では、薄墨の筆ペンが市販されていますので、それを使うと便利です。もし手元にない場合は、普通の黒い筆ペンでも構いませんが、できれば薄墨を用意しておきましょう。
薄墨で書くのは、不祝儀袋の「表書き」と「氏名」のみです。中袋の住所や氏名、金額は、後述するように普通の黒い筆ペンや万年筆で書きます。
2.表書きと氏名の書き方
不祝儀袋の表面には、上段に「御霊前」、下段にご自身の氏名を書きます。
- 表書き(上段):
- 中央に「御霊前」と書きます。
- 文字は、バランスよく、少し太めに書くと美しく見えます。
- 氏名(下段):
- 「御霊前」の真下に、少し小さめの文字でフルネームで書きます。
- 夫婦連名で出す場合は、夫の名前を中央に書き、その左隣に妻の名前を書きます。
- 連名の場合は、右から目上の方、左に目下の方の順で書くのが一般的です。3名以上になる場合は、代表者の氏名のみを書き、その左に「他一同」と書くか、別紙に全員の氏名を書いて中袋に入れます。
- 会社として出す場合は、中央に代表者の氏名、右側に社名を少し小さく書きます。
3.中袋の書き方
不祝儀袋の中には、お札を入れるための「中袋(なかぶくろ)」が入っています。
この中袋にも、住所、氏名、金額を記入します。
- 表面:
- 中央に、漢数字で金額を書きます。
- 例:「金壱萬圓也(きんいちまんえんなり)」「金参萬圓也(きんさんまんえんなり)」
- 「壱」「弐」「参」「伍」「拾」といった旧字体の漢数字を使うのが正式なマナーです。
- 「也」は入れても入れなくても構いませんが、入れるとより丁寧な印象になります。
- 裏面:
- 左下に、郵便番号、住所、氏名を丁寧に記入します。
- 故人様との関係性を示す「続柄(つづきがら)」も書いておくと、ご遺族が香典帳を整理する際に親切です。
中袋の記入には、薄墨ではなく、普通の黒い筆ペンや万年筆を使います。これは、香典帳への記帳や整理の際に読みやすくするためです。
4.不祝儀袋の水引(みずひき)について
不祝儀袋には、「黒白(くろしろ)」または「双銀(そうぎん)」の水引が使われています。
- 結び方:
- 水引の結び方は「結び切り(むすびきり)」または「あわじ結び」を選びます。
- 「結び切り」は、一度結ぶと簡単にほどけないことから、「二度と不幸なことが起こらないように」という願いが込められています。
- 「あわじ結び」も同様に、簡単にほどけない結び方です。
- 水引の色:
- 黒白の水引が最も一般的です。
- 双銀の水引は、高額な香典(3万円以上が目安)を包む場合に使われることが多いです。
意外と知らない「御霊前」に入れるお札の準備と包み方
不祝儀袋に入れるお札にも、いくつかのマナーがあります。
1.お札は新札?旧札?
ご祝儀では「新札」を用意するのがマナーですが、お葬式では**「旧札(使い古したお札)」**を使うのがマナーです。
これは「不幸を予期して、あらかじめ新札を用意していた」とご遺族に思わせてしまうことを避けるためです。
もし手元に新札しかない場合は、一度お札を折ってから不祝儀袋に入れるようにしましょう。
2.お札の向きは?
中袋に入れるお札の向きにも決まりがあります。
お札の肖像画が、中袋の裏側を向くように入れます。
また、お札の向きはすべて揃えて入れます。これは、故人様への敬意を表すためです。
3.金額の相場と、避けるべき数字
香典の金額は、故人様との関係性や、ご自身の年齢によって異なります。
- 両親: 5万円〜10万円
- 兄弟・姉妹: 3万円〜5万円
- 祖父母: 1万円〜3万円
- 親戚: 1万円〜3万円
- 友人・知人: 5千円〜1万円
- 勤務先の上司・同僚: 5千円
あくまで一般的な目安です。大切なのは金額よりも、故人様を悼む気持ちです。
また、香典の金額には避けるべき数字があります。
- 「4」や「9」: 「死」や「苦」を連想させるため、避けるべきとされています。
- 「偶数」: 「割り切れる」ことから、故人様との縁が切れることを連想させるため、避けるべきという考え方もあります。ただし、最近では2万円や4万円を包む方も増えています。地域や慣習にもよりますので、不安な場合は奇数にしましょう。
お葬式の服装は大丈夫?「御霊前」を渡す際のマナー
お通夜やお葬式に参列する際、服装や身だしなみも非常に重要なマナーです。
特に女性の場合、急な訃報で「着ていく服がない」「サイズが合わなくなってしまった」と慌ててしまうこともあるでしょう。
そんな時は、喪服・礼服のレンタルサービスを活用するのも一つの手です。
デザイン・質・マナーにこだわる方の喪服・礼服のレンタル【Cariru BLACK FORMAL】は、トレンドを押さえた上質なブラックフォーマルを、必要な時に必要なものだけを借りられる便利なサービスです。急な訃報でも、16時までの注文で最短翌日午前中に届けてくれるので、いざという時も安心です。
必要なものがすべて揃ったフルセットも豊富に用意されているので、マナーに自信がない方も、安心して参列できます。
- 服装: 正喪服、準喪服、略喪服など、TPOに合わせた服装を選びましょう。
- 小物: 真珠のネックレスやイヤリングなど、派手すぎないものを選びます。
- バッグ: 黒無地で光沢のない、シンプルなデザインのものが良いでしょう。
- 靴: 黒のパンプスなど、ヒールが低くシンプルなデザインを選びます。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
「御霊前」の渡し方と、受付での作法
いよいよ、受付で「御霊前」を渡す場面です。
緊張するかもしれませんが、落ち着いて、故人様とご遺族への気持ちを込めてお渡ししましょう。
1.ふくさから取り出すのがマナー
「御霊前」を入れた不祝儀袋は、「ふくさ」という布に包んで持参するのが正式なマナーです。
受付で不祝儀袋をふくさから取り出し、袱紗を台にして、両手で渡します。
2.受付での挨拶と一連の流れ
- 受付に一礼して、「この度はご愁傷様です(ごしゅうしょうさまです)」と簡潔に挨拶します。
- ふくさから不祝儀袋を取り出し、相手から見て正面になるように向きを変えます。
- 両手で不祝儀袋を差し出しながら、「心ばかりですが、御霊前にお供えください」と伝えます。
- 芳名帳(ほうめいちょう)に記帳します。
- お返しに、会葬御礼(かいそうおんれい)の品を受け取ります。
- 最後に一礼して、受付を離れます。
葬儀後の「御霊前」はどうなるの?香典返しのマナー
お葬式の後に、ご遺族は受け取った「御霊前」に対して、「香典返し(こうでんがえし)」を贈ります。
香典返しは、香典をいただいたことに対するお礼と、無事に葬儀を終えられたというご報告を兼ねたものです。
香典返しに関する詳しいマナーや贈り方については、こちらの記事も参考にしてください。
ご葬儀を終えられたご遺族は、さまざまな手続きや、故人様の遺品整理など、やることが山積みです。
その中で、香典返しを選んだり、発送の手配をしたりするのは、精神的にも肉体的にも大きな負担になります。
もし、香典返し選びでお困りの際は、ギフト専門店のオンラインストアを活用するのもおすすめです。
【シャディ公式】内祝や、お返しも!ギフト専門店【シャディギフトモール】は、カタログギフトから食品、タオル、洗剤まで、様々な用途に合わせた1万点以上の商品を揃えています。のし紙やメッセージカードも無料で用意してくれるので、香典返しに必要なものがすべて揃います。
ご遺族が安心して香典返しを選べるよう、こうしたサービスを上手に活用するのも良い方法です。
葬儀全体の流れを理解して、心穏やかに故人様を見送るために
「御霊前」のマナーは、お葬式という特別な場での、ほんの一部に過ぎません。
お葬式には、これ以外にも多くの作法や手続きが存在します。
「お葬式って、一体どういう流れで進むの?」「急に亡くなってしまったら、何をどうすればいいの?」
そうした疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
お通夜やお葬式の流れを事前に知っておくことは、いざという時に慌てず、心穏やかに故人様を見送るための大切な心構えです。
【保存版】葬式の流れをやさしく解説|後悔しない準備と心構えという記事では、葬儀の流れを初心者の方にも分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
元葬儀社プランナーが教える、後悔しないお葬式選びのポイント
さて、ここからは私自身の経験に基づいた、より深いお話になります。
お葬式は、人生で何度も経験することではないため、ほとんどの方が「初めて」の経験です。
そのため、十分な知識がないまま、限られた時間の中で、大きな決断を迫られることになります。
特に、故人様が突然亡くなられた場合、ご遺族は精神的にも混乱しているため、冷静な判断が難しくなることが多いです。
- どの葬儀社を選べばいいのか分からない…
- 高額な費用を請求されないか心配…
- 自分たちの希望に合ったお葬式ができるのだろうか…
こうした不安を抱えながら、数時間以内に葬儀社を決めなければならない状況は、ご遺族にとって大きな負担です。
「本当に良い葬儀社と出会い、故人様を心から見送ってほしい」
私は、長年現場で働いてきた中で、そう強く願ってきました。
良い葬儀社を選ぶためには、「相見積もり」を取ることが非常に重要です。
複数の葬儀社から見積もりを取ることで、費用やサービス内容を比較検討し、納得のいく葬儀社を選ぶことができます。
しかし、一社一社問い合わせをするのは、とても手間がかかるものです。
そこで活用していただきたいのが、東証プライム上場企業である株式会社エス・エム・エスが運営する【安心葬儀】です。
【安心葬儀】は、全国7000以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を無料で紹介してくれる相見積もりサービスです。
時間がない中でも、複数の葬儀社の費用やサービス内容を簡単に比較検討できるため、「良い葬儀社を見つけたい」「費用を抑えたい」といった方におすすめです。
私も、葬儀業界にいた人間として、こうしたサービスがもっと広まってほしいと心から願っています。
葬儀後の大切なステップ:遺品整理
お葬式が無事に終わった後も、ご遺族には故人様が残されたものの整理という、大きな作業が待っています。
「遺品整理」と聞くと、単に不要なものを片付けることだと思われがちですが、故人様の思い出が詰まった品々を整理し、気持ちの整理をつけるための、非常に大切なプロセスです。
しかし、一人で遺品整理を行うのは、精神的にも肉体的にも負担が大きいです。
特に、実家が遠方にある場合や、故人様がたくさんの物を大切にされていた場合、どこから手をつけて良いか分からない方も多いでしょう。
そんな時は、遺品整理の専門業者に依頼するという選択肢があります。
遺品整理の専門業者は、故人様の遺品を丁寧に扱ってくれるだけでなく、不用品の処分や、家屋の清掃まで一貫して行ってくれます。
専門業者に依頼することで、ご遺族は無理なく、故人様との思い出と向き合う時間を作ることができます。
プロに任せる安心感:遺品整理専門【ライフリセット】
遺品整理専門の【ライフリセット】は、故人様が残された遺品や不要物の整理を、ご遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に行ってくれるサービスです。
「実家の両親が亡くなったので依頼したい」「生前に自分で整理しておきたい」といった様々なご要望に応えてくれます。
まとめ:心を込めて「御霊前」を渡し、故人様を見送る
この記事では、お葬式の「御霊前」にまつわるさまざまなマナーについて、詳しく解説してきました。
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 「御霊前」は、四十九日の法要までの仏式で使われる言葉。宗派が分からない場合は「御香典」が最も無難。
- 表書きは「薄墨」で、氏名はフルネームで丁寧に書く。
- 中袋の金額は漢数字で、住所氏名も忘れずに記入する。
- お札は旧札を使い、肖像画が裏側を向くように入れる。
- 「ふくさ」に包んで持参し、受付で丁寧な挨拶と共に渡す。
- 服装や身だしなみにも気を配り、故人様への敬意を表す。
お葬式は、故人様との最後の貴重な時間です。
「これで大丈夫かな?」と不安に思うよりも、この記事で正しい知識を身につけて、心穏やかに故人様を見送っていただきたいと願っています。
ご葬儀を控えたご家族の皆様、そしてこれからご自身や大切なご家族の「終活」をお考えの皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
これからも、このブログを通じて、皆様のお別れが「後悔のない、あたたかいお別れ」になるよう、心を込めて情報発信を続けてまいります。