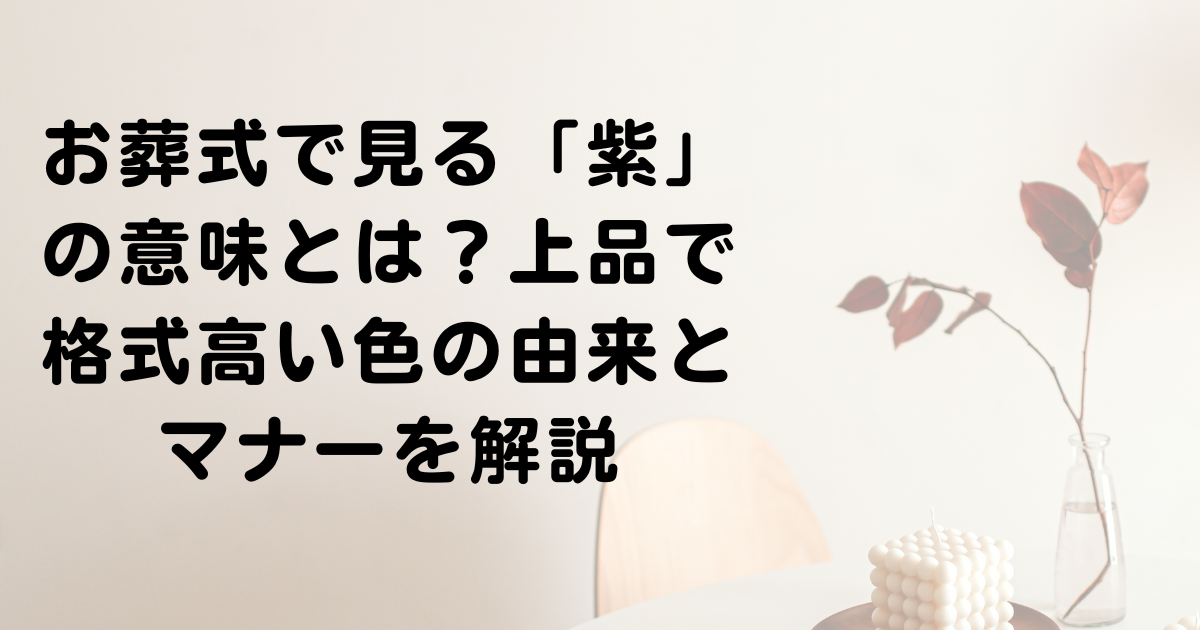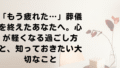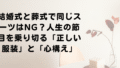ここ数年、終活という言葉をよく耳にするようになりました。人生の終わりに向けて、ご自身のことを整理し、ご家族に負担をかけないように準備しておくことは、とても大切なことです。しかし、「終活を始めたいけれど、何から手をつけていいかわからない」「葬儀について考えるのは、縁起でもない」と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、元葬儀社プランナーである私、Keisukeが、葬儀に関する疑問や不安を解消できるよう、わかりやすく丁寧に解説していきます。
特に今回は、葬儀で使われる色、特に「紫」に焦点を当ててお話しします。
「葬儀で紫色のものを見かけるけれど、どんな意味があるんだろう?」 「紫色の香典袋やふくさは使っていいの?」
といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。
筆者プロフィール
Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
葬儀で「紫」が持つ意味とは?上品で格式高い「高貴な色」の由来を解説
葬儀の場では、さまざまな「色」が使われています。最も多いのは、やはり白と黒でしょう。故人様との最後の別れを告げる場として、清楚で厳粛な雰囲気を演出するために、これらの色が選ばれることが多いです。
しかし、目を凝らしてみると、祭壇の花や僧侶の衣、故人様の棺を覆う布などに、しばしば紫色が使われていることに気づくことがあります。
なぜ、葬儀の場で紫が使われるのでしょうか。
その答えは、紫が古くから「高貴な色」として特別な意味を持ってきた歴史にあります。
1. 冠位十二階と僧侶の衣
日本で紫が特に重要な色とされたのは、飛鳥時代の**「冠位十二階」**が始まりです。
これは、時の権力者である聖徳太子が定めた身分制度で、個人の才能や功績に応じて位を授け、それを冠の色で示すというものでした。この制度で最も高い位である「大徳」と「小徳」には、それぞれ「濃い紫」と「薄い紫」の冠が与えられました。
紫の染料は、当時とても貴重で高価なものでした。ムラサキという植物の根からしか取れず、大量に生産することが難しかったためです。そのため、紫色はごく一部の特権階級の人しか身につけられない「禁色(きんじき)」とされ、権威や格式の象徴となりました。
仏教の世界でも、僧侶の位階を表すために紫色の衣が用いられることがあります。特に、高い徳を積んだ僧侶に許された「紫衣(しえ)」は、現代に至るまで特別な意味を持ち続けています。
2. 仏教における紫の意味
仏教、特に密教の世界では、仏様や菩薩様の体が紫色の光を放つとされ、紫色は「仏の慈悲」や「悟り」を表す神聖な色と考えられています。また、極楽浄土の蓮池に咲く花の色としても紫が描かれることがあり、**「来世への旅立ち」や「死後の世界」**とのつながりを示す色でもあります。
このように、紫は単に高貴な色であるだけでなく、仏教の教えや死生観とも深く結びついてきたのです。
3. 葬儀における紫の使い方
これらの背景から、葬儀において紫が使われる場面は多岐にわたります。
- 僧侶の衣: 格式高いお寺の住職や、高い位の僧侶が紫色の衣を身につけることがあります。
- 祭壇の装花: 白菊や百合などの白い花をメインに、アクセントとして紫色の花が使われることがあります。
- 棺の覆い: 故人様の棺を覆う布に紫色の布が使われることがあります。故人様の威厳や格式を示す意味合いもあります。
- 小物: ふくさ、数珠入れ、風呂敷など、弔事の場で使われる小物に紫色が選ばれることも多いです。
特に、紫色のふくさや数珠入れは、慶弔どちらの場面でも使える**「万能な色」**とされています。慶事では明るい色、弔事では落ち着いた色が基本ですが、紫色は例外的に両方で失礼にあたらない色なのです。
葬儀の準備、何から始めればいい?
大切なご家族とのお別れは、誰もが直面する可能性があります。しかし、いざその時が来てしまうと、悲しみに暮れる中で葬儀の手配や手続きを進めなければならず、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
「もっと良いお葬式にしてあげたかった」 「費用が思ったよりも高くなってしまった」
といった後悔をしないためにも、元気なうちから少しずつ情報収集をしておくことが、ご本人様にとっても、残されたご家族にとっても、何よりの安心につながります。
もし、今すぐ葬儀について具体的な相談をしたい、信頼できる葬儀社を探したいとお考えでしたら、東証プライム上場企業である株式会社エス・エム・エスが運営する【安心葬儀】というサービスがおすすめです。
【安心葬儀】の特長
- 時間がない中でも良い葬儀社が見つかる: 突然の訃報で時間がない中、複数の葬儀社からまとめて見積もりを取ることができ、比較検討がスムーズに進みます。
- 全国7000社以上の優良葬儀社から選べる: 全国各地の厳選された葬儀社の中から、ご希望の条件に合った最適な会社を紹介してもらえます。
- 費用やサービス内容を事前に確認できる: 費用の内訳やサービス内容を、透明性の高い形で確認できるため、「知らない間に高額な費用がかかってしまった」という心配がありません。
終活の一環として、事前に見積もりを取っておくこともできます。ご家族の負担を減らすためにも、一度相談してみてはいかがでしょうか。
葬儀の服装マナー:紫色のアイテムは使える?
葬儀に参列する際の服装は、「喪服」が基本です。男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマル(ワンピースやアンサンブルなど)が一般的で、ネクタイや靴、バッグなども黒で統一するのがマナーとされています。
しかし、小物などで少しだけ色を入れたい、あるいは紫色のアイテムはマナー違反になるのか、と気になる方もいらっしゃるかもしれません。
1. 葬儀にふさわしい「紫」とは
結論から言えば、紫色の小物であれば、マナー違反にはなりません。
特に、深みのある落ち着いた紫は、格式高く上品な印象を与えるため、弔事の場にもふさわしい色とされています。
- 袱紗(ふくさ): 香典袋を包むための布。落ち着いた紫色は、弔事だけでなく慶事にも使えるため、一つ持っておくと便利です。
- 数珠袋(じゅずぶくろ): 数珠を入れる袋。紫色のものは、宗派を問わず広く使われています。
- ネクタイ: 一般的には黒のネクタイを着用しますが、ごく稀に、地方の風習などで紫色のネクタイを着用する場合もあります。ただし、全国的には黒が一般的ですので、迷う場合は黒を選ぶのが無難でしょう。
- 帯揚げ・帯締め(和装の場合): 和装で参列する場合、帯揚げや帯締めに、深みのある紫やグレーなど、落ち着いた色を選ぶのが一般的です。
ただし、明るすぎる紫や、派手な柄のものは避けるべきです。あくまで、落ち着いた雰囲気を保つことが大切です。
2. 喪服の準備、どうしていますか?
「喪服を持っていない」「サイズが合わなくなってしまった」 「急な訃報で、手元に喪服がない」
このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。特に女性の場合、年齢や体型の変化に合わせて、その都度喪服を買い替えるのは、経済的にも大きな負担になります。
そんな時におすすめなのが、喪服のレンタルサービスです。
インターネットで気軽に申し込める【Cariru BLACK FORMAL】は、質にこだわったブランドの喪服を、必要な時だけレンタルできる便利なサービスです。
【Cariru BLACK FORMAL】のおすすめポイント
- デザインと質にこだわった品揃え: 弔事のマナーに沿って厳選された、質の高いブラックフォーマルが豊富に揃っています。
- 急な訃報にも対応: 16時までの注文で、最短翌日午前中には届けてもらえるので、急なご参列でも安心です。
- 必要なものが全て揃うフルセット: ジャケット、ワンピースだけでなく、バッグ、サブバッグ、ネックレス、イヤリング、数珠、袱紗まで揃ったフルセットもあります。
- クリーニング不要で返却できる: 返却時はそのまま送るだけでOK。クリーニングの手間がありません。
購入するよりも手軽でリーズナブルに、質の良い喪服を着ることができます。急な時だけでなく、事前に準備しておきたい方にもぴったりのサービスです。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
服装マナーについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
葬儀後の「遺品整理」と「香典返し」
お葬式が終わった後も、やるべきことはたくさんあります。
特に、遺品整理と香典返しは、ご遺族にとって大きな負担となりがちです。
1. 遺品整理:故人様を偲ぶ大切な時間
故人様がお部屋に残された遺品や不要物を整理することは、故人様との思い出を振り返る大切な時間でもあります。しかし、遺品の量が多い場合や、遠方に住んでいる場合など、ご遺族だけで全てを整理するのは大変なことです。
そういったお悩みを抱えている方のために、遺品整理専門のサービスがあります。
【ライフリセット】は、ご遺族に寄り添いながら、遺品整理のお手伝いをしてくれる専門業者です。
【ライフリセット】のおすすめポイント
- 故人様の想いを大切に: 単に物を片付けるだけでなく、ご遺族の気持ちに寄り添い、故人様の想いのこもった遺品を丁寧に扱ってくれます。
- 生前整理にも対応: ご本人が元気なうちに、ご自身の持ち物を整理する「生前整理」にも対応しています。
- 専門家による安心のサービス: 遺品整理に関する専門知識を持ったスタッフが、適切に作業を進めてくれます。
ご遺族の負担を少しでも減らし、故人様とのお別れに専念するためにも、専門家にお任せするのも一つの選択肢です。
2. 香典返し:感謝の気持ちを伝える大切な贈り物
お葬式でいただいた香典へのお返しとして、香典返しを贈るのが日本の慣習です。
香典返しは、四十九日法要を終えた後、忌明けの挨拶とともに贈るのが一般的です。感謝の気持ちを伝える大切な贈り物ですので、失礼のないように選びたいものです。
香典返しのマナー
- 金額の目安: いただいた香典の金額の、半額から3分の1程度の品物を選ぶのが一般的です。
- 品物の選び方:
- 「消えもの」を選ぶ: お茶やコーヒー、お菓子、海苔など、食べたり使ったりしてなくなるものが良いとされています。
- 「不幸が繰り返されないように」という意味: 洗剤やタオルなど、後に残らない日用品も適しています。
- 「カタログギフト」も人気: 相手の方に好きなものを選んでもらえるカタログギフトも、香典返しとして人気があります。
香典返しを選ぶなら、ギフト専門店の【シャディギフトモール】がおすすめです。
シャディは1926年創業の老舗ギフト専門店。弔事だけでなく、様々な用途に対応した豊富な品揃えが魅力です。
【シャディギフトモール】のおすすめポイント
- 豊富な商品ラインナップ: 1万点以上の商品の中から、ご予算や相手の方の好みに合わせて選べます。
- のし紙やメッセージカードも無料: 弔事用ののし紙や、感謝の気持ちを伝えるメッセージカードを無料で付けてもらえます。
- ギフトのプロがサポート: どんなものを選べばいいか迷った時も、専門のスタッフがサポートしてくれます。
感謝の気持ちを込めて、最適な香典返しを選んでみませんか?
香典返しについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
まとめ:紫の意味を知って、故人様との最期のお別れを
今回は、葬儀で使われる「紫」の意味について、その歴史やマナーを交えながら解説しました。
紫は、古くから「高貴」で「神聖」な色として、特別な意味を持ち続けてきました。
故人様への敬意を表し、格式高く厳粛な雰囲気の中で、最期のお別れを告げる場にふさわしい色なのです。
故人様との最期のお別れは、一生に一度の大切な儀式です。
紫色の意味を知ることで、より深く故人様を偲び、心を込めてお見送りすることができるのではないでしょうか。
この記事が、終活を考えていらっしゃる方、ご家族の葬儀について不安を抱えている方にとって、少しでも安心につながるきっかけになれば幸いです。
これからも、このブログを通じて、皆様のお役に立てる情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。