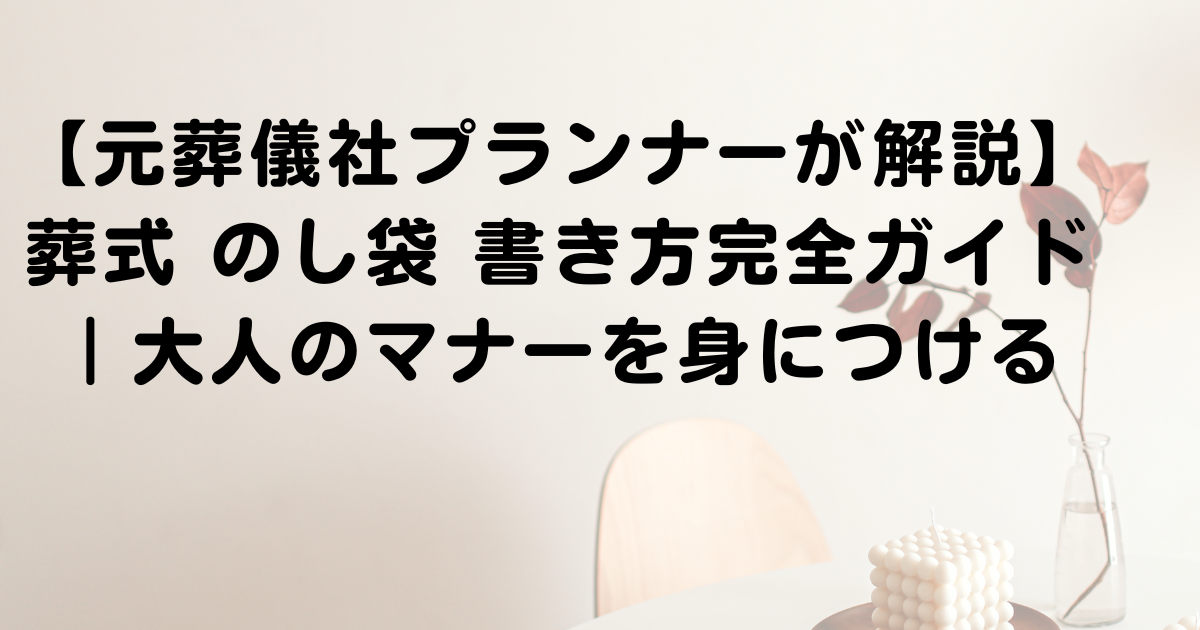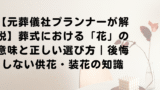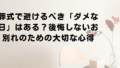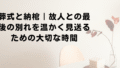こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
ご葬儀は、人生の中でそう何度も経験することではありません。だからこそ、いざという時に戸惑いや不安を感じるのは当然のことです。特に、弔事のマナーは日常とは異なることが多く、ひとつひとつの作法に「これでいいのだろうか…」と心を悩ませてしまう方も少なくないでしょう。
今回は、その中でも特に多くの方が悩まれる「葬式ののし袋(不祝儀袋)」の書き方について、元葬儀社プランナーとして800件以上の葬儀に立ち会ってきた私の経験をもとに、ひとつずつ丁寧にご説明していきます。
この記事を最後までお読みいただければ、もう不祝儀袋の書き方で迷うことはありません。自信を持って故人様への想いを込めた香典を包み、大人のマナーを身につけることができるはずです。
故人様への想いを伝える大切な「のし袋」
お香典は、故人様への弔意を表すとともに、ご遺族の葬儀にかかる費用の一部を負担し、経済的な助けとなる意味合いがあります。そして、そのお香典を包む「のし袋」は、単なる入れ物ではありません。
のし袋に記された文字は、故人様への最後の別れを惜しむあなたの真摯な気持ちを表すものです。だからこそ、正しいマナーで丁寧に書くことが、何よりも大切なのです。
特に、近年ではご葬儀の形式も多様化し、地域や宗派によって異なる慣習も多く存在します。画一的な情報だけでは対応しきれないことも増えていますので、この記事では、さまざまなケースに対応できるよう、より実践的な知識に焦点を当ててお伝えしていきます。
1. 葬式の「のし袋」を選ぶ
まず最初に、不祝儀袋を用意するところから始めましょう。お香典袋とも呼ばれるこの袋は、ご祝儀袋とは全く異なるものです。間違えてしまうと大変失礼にあたりますので、注意が必要です。
不祝儀袋には、主に以下の種類があります。
- 水引の色:黒白、双銀、黄白
- 水引の結び方:結び切り
- 袋の装飾:蓮の絵柄の有無
選び方のポイント①:水引の色と結び方
水引は、袋の表面に結ばれた飾りの紐のことです。葬儀用の不祝儀袋では、黒白または双銀(銀色のみ)の水引が一般的です。
- 黒白:最も一般的で、仏式、神式、キリスト教式など、宗派を問わず広く使用できます。
- 双銀:格調高い水引とされ、高額な香典(3万円以上が目安)を包む際に使われることが多いです。
また、水引の結び方にも注目してください。ご葬儀では、「結び切り」という結び方のものが使われます。「結び切り」は、一度結ぶと簡単にほどけないことから、「二度と繰り返すことのないように」という願いが込められています。
蝶結び(花結び)は、何度でも結び直せることから、お祝い事やお礼の際に用いられる結び方です。間違って購入しないように注意しましょう。
選び方のポイント②:宗派による違い
宗派によっては、特定の不祝儀袋を使うのがマナーとされています。
- 仏式:蓮の花の絵柄がついたものを使用できます。
- 神式・キリスト教式:蓮の絵柄は使えません。無地の不祝儀袋を選びましょう。
仏式のご葬儀に参列する場合でも、宗派がわからない場合は、蓮の絵柄がない無地のものを選んでおけば間違いありません。
選び方のポイント③:金額による違い
不祝儀袋は、包む金額によっても選ぶべきものが異なります。
- 5千円~1万円程度:水引が印刷された簡易的な不祝儀袋で十分です。
- 1万円~5万円程度:黒白や双銀の水引がついた、少し立派なものを選びましょう。
- 5万円以上:双銀の水引がついた、より格式の高い不祝儀袋がふさわしいでしょう。
金額に見合わない不祝儀袋だと、かえって失礼にあたることがあります。例えば、5千円しか包んでいないのに豪華な袋を使ったり、逆に5万円包んでいるのに簡易的な袋を使ったりするのは避けた方が良いでしょう。
2. 表書きの「書き方」
不祝儀袋を選んだら、いよいよ表書きを書いていきます。ここが最も戸惑う方が多いポイントです。
筆記具は「薄墨」が基本
弔事の文字は、薄墨(うすずみ)で書くのがマナーです。これは、悲しみの涙で墨がにじんでしまった、という気持ちを表すためとされています。
- 薄墨の筆ペン:文房具店やコンビニなどで手軽に購入できます。
- 薄墨の筆:より丁寧な印象になります。
もし薄墨が手元にない場合は、黒い筆ペンやサインペンでも構いませんが、できれば薄墨を用意するのが望ましいでしょう。ただし、ボールペンや鉛筆は失礼にあたりますので、絶対に避けましょう。
表書きの書き方:宗派による違い
表書きとは、袋の上の部分に書く言葉のことです。宗派によって書き方が異なりますので、ご遺族に確認できる場合は事前に確認しておきましょう。
| 宗派 | 表書きの言葉 |
| 仏式(四十九日より前) | 「御霊前(ごれいぜん)」 |
| 仏式(四十九日より後) | 「御仏前(ごぶつぜん)」 |
| 神式 | 「御玉串料(おたまぐしりょう)」「御榊料(おさかきりょう)」 |
| キリスト教式 | 「お花料(おはなりょう)」 |
| どの宗派でもOK | 「御香典(ごこうでん)」「御香料(ごこうりょう)」 |
一般的に、仏式のご葬儀に参列する場合は「御霊前」と書くのが無難です。しかし、一部の宗派(浄土真宗など)では「御霊前」を使わず、最初から「御仏前」と書くのがマナーとされています。
もし宗派がわからない場合は、「御香典」または「御香料」と書いておけば、失礼にあたることはありません。この2つは、どの宗派でも広く使える万能な表書きです。
表書きの書き方:連名にする場合
夫婦や職場の連名で香典を包む場合もあります。
- 夫婦の場合:中央に夫のフルネームを書き、その左隣に妻の名前のみを記入します。
- 連名(3名以下)の場合:中央に格上の方(会社であれば役職者など)のフルネームを書き、その左隣に続けて名前を書いていきます。
- 連名(4名以上)の場合:「〇〇一同」や「〇〇有志」と書き、別に紙に全員の名前を記載して中袋に入れます。
3. 中袋の「書き方」と「入れ方」
不祝儀袋の中には、「中袋(なかぶくろ)」と呼ばれる白い封筒が入っています。これには、お金を入れます。中袋の書き方にもマナーがあります。
中袋の書き方
- 表面:中央に「金額」を漢数字で丁寧に書きます。
- 裏面:左側に「郵便番号、住所、氏名」を記入します。
金額の書き方は、改ざん防止のため、旧字体(大字)の漢数字を使うのが一般的です。
- 1,000円 → 壱仟円
- 3,000円 → 参仟円
- 5,000円 → 伍仟円
- 10,000円 → 壱萬円
- 50,000円 → 伍萬円
お札の入れ方
お札は、中袋に入れる前に必ず確認すべきことがあります。
- 新札は避ける:新札は、事前に不幸を予期して準備していた、という意味に取られかねません。古いお札(使用感のあるもの)を使いましょう。もし新札しかない場合は、一度折り目を付けてから入れるのがマナーです。
- 肖像画の向き:お札の肖像画が裏向きになるように、中袋に入れます。これは、悲しみに顔を伏せる、という気持ちを表すためと言われています。
お札の枚数にも注意が必要です。偶数は割り切れるため、「縁が切れる」ことを連想させてしまい、避けるべきとされています。また、**「4」(死)や「9」(苦)**を連想させる枚数も避けましょう。
香典の相場は?
香典の金額は、故人様との関係性やご自身の年齢によって異なります。
| 故人様との関係 | 相場(金額) |
| 両親 | 5万円~10万円 |
| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |
| 祖父母 | 1万円~3万円 |
| 親戚 | 5千円~1万円 |
| 友人・知人 | 5千円 |
| 勤務先の上司・同僚 | 5千円 |
あくまで相場ですので、ご自身の経済状況を考慮して無理のない範囲で包むことが大切です。また、ご葬儀の形式が「家族葬」などで辞退されている場合は、無理に持参する必要はありません。
4. 葬式に参列する際の服装と持ち物
のし袋の準備が整ったら、次にご葬儀に参列する際の服装や持ち物について確認しておきましょう。
ご葬儀は、故人様と最後のお別れをする大切な儀式です。失礼のない服装で、落ち着いた気持ちで参列することが何よりも重要です。
喪服について
喪服は、正式な儀式にふさわしい「正喪服」「準喪服」「略喪服」の3種類があります。一般的にご葬儀に参列する場合は、「準喪服」を着用するのがマナーです。
- 男性:ブラックスーツ、白いワイシャツ、黒のネクタイ、黒い靴下、黒い革靴。
- 女性:黒のワンピースやアンサンブル、黒いストッキング、黒いパンプス。
喪服は、急な訃報にも対応できるよう、一着は持っておきたいものです。しかし、体型の変化や流行によって、いざという時に「サイズが合わない」「デザインが古い」といった悩みも出てきますよね。
私も葬儀社で働いていた際、急な訃報で喪服をどうしたらいいか相談を受けることがよくありました。特に、お仕事帰りなどで急遽駆けつける場合、喪服の用意ができず焦ってしまう方も少なくありません。また、めったに着る機会がない喪服を新調するのは、経済的にも負担が大きいと感じる方もいらっしゃるでしょう。
そんな時におすすめしたいのが、喪服のレンタルサービスです。例えば、【Cariru BLACK FORMAL】は、デザインや質にこだわった上質な喪服を、必要な時に必要なだけ借りられるので非常に便利です。人気のブランドも多数取り扱っており、ジャケットやワンピースはもちろん、バッグ、数珠、袱紗など、弔事に必要な小物がすべてセットになっているプランも豊富にあります。
【Cariru BLACK FORMAL】は、24時間いつでもネットで申し込めて、16時までの注文なら最短で翌日午前中に届けてくれるので、急な訃報にも対応できます。返却時のクリーニングも不要で、非常に手軽に利用できるのが嬉しいポイントです。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
もし今、喪服のことでお悩みであれば、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
持ち物について
ご葬儀に持参するものは、以下の通りです。
- 不祝儀袋(香典)
- 袱紗(ふくさ):香典を包む布です。紫色の袱紗は慶弔両方に使えるので便利です。
- 数珠:宗派によって形が異なりますが、ご自身の宗派の数珠を持参しましょう。
5. 葬儀後のマナーと香典返し
無事にご葬儀が終わり、ご遺族は故人様への想いとともに、参列してくださった方々への感謝の気持ちを伝えることになります。それが「香典返し」です。
香典返しの基本
香典返しは、いただいた香典へのお礼として贈る品物のことです。
- 贈る時期:四十九日の法要を終えた後、1ヶ月以内を目安に贈るのが一般的です。
- 金額の目安:いただいた香典の金額の半額~3分の1程度が相場とされています。
- 品物の選び方:不幸を「消し去る」という意味から、消え物(食品や洗剤など)が選ばれることが多いです。最近では、相手に好きなものを選んでもらえる「カタログギフト」も人気です。
香典返しは、故人様への最後の別れを惜しんでくださった方々への、感謝の気持ちを伝える大切な機会です。失礼のないように、しっかりと準備しておきたいものです。
香典返しを用意する際、たくさんの品物の中から選ぶのは大変ですよね。特に、喪主として初めての経験であれば、何を選べば良いのか、マナーはどうすれば良いのか、悩みが尽きないことでしょう。
そんな時は、ギフト専門店のオンラインショップを利用するのがおすすめです。例えば、【シャディギフトモール】は、1926年創業のギフト専門店で、様々な用途に対応できる1万点以上の商品が揃っています。
香典返しにふさわしい品物はもちろん、包装やのし紙、メッセージカードも無料で豊富に用意されているので、マナーに沿った贈り物を手軽に準備できます。カタログギフトの種類も豊富なので、贈る相手に喜んでもらえるものが見つかるはずです。
6. 万が一に備えて「終活」を考える
ここまで、ご葬儀のマナーについて詳しく見てきましたが、ご葬儀は突然訪れることがほとんどです。だからこそ、日頃から「もしもの時」に備えておくことが、残されたご家族の負担を減らすことにつながります。
終活のすすめ
「終活」とは、人生の終わりに向けて、身の回りのことや財産、大切な人へのメッセージなどを整理しておく活動のことです。
具体的には、以下のようなことをしておくと良いでしょう。
- エンディングノートの作成:ご自身の希望する葬儀の形式や、財産、介護のことなどを書き記しておきます。
- お墓や供養方法の検討:お墓をどうするか、永代供養にするかなど、事前に家族と話し合っておきます。
- 遺言書の作成:法的に有効な遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぐことができます。
しかし、「終活をしたいけれど、何から手をつければいいかわからない」「誰に相談したらいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
実は、私も父を突然亡くした際、葬儀の手配から遺品整理まで、本当に多くのことに直面しました。時間がない中で、精神的にも経済的にも大きな負担がかかり、本当に苦しい経験でした。
だからこそ、「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」という思いで、葬儀業界に飛び込みました。
葬儀の準備は、逝去後わずか数時間以内に行うことが大半です。時間がない中で、十数万円〜数百万円という高額な費用がかかる葬儀社を選ばなければなりません。そして、葬儀社の品質は玉石混交で、ご遺族が納得のいく葬儀ができなかったという話も耳にします。
そんな時、頼りになるのが、信頼できる葬儀社の情報を集めることです。
例えば、東証プライム上場企業のエスエムエスが運営する【安心葬儀】は、全国7000以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を紹介してくれるサービスです。
複数の葬儀社から見積もり(相見積もり)を取ることができるので、価格やサービス内容を比較検討し、納得のいく葬儀社を見つけることができます。時間がなくても、専門のスタッフが丁寧に対応してくれるので、安心して任せることができます。
終活をご検討中の方や、ご家族のもしもの時に備えて情報を集めておきたい方は、ぜひ一度【安心葬儀】に相談してみてはいかがでしょうか。
7. 遺品整理も忘れずに
ご葬儀が終わった後、ご遺族が直面するのが「遺品整理」です。故人様が大切にしていた遺品を整理する作業は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
遺品整理のポイント
- 故人様の想いを尊重する:遺品は、故人様が生きてきた証です。ひとつひとつ丁寧に、故人様の想いを汲み取りながら整理することが大切です。
- 専門業者に依頼する:故人様のお部屋が広い場合や、遺品が多い場合は、専門の業者に依頼することも検討しましょう。
- 形見分け:親族や友人で形見分けをしたい場合は、事前に誰に何を渡すか決めておきましょう。
遺品整理は、ご家族だけで行うには時間も体力も必要です。特に、遠方に住んでいる場合や、仕事が忙しい場合は、なかなか進まないこともあるでしょう。
そんな時は、遺品整理の専門業者に依頼するのも一つの方法です。
例えば、【ライフリセット】は、故人様がお部屋に残した遺品や不要物を整理してくれる専門業者です。遺品整理のプロが、故人様の遺品を丁寧に扱い、ご家族の気持ちに寄り添って作業を進めてくれます。
また、最近ではご自身が元気なうちに身の回りの整理をする「生前整理」も注目されています。ご自身の持ち物を整理しておくことで、ご家族に負担をかけることなく、安心して老後を過ごすことができます。
遺品整理や生前整理でお悩みの方は、ぜひ一度【ライフリセット】にご相談されてみてはいかがでしょうか。
まとめ|大人のマナーを身につけて、心穏やかにお別れを
今回は、「葬式のし袋の書き方」を中心に、葬儀に関する様々なマナーについて解説してきました。
- のし袋:黒白・双銀の水引で、「結び切り」のものを選ぶ。金額や宗派によって使い分ける。
- 表書き:「御霊前」「御香典」など、宗派に合わせた言葉を「薄墨」で書く。
- 中袋:金額は旧字体の漢数字で丁寧に記入し、お札は新札を避け、肖像画が裏向きになるように入れる。
- 服装:準喪服を着用し、袱紗と数珠も持参する。
- 葬儀後のマナー:香典返しは、金額の半額~3分の1を目安に、四十九日を過ぎてから贈る。
ご葬儀は、故人様との最後の時間です。慌ただしい日々の中で、ひとつひとつのマナーを気にしすぎて、故人様への想いを伝えきれなかった…なんてことになっては悲しいですよね。
この記事が、みなさまが心穏やかに、そして故人様への敬意を持って、お別れの時間を過ごすための一助となれば幸いです。
これからも、このブログでは「後悔しないお別れ」のために、さまざまな情報をお届けしていきます。
葬儀についてもっと詳しく知りたい方へ
これらの記事も、ぜひご参考にしてみてください。
もし、葬儀に関して「こんな時どうしたらいいんだろう?」といったご不安やご不明な点があれば、いつでもお気軽にお声がけください。みなさまのお役に立てるよう、心を込めて情報をお届けしていきます。