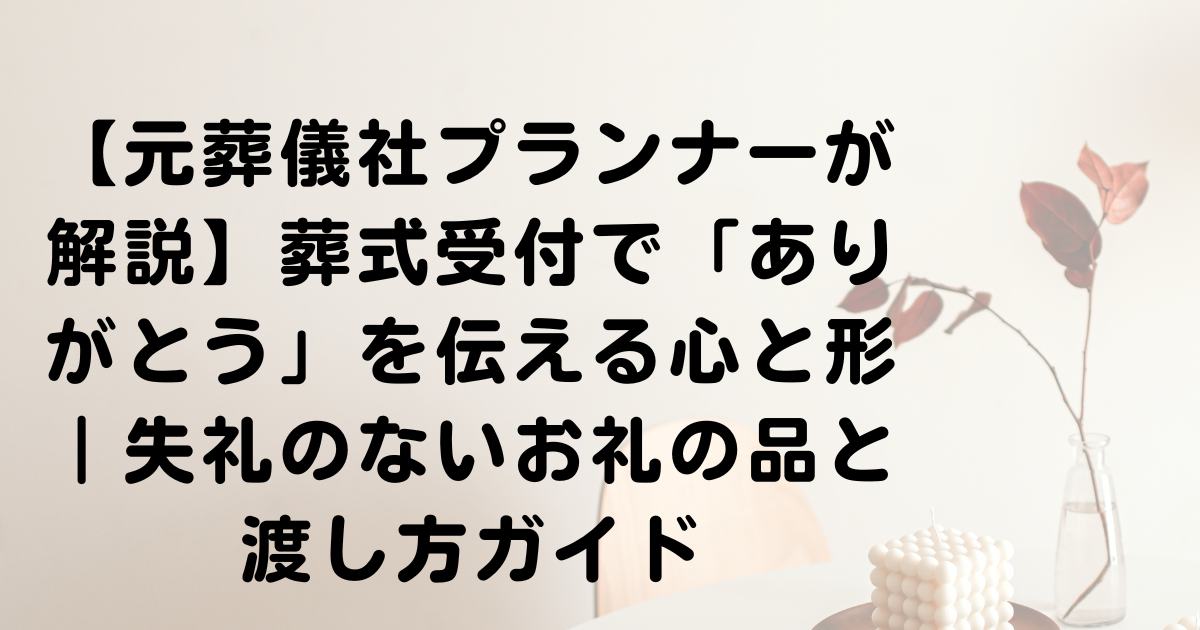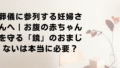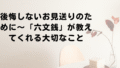はじめに:大切な人を送る、最後の「おもてなし」
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
以前、葬儀社でプランナーとして働いていた経験から、お葬式という特別な時間を、ご遺族が心穏やかに過ごせるよう、日々情報発信をしています。私自身、20代の頃に父を突然亡くし、何もかもがわからず不安に苛まれた経験があります。だからこそ、今、このブログを読んでくださっている皆さんの心に寄り添い、少しでもお力になれたらと願っています。
お葬式は、故人様とのお別れの場であると同時に、故人様を想い、駆けつけてくださった方々への感謝を伝える場でもあります。特に、受付という大切な役割を担ってくださる方々へは、心からの「ありがとう」を伝えたいものです。
この記事では、元葬儀社プランナーとしての経験をもとに、葬式受付のお礼について、その心構えから具体的なお礼の品、そして渡し方のマナーまで、幅広く、そして丁寧に解説していきます。
「何を渡したらいいの?」「いくらぐらいのものがいいの?」「いつ、どうやって渡すのが正しいの?」といった疑問をお持ちの方に、安心して準備を進めていただけるよう、具体的な情報をお届けします。どうぞ、最後までゆっくりとご覧ください。
1. そもそも、なぜ葬儀の受付にお礼が必要なのか?
「葬儀の受付って、手伝ってもらうのが当たり前じゃないの?」
もしかしたら、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、受付という役割は、想像以上に多岐にわたり、精神的な負担も大きいものです。
受付が担う、3つの大切な役割
受付係は、単にお香典を受け取るだけではありません。
- ご参列者の対応:弔問に訪れる方々を一番最初にお迎えし、お悔やみの言葉を交わします。
- お香典の管理:故人様への想いが込められたお香典を、正確に記帳し、大切に管理します。
- ご案内役:記帳やご焼香の案内、返礼品の受け渡しなど、スムーズな式進行をサポートします。
悲しみに暮れるご遺族に代わり、これらの役割をテキパキとこなしてくれる受付係は、お葬式を円滑に進める上で、なくてはならない存在です。
特に、ご遺族にとっては、悲しみの中で「誰に受付を頼むか」という決断も大きな負担となります。そんな中、快く引き受けてくださった方々へ、感謝の気持ちを伝えることは、人間関係を円滑にする上で非常に大切なことです。
受付係を頼む相手と関係性
受付を依頼するのは、故人様やご遺族と特に親しい関係にある方々がほとんどです。
- 故人様の友人や知人
- ご遺族の親戚や友人
- 会社関係の方(同僚や部下)
- 町内会や地域の有志の方々
いずれの場合も、ご遺族との信頼関係がなければお願いすることはできません。また、受付係は、故人様との最後の時間を大切にしたいご遺族の代わりに、たくさんのご参列者と向き合い、細やかな気配りをしてくれます。この心遣いに対し、感謝の気持ちを形にして伝えるのが、「受付のお礼」なのです。
「ありがとう」という言葉を添えて渡すお礼の品には、「大変な役目を引き受けてくれて、本当にありがとう」「おかげで無事に故人を見送ることができました」という、ご遺族の心からの感謝の気持ちが込められているのです。
2. 葬式受付のお礼、相場はいくら?何を用意すればいいの?
いざお礼を用意しようと思っても、
「いくらぐらいのものが妥当なの?」 「何を渡したら失礼にあたらない?」
と迷う方は少なくありません。ここでは、お礼の相場とお礼の品について、具体的な例を挙げて解説していきます。
お礼の相場:金銭で渡す場合
まず、最も一般的なお礼の渡し方は、現金や商品券です。
- 友人・親戚など:3,000円〜5,000円
- 会社関係の方:3,000円〜5,000円
- 専門家(会計士など):10,000円以上
一般的な相場は、3,000円〜5,000円が目安です。ただし、故人様やご遺族と特に親しい関係にある方、あるいは受付だけでなく、車の手配や様々な雑務まで幅広く手伝ってくださった方には、少し多めに渡すこともあります。
お渡しする際は、そのまま現金を渡すのではなく、白い封筒や不祝儀袋(のし袋)に入れるのがマナーです。
- 表書き:「御礼」「志」
- 水引:結び切り(一度きりを意味する)
地域や慣習によっては、何も書かずに白い封筒に入れるだけ、という場合もあります。迷った場合は、葬儀社の担当者に相談してみましょう。
お礼の品物で渡す場合
現金ではなく、品物でお礼を渡すことも一般的です。
- 品物の相場:3,000円〜5,000円程度
品物を選ぶ際は、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
- 重すぎないもの、かさばらないもの
- 日持ちするもの
- 相手の好みを気にせず渡せるもの
具体的には、以下のようなものが喜ばれます。
- お菓子:焼き菓子やクッキーの詰め合わせなど、日持ちがして個包装されているものが便利です。
- お茶・コーヒー:普段使いしやすい、少し上質なものが喜ばれます。
- 商品券・ギフトカード:相手に好きなものを選んでもらえるため、非常に喜ばれます。
お礼の品を選ぶのが難しい、という場合は、カタログギフトもおすすめです。相手に好きなものを選んでもらえるため、失敗がありません。
シャディギフトモールのような専門サイトを利用すれば、予算に合わせて様々な種類のカタログギフトを探すことができます。葬儀のお返し(香典返し)にも使える品物が多く、お礼の品としても重宝します。オンラインで手軽に注文でき、熨斗(のし)や包装にも対応してくれるため、忙しい時でも安心して準備できます。
もし、受付の方に小さなお子様がいる場合は、お菓子の詰め合わせを少し多めにしたり、別で用意して渡すなど、細やかな気配りが喜ばれます。
また、遠方から手伝いに来てくださった方には、交通費や宿泊費として、少し多めに現金を包むこともあります。
【元葬儀社プランナーのワンポイントアドバイス】 お礼の品物を選ぶ際は、「消えもの」を選ぶのが一般的です。「消えもの」とは、消費してなくなるもののこと。不幸を後に残さない、という意味合いから選ばれます。お菓子や食品、洗剤などがこれにあたります。
3. お礼を渡すタイミングと、スマートな渡し方
「お礼を渡すタイミングっていつがいいの?」
これもよくいただく質問です。適切なタイミングで、気持ちを込めてお礼を渡すことで、相手に感謝の気持ちがより伝わります。
お礼を渡すベストなタイミングは「お葬式の後」
お礼を渡すタイミングは、一般的にお葬式の一切が済んだ後です。
- 具体的には?:通夜や告別式が終わり、ご参列者をお見送りした後、受付係の方に集まっていただき、改めて感謝の言葉を伝える場を設けるのが理想的です。
ただし、お葬式後すぐに火葬場へ向かうなど、時間が限られている場合は、その場で渡すことが難しいかもしれません。その場合は、後日改めてお礼に伺うか、ご自宅へお礼の品を郵送するなどの対応も可能です。
スマートな渡し方のマナー
お礼を渡す際は、以下のポイントを押さえておくと、より丁寧な印象になります。
- 感謝の言葉を伝える:お礼の品を渡す前に、「この度は、お忙しい中、受付を引き受けてくださり、本当にありがとうございました」「おかげさまで、滞りなく故人を見送ることができました」など、心からの感謝の言葉を伝えましょう。
- 直接手渡しする:できれば、一人ひとりに手渡しするのが丁寧です。まとめて渡す場合は、皆さんの前で感謝の言葉を述べた上で渡しましょう。
- 両手で渡す:品物や封筒は、両手で丁寧に渡します。
- タイミングを見計らう:忙しい葬儀の最中に渡すのは避け、ご遺族も受付係も落ち着いたタイミングを選びましょう。
【注意!】 お礼の品物を選ぶ際、四つ足生臭もの(肉や魚)は避けるのが一般的です。これらは仏教の教えで殺生を連想させるため、慶事では喜ばれますが、弔事の贈り物には不向きとされています。
4. 葬式受付に関する、知っておきたいQ&A
ここまでお礼について解説してきましたが、他にも受付に関する疑問は尽きないものです。ここでは、よくある質問にお答えしていきます。
Q1. 会社の人に受付をお願いした場合、お礼はどうする?
A. 会社の方にお願いした場合も、基本的には同様にお礼を用意します。
- 相場:3,000円〜5,000円程度
- 渡し方:後日、職場へお礼に伺うのが一般的です。
ただし、会社によっては「社内のことなので、お礼は不要」という慣習がある場合もあります。事前に上司や同僚に確認してみると良いでしょう。
Q2. 遠方から手伝いに来てくれた親戚には、交通費も渡すべき?
A. 遠方から来てくださった方には、お礼とは別に**「お車代」**として交通費を渡すのが一般的です。
- 金額:実費、またはそれに準ずる額
- 渡し方:現金の場合は、白い封筒に入れ「御車代」と表書きをします。
「遠いところ、わざわざありがとう」という感謝の気持ちを込めてお渡ししましょう。
Q3. 受付をお願いする人がいない場合はどうすればいい?
A. 昨今では、ご遺族や親戚が少なく、受付係を立てることが難しいケースも増えています。その場合は、葬儀社に受付代行を依頼することも可能です。
- 費用:葬儀社によって異なりますが、数万円程度が目安です。
- メリット:ご遺族の負担が減り、お別れに集中できます。
【元葬儀社プランナーのワンポイントアドバイス】 ご親戚やご友人に受付をお願いする際は、葬儀の準備で忙しい中、いつ誰に連絡すべきか迷ってしまうものです。訃報の連絡と合わせて、受付をお願いしたい旨を早めに伝えることで、相手も心の準備がしやすくなります。
5. 葬儀全般に関する、押さえておきたい知識
お葬式の準備は、時間との勝負です。訃報を受けてから慌ただしく準備を進める中で、様々な疑問や不安が湧いてくることでしょう。受付のお礼だけでなく、お葬式全般に関する知識を少しでも持っておくことで、いざという時に冷静に対応できるようになります。
知っておきたい「お葬式の流れ」
まず、お葬式の全体像を把握しておくことが大切です。
- 逝去:医師から死亡診断書を受け取ります。
- 葬儀社への連絡:故人様を搬送してもらうため、葬儀社に連絡します。
- 打ち合わせ:葬儀社の担当者と、葬儀の形式や日程、費用などを決めます。
- 訃報の連絡:親族や友人、会社関係などへ連絡します。
- 通夜:夜間に執り行われるお通夜です。
- 告別式・火葬:故人様との最後のお別れをし、火葬します。
- 精進落とし・初七日法要:火葬後に会食を設けます。
突然のことで何から手をつけて良いかわからない、という方は、【保存版】葬式の流れをやさしく解説|後悔しない準備と心構えもぜひ参考にしてみてください。事前に流れを把握しておくだけでも、心の負担は大きく軽減されます。
葬儀社選びの重要性
お葬式を成功させる上で最も重要なのが、信頼できる葬儀社を選ぶことです。
しかし、急なことで複数の葬儀社を比較する時間がないのが現実です。故人様を搬送してもらうために、すぐに目の前の葬儀社に決めてしまい、後で後悔するケースも少なくありません。
そこでおすすめなのが、複数の葬儀社から見積もりを取る「相見積もり」です。
安心葬儀というサービスを利用すれば、全国7000以上の葬儀社から、ご希望の条件に合わせて最適な優良葬儀社を紹介してもらえます。東証プライム上場企業のエスエムエスが運営しているため、安心して利用できます。
「時間がないから」と一社に絞り込むのではなく、短時間でも複数の選択肢を持つことが、「後悔しないお別れ」につながります。
受付以外のマナー:服装について
受付のお礼と同様に、お葬式のマナーとして重要なのが「服装」です。特に女性は、喪服のデザインや小物選びで悩むことが多いでしょう。
- 喪服:故人様を悼む気持ちを表現するため、格式に沿った服装を心がけましょう。
- 小物:バッグや靴は黒色で、装飾の少ないものを選びます。
「久しぶりに喪服を着たらサイズが合わない」「急なことで準備する時間がない」という場合は、喪服のレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。
Cariru BLACK FORMALでは、デザインや質にこだわった喪服や礼服をレンタルできます。ジャケット・ワンピース・バッグ・数珠・袱紗などがセットになったフルセットが豊富に揃っており、急な訃報でも安心です。16時までの注文で最短翌日午前中に届くため、忙しい方にもおすすめです。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
また、服装について詳しく知りたい方は、【元葬儀社プランナーが解説】もう迷わない「葬式の服装」完全ガイド|大人として恥をかかないためにをご参照ください。
6. 葬儀後の「お返し」と「整理」
お葬式が終わり、故人様を見送った後も、やるべきことは残っています。
香典返しについて
受付でいただいたお香典へのお返しとして、香典返しを用意します。
- 時期:忌明け(四十九日法要後)に行うのが一般的です。
- 相場:いただいたお香典の半額〜3分の1程度の品物を用意します。
「何を選んだらいいの?」「どうやって渡すのが正しいの?」と迷ったときは、【元葬儀社プランナーが解説】葬式後の香典返し|失礼のない贈り方・選び方ガイドを参考に、失礼のないように準備を進めましょう。
香典返しも、カタログギフトがおすすめです。シャディギフトモールでは、香典返しに特化したカタログギフトも豊富に取り揃えられています。
遺品整理について
お葬式が終わった後、ご遺族を悩ませるのが遺品整理です。
- 故人様の想い出の品
- 不要になった家具や家財
- 処分に困るもの
悲しみの中で、これらの整理を行うのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。また、貴重品や故人様の想いが詰まった品を不用意に処分してしまうリスクもあります。
そのような場合は、遺品整理の専門業者に依頼することを検討してみましょう。
ライフリセットのような専門業者に依頼すれば、故人様の想いを尊重しながら、丁寧に遺品整理を行ってくれます。ご遺族の気持ちに寄り添い、必要なものを仕分けし、不要なものを適切に処分してくれます。また、生前にご本人様が「生前整理」として依頼するケースも増えています。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも、心を落ち着かせる大切な選択です。
まとめ:心からの「ありがとう」を込めて
この記事では、葬式受付のお礼について、その心構えから具体的な方法まで、幅広く解説しました。
- 受付のお礼は、感謝の気持ちを伝える大切なマナーです。
- お礼の相場は、3,000円〜5,000円程度。現金や品物で渡します。
- お礼を渡すタイミングは、お葬式の一切が済んだ後がベストです。
- お礼の品は、相手の負担にならない「消えもの」を選ぶのがおすすめです。
お葬式という特別な時間は、故人様を送り出すための大切な儀式です。しかし同時に、お別れのために駆けつけてくださった方々への感謝を伝える時間でもあります。
受付係の方々へ、心からの「ありがとう」を伝えること。それは、故人様とのご縁を大切にし、また故人様を想ってくださった方々とのご縁をこれからも繋いでいくための、大切な一歩となります。
この記事が、皆さんの不安を少しでも和らげ、心穏やかにお葬式を迎えられる一助となれば幸いです。
お葬式に関するご相談や疑問があれば、いつでも当ブログを訪れてみてください。皆さんの「後悔しないお別れ」のために、心を込めて情報発信を続けていきます。
筆者プロフィール
Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。