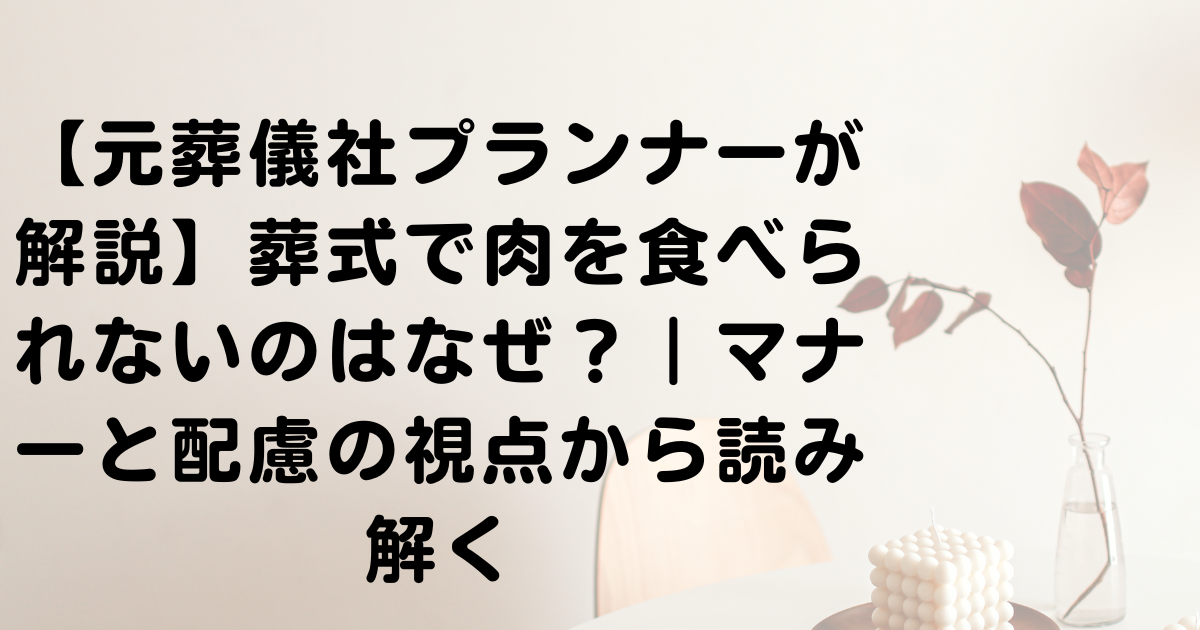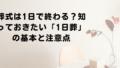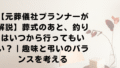こんにちは、元葬儀社プランナーのKeisukeです。
葬儀というと、多くの人が「儀式」「別れ」「喪失感」といったイメージを抱かれるかもしれません。しかし、実際の現場ではもっと細やかな“気づかい”が積み重なって、ご遺族の悲しみを包み込んでいきます。
その中の一つに、「肉料理は出してはいけない」「肉は食べてはいけない」といった“食のタブー”があります。
「なぜ葬式では肉を避けるのか?」「実際のところ、絶対にダメなのか?」「故人が肉好きだった場合は?」——こういった疑問は、実は多くの方から相談される内容の一つでした。
この記事では、葬儀の食事マナーの中でも特に「肉を食べない」という点に焦点を当てて、宗教的・文化的背景、実際のマナー、最近の変化や対応の工夫まで、やさしく、ていねいに解説していきます。
- 肉がタブーとされる背景とは?仏教的な考え方
- 実際にはどこまで気をつけるべき?地域差と現代の傾向
- 参列者として「肉が出たらどうすればいいの?」という疑問
- お葬式の準備は「心の余裕」がカギ|信頼できる葬儀社を見つけるには
- 葬儀で肉を出すときの配慮と工夫|“正しさ”より“気づかい”を
- 精進落としと“肉を食べること”の意味|時代とともに変わる常識
- 多様な背景を持つ人への配慮|ベジタリアン・宗教・アレルギー対応
- 葬儀の服装に困ったら?必要なものをすぐに整える工夫
- 葬儀が終わっても終わらない「片付け」と「心の整理」
- 信頼できる遺品整理のプロとともに|【ライフリセット】のご紹介
- 香典返しに迷ったら?贈って安心のギフト選びとは
- 香典返しに迷わない!ギフト専門店【シャディギフトモール】がおすすめ
- 肉を食べない本当の意味と、故人を想う心のかたち
- 宗教や慣習を「怖がらず」、でも「軽んじず」
- 信頼できる葬儀社を選ぶという“最初の分岐点”
- 「後悔しないお別れ」のために、いま考えられること
- おわりに|大切な人の死を通して、“生きる”を考える
肉がタブーとされる背景とは?仏教的な考え方
日本の葬儀の多くは仏教に基づいて行われます。仏教においては、「殺生を避ける」ことが基本的な教えのひとつです。この教えから、葬儀や精進料理の場では、肉や魚を避ける=動物の命を奪った食べ物を口にしないという慣習が根付いています。
特に通夜や葬儀当日の会食(お斎/おとき)では、肉や魚を使わず、精進料理を提供するのが正式な形とされてきました。
精進料理とは、五葷(ごくん:にんにく、ねぎ、らっきょうなど)や動物性食品を使わず、素材そのものの味を活かした料理です。
この背景には、故人の冥福を祈るとともに、「穢れ(けがれ)」を遠ざけるという古来の考え方も関係しています。葬儀そのものが“死”に関わるため、肉や魚のように「命を奪う」食材は避けられてきたのです。
実際にはどこまで気をつけるべき?地域差と現代の傾向
とはいえ、実際には葬儀の料理に肉が出されることも増えてきています。特に都市部やホテルでの会食では、精進料理ではなく、普通の和食や洋食が出されることも珍しくありません。
これは、以下のような背景によるものです。
- 宗教色が薄れてきている
- 参列者の多様化(子どもや外国人など)
- 時間やコストの都合
- 故人や家族の希望を重視する流れ
たとえば、関西地方の一部では昔から比較的柔軟な対応がされており、精進料理でなくても問題視されないこともあります。一方で、東北や北陸地方などでは今でも厳格に守られているケースが多いと感じます。
筆者が葬儀社で担当していたあるご家庭では、「父が大の焼肉好きだったから、みんなで焼肉を囲む“お斎”にしたい」とのご希望がありました。最終的に、法要の後に身内だけで焼肉店に行かれたそうです。「宗教的なタブーを気にする人がいるから」との配慮で、通夜や葬儀の当日は精進料理を出し、親しい人たちの間だけで“いつもの食卓”を再現したわけです。
参列者として「肉が出たらどうすればいいの?」という疑問
もし葬儀の場で、肉が出てきたらどうすればいいのか。参列者としては少し悩ましいところですが、答えはシンプルです。
基本的には「出されたものをありがたくいただく」のがマナーです。
ご遺族が意図して肉料理を出しているのであれば、それを拒むことのほうがかえって失礼になる場合があります。ただし、宗教的な理由やアレルギーなどで肉を避けている場合は、事前に伝えるか、周囲に静かに伝えて残すようにしましょう。
どうしても気になる場合は、「葬儀における食事のマナー」を事前に知っておくことで、心の準備ができるようになります。たとえば、以下の記事では、葬式の全体の流れの中でのマナーや立ち振る舞いについて、やさしくまとめています。
お葬式の準備は「心の余裕」がカギ|信頼できる葬儀社を見つけるには
「食事のことまで考えるなんて大変」と感じられる方も多いでしょう。実際、葬儀は急に発生することが多く、食事の手配、服装の準備、会場の選定など、やるべきことが一気に押し寄せます。
その中でも特に大切なのが、「信頼できる葬儀社選び」です。
私自身も、父の葬儀で時間のない中で焦って決めた結果、後悔が残る対応をされてしまった苦い経験があります。だからこそ、いま事前に情報収集しておくことが重要だと強く感じています。
最近では、全国の優良な葬儀社を比較・見積もりできる【安心葬儀】というサービスが注目されています。
✅ 全国7000以上の葬儀社から比較
✅ 東証プライム上場企業のエス・エム・エスが運営
✅ 数時間以内に葬儀社の紹介が受けられる
✅ 葬儀費用の相場や流れも分かりやすく説明あり
限られた時間の中で、「心の余裕」を確保するための強い味方になるサービスです。葬儀の現場を知る者として、こうしたサポートを上手に活用してほしいと願っています。
葬儀で肉を出すときの配慮と工夫|“正しさ”より“気づかい”を
葬儀において肉料理を提供することが必ずしもタブーではなくなってきているとはいえ、やはり「気をつけておいたほうが良い」ことがあるのも事実です。特に、親戚の中に年配の方や信心深い方がいらっしゃる場合、昔ながらの価値観を大切にしている方の気持ちに配慮することが、何より大切です。
たとえば、ホテルの仕出し料理などで肉が含まれるメニューを選ぶ場合でも、
- 主菜に肉が使われていても、副菜や前菜は精進風に仕立てる
- 「豚・牛は避けて、鶏肉や魚介類のみ」にとどめる
- お斎ではなく、「精進落とし」として分けて出す
- メニューの案内に“精進料理ではありません”と明記する
など、「宗教的な配慮を欠いたわけではない」という姿勢を示すことができます。
特に家族葬や親しい人だけの少人数の葬儀では、故人の好みに合わせた料理を出すというご家庭も増えています。「おじいちゃんの好きだった唐揚げを、最後にみんなで囲もう」という思い出を共有することは、悲しみの中に温かさを生む瞬間でもあります。
こうした場合でも、「全員が快く受け取れるような工夫」を忘れずにという視点が大切です。
精進落としと“肉を食べること”の意味|時代とともに変わる常識
「肉はダメ」とされる一方で、「精進落とし」という言葉をご存じでしょうか?
精進落としとは、忌明け(四十九日法要など)の際に、それまでの喪に服する生活を終えて日常生活に戻るという意味を込めた行事の一環です。このときには、精進料理から離れ、肉や魚を含む食事をとるのが一般的とされてきました。
つまり、「肉を食べること=故人を軽んじている」と捉えるのではなく、
“日常に戻ること”=“生きていくための再出発”
と考えることもできます。
実際、現代では「通夜・葬儀の料理は肉なし、忌明け後の会食では肉あり」といった形で、段階的に移行するようなスタイルも見受けられます。
葬儀に参列する際に、こうした流れを知っておくだけでも、慣れない場面での戸惑いを減らすことができます。
多様な背景を持つ人への配慮|ベジタリアン・宗教・アレルギー対応
最近では、ベジタリアンやビーガン、食物アレルギー、イスラム教徒など、食に関する制限を持つ参列者への配慮も求められるようになってきました。
たとえば:
- 野菜中心の別メニューを1~2人分用意しておく
- あらかじめアレルゲン表示をした料理を注文する
- 受付でアレルギーや希望を確認しておく
といった方法が挙げられます。
実際に私が担当したあるご葬儀では、ご遺族が「うちの甥がイスラム教徒で豚肉がNGなんです」と事前に伝えてくださったことで、個別にハラール対応の弁当をご用意したケースもありました。
こういった準備は、参列者にとって大きな安心になりますし、“細やかな気づかい”が、心に残るお葬式になることも少なくありません。
葬儀の服装に困ったら?必要なものをすぐに整える工夫
肉の話題からは少し離れますが、もうひとつよくある「困りごと」が、急な訃報での服装の準備です。
「喪服が昔のものしかなくてサイズが合わない」
「突然のことで靴やバッグが間に合わない」
「マナー的にこれで大丈夫か不安…」
こういった声は本当によく聞きます。
そんな時に便利なのが、【Cariru BLACK FORMAL】というレンタルサービスです。
✅ 葬儀マナーに沿ったアイテムをすぐに揃えられる
✅ ジャケット・ワンピース・バッグ・靴・アクセサリーなど一式対応
✅ ネットで選べて、最短翌日午前中にお届け
✅ 高品質でデザイン性の高いフォーマルをレンタル可能
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
購入よりもリーズナブルで、着たあとはクリーニング不要で返却できるため、忙しい中でも心に余裕を持って準備ができる点が好評です。
「肉を避けるべきか」だけでなく、「服装の不安をどう減らすか」も含めて、今の時代に合った柔軟な考え方が求められているのかもしれません。
葬儀が終わっても終わらない「片付け」と「心の整理」
葬儀が無事終わったあと、「ようやくひと段落……」と思うのもつかの間。ご遺族にとっては、ここからがまた新しい現実との向き合いの始まりです。
その中でも、特に多くの方が負担に感じるのが、
故人の遺品の整理
です。
私も、葬儀後のご相談で最も多いのがこの「遺品整理」に関する内容です。
遺品整理に潜む“心の負担”
「何を残して、何を手放すべきかわからない」
「衣類や写真、書類、日用品……物が多すぎて手がつけられない」
「兄弟間で処分に対する温度差がある」
「一つひとつに思い出があって、捨てられない」
こういったお声を、本当にたくさん耳にしてきました。
遺品整理は、単なる“物の片付け”ではありません。
そこには必ず、「感情」が伴います。
だからこそ、ご自身だけで無理をせず、専門の業者に相談することも選択肢の一つです。
信頼できる遺品整理のプロとともに|【ライフリセット】のご紹介
特におすすめしたいのが、遺品整理専門の【ライフリセット】というサービスです。
このサービスの強みは以下の通りです:
✅ ご遺族の気持ちに寄り添った対応
✅ 分別・処分・清掃までトータル対応
✅ 遠方からの依頼でもOK(立ち合い不要プランあり)
✅ 生前整理にも対応
大切な方を失った直後は、どうしても「判断力が落ちる」状態になりやすいもの。
そんなときに、無理に全部自分で片付けようとせず、プロの手を借りることで心にも時間にも余裕が生まれます。
特に、高齢の親の家の片付けに直面している40代・50代の方には強くおすすめしたいサービスです。
一人で抱え込まず、“家族の思い出を大切に残す”ための選択肢として、ぜひ知っておいてください。
香典返しに迷ったら?贈って安心のギフト選びとは
もうひとつ、葬儀後に訪れる“悩ましい課題”が、香典返しの準備です。
最近では香典返しを「当日返し(即日返し)」とするケースも多いですが、四十九日を終えてから贈るスタイルも根強く残っています。
いずれにしても悩むのが…
- 何を贈れば良いのか
- いくらの品が適切なのか
- 贈り先の住所が分からない/まとめて管理できない
- のし紙や挨拶状の書き方がわからない
という点です。
私が葬儀社にいた頃も、特に年配の方が「失礼があったら…」と慎重になる姿をよく見ました。
香典返しは、形式の中にも「心づかい」が表れる部分。
できればしっかり選びたいものですよね。
香典返しに迷わない!ギフト専門店【シャディギフトモール】がおすすめ
そんなときに頼りになるのが、ギフト専門の【シャディ公式】が運営する通販サイト、シャディギフトモールです。
このサービスのポイント:
✅ 創業1926年、老舗の安心感
✅ 香典返し・法要返礼品に特化したカテゴリが充実
✅ カタログギフト、食品、お茶・海苔・タオルなど定番品も多数
✅ のし・包装・挨拶状無料、メッセージカードもOK
✅ 新規会員登録で500円クーポンももらえる
私の体験上、香典返しは「間違いのない定番品」を選ぶのが一番安心です。
その中でも、品質や包装に安心できる専門店を使うことで、喪主としての責任をしっかり果たすことができます。
肉を食べない本当の意味と、故人を想う心のかたち
葬儀のあと、「肉は食べてはいけないのか?」と迷う人が今も少なくありません。
しかし本質的には、“何を口にするか”以上に、“どのような心で過ごすか”が大切なのです。
先にお話ししたように、仏教における精進料理は、単なる菜食主義ではなく「殺生を避け、心を静め、哀悼の念に集中する」ための習慣でした。
現代の私たちは、宗派や地域の習慣に囚われすぎてしまい、かえって「これでいいのか」と悩むことも多くなっています。
しかし、**大切なのは“形式ではなく、故人を想う気持ち”**です。
たとえば葬儀後の会食で、肉が出てきたとしても、それを「ありがたくいただくこと」は失礼ではありません。
むしろ「食を通じて命をいただくこと」を実感し、故人の命、いのちの連なりに感謝を捧げることこそが供養の本質ともいえるでしょう。
宗教や慣習を「怖がらず」、でも「軽んじず」
私が葬儀社に勤めていたとき、こんなご家族がいらっしゃいました。
「親が厳格な仏教徒で、精進料理しか出さないと決めた。
でも自分たちはそこまで信仰がなくて……。
どうしたらいいのか、正直わからないんです。」
このようなケースはよくあります。
結論から言えば、「どうしてそれを選ぶのか」「なぜそれを避けるのか」を自分たちで話し合って、納得したうえで決めることが一番大切です。
宗教的な背景を尊重しつつ、現代的な価値観も取り入れながら、バランスを取っていく。
その姿勢が、故人にも十分に伝わると私は信じています。
信頼できる葬儀社を選ぶという“最初の分岐点”
今回の「肉を食べてはいけないのか?」という疑問もそうですが、実は多くの不安や迷いは、葬儀をお願いする葬儀社がしっかりしていれば、ほとんど解消できることが多いです。
経験豊富なプランナーであれば、
- 宗派に応じた会食内容
- 精進落としの意味
- 法要の準備とマナー
- 食事に配慮が必要な場合の対処法
など、あなたの状況に合わせて、柔軟かつ丁寧にアドバイスしてくれるはずです。
実際に、私が現役プランナーの頃も「お肉は避けた方が良いか」や「法要のお弁当に海老や鰻が入ってもいいか」といったご相談は日常的にありました。
そうした質問に、その場その場で真摯に答えられるスタッフがいるかどうかが、葬儀の“安心感”を左右するといっても過言ではありません。
「後悔しないお別れ」のために、いま考えられること
「葬式で肉を食べてはいけない」と聞くと、
「じゃあどうしたらいいの?」と不安になって当然です。
けれども、ここまで読んでくださったあなたには、もうわかっていただけたかと思います。
本当に大事なのは、“故人を思い、心静かに過ごす時間”をどう持つか。
「食べ物」そのものに善悪はなく、「気持ちのあり方」が供養になる。
人それぞれ、家族それぞれのやり方があって当然です。
決まりきった“正解”がないからこそ、心を込めて向き合う姿勢が何よりも尊いのです。
どうか、「これは間違いだったのではないか」「あのとき、こうすれば良かったのでは」などと、後悔することのないよう、信頼できる情報と、支えてくれる人の手を借りてください。
おわりに|大切な人の死を通して、“生きる”を考える
「肉を食べてはいけないのか」という一つの疑問から始まった今回のテーマですが、
振り返ってみるとそれは、“死”と“生”をどう受け止めるかという問いそのものでした。
誰かを失った悲しみは、時に深く、長く、重たいものです。
けれど、そこから私たちが学び、次の世代へと受け継ぐこともまた、亡き人の教えではないでしょうか。
どうか、あなたとあなたのご家族のこれからが、
“心のこもったお別れ”とともに、後悔のない時間を歩んでいけることを、心から願っています。