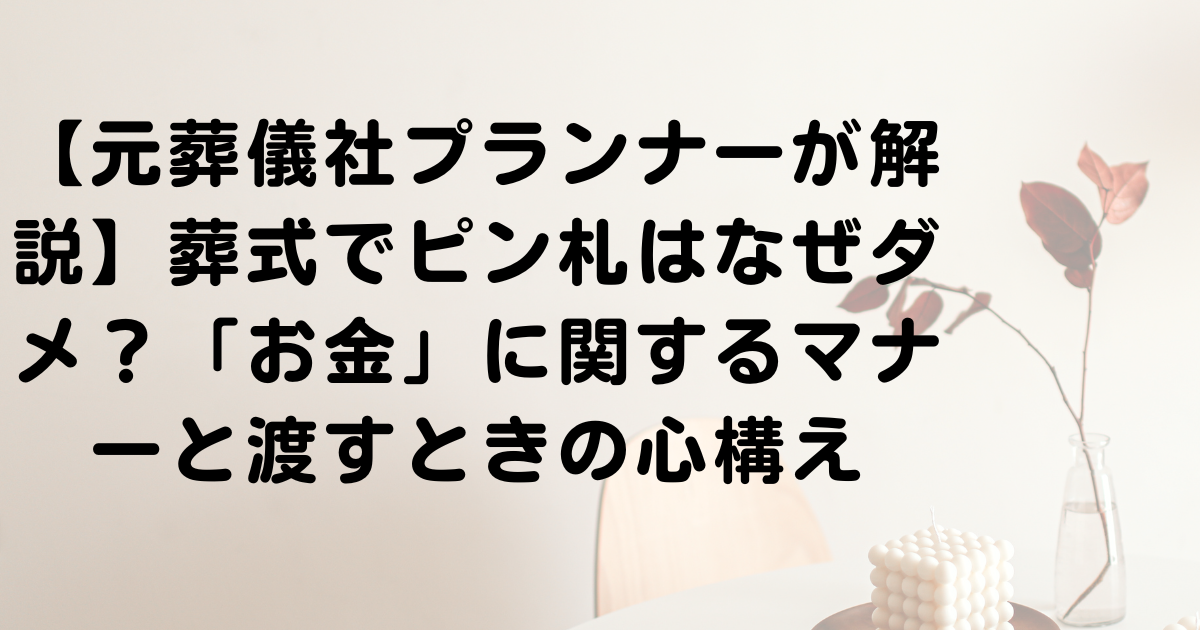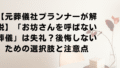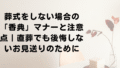こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
先日、読者の方からこのようなご質問をいただきました。
「近々、お葬式に参列する予定です。香典を包むお金について、ひとつ疑問があります。結婚式では新札を包むのがマナーと聞きますが、葬式ではなぜピン札は避けるべきなのでしょうか?急な訃報で銀行に行く暇もなく、手元に新券しかなかった場合はどうすればよいですか?」
ご質問、ありがとうございます。
この方は、「新札は慶事で使うもの」という認識はお持ちでしたが、その意味や、もし手元に新札しかなかった場合の対処法について、疑問をお持ちでした。
お葬式は、人生で何度も経験することではないので、誰しもが多くの疑問や不安を抱くものです。とくに「お金」に関するマナーは、故人様やご遺族への気持ちを表す大切な行為であるため、失礼のないようにしたいと考えるのは当然のことでしょう。
そこでこの記事では、元葬儀社プランナーとして800件以上のご葬儀に携わってきた私の経験をもとに、葬式におけるお金のピン札にまつわる疑問を、丁寧にわかりやすく解説していきます。
葬式でピン札はなぜダメ? 香典に「新札」が不適切な理由
まず、ご質問にあった「なぜ葬式でピン札はダメなのか」という疑問からお答えします。
結論から言うと、香典にピン札(新札)を避けるべき理由は、「不幸を予期していたわけではない」という気持ちを伝えるためです。
結婚式では、「この日を心待ちにしていました」という気持ちを表すために、前もって準備した新札を包むのがマナーとされています。
一方、お葬式は、突然の訃報によって執り行われることがほとんどです。そのため、前もって準備していたかのように見える新札は、「不幸を予期して待っていた」と受け取られかねない、という考え方から避けるべきとされているのです。
これは、故人様やご遺族に対する配慮、思いやりの気持ちから生まれた日本ならではの繊細なマナーと言えるでしょう。
もちろん、これはあくまで「心遣い」であり、新札だからといって故人様やご遺族を不快にさせる意図があるわけではありません。しかし、古くから続く慣習として、多くの人がこの考え方を大切にしています。
手元にピン札しかなかった場合の対処法
では、ご質問にあった「急な訃報で銀行に行く暇がなく、手元に新札しかなかった場合」はどうすればよいのでしょうか。
一番簡単な方法は、お札に折り目をつけることです。
具体的には、お札を一度、縦横どちらかに軽く折り、折り目をつけてから香典袋に入れるようにします。このひと手間を加えることで、「急いで準備しました」という気持ちが伝わり、マナーとして問題ありません。
昔は、お葬式に参列する機会も多かったため、自宅に使い古したお札を何枚か用意しておいた、という方もいらっしゃいました。しかし、現代ではキャッシュレス化も進み、常に手元に現金があるとは限りません。
また、香典袋に入れるお札は、できるだけ肖像画が裏側になるように入れるのが一般的です。これは、悲しみの中で故人様への敬意を表すため、顔を下向きにすることで「悲しくて顔を伏せている」という気持ちを込める、という説があります。
香典の金額は? 誰に聞けばいい?
香典を包む際、もうひとつ悩ましいのが金額です。
いくら包めばよいか、という明確なルールはありませんが、一般的な相場は存在します。
故人様との関係性によって金額は異なりますが、一般的には以下の金額が目安とされています。
- 故人様が両親の場合: 5万円〜10万円
- 故人様が兄弟姉妹の場合: 3万円〜5万円
- 故人様が祖父母の場合: 1万円〜3万円
- 故人様が親戚(伯父・伯母など)の場合: 1万円
- 故人様が友人・知人の場合: 5千円〜1万円
- 故人様が会社関係者の場合: 5千円〜1万円
ただし、これはあくまで一般的な目安です。地域や宗派、ご自身の年齢や経済状況によっても異なります。
また、金額には「4(死)」や「9(苦)」といった不吉な数字を避けるのがマナーとされています。
たとえば、4,000円や9,000円といった金額は避け、5,000円や10,000円などにするのが一般的です。
しかし、急なことで、誰に聞けばいいかわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、ご親族や、親しいご友人などに相談してみるのが一番確実な方法です。
そもそも「香典」とは? その意味と由来
香典とは、故人様への供養のためのお線香やお花、お香の代わりに、現金を供えることから始まった慣習です。
昔は、突然の訃報で、遠方から駆けつけることが困難な時代でした。そこで、旅費や故人様の供養のためのお金として、現金を包んだのが由来とされています。
また、もう一つの大切な意味合いとして、ご遺族への経済的な負担を少しでも軽減したい、という気持ちが込められています。
ご葬儀には、まとまった費用がかかります。
ご遺族は、大切な方を亡くした悲しみの中で、葬儀の手配や費用のことを考えなければなりません。そのような状況で、少しでも経済的な助けになれば、という温かい心遣いが香典には込められているのです。
この香典の文化は、現代においてもその意味合いは変わりません。
葬式のお金、香典以外にもかかる費用は?
ご葬儀にかかる費用は、香典だけではありません。
ご遺族にとって、ご葬儀の費用は非常に大きな負担となります。
- 葬儀一式費用: 祭壇、棺、霊柩車、火葬費用、骨壺など、ご葬儀を執り行うために必要な費用です。
- お布施: 読経や戒名を授けていただくお礼として、お寺や僧侶にお渡しするお金です。
- 飲食接待費用: 通夜振る舞いや精進落としなど、参列者をもてなすための費用です。
これらの費用は、葬儀の規模や形式、地域や葬儀社によって大きく異なります。
最近では、ご自身の葬儀について事前に調べておく「終活」に取り組む方も増えています。
将来、大切なご家族に金銭的な負担をかけたくない、という思いから、ご自身の葬儀費用を事前に準備しておく方もいらっしゃいます。
また、ご家族の葬儀を検討されている方にとっては、費用を比較検討し、納得のいく形で故人様をお見送りしたい、と考えるのは当然のことでしょう。
良い葬儀社を見つけるには?
ご葬儀の費用は、葬儀社によって大きく異なります。
- 「費用が予想以上に高かった」
- 「追加料金が多く、不透明だった」
- 「スタッフの対応が不親切だった」
このような後悔をしないためにも、良い葬儀社を選ぶことは非常に重要です。
しかし、ご家族が亡くなられてから数時間以内に葬儀社を決定しなければならないケースも多く、時間がない中で焦って決めてしまう、という方も少なくありません。
そこで、私が元プランナーとしておすすめしたいのが、複数の葬儀社から見積もりをとる「相見積もり」です。
相見積もりをすることで、費用の内訳を比較でき、適正な価格を知ることができます。また、複数の担当者と話すことで、その葬儀社の雰囲気やスタッフの対応も確認できます。
「でも、たくさんの葬儀社に連絡するのは大変だし、時間もない…」
そのように感じられる方もいらっしゃるでしょう。
そのような方におすすめしたいのが、株式会社エス・エム・エスが運営する【安心葬儀】です。
【安心葬儀】は、全国7,000以上の優良な葬儀社の中から、ご希望の条件に合わせて最適な会社を紹介してくれるサービスです。
東証プライム上場企業が運営しているため、安心してご利用いただけます。
終活のすすめ
ご自身の終活を検討されている方も、ご家族の葬儀を考えている方も、まずは情報収集から始めてみませんか?
「まだ早い」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自身の考えを整理し、ご家族と話し合う時間を持つことで、もしもの時に慌てることなく、心穏やかに故人様をお見送りすることができます。
「【保存版】葬式の流れをやさしく解説|後悔しない準備と心構え」という記事も参考にしていただければ幸いです。
終活は、残されたご家族への「最後のプレゼント」とも言えるでしょう。
葬儀後のお金、香典返しはどうすればいい?
さて、香典をいただいた側のご遺族は、次に「香典返し」について考えることになります。
香典返しとは、香典をいただいた方々へのお礼の品のことです。
「香典をいただいたのに、お返しを用意するなんて…」と恐縮される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは日本に古くから伝わる大切な習慣であり、いただいたご厚意に対して感謝の気持ちを伝えるためのものです。
香典返しの相場は、いただいた香典の金額の3分の1から半分程度が一般的です。これを「半返し」と呼びます。
たとえば、1万円の香典をいただいた場合は、3,000円から5,000円程度の品物をお返しします。
香典返しを贈る時期は、忌明け(四十九日法要後)が一般的です。これは、「無事に四十九日を終えました」というご報告の意味も込められています。
しかし、最近では、「当日返し」といって、通夜や葬儀の当日に香典返しをお渡しするケースも増えてきました。
これは、遠方からお越しの方や、急なことで後日連絡をとるのが難しい方への配慮から始まったものです。当日に香典返しをお渡しする場合は、一律2,000円から3,000円程度の品物を準備することが多いです。
香典返し、何を贈れば喜ばれる?
香典返しに選ばれる品物には、いくつかのマナーがあります。
「消えもの」と呼ばれる、使ったらなくなるものが良いとされています。これは、「不幸が残らないように」という願いが込められているからです。
具体的には、以下のようなものがよく選ばれています。
- お茶、コーヒー: 毎日飲むものなので、どなたにも喜ばれます。
- お菓子: 個包装になっているものだと、分けやすくて便利です。
- タオル、石鹸: 日用品なので、いくつあっても困りません。
- カタログギフト: 相手に好きなものを選んでもらえるので、非常に人気があります。
なかでも、カタログギフトは、贈る側の負担が少なく、受け取る側も自分の好きなものを選べるため、近年非常に人気が高まっています。
香典返しで何を贈るかお悩みの方に、私がおすすめしたいのが【シャディギフトモール】です。
シャディ株式会社は1926年創業のギフト専門店で、幅広い年齢層の方に喜ばれる品物を豊富に取り揃えています。
特に、香典返しに最適なカタログギフトの種類が豊富で、価格帯も幅広く用意されているので、きっとぴったりのものが見つかるはずです。
香典返しに関する詳しいマナーについては、「【元葬儀社プランナーが解説】葬式後の香典返し|失礼のない贈り方・選び方ガイド」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
お葬式のお金、喪服の準備も意外と大変…
お葬式に参列する際、もうひとつお金がかかるのが「喪服」です。
ご葬儀は突然のことで、喪服の準備が間に合わない、という方もいらっしゃるでしょう。
- 「久しぶりに着ようと思ったらサイズが合わなくなっていた」
- 「季節に合った喪服が手元にない」
- 「急なことでクリーニングに出す時間がない」
このようなお悩みを持つ方も少なくありません。
また、喪服は普段着る機会が少ないため、購入するとかなりの出費になります。
そこで、私がおすすめしたいのが、喪服のレンタルサービスです。
必要なときに、必要な期間だけ借りられるレンタルサービスは、金銭的な負担を減らすだけでなく、保管やクリーニングの手間も省けるので、非常に便利です。
特におすすめなのが、デザイン・質・マナーにこだわる方のための喪服・礼服のレンタル【Cariru BLACK FORMAL】です。
このサービスは、弔事のマナーに沿って厳選された、質の高い人気ブランドのブラックフォーマルを、購入するよりもリーズナブルに利用できます。
ジャケット、ワンピースはもちろん、バッグ、数珠、袱紗など、必要なものがフルセットでレンタルできるので、急な訃報でも慌てずに対応できます。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
喪服の選び方や着こなし方については、「【元葬儀社プランナーが解説】もう迷わない「葬式の服装」完全ガイド|大人として恥をかかないために」という記事もご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
葬儀後のお金、遺品整理はどうすればいい?
ご葬儀を終え、一段落ついた後、ご遺族が直面するのが「遺品整理」です。
故人様のお部屋に残された大切な遺品や、不要になった家財などを整理する作業は、時間も労力もかかります。
また、故人様との思い出が詰まった品々を前に、感情的になり、なかなか作業が進まない、という方も少なくありません。
特に、遠方にお住まいのご家族や、ご高齢のご両親が亡くなられた場合、遺品整理は大きな負担となるでしょう。
このような場合、無理に自分たちだけで頑張ろうとせず、専門の業者に依頼するという選択肢も考えてみてください。
遺品整理の専門業者は、遺品の仕分けから運び出し、清掃まで、一連の作業をすべて代行してくれます。
なかでも、株式会社アシストが運営する【ライフリセット】は、遺品整理の専門家として、ご遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に作業を進めてくれます。
遺品整理と一口に言っても、故人様が大切にされていた品物は、ただの「モノ」ではありません。そこに込められた想いを大切にしながら、ひとつひとつ丁寧に扱ってくれる業者を選ぶことが重要です。
【ライフリセット】は、故人様への敬意を払い、ご遺族の心に寄り添うことを大切にしています。
ご自身やご家族の「終活」の一環として、生前整理を検討される方も増えています。将来、ご家族に負担をかけたくないという思いから、元気なうちに身の回りの整理を始める方もいらっしゃいます。
遺品整理や生前整理について、少しでもご興味がある方は、ぜひ一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
まとめ:後悔しないお別れのために、今できること
この記事では、葬式におけるお金のピン札にまつわるマナーから、ご葬儀にかかる費用、そして葬儀後のお金に関する悩みまで、幅広く解説してきました。
お葬式は、故人様とのお別れの時間を、心穏やかに過ごすための大切な儀式です。
しかし、突然の訃報で、多くの不安や疑問に直面することは避けられません。
この記事が、もしもの時に慌てず、故人様やご遺族への心遣いを大切にしながら、後悔のないお別れを迎えるための一助となれば、これ以上嬉しいことはありません。
私は元葬儀社プランナーとして、ご遺族の不安や戸惑いに数えきれないほど寄り添ってきました。
ご葬儀に関する情報は、一人で抱え込まず、信頼できる専門家やサービスを頼ることで、金銭的・精神的な負担を大きく軽減することができます。
このブログでは、これからも皆様が安心して「お別れ」を迎えられるよう、様々な情報を発信していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。