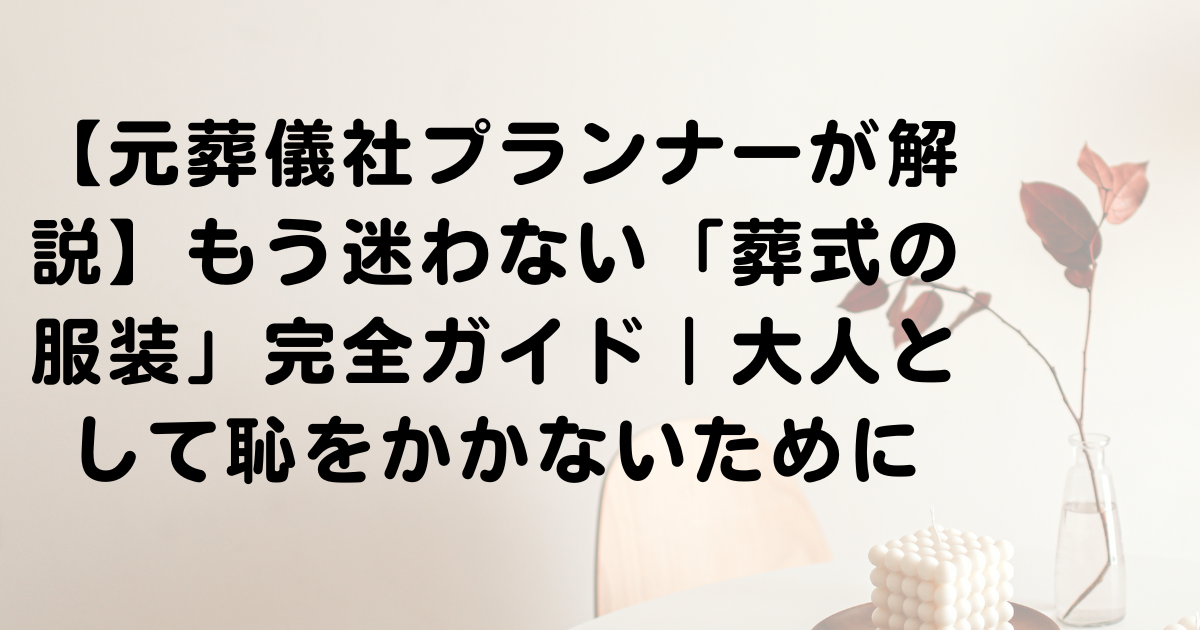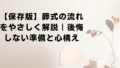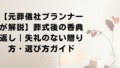こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisuke(けいすけ)です。
私は地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らす42歳の元葬儀社プランナーです。
12年間にわたり800件以上のご葬儀を担当し、現場で培ってきた知識と経験を、少しでも多くの方に役立ててもらえたらと思い、このブログを立ち上げました。
今回のテーマは「葬式の服装」。
誰しも人生の中で避けられない“お別れの場”ですが、服装マナーに自信があるという方は意外と少ないものです。
「これで大丈夫なのかしら…」
「昔とマナーが変わっていたらどうしよう…」
「子どもは何を着せれば?」
私が葬儀社で働いていた頃、最も多かったご質問のひとつが「服装」についてでした。
大切な方との最後のお別れだからこそ、礼を失したくない。
そう思って悩むのは、何よりもご遺族や故人に敬意を払いたいというお気持ちの表れだと思います。
この記事では、そうしたお悩みや不安を解消できるよう、以下のような内容を丁寧に解説していきます。
第1章:葬式の服装に「正解」はあるのか?
「喪服を着ていけばいいんでしょ?」
実はこの質問、答えが一番難しいものでもあります。なぜなら、“喪服”とひとことで言っても、実に多くの種類があるからです。
特に40代以上の方であれば、冠婚葬祭に対して一定の常識やマナーを意識している方が多いと思います。ですが、「昔ながらの常識」が現代では必ずしも正解とは限らないケースもあるのです。
たとえば、昭和の時代には「喪服は必ず和装」という認識が強くありましたが、現在では洋装が主流です。また、黒一色が当然と思われがちですが、葬儀の種類や立場(喪主・親族・一般参列者)によっても、服装の選び方は変わってきます。
また、地域や宗教によっても“正解”が微妙に異なるのも厄介なポイントです。
「同じ県内でも、隣町ではまったく風習が違った」ということも珍しくありません。
だからこそ、“形式よりも気持ちを尊重した服装選び”が大切になってくるのです。
次章からは、男女別・世代別・シーン別に、より具体的な服装マナーを詳しく見ていきましょう。
第2章:男性の葬式の服装マナー|基本と例外
男性の葬儀の服装は、女性に比べて選択肢が少ない分、基本を押さえていれば大きな失敗はありません。ただし、「きちんとして見えるかどうか」が非常に重要です。
■ 正喪服・準喪服・略喪服とは?
葬儀における男性の服装は、格式によって3つに分けられます。
- 正喪服:モーニングコート(昼用)、タキシード(夜用)など。主に喪主や親族代表などが着用。
- 準喪服:一般的に多くの参列者が着る「ブラックスーツ」。
- 略喪服:黒やグレーのダークスーツ。急な訃報などに対応するための「最低限の礼儀」。
ほとんどのケースでは、「準喪服=ブラックスーツ」があれば問題ありません。
■ ブラックスーツの正しい着こなし方
ブラックスーツであれば何でもいい、と思われがちですが、葬儀用の礼服は“冠婚葬祭専用”の漆黒のスーツであることがポイントです。ビジネス用の黒スーツは、微妙に色味が異なり、光沢も強いため、葬儀の場では「浮いてしまう」ことがあります。
以下のようなポイントに注意してください:
- シングルまたはダブルの黒無地スーツ(漆黒)
- 白無地のシャツ(レギュラーカラーまたはワイドカラー)
- 黒無地のネクタイ(光沢のないもの)
- 黒の革靴(紐付きが基本、スリッポンはNG)
- 黒の靴下(くるぶしが見えない長さ)
さらに、腕時計やアクセサリー類は極力控えるのが基本マナーです。どうしても腕時計をする必要がある場合は、金属部分が目立たない黒の革ベルトのものを選ぶのが無難です。
急な訃報でも安心|喪服が手元にないときの対応
実際には、「突然の訃報で準備が間に合わない」「体型が変わってしまい、昔の喪服が入らない」などの声も多く聞かれます。そんなときに助けになるのがブラックフォーマルのレンタルサービスです。
特に男性の場合は、何年も着る機会がなく、いざという時に慌てて買いに走ってもサイズが合わなかったり、TPOに合わないものを選んでしまうリスクもあります。
そんなときにおすすめなのが、デザインと質、マナーを兼ね備えた喪服レンタルサービス【Cariru BLACK FORMAL】です。
▶ Cariru BLACK FORMALの特長
- 24時間ネット申込み可能・最短で翌日午前に到着
- ブランド礼服・フォーマル小物も一式揃う
- クリーニング不要でそのまま返却OK
- 5,000円以上で送料無料/3泊4日~90日まで選べるレンタル期間
突然の訃報でも、必要な時に必要なものをすぐに届けてくれる安心感は非常に心強いものです。特に「見た目に気を使いたい」「社会人として失礼のない服装をしたい」という方にとって、Cariruのサービスは非常に頼れる存在です。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
次章では、女性の服装マナーについて解説していきます。男性よりも選択肢が多く、迷いやすいポイントがたくさんあるので、ぜひご覧ください。
第3章:女性の葬式の服装マナー|迷いやすいからこそ基本が大事
男性の服装が「ブラックスーツ」でほぼ固定されているのに対し、女性の服装は選択肢が広い分、迷いがちです。スカートかパンツか、和装か洋装か、アクセサリーや髪型、バッグや靴など…迷うポイントは数えきれません。
それでも、基本をしっかり押さえておけば、大きなマナー違反になることは避けられます。ここでは「一般参列者」としての正しい服装を中心に、シンプルで品のある喪服スタイルをご紹介します。
■ 洋装スタイルの基本
現代の葬儀では、ほとんどの女性が洋装のブラックフォーマルを着用しています。以下が基本です:
- 黒無地のワンピース or アンサンブルスーツ
- スカート丈は膝下~ふくらはぎ程度
- 肌の露出を控えたデザイン(ノースリーブNG、胸元も詰まったものが◎)
- ストッキングは黒の無地(網タイツやラメ入りNG)
- 靴は黒のプレーンなパンプス(光沢や装飾なし)
- バッグは布製・革製の黒無地(光沢・金具装飾NG)
■ パンツスタイルはOK?
実は、女性のパンツスーツスタイルはここ数年で市民権を得つつあります。特に冬場や高齢者、妊婦、身体的な事情がある方にとっては実用的な選択です。
ただし、親族や喪主などの立場でなければ、パンツスーツでも大きな問題はありません。心配な方は、念のため地味でフォーマル感のあるセットアップを選びましょう。
■ 和装を選ぶ場合
年配の方や故人との関係が深い方が、あえて和装を選ばれることもあります。喪服としての和装は、以下の通りです:
- 黒無地の喪服(五つ紋付き)
- 黒の帯(帯揚げ・帯締めも黒)
- 白い半襟と足袋
和装は格式が高く、特に親族・喪主側であれば好印象ですが、着付けや所作のハードルが高いため、現在は少数派です。無理せず洋装でもまったく問題ありません。
■ アクセサリー・髪型・メイクの注意点
意外と見落とされがちなのが、小物や髪型・メイクのマナーです。
◯ アクセサリー:
- 真珠の一連ネックレス(2連は「不幸が重なる」とされNG)
- 金属・宝石・派手なデザインは避ける
◯ 髪型:
- 黒・ダークカラーでまとめる(染髪が明るい場合はヘアスプレーでトーンダウン)
- ロングヘアは束ねる(ハーフアップや夜会巻きなど)
◯ メイク:
- 派手な色は避け、ナチュラルメイクが基本
- マットな仕上がりで控えめに(ラメやツヤ感はNG)
■ 年齢・体型による注意点
40代以降の方からは、「体型が変わって昔の喪服が入らない」「似合わなくなった」という相談をよくいただきます。
年齢を重ねると、スカート丈やジャケットのラインも気になるものです。
「体型に合わない服装」は、それだけで印象が悪くなることも…。特に格式ある場では、自分にフィットした喪服を選び直すのも、大人としてのたしなみです。
■ 自分に合ったブラックフォーマルが手元にないときは?
「急に必要になって間に合わない」「今の体型に合うものがない」というときに便利なのが、前章でもご紹介した喪服レンタルサービス【Cariru BLACK FORMAL】です。
女性向けには、ワンピース・ジャケット・バッグ・靴・ネックレスなど、一式がそろったセットが多数用意されています。マナーに配慮した上質なデザインのものが揃っており、冠婚葬祭にふさわしいスタイルが即座に整う点が魅力です。
「買い直すほどじゃないけど、今の自分に合うものを着たい」
「次にいつ着るかわからないし、保管も大変…」
そんな方には、Cariruのレンタルは非常におすすめです。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
次章では、「子ども・学生・乳幼児の葬式の服装」について解説します。小さなお子さんがいるご家庭では特に悩ましいポイントですので、丁寧に取り上げていきます。
第4章:子ども・学生・乳幼児の服装はどうすれば?|“子どもらしさ”と“礼儀”のバランス
お子さんを連れてのお葬式。親としては「どんな服を着せたらいいのか」「マナー違反にならないか」と心配になりますよね。私自身も二児の父なので、その気持ちはよくわかります。
葬儀は厳粛な場ではありますが、「子どもだから絶対に黒を着せないといけない」ということはありません。むしろ大切なのは、“子どもらしさを残しつつ、きちんとした印象”を与えることです。
ここでは年齢別に、無理なくマナーを守れる服装選びのポイントをご紹介します。
■ 小学生~高校生の服装
成長段階にある学生世代には、以下のような服装がおすすめです:
◯ 制服がある場合:
- 制服があれば、それを着用するのが基本です。
- 制服が式服と見なされるため、わざわざ喪服を用意する必要はありません。
- 派手な飾りやアクセサリーは控え、ネクタイやリボンは黒・紺系が無難です。
◯ 制服がない場合・私服で出席する場合:
- 男の子:白シャツ+黒や紺のジャケット・ズボン
- 女の子:白ブラウス+黒や紺のスカート、ワンピースなど
- 靴は黒のローファーやスニーカー(キャラクター柄は避ける)
学生服がない私服の場合は、「清潔感のある地味な服装」を心がければ十分です。全身黒にこだわらなくても、場の雰囲気を壊さなければ問題ありません。
■ 未就学児・乳幼児の服装
0~6歳くらいの小さなお子さまの場合は、喪服にこだわる必要はありません。ただし、派手な柄や原色系は避けて、落ち着いた色合いでまとめるようにしましょう。
- 男の子:白やグレーのシャツ、ネイビーのズボンなど
- 女の子:黒・紺・グレーのワンピースやセットアップ
- 靴下・靴もできるだけシンプルに(キャラクター・蛍光色は避ける)
「静かにしていられるか心配…」という声もよく聞きますが、小さな子どもが多少動いたり声を出したりしても、周囲の大人は理解があります。
むしろ無理に叱ったり、極端に緊張させてしまう方が、子どもにとってもストレスです。
■ 子ども連れ参列時の親の心得
子どもを連れて参列する場合は、服装以外にも以下の点に配慮すると安心です。
- 式場に事前に子ども連れでの参列可否を確認する
- おもちゃやお菓子は“音が出ない・派手でないもの”を選ぶ
- 状況に応じて、控室や車の中で過ごす準備もしておく
「子どもがいても、ちゃんとお別れの場に立ち会ってほしい」
そんな親心は、故人にも周囲の方にもきっと伝わります。服装と同じく、「想い」と「準備」が大切なのです。
■ 急な訃報でも慌てないために
子どもの成長は早く、1~2年前に買った喪服やワンピースが着られなくなっていることもありますよね。
そんなときは、事前に「今着られるフォーマルがあるか」確認しておくことをおすすめします。とくに中高生のお子さまがいるご家庭は、制服が使えるかどうかのチェックもお忘れなく。
第5章:季節別(夏・冬)の服装で気をつけるべきこと|暑さ寒さとの付き合い方
ご葬儀の場は、季節に関係なく突然訪れるものです。そのため、「真夏の炎天下で喪服を着なければならない」「真冬の寒さの中で参列する」ということも少なくありません。
ここでは、夏・冬の葬儀における服装選びの注意点と工夫についてご紹介します。
■ 夏(6月〜9月)の葬儀|暑さ対策をしつつ、マナーを守る
夏の葬儀は、気温が30度を超える中での長時間参列もあり得ます。とくに屋外での火葬や出棺の場面では、汗だくになってしまうこともしばしば…。
とはいえ、カジュアルな服装にするわけにはいきません。大切なのは、「暑さ対策とマナーのバランス」です。
◯ 男性:
- ジャケット着用が基本。ただし式場内では脱いでもOK
- 通気性のよい薄手の夏用礼服がおすすめ
- 汗対策でインナーに白の速乾肌着を着用すると快適
◯ 女性:
- 半袖のワンピースやアンサンブルでOK(ノースリーブはNG)
- 通気性のよい素材(ポリエステルやレーヨン混合など)
- ストッキングは黒の薄手を選び、サンダルはNG
◯ 小物の工夫:
- 日傘は無地の黒やグレーなら使用可(柄入り・カラフルは避ける)
- ハンカチは白か黒で、レースなど装飾の少ないものを
- 制汗シートや冷却スプレーは、控え室などで使用
暑くて汗をかいたまま過ごすのは、体調にも悪影響があります。適度に涼を取りながらも、見た目が乱れないよう意識しましょう。
■ 冬(12月〜2月)の葬儀|寒さ対策と格式のバランス
冬の葬儀では、防寒対策が欠かせません。しかし、「ダウンジャケットや派手なコートで参列」はやはり場にそぐいません。
寒さの中でも、落ち着いた見た目を保ちながら体を守ることが大切です。
◯ アウター選びのポイント:
- 黒・紺・ダークグレーの無地コートがベスト(ウールやカシミアなど)
- フードや装飾(ファー・大きなボタン・ロゴ入り)は避ける
- ロング丈で体をしっかり覆えるデザインが理想
◯ インナー・小物の工夫:
- ヒートテックや防寒インナーはOK(色が透けないよう注意)
- 手袋やマフラーも無地でシンプルなものを
- 女性は厚手の黒タイツも可(ただし透け感のないものを選ぶ)
冬の式場や火葬場は、建物によっては暖房が不十分なこともあります。冷え対策をしっかりしつつ、品格を損なわないような素材や色選びを心がけましょう。
■ 春・秋の“微妙な気温”の時期はどうする?
春や秋は、寒暖差が激しいため服装選びに迷いやすい季節です。特に3月や10月は、朝晩は冷えるのに昼は暑い…といった気候になることも。
そんなときは、重ね着で調整できる服装が便利です。
- 女性:ワンピース+ジャケット、薄手のストールで温度調整
- 男性:通年用の礼服にインナーで保温対応
無理に季節感を演出する必要はありません。あくまでも黒を基調にしたシンプルな装いをベースに、体調を崩さない範囲で調整していきましょう。
第6章:和装と洋装、どちらを選ぶべきか
和装の喪服(五つ紋付き黒無地)は格式が高く、親族や喪主であればとても丁寧な印象を与えます。ただし、現代では着付けや所作の難しさ、移動のしづらさなどから洋装が一般的です。
- ご高齢の方が和装を着る場合:サポートしてくれる人がいるかを事前に確認
- 若い世代は無理せず洋装でOK
- 着物を選ぶなら、バッグや草履・髪型も含めて統一感を大切に
「伝統を守りたい」というお気持ちは素晴らしいものです。ご自身の立場・体調・環境に応じて無理なく判断しましょう。
第7章:小物・アクセサリー・髪型・靴の注意点(総まとめ)
- バッグ:黒の布製orシンプルな革製、光沢や装飾はNG
- 靴:黒のプレーンパンプス・革靴。ピンヒールやサンダルは避ける
- アクセサリー:真珠の一連ネックレス(2連はNG)
- 髪型:すっきりまとめ、派手なヘアアクセサリーは避ける
- メイク:ナチュラルに。ラメや赤リップは控える
細部まで気を配ることで、全体として“落ち着いた印象”を与えることができます。
第8章:地域差や葬儀形式に注意|迷ったら専門サイトで確認を
葬儀のマナーや服装には、地域性や宗派による違いがあります。
「昔はこうだった」「自分の親のときはこうした」といった経験だけでは判断が難しいことも。
特に、喪主・親族として参列する場合や、事前に準備する時間がない場合は、信頼できる情報源を活用するのが安心です。
そこでおすすめなのが、東証プライム上場企業のエス・エム・エスが運営する【安心葬儀】です。
▶ 葬儀社選びに失敗しないための第一歩|【安心葬儀】
- 全国7,000以上の葬儀社から、条件にあった優良業者を比較
- 24時間対応・電話相談OK
- 葬儀費用の相場・流れ・準備すべきことがすべてわかる
「故人をきちんと送りたい。でも、時間がない」「どこに頼めば安心か不安」という方にとって、情報の集約されたポータルサイトは心強い味方になります。
第9章:お葬式の後も…遺品整理に困ったら
お葬式は終わっても、残された家族にはやるべきことが山のようにあります。
中でも精神的にも肉体的にも負担が大きいのが、遺品整理です。
私も現役時代、ご葬儀後のご家族から「何から手を付けてよいかわからない」「遠方で片づけに通えない」といったご相談を何度も受けました。
そんなときに役立つのが、遺品整理の専門業者【ライフリセット】です。
▶ 遺品整理・生前整理なら【ライフリセット】
- 遺品・不用品の整理をプロが一括対応
- 生前整理にも対応可能
- 見積もり無料・全国対応
- 実家や賃貸の明け渡しにも対応
「自分でやるには時間も体力も足りない」「片付けをめぐって親族と揉めたくない」
そんな悩みを抱える方にとって、専門家の手を借りることは心の余裕にもつながります。
最後に:服装マナーは“想い”の表現のひとつ
葬儀の服装において大切なのは、単なる「正解」ではありません。
大切な方を見送る場で、どれだけ誠実に気持ちを表現できるか。服装はその一部です。
- 立場に合った装いをする
- 清潔感と控えめさを意識する
- 暑さ寒さにも配慮する
- そして何より、「失礼のないようにしたい」という心を持つこと
この記事が、あなたやご家族の不安を少しでも軽くし、後悔のないお別れの一助になれば幸いです。
📌 Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
800件を超える現場経験をもとに、葬儀の基本から終活、信頼できるサービス選びまで、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できることを一緒に考えていきましょう。