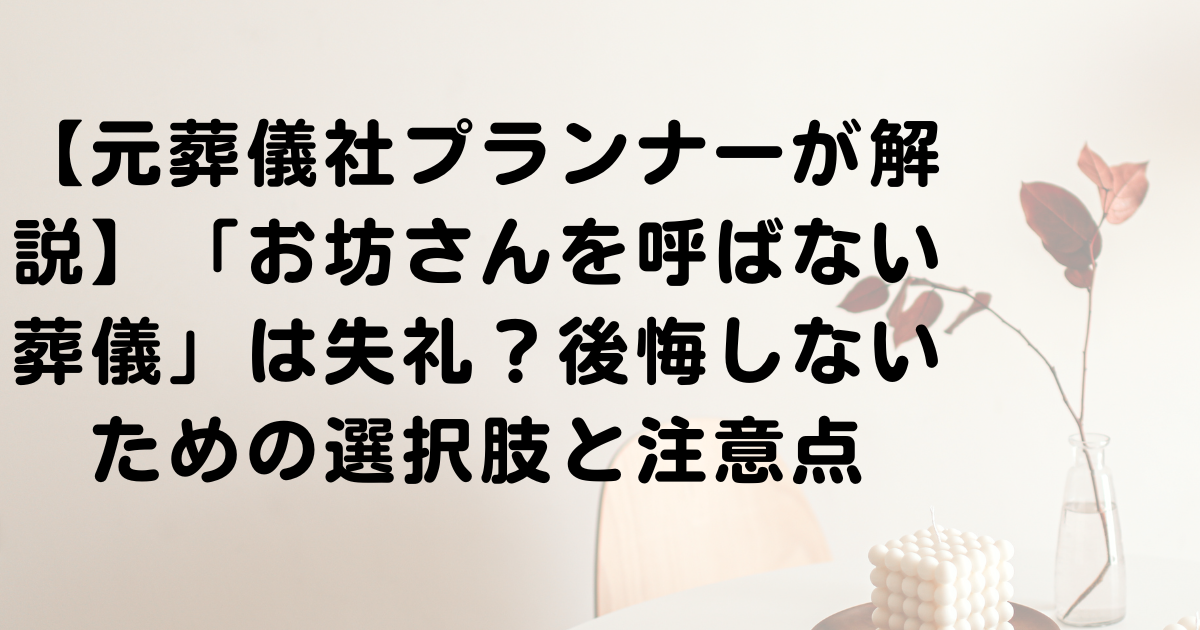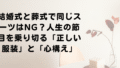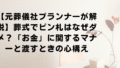プロフィール
Keisuke(けいすけ)|元葬儀社プランナーの終活ブログ運営者
こんにちは。ブログ「家族を想うお葬式ガイド」を運営しているKeisukeです。
現在42歳。地方の中堅都市で、妻と2人の子ども(中2と小5)と暮らしています。以前は12年間、葬儀社でプランナーとして働いており、これまでに担当したご葬儀はのべ800件を超えました。
業界に入ったのは、20代後半に父を突然亡くしたことがきっかけです。右も左もわからず葬儀の手配に奔走し、精神的にも経済的にも本当に苦しかった経験があります。「同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と思い、業界に飛び込みました。
現場では、日々ご遺族の不安や戸惑いに寄り添いながら、費用や手続き、宗教儀礼やマナーについて数えきれないほど相談を受けてきました。しかし同時に、「情報の格差」によって損をしてしまう人が多い現実も見えてきました。
退職後は、家族との時間を大切にしたくて在宅ワークに切り替え、このブログを立ち上げました。お葬式の基本や費用の仕組み、避けられるトラブル、信頼できるサービスの選び方など、わかりやすく丁寧に発信しています。
終活やお墓のこと、エンディングノートや保険なども少しずつ扱っていきます。
「後悔しないお別れ」のために、今できる準備を一緒に考えてみませんか?
あなたやご家族の未来が少しでも安心に近づくよう、心を込めて運営しています。
はじめに:お坊さんを呼ばないお葬式、本当に大丈夫?
こんにちは、元葬儀社プランナーのKeisukeです。
ご家族との大切なお別れについて考えるとき、多くの人が「お坊さん」の存在を意識されるのではないでしょうか。お通夜や葬儀・告別式でお経を読んでいただき、故人を弔う――。これは、私たち日本人の間で長く続いてきた慣習です。
しかし最近、「お坊さんを呼ばない葬儀」が増えているのをご存知でしょうか?
「お坊さんを呼ばないなんて、故人に申し訳ないのでは…?」 「無宗教の葬儀なんて、周りの人にどう思われるだろう…」
このように、不安や戸惑いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に年配の方にとっては、「葬儀といえばお坊さんがいて当たり前」という感覚が強いでしょうから、なおさら抵抗があるかもしれませんね。
でも、安心してください。結論から申し上げますと、「お坊さんを呼ばない葬儀」は、決して失礼なことでも、非常識なことでもありません。
現代では、さまざまな事情から宗教儀礼を省くことを選ぶご家族が増えています。大切なのは、周りの目や慣習にとらわれることではなく、ご家族が故人様とどのように向き合いたいか、そしてどのようなお別れの形を望んでいるか、を考えることです。
この記事では、お坊さんを呼ばない葬儀を検討している方、あるいは今後どうしようかと考えている方に向けて、元葬儀社プランナーの視点から、そのメリットやデメリット、具体的な選択肢、そして後悔しないための注意点をわかりやすく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「お坊さんを呼ばない葬儀」に対する疑問や不安が晴れ、ご家族にとって最善のお別れの形を見つけるヒントが得られるはずです。どうぞ最後までお付き合いください。
なぜ今、「お坊さんを呼ばない葬儀」が増えているのか
以前の私は「葬儀=宗教儀式」という考えが強く、お坊さんを呼ばない葬儀はごく一部の特殊なケースだと思っていました。しかし、現場で多くのご家族と接するうちに、そうではないと気づかされました。
では、なぜ現代においてお坊さんを呼ばない葬儀が増えているのでしょうか。その背景には、いくつかの理由があります。
1. 経済的な理由:お布施の負担が大きい
まず、最も大きな理由の一つが、経済的な負担です。
お坊さんにお経をあげていただくには、「お布施」をお渡しするのが一般的です。しかし、このお布施に決まった金額はありません。地域や寺院、宗派、そして故人様との関係性などによってさまざまですが、数十万円から、場合によっては百万円を超えるケースもあります。
経済的な不安を抱えるご家庭が増えている現代において、このお布施の金額は決して無視できるものではありません。「できれば費用を抑えたい」という思いから、宗教儀礼を省く選択をするご家族は決して少なくないのです。
また、そもそもお布施の金額が不透明なことに戸惑う方もいらっしゃいます。 「いくらお渡しすればいいのかわからない…」 「相場より少なくて、失礼にあたらないだろうか…」 そうした不安を抱えるくらいなら、いっそのことお坊さんを呼ばない方が良い、と考える方も増えています。
私も現場で、お布施の相場について聞かれることがよくありました。ご遺族の負担を少しでも減らしてあげたい、という気持ちから、葬儀社として提携しているお寺様を紹介することもありましたが、それでもやはり「心の負担」は残るものです。
2. 宗教的な理由:特定の信仰がない・宗教観の多様化
次に、日本人の宗教観の変化も大きな要因です。
日本には「特定の宗教を熱心に信仰している」という方は、実はあまり多くありません。多くの人が、お正月には神社へ初詣に行き、クリスマスを祝い、そして葬儀の時には仏式でお坊さんにお経をあげてもらう、というように、宗教を生活の中の「文化」として捉えていることが多いのが現状です。
しかし、そもそも「仏教徒ではない」という方や、「特定の宗派には属していない」という方も増えています。
また、「故人が生前から無宗教だった」というケースも少なくありません。 「お父さんは無宗教だったから、お坊さんを呼ばなくていいよ」 「自分たちも特定の宗教にこだわっていないし、形式的なお葬式は避けたい」 このような考えを持つご家族にとって、無理に仏式の葬儀を行う必要はない、と考えるのは自然な流れと言えるでしょう。
私もプランナーとして働いていた頃、ご遺族から「うちは特定の宗派のお寺さんとのお付き合いがないんです」と相談されることが多くありました。菩提寺(ご先祖様のお墓があるお寺)がない場合、どの宗派のお坊さんにお願いすればいいのか、そもそもお願いする必要があるのか、といった点で悩まれるのです。
現代では、様々な価値観が尊重される時代になりました。「お別れの形」もまた、その一つです。宗教的な形式にとらわれず、故人様の人柄を偲び、ご家族らしい形で送りたいと考える人が増えているのです。
3. 葬儀の形式の多様化:自由な形を求める声
最近の葬儀は、かつてのような「大勢の参列者が集まる盛大なもの」だけではありません。
・ごく身近な人だけでお別れをする「家族葬」
・お通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」
・形式にとらわれず、故人様らしい演出を盛り込む「自由葬」
このように、さまざまな形式の葬儀が登場しています。
特に直葬(火葬式)は、費用を抑えられることや、ご遺族の精神的・肉体的な負担が少ないことから、近年選ばれる方が非常に増えています。この直葬では、お通夜や告別式を行わないため、そもそもお坊さんを呼ぶ必要がありません。
このように、葬儀の形式が多様化したことで、お坊さんを呼ばないという選択肢も、ごく一般的なものとして受け入れられるようになってきました。
お坊さんを呼ばない葬儀のメリット・デメリット
ここまで、お坊さんを呼ばない葬儀が増えている背景をお話ししてきました。しかし、どんな選択にもメリットとデメリットがあります。後悔しないためにも、両方をしっかりと理解しておくことが大切です。
メリット:費用、自由度、精神的な負担
お坊さんを呼ばない葬儀の最大のメリットは、やはり経済的な負担の軽減です。
お布施が必要なくなることで、葬儀費用を大幅に抑えることができます。これは、残されたご家族にとって大きな安心材料になるはずです。
また、葬儀の自由度が高まることも大きなメリットです。
宗教的な形式やしきたりにとらわれる必要がありませんから、故人様が好きだった音楽を流したり、生前の思い出を語り合う時間を設けたり、故人様らしさを存分に表現したお別れの場を作ることができます。
さらに、ご遺族の精神的な負担が減るという点も見逃せません。
お坊さんとのやりとりや、お布施の金額をどうするかといった悩みがなくなることで、より故人様とのお別れに集中できます。私も葬儀社プランナーとして、ご遺族が「お坊さんに失礼がないように」と気遣い、疲弊してしまう姿を何度も見てきました。そうした心配がなくなるだけでも、心にゆとりが生まれます。
デメリット:親族の理解、供養、お墓の問題
一方で、お坊さんを呼ばない葬儀には、いくつかのデメリットも存在します。
1. 親族の理解を得られない可能性がある
これが最も注意すべき点かもしれません。特に、年配の親族や昔ながらの考えを持つ方がいる場合、「お坊さんを呼ばないなんてとんでもない!」と反対される可能性があります。
「故人様がかわいそうだ」 「ご先祖様に申し訳が立たない」 「葬儀とはちゃんとお経を読んでもらうものだ」
こうした考えを持つ親族と、ご家族の間でトラブルになってしまうケースも珍しくありません。葬儀は、故人様のためだけではなく、残されたご家族や親族にとっても大切な儀式です。後々の人間関係にまで影響を与えかねませんので、事前にきちんと話し合い、理解を得ておくことが何よりも重要です。
私も、ご遺族から「親戚を説得するのが一番大変なんです」というお悩みをよく聞きました。そうした場合は、私のような第三者(葬儀社)の立場から、なぜその形式を選んだのか、どんなメリットがあるのかを丁寧に説明し、ご遺族が親族に話しやすくなるようサポートすることもありました。
2. 故人様の「供養」の問題
「お坊さんを呼ばない葬儀は、故人様をきちんと供養できないのでは?」という不安を持つ方もいるでしょう。
仏教において、「供養」とは、お経を読んでもらうことで故人様を極楽浄土へ送り、仏様の世界で幸せに暮らせるよう願う行為を指します。
お坊さんを呼ばない場合、この供養の儀式は行われません。もちろん、故人様を想う気持ちがあれば、形がなくても十分供養にはなりますが、宗教的な意味での供養を望む方にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
3. 納骨先、お墓の問題
そして、非常に重要なのが、お墓の問題です。
もし故人様が、代々お付き合いのあるお寺(菩提寺)のお墓に入る予定であれば、お坊さんを呼ばない葬儀は絶対に避けるべきです。
なぜなら、多くの菩提寺では、そのお寺の宗派に則った葬儀を行わなければ、お墓への納骨を拒否されてしまう可能性があるからです。菩提寺との関係性は、ご家族やご先祖様代々続いてきた大切なものです。お墓の問題は、故人様だけでなく、その後のご家族にも大きな影響を与えます。
「うちは菩提寺がないから大丈夫」と考えている方も、永代供養墓や樹木葬など、新たにお墓を求める場合は、その施設の運営元が宗教団体ではないか、無宗教の葬儀でも受け入れてくれるのか、事前に確認しておく必要があります。
特に、お墓の問題はご家族の中でも意見が分かれやすい部分です。将来を見据えた「終活」の一つとして、生前からご家族で話し合っておくことを強くお勧めします。
「お坊さんを呼ばない葬儀」の具体的な選択肢
お坊さんを呼ばない葬儀には、いくつかの形式があります。ご家族の状況や故人様の意向に合わせて、最適なものを選びましょう。
1. 直葬(火葬式)
最もシンプルで、近年選ばれる方が急増している形式です。お通夜や告別式は行わず、火葬のみを行います。
病院や施設から故人様をご自宅や安置施設に搬送し、ご家族でゆっくりとお別れをします。その後、火葬場で最期のお別れをして火葬を行います。
・メリット: 費用を大幅に抑えられる、時間や体力的な負担が少ない、宗教的なしきたりにとらわれない
・デメリット: 親族の理解が得にくい、お別れの時間が短い、知人や友人が参列できない
「できるだけ費用を抑えたい」「ご家族だけで静かに見送りたい」という方には最適な選択肢です。
2. 無宗教葬(自由葬)
特定の宗教や宗派にとらわれず、故人様の人柄や生涯を偲ぶことを目的とした葬儀です。
決まった形式はありません。故人様が好きだった音楽を流したり、思い出の写真をスライドショーにしたり、生前のエピソードを語り合う時間を設けたりと、ご家族の思いを形にすることができます。
・メリット: 自由度が高い、故人様らしいお別れができる、参列者が故人様を偲ぶことに集中できる ・デメリット: 企画力が必要、葬儀社の力量が問われる、親族の理解が得にくい
「形式にとらわれず、故人様らしいお別れをしたい」という方におすすめです。
3. 音楽葬
無宗教葬の一種で、故人様が好きだった音楽や、生演奏をBGMとして使用する葬儀です。
故人様が愛した音楽に包まれながら、生前の思い出を振り返る、温かいお別れの場になります。
・メリット: 故人様の個性を表現できる、厳粛な雰囲気の中にも温かさがある ・デメリット: 費用が割高になる可能性がある、会場の設備が必要
「故人様が音楽好きだった」という方にはぴったりの形式です。
「お坊さんを呼ばない葬儀」で後悔しないための3つのポイント
お坊さんを呼ばない葬儀を選ぶ場合、後で「こうすればよかった…」と後悔しないために、特に注意してほしいポイントが3つあります。
1. 親族に「なぜそうするのか」を丁寧に説明する
前述したように、親族の理解は非常に重要です。
「経済的な負担を減らすため」「故人が宗教にこだわっていなかったから」など、ご家族がなぜその選択をしたのかを、ご自身の言葉で丁寧に伝えるようにしましょう。 「無駄な出費だから」といったような一方的な言い方ではなく、「故人の意思を尊重して、お金をかけずとも心のこもったお別れをしてあげたい」といったように、相手が納得しやすい言葉を選ぶことが大切です。
2. 納骨先やお墓について事前に確認する
これも非常に重要なポイントです。
特に菩提寺がある場合は、必ず事前に相談しましょう。もし菩提寺の了承が得られないのであれば、お坊さんを呼ぶか、別のお墓を探すか、どちらかの選択を迫られることになります。
「お墓はまだ決まっていないから大丈夫」と考えている方も、将来的にお墓を建てる可能性があるなら、無宗教の葬儀でも受け入れてくれる霊園や、永代供養墓を探しておくことをお勧めします。
3. 葬儀社選びは慎重に!
無宗教葬や直葬に不慣れな葬儀社も、残念ながらまだ存在します。
そうした葬儀社に依頼してしまうと、十分なサポートが受けられず、結果としてご遺族が「思っていたのと違った」と後悔してしまうことになりかねません。
お坊さんを呼ばない葬儀を検討する際は、複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。
その際には、「無宗教葬に対応していますか?」「過去の実績はありますか?」と、直接聞いてみるのが一番確実です。見積もりだけでなく、担当者の対応や提案力なども含めて、ご家族の想いに寄り添ってくれる信頼できる葬儀社を選びましょう。
遺族として、参列者として。お葬式の服装について
お葬式の形が多様化する中でも、参列者が身につける「服装」は、故人様やご遺族に対する敬意を表す大切なマナーです。
「直葬だから、どんな服装でもいいの?」 「無宗教葬だから、喪服じゃなくてもいいのかな?」
このように、服装について悩まれる方もいらっしゃいます。
結論から言うと、どんな形式の葬儀であっても、故人様やご遺族に失礼のない服装を心がけることが大切です。 基本的には、黒を基調とした喪服を着用するのがマナーです。
ただ、突然の訃報で喪服を用意する時間がない、久しぶりに着てみたらサイズが合わなくなっていた、ということもあるかと思います。特に女性の場合、年齢や体型の変化に合わせて喪服を買い替えるのは、なかなか大変なことです。
そんな時におすすめなのが、喪服のレンタルサービスです。
必要な時に、必要なものを、必要な期間だけ借りられるので、とても便利です。 デザインやマナーにこだわって選びたい方には、高品質な喪服をリーズナブルに借りられるサービスもあります。
人気のブランド喪服や、ワンピース、ジャケット、さらにはバッグやネックレス、数珠、袱紗までフルセットでレンタルできるサービスもあります。 急な訃報でも、ネットで24時間いつでも申し込めて、最短で翌日に届けてくれるサービスもあるので、万が一の時にも安心です。
✅ マナー・デザイン・質にこだわる方の喪服・礼服のレンタルCariru BLACK FORMAL
こういったサービスを賢く利用することで、服装に関する心配事をなくし、故人様とのお別れに集中することができます。 「お葬式の服装について、もっと詳しく知りたい」という方は、以下の記事も参考にしてみてください。
お葬式の後、遺品整理はどうすればいい?
お葬式が終わると、ほっと一息つかれることかと思います。 しかし、その後に待ち受けているのが、故人様の「遺品整理」です。
遺品整理は、ただ物を片付けるだけではありません。故人様との思い出が詰まった品々を前に、向き合い、心を整理する大切な時間でもあります。 しかし、いざ始めてみると、
「どこから手をつけていいかわからない」 「物理的に量が多すぎて、自分たちだけではどうにもならない」 「遠方に住んでいるので、なかなか時間が取れない」
といったお悩みを抱える方が非常に多いです。
特に、ご実家が空き家になってしまう場合、残された家財道具や不用品の処分は大きな負担となります。 そんな時、無理にご自身だけで抱え込まず、専門の業者に相談するという選択肢も考えてみてください。
遺品整理の専門業者に依頼することで、故人様の想い出の品を丁寧に仕分けし、不用品を適切に処分してくれます。また、遺品の供養や貴重品の探索など、ご家族の心に寄り添ったサービスを提供してくれる業者も増えています。
「終活」として、生前ご自身で身の回りの整理をされる方もいらっしゃいます。 ご家族の負担を少しでも減らしたい、という想いから専門業者に依頼される方も多いので、遺品整理の選択肢の一つとして覚えておいて損はありません。
お葬式の後の香典返しは?
お葬式に参列してくださった方々からいただいた香典。お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝える「香典返し」も、大切なマナーです。
「いつまでに返せばいいの?」 「何を選べばいいの?」 「相場はどれくらい?」
こうした疑問を持つ方も多いでしょう。
香典返しは、四十九日の法要を終えた頃に、いただいた金額の半分から3分の1程度の品物を贈るのが一般的です。
カタログギフトや、お茶、お菓子、タオルなど、どなたにでも喜んでいただけるような品物を選ぶと良いでしょう。最近は、ネットで簡単に香典返しを選び、手配してくれるサービスも増えています。
オンラインショップを利用すれば、わざわざお店に出向く手間も省けますし、豊富な品揃えの中から、故人様やご家族の想いを込めた品を選ぶことができます。
香典返しは、故人様との最期のお別れに立ち会ってくださった方々への、感謝の気持ちを形にする大切な機会です。マナーを守り、心を込めてお返しを選びましょう。 香典返しについて、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
まとめ:大切なのは、ご家族の納得と故人様への想い
お坊さんを呼ばない葬儀は、決して「手抜き」や「不謹慎」なものではありません。
費用を抑えたい、宗教にこだわらない、故人様らしいお別れをしたい――。そうしたご家族の想いを形にする、一つの選択肢です。 大切なのは、「何が正しいか」ではなく、「ご家族にとって、故人様にとって、何が最善か」を考えることです。
ご家族が「このお別れの形でよかった」と心から思えること。 そして、故人様への感謝や愛情を、自分たちらしい形で伝えること。
それが、後悔のないお別れへと繋がります。
しかし、いざという時に、すべてを一人で判断するのはとても大変なことです。 私も、父を亡くした時に右も左もわからず、とても苦労しました。だからこそ、皆さんには同じ思いをしてほしくありません。
もし、お葬式について不安なこと、わからないことがあるなら、まずは専門家に相談することをお勧めします。 複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することで、ご家族に寄り添ってくれる信頼できるパートナーを見つけることができます。
時間がない中で決断を迫られることも多い葬儀ですが、相見積もりサービスを活用すれば、複数の優良な葬儀社を効率よく比較検討することができます。 東証プライム上場企業が運営しているサービスなので、安心して利用できるはずです。
このブログが、あなたやご家族の「後悔しないお別れ」の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。 何かお葬式に関する疑問や、終活について聞いてみたいことがあれば、いつでもコメント欄でご質問ください。